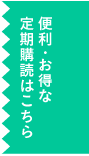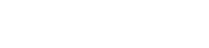ハードコア・パンクのライヴでダイブし、ダンスホール・レゲエ やドラムンベースのパーティーで踊り続けていた筆者は、2010年に体験した2つの夏祭り──高円寺の阿波踊りと錦糸町河内音頭に自らのアイデンティティーを揺さぶられ、日本のフォークロアを巡る旅に出かける。[写真●ケイコ・K.オオイシ]

PROFILE
大石始
ライター/エディター/DJ
おおいし・はじめ:ライター/エディター/DJ。1975年、東京生まれ。音楽雑誌編集者を経て、2008年からフリーランスに。2010年に初の著作『関東ラガマフィン』を、2011年には共同監修を手がけた『GLOCAL BEATS』を上梓。「CDジャーナル」のウェブサイトでインタビュー・シリーズ“THE NEW GUIDE TO JAPANESE TRADITIONAL MUSIC”を連載中。DJとして海外アーティストとの共演多数。2012年にはコンピ『DISCOVER NEW JAPAN 民謡ニューウェーブVOL.1』をプロデュース。
第1回 エネルギー渦巻く音楽の場を求めて──コロンビアから相馬へ
[caption id="attachment_1252" align="alignnone" width="640"] カルナバルのパレード。ラティーノたちのエネルギーが爆発する[/caption]
二〇一一年三月一一日、僕は南米コロンビアのタガンガにいた。カリブ海に面したその小さな町は各国のトラヴェラーが集まるビーチタウンで、 僕はその前日、フランス人が経営する洒落たゲストハウスにチェックインしたばかりだった。タガンガにやってきたのは、とあるミュージシャンに会うため。また、その直前にタガンガ近郊のバランキージャで行われていたカルナバルでハメを外しすぎた僕にとっては、身体全体に広がる疲労を癒すという目的もあった。町中には僕と同じようなトラヴェラーが溢れていて、パーティー・フリーク同士の妙な連帯感のようなものもあったのだろう、喧噪のバランキージャとは異なるリラックスしたムードに少しずつ疲れが取れていくのを実感していた。
現地時間三月一一日、タガンガはいつもと変わらぬ静かな朝を迎えていた。鳥のさえずりで目を覚ました僕は、コーヒーを呑みながらいつものようにメールをチェックし、続いてTwitterにログインした。普段は友人たちの呑気なツイートに苦笑いしたり、突っ込みを入れているものだが、その日のタイムラインは目を疑うものだった。延々と並ぶパニック状態のツイート。被害状況を伝えるニュースのリンク。ゲストハウスのテレビでは、見たこともない大波が家や車を押し流していく映像が流れている。僕はその場で東京の実家に電話をかけた。久々に話す母は拍子抜けするほどいつもと変わらない様子だったが、母の話を聞いても、日本で何が起きているのかさっぱり実感が沸かなかった。
それから二週間後、僕は住み慣れた東京の自宅へ戻った。日本を離れている間、福島第一原発事故があった。その状況はコロンビアでもテレビや新聞のトップニュースとして報道されていて、おせっかいでお人好しのコロンビア人たちから「お前の家族は大丈夫か? 本当に気の毒に思うよ」と心配され続けていたが、帰国してもなお、僕は日本で起きていることに実感を持てないままでいた。久々に会う友人たちはみんな疲れきっていた。マスクをしていた友人に「どうしたの? 風邪?」と聞くと、少し呆れながら「放射能対策ですよ」と返された。まさに浦島太郎状態である。
旅のバタバタが落ち着いた頃、僕はYoutubeで三月一一日のニュース映像を片っ端から見た。そこに映っていたのは、静かな田舎町が大波に呑み込まれ、人々が途方に暮れている光景だった。コロンビアでも同じ映像を見ていたはずなのに、僕はその悲惨な映像に心を揺さぶられた。稲が青々と広がる水田が、使い込まれた漁船が、人々の思い出が詰まった家々が跡形もなく流されてゆく。命が、生活が、歴史が流されてゆく。そのとき、僕はようやく事の重大さが理解することができたのだった。
一方で、僕の心のなかにはコロンビアで目の当たりにした美しい光景がくっきりと刻み込まれていた。なかでももっとも印象深かったのは、バランキージャのカルナバルである。バランキージャはかなり大きな町ではあるが、普段は首都ボゴタのように音楽が溢れているわけでもないし、これといった見所がある町でもない。だが、カルナバルの期間だけ──つまり一年に四日間だけ──バランキージャはまるで魔法がかかったように特別な場所になる。
カルナバル期間中に観た大御所フォルクローレ歌手、ペトロナ・マルチネスのステージは衝撃的だった。会場はラ・プラッサ・デ・ラ・パスという公園に建てられた野外ステージ。一九三九年生まれのペトロナがスタッフの肩を借りながらヨロヨロと階段を登っているのを見たとき、僕はそのパフォーマンスにさほど期待できないであろうことを覚悟した。だが、ひとたびタンボーラ(太鼓)がリズムを刻み出すと、彼女は軽やかにステップを踏みはじめ、その直前まで会場を賑わせていた若手を圧倒する声量で歌い出したのである。その瞬間、それまで好き勝手に大騒ぎしていたオーディエンスとペトロナのヴァイブレーションが一体となった。緊張と熱狂が共存する凛とした空気が充満し、すべての視線がペトロナに注がれる。先ほどまでヨボヨボと階段を上がっていた老婆の姿は、もうそこにはなかった。
[caption id="attachment_1251" align="alignnone" width="333"]
カルナバルのパレード。ラティーノたちのエネルギーが爆発する[/caption]
二〇一一年三月一一日、僕は南米コロンビアのタガンガにいた。カリブ海に面したその小さな町は各国のトラヴェラーが集まるビーチタウンで、 僕はその前日、フランス人が経営する洒落たゲストハウスにチェックインしたばかりだった。タガンガにやってきたのは、とあるミュージシャンに会うため。また、その直前にタガンガ近郊のバランキージャで行われていたカルナバルでハメを外しすぎた僕にとっては、身体全体に広がる疲労を癒すという目的もあった。町中には僕と同じようなトラヴェラーが溢れていて、パーティー・フリーク同士の妙な連帯感のようなものもあったのだろう、喧噪のバランキージャとは異なるリラックスしたムードに少しずつ疲れが取れていくのを実感していた。
現地時間三月一一日、タガンガはいつもと変わらぬ静かな朝を迎えていた。鳥のさえずりで目を覚ました僕は、コーヒーを呑みながらいつものようにメールをチェックし、続いてTwitterにログインした。普段は友人たちの呑気なツイートに苦笑いしたり、突っ込みを入れているものだが、その日のタイムラインは目を疑うものだった。延々と並ぶパニック状態のツイート。被害状況を伝えるニュースのリンク。ゲストハウスのテレビでは、見たこともない大波が家や車を押し流していく映像が流れている。僕はその場で東京の実家に電話をかけた。久々に話す母は拍子抜けするほどいつもと変わらない様子だったが、母の話を聞いても、日本で何が起きているのかさっぱり実感が沸かなかった。
それから二週間後、僕は住み慣れた東京の自宅へ戻った。日本を離れている間、福島第一原発事故があった。その状況はコロンビアでもテレビや新聞のトップニュースとして報道されていて、おせっかいでお人好しのコロンビア人たちから「お前の家族は大丈夫か? 本当に気の毒に思うよ」と心配され続けていたが、帰国してもなお、僕は日本で起きていることに実感を持てないままでいた。久々に会う友人たちはみんな疲れきっていた。マスクをしていた友人に「どうしたの? 風邪?」と聞くと、少し呆れながら「放射能対策ですよ」と返された。まさに浦島太郎状態である。
旅のバタバタが落ち着いた頃、僕はYoutubeで三月一一日のニュース映像を片っ端から見た。そこに映っていたのは、静かな田舎町が大波に呑み込まれ、人々が途方に暮れている光景だった。コロンビアでも同じ映像を見ていたはずなのに、僕はその悲惨な映像に心を揺さぶられた。稲が青々と広がる水田が、使い込まれた漁船が、人々の思い出が詰まった家々が跡形もなく流されてゆく。命が、生活が、歴史が流されてゆく。そのとき、僕はようやく事の重大さが理解することができたのだった。
一方で、僕の心のなかにはコロンビアで目の当たりにした美しい光景がくっきりと刻み込まれていた。なかでももっとも印象深かったのは、バランキージャのカルナバルである。バランキージャはかなり大きな町ではあるが、普段は首都ボゴタのように音楽が溢れているわけでもないし、これといった見所がある町でもない。だが、カルナバルの期間だけ──つまり一年に四日間だけ──バランキージャはまるで魔法がかかったように特別な場所になる。
カルナバル期間中に観た大御所フォルクローレ歌手、ペトロナ・マルチネスのステージは衝撃的だった。会場はラ・プラッサ・デ・ラ・パスという公園に建てられた野外ステージ。一九三九年生まれのペトロナがスタッフの肩を借りながらヨロヨロと階段を登っているのを見たとき、僕はそのパフォーマンスにさほど期待できないであろうことを覚悟した。だが、ひとたびタンボーラ(太鼓)がリズムを刻み出すと、彼女は軽やかにステップを踏みはじめ、その直前まで会場を賑わせていた若手を圧倒する声量で歌い出したのである。その瞬間、それまで好き勝手に大騒ぎしていたオーディエンスとペトロナのヴァイブレーションが一体となった。緊張と熱狂が共存する凛とした空気が充満し、すべての視線がペトロナに注がれる。先ほどまでヨボヨボと階段を上がっていた老婆の姿は、もうそこにはなかった。
[caption id="attachment_1251" align="alignnone" width="333"] ラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージに立つペトロナ・マルチネス[/caption]
このラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージは、その周囲を踊り手が回れるように作られている。つまり、日本の盆踊りの櫓(やぐら)と同じスタイル。そこで演奏される音楽はブジェレンゲやクンビア、マパレといったコロンビアの伝統リズムで、太鼓とマラカスのビートを軸にした素朴なものばかりだ。コロンビアの伝統音楽は奴隷たちが持ち込んだアフリカ文化、インディヘナと呼ばれる先住民文化、そして植民者が持ち込んだヨーロッパ文化が複雑に入り交じっているのが特徴だが、ラ・プラッサ・デ・ラ・パスで鳴り響くリズムは特にアフリカ色が強い。
そのリズムに合わせ、人々はステージの周りを練り歩く。そのなかには美しい衣裳で着飾った踊り手がいれば、地元のチンピラも、観光客もいる。ただしアジア人はあまりいないので、ステージ上でその光景を眺めていた僕とフォトグラファーの妻はやたらと注目を集めることになってしまった。夜が更けるにつれ、ステージを回る踊りの輪は少しずつ大きくなっていく。そして、人々のステップはタンボーラとマラカスが刻むビートと溶け合い、巨大なグルーヴが作り出されていった。
コロンビアに帰ってきてからの僕の頭のなかには、カルナバルの夜の幸福な光景と被災地の悲惨な風景という、ある種両極端のイメージが混在していた。かたや人々のエネルギーが渦巻くバランキージャ。かたや津波と放射能によって人と人の絆がズタズタにされてしまった東北。その両方のイメージを無理に統合する必要はないだろうけれど、ガタガタになった日本という国で、僕はカルナバルのエネルギーを無意識のうちに求めていた。それはあくまでも個人的欲求だったのかもしれないが、一方では、一〇代の頃から愛してきた音楽とダンスが現在の日本で何らかの効力を持たないだろうか?という漠然とした願いのようなものもあった。そして、僕のなかでは祝祭空間を作り出す〈祭り〉への関心が改めて高まっていった。
ラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージに立つペトロナ・マルチネス[/caption]
このラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージは、その周囲を踊り手が回れるように作られている。つまり、日本の盆踊りの櫓(やぐら)と同じスタイル。そこで演奏される音楽はブジェレンゲやクンビア、マパレといったコロンビアの伝統リズムで、太鼓とマラカスのビートを軸にした素朴なものばかりだ。コロンビアの伝統音楽は奴隷たちが持ち込んだアフリカ文化、インディヘナと呼ばれる先住民文化、そして植民者が持ち込んだヨーロッパ文化が複雑に入り交じっているのが特徴だが、ラ・プラッサ・デ・ラ・パスで鳴り響くリズムは特にアフリカ色が強い。
そのリズムに合わせ、人々はステージの周りを練り歩く。そのなかには美しい衣裳で着飾った踊り手がいれば、地元のチンピラも、観光客もいる。ただしアジア人はあまりいないので、ステージ上でその光景を眺めていた僕とフォトグラファーの妻はやたらと注目を集めることになってしまった。夜が更けるにつれ、ステージを回る踊りの輪は少しずつ大きくなっていく。そして、人々のステップはタンボーラとマラカスが刻むビートと溶け合い、巨大なグルーヴが作り出されていった。
コロンビアに帰ってきてからの僕の頭のなかには、カルナバルの夜の幸福な光景と被災地の悲惨な風景という、ある種両極端のイメージが混在していた。かたや人々のエネルギーが渦巻くバランキージャ。かたや津波と放射能によって人と人の絆がズタズタにされてしまった東北。その両方のイメージを無理に統合する必要はないだろうけれど、ガタガタになった日本という国で、僕はカルナバルのエネルギーを無意識のうちに求めていた。それはあくまでも個人的欲求だったのかもしれないが、一方では、一〇代の頃から愛してきた音楽とダンスが現在の日本で何らかの効力を持たないだろうか?という漠然とした願いのようなものもあった。そして、僕のなかでは祝祭空間を作り出す〈祭り〉への関心が改めて高まっていった。
 カルナバルのパレード。ラティーノたちのエネルギーが爆発する[/caption]
二〇一一年三月一一日、僕は南米コロンビアのタガンガにいた。カリブ海に面したその小さな町は各国のトラヴェラーが集まるビーチタウンで、 僕はその前日、フランス人が経営する洒落たゲストハウスにチェックインしたばかりだった。タガンガにやってきたのは、とあるミュージシャンに会うため。また、その直前にタガンガ近郊のバランキージャで行われていたカルナバルでハメを外しすぎた僕にとっては、身体全体に広がる疲労を癒すという目的もあった。町中には僕と同じようなトラヴェラーが溢れていて、パーティー・フリーク同士の妙な連帯感のようなものもあったのだろう、喧噪のバランキージャとは異なるリラックスしたムードに少しずつ疲れが取れていくのを実感していた。
現地時間三月一一日、タガンガはいつもと変わらぬ静かな朝を迎えていた。鳥のさえずりで目を覚ました僕は、コーヒーを呑みながらいつものようにメールをチェックし、続いてTwitterにログインした。普段は友人たちの呑気なツイートに苦笑いしたり、突っ込みを入れているものだが、その日のタイムラインは目を疑うものだった。延々と並ぶパニック状態のツイート。被害状況を伝えるニュースのリンク。ゲストハウスのテレビでは、見たこともない大波が家や車を押し流していく映像が流れている。僕はその場で東京の実家に電話をかけた。久々に話す母は拍子抜けするほどいつもと変わらない様子だったが、母の話を聞いても、日本で何が起きているのかさっぱり実感が沸かなかった。
それから二週間後、僕は住み慣れた東京の自宅へ戻った。日本を離れている間、福島第一原発事故があった。その状況はコロンビアでもテレビや新聞のトップニュースとして報道されていて、おせっかいでお人好しのコロンビア人たちから「お前の家族は大丈夫か? 本当に気の毒に思うよ」と心配され続けていたが、帰国してもなお、僕は日本で起きていることに実感を持てないままでいた。久々に会う友人たちはみんな疲れきっていた。マスクをしていた友人に「どうしたの? 風邪?」と聞くと、少し呆れながら「放射能対策ですよ」と返された。まさに浦島太郎状態である。
旅のバタバタが落ち着いた頃、僕はYoutubeで三月一一日のニュース映像を片っ端から見た。そこに映っていたのは、静かな田舎町が大波に呑み込まれ、人々が途方に暮れている光景だった。コロンビアでも同じ映像を見ていたはずなのに、僕はその悲惨な映像に心を揺さぶられた。稲が青々と広がる水田が、使い込まれた漁船が、人々の思い出が詰まった家々が跡形もなく流されてゆく。命が、生活が、歴史が流されてゆく。そのとき、僕はようやく事の重大さが理解することができたのだった。
一方で、僕の心のなかにはコロンビアで目の当たりにした美しい光景がくっきりと刻み込まれていた。なかでももっとも印象深かったのは、バランキージャのカルナバルである。バランキージャはかなり大きな町ではあるが、普段は首都ボゴタのように音楽が溢れているわけでもないし、これといった見所がある町でもない。だが、カルナバルの期間だけ──つまり一年に四日間だけ──バランキージャはまるで魔法がかかったように特別な場所になる。
カルナバル期間中に観た大御所フォルクローレ歌手、ペトロナ・マルチネスのステージは衝撃的だった。会場はラ・プラッサ・デ・ラ・パスという公園に建てられた野外ステージ。一九三九年生まれのペトロナがスタッフの肩を借りながらヨロヨロと階段を登っているのを見たとき、僕はそのパフォーマンスにさほど期待できないであろうことを覚悟した。だが、ひとたびタンボーラ(太鼓)がリズムを刻み出すと、彼女は軽やかにステップを踏みはじめ、その直前まで会場を賑わせていた若手を圧倒する声量で歌い出したのである。その瞬間、それまで好き勝手に大騒ぎしていたオーディエンスとペトロナのヴァイブレーションが一体となった。緊張と熱狂が共存する凛とした空気が充満し、すべての視線がペトロナに注がれる。先ほどまでヨボヨボと階段を上がっていた老婆の姿は、もうそこにはなかった。
[caption id="attachment_1251" align="alignnone" width="333"]
カルナバルのパレード。ラティーノたちのエネルギーが爆発する[/caption]
二〇一一年三月一一日、僕は南米コロンビアのタガンガにいた。カリブ海に面したその小さな町は各国のトラヴェラーが集まるビーチタウンで、 僕はその前日、フランス人が経営する洒落たゲストハウスにチェックインしたばかりだった。タガンガにやってきたのは、とあるミュージシャンに会うため。また、その直前にタガンガ近郊のバランキージャで行われていたカルナバルでハメを外しすぎた僕にとっては、身体全体に広がる疲労を癒すという目的もあった。町中には僕と同じようなトラヴェラーが溢れていて、パーティー・フリーク同士の妙な連帯感のようなものもあったのだろう、喧噪のバランキージャとは異なるリラックスしたムードに少しずつ疲れが取れていくのを実感していた。
現地時間三月一一日、タガンガはいつもと変わらぬ静かな朝を迎えていた。鳥のさえずりで目を覚ました僕は、コーヒーを呑みながらいつものようにメールをチェックし、続いてTwitterにログインした。普段は友人たちの呑気なツイートに苦笑いしたり、突っ込みを入れているものだが、その日のタイムラインは目を疑うものだった。延々と並ぶパニック状態のツイート。被害状況を伝えるニュースのリンク。ゲストハウスのテレビでは、見たこともない大波が家や車を押し流していく映像が流れている。僕はその場で東京の実家に電話をかけた。久々に話す母は拍子抜けするほどいつもと変わらない様子だったが、母の話を聞いても、日本で何が起きているのかさっぱり実感が沸かなかった。
それから二週間後、僕は住み慣れた東京の自宅へ戻った。日本を離れている間、福島第一原発事故があった。その状況はコロンビアでもテレビや新聞のトップニュースとして報道されていて、おせっかいでお人好しのコロンビア人たちから「お前の家族は大丈夫か? 本当に気の毒に思うよ」と心配され続けていたが、帰国してもなお、僕は日本で起きていることに実感を持てないままでいた。久々に会う友人たちはみんな疲れきっていた。マスクをしていた友人に「どうしたの? 風邪?」と聞くと、少し呆れながら「放射能対策ですよ」と返された。まさに浦島太郎状態である。
旅のバタバタが落ち着いた頃、僕はYoutubeで三月一一日のニュース映像を片っ端から見た。そこに映っていたのは、静かな田舎町が大波に呑み込まれ、人々が途方に暮れている光景だった。コロンビアでも同じ映像を見ていたはずなのに、僕はその悲惨な映像に心を揺さぶられた。稲が青々と広がる水田が、使い込まれた漁船が、人々の思い出が詰まった家々が跡形もなく流されてゆく。命が、生活が、歴史が流されてゆく。そのとき、僕はようやく事の重大さが理解することができたのだった。
一方で、僕の心のなかにはコロンビアで目の当たりにした美しい光景がくっきりと刻み込まれていた。なかでももっとも印象深かったのは、バランキージャのカルナバルである。バランキージャはかなり大きな町ではあるが、普段は首都ボゴタのように音楽が溢れているわけでもないし、これといった見所がある町でもない。だが、カルナバルの期間だけ──つまり一年に四日間だけ──バランキージャはまるで魔法がかかったように特別な場所になる。
カルナバル期間中に観た大御所フォルクローレ歌手、ペトロナ・マルチネスのステージは衝撃的だった。会場はラ・プラッサ・デ・ラ・パスという公園に建てられた野外ステージ。一九三九年生まれのペトロナがスタッフの肩を借りながらヨロヨロと階段を登っているのを見たとき、僕はそのパフォーマンスにさほど期待できないであろうことを覚悟した。だが、ひとたびタンボーラ(太鼓)がリズムを刻み出すと、彼女は軽やかにステップを踏みはじめ、その直前まで会場を賑わせていた若手を圧倒する声量で歌い出したのである。その瞬間、それまで好き勝手に大騒ぎしていたオーディエンスとペトロナのヴァイブレーションが一体となった。緊張と熱狂が共存する凛とした空気が充満し、すべての視線がペトロナに注がれる。先ほどまでヨボヨボと階段を上がっていた老婆の姿は、もうそこにはなかった。
[caption id="attachment_1251" align="alignnone" width="333"] ラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージに立つペトロナ・マルチネス[/caption]
このラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージは、その周囲を踊り手が回れるように作られている。つまり、日本の盆踊りの櫓(やぐら)と同じスタイル。そこで演奏される音楽はブジェレンゲやクンビア、マパレといったコロンビアの伝統リズムで、太鼓とマラカスのビートを軸にした素朴なものばかりだ。コロンビアの伝統音楽は奴隷たちが持ち込んだアフリカ文化、インディヘナと呼ばれる先住民文化、そして植民者が持ち込んだヨーロッパ文化が複雑に入り交じっているのが特徴だが、ラ・プラッサ・デ・ラ・パスで鳴り響くリズムは特にアフリカ色が強い。
そのリズムに合わせ、人々はステージの周りを練り歩く。そのなかには美しい衣裳で着飾った踊り手がいれば、地元のチンピラも、観光客もいる。ただしアジア人はあまりいないので、ステージ上でその光景を眺めていた僕とフォトグラファーの妻はやたらと注目を集めることになってしまった。夜が更けるにつれ、ステージを回る踊りの輪は少しずつ大きくなっていく。そして、人々のステップはタンボーラとマラカスが刻むビートと溶け合い、巨大なグルーヴが作り出されていった。
コロンビアに帰ってきてからの僕の頭のなかには、カルナバルの夜の幸福な光景と被災地の悲惨な風景という、ある種両極端のイメージが混在していた。かたや人々のエネルギーが渦巻くバランキージャ。かたや津波と放射能によって人と人の絆がズタズタにされてしまった東北。その両方のイメージを無理に統合する必要はないだろうけれど、ガタガタになった日本という国で、僕はカルナバルのエネルギーを無意識のうちに求めていた。それはあくまでも個人的欲求だったのかもしれないが、一方では、一〇代の頃から愛してきた音楽とダンスが現在の日本で何らかの効力を持たないだろうか?という漠然とした願いのようなものもあった。そして、僕のなかでは祝祭空間を作り出す〈祭り〉への関心が改めて高まっていった。
ラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージに立つペトロナ・マルチネス[/caption]
このラ・プラッサ・デ・ラ・パスのステージは、その周囲を踊り手が回れるように作られている。つまり、日本の盆踊りの櫓(やぐら)と同じスタイル。そこで演奏される音楽はブジェレンゲやクンビア、マパレといったコロンビアの伝統リズムで、太鼓とマラカスのビートを軸にした素朴なものばかりだ。コロンビアの伝統音楽は奴隷たちが持ち込んだアフリカ文化、インディヘナと呼ばれる先住民文化、そして植民者が持ち込んだヨーロッパ文化が複雑に入り交じっているのが特徴だが、ラ・プラッサ・デ・ラ・パスで鳴り響くリズムは特にアフリカ色が強い。
そのリズムに合わせ、人々はステージの周りを練り歩く。そのなかには美しい衣裳で着飾った踊り手がいれば、地元のチンピラも、観光客もいる。ただしアジア人はあまりいないので、ステージ上でその光景を眺めていた僕とフォトグラファーの妻はやたらと注目を集めることになってしまった。夜が更けるにつれ、ステージを回る踊りの輪は少しずつ大きくなっていく。そして、人々のステップはタンボーラとマラカスが刻むビートと溶け合い、巨大なグルーヴが作り出されていった。
コロンビアに帰ってきてからの僕の頭のなかには、カルナバルの夜の幸福な光景と被災地の悲惨な風景という、ある種両極端のイメージが混在していた。かたや人々のエネルギーが渦巻くバランキージャ。かたや津波と放射能によって人と人の絆がズタズタにされてしまった東北。その両方のイメージを無理に統合する必要はないだろうけれど、ガタガタになった日本という国で、僕はカルナバルのエネルギーを無意識のうちに求めていた。それはあくまでも個人的欲求だったのかもしれないが、一方では、一〇代の頃から愛してきた音楽とダンスが現在の日本で何らかの効力を持たないだろうか?という漠然とした願いのようなものもあった。そして、僕のなかでは祝祭空間を作り出す〈祭り〉への関心が改めて高まっていった。
*
二〇一〇年、僕は二つの〈祭り〉をはじめて体験した。ひとつは高円寺の阿波おどり。もうひとつは、すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り。東京生まれの僕は随分前からその祭りの存在を知っていたけれど、どちらに対してもまったくといっていいほど興味を持っていなかった。ハードコア・パンクのライヴでダイヴをしたり、ダンスホール・レゲエやドラムンベースのパーティーで朝まで踊り続けていた僕からすると、どちらも辛気くさくて何の刺激も感じないものだったのだ。 高円寺の阿波おどりに関して初めて興味をもったのは、高円寺の連(阿波おどりではひとつのチームのことをこう呼ぶ)の演奏を収めたコンピレーション・アルバム『ぞめき壱 高円寺阿波おどり』をを聴いたときだ。このアルバムは、音楽としての阿波おどりにスポットをあてた画期的な作品。文化保存を目的にしたものではなく、生々しい躍動をそのままパッキングし、音楽面のおもしろさを抽出したその内容に僕は夢中になった。低音の震えはダンスホール・レゲエを聴き続けてきた僕にとっても衝撃的なものだったし、自由奔放なリズム・パターンやアンサンブルは──アフリカのブルンディ・ドラムやブラジルのアフロ・ブロコを連想させても──少なくとも東京のクラブでは経験したことのないものだった。 『ぞめき壱 高円寺阿波おどり』のプロデューサー、久保田麻琴は僕がここ一〇年のうちに出会った日本人のなかでもっとも影響を受けた人物である。七〇年代から活動を続けてきた彼は、言うまでもなく日本屈指のワールド・ミュージック系プロデューサーであり、七〇年代からトレンドセッターであり続けている(僕からしてみると、紛れもない)怪物。だが、彼が日本のフォークロアに対して意識的になったのは21世紀に入ってからであり、いくつかの体験を経て〈耳が開いていった〉と言う。〈耳が開く〉。一〇代の頃から英米のポップ・カルチャーに浸かり、かつてはニューヨークやロンドンに対して狂おしいほどの憧れを持っていた僕に、その言葉はズシリと響いた。 初めて体験した高円寺の阿波おどりに渦巻いていたヴァイブレーションは、一言で言って想像以上だった。見慣れた高円寺の街中に数えきれないぐらいの連が溢れ、町中に太鼓の重低音と鉦の高音が鳴り響く。久保田プロデュースのコンピレーションを聴いて免疫ができているつもりだったが、いくつかの連が作り出すグルーヴは日本のフォークロアに対する僕の先入観を激しく揺さぶった。町とビートが共振するその光景は、アフロ・ブロコの轟音が鳴り響くブラジルはサルヴァドールの日常と何ら変わらない。祭りの最後には、高円寺駅から青梅街道方面に伸びるメインストリートにすべての連が集結するのだが、その圧倒的な祝祭空間に僕は震えた。その感覚は、キングストンのサウンドシステムやトリニダード・トバゴのカーニヴァルで感じたものともよく似ていた。 その翌週に開催されたすみだ錦糸町河内音頭大盆踊りもまた、僕の耳を開くきっかけとなった。それまで河内音頭に興味を持ったことはなかったが、月乃家小菊の“気持ちヨホホイホイ”という風変わりな曲が僕の意識を変えた。いや、厳密に言うと、ハメられたのはスティーヴン・スタンレーというジャマイカのベテラン・エンジニアによる同曲のダブ・ヴァージョンのほう。まったりとした音頭をスティーヴンがギタギタにダブミックスした、なんとも過激で個性豊かなそのダブ・ヴァージョンは、東京のアンダーグラウンド・クラブではちょっとした話題になっていた。僕にしても、以前から敬愛していたスティーヴン・スタンレーが関わっていなければその曲が入ったCDを手にすることもなかっただろうが、その不思議なグルーヴは、根っからのレゲエ好きである僕のツボを憎いぐらいに突いてきたのだった。ただし、“気持ちヨホホイホイ”は河内音頭ではなく、河内音頭との関係も深い江州(ごうしゅう)音頭の楽曲。そのときの僕はそんなことも分かっていなかったけれど、無性に胸が騒ぐものがあったのである。 阿波おどりがカーニヴァルだとすれば、河内音頭はサウンドシステムだ。前者は町全体をジャックするが、後者はひとつの場にエネルギーの渦を作り出す。錦糸町河内音頭大盆踊りの会場は、首都高の高架下に広がる広場。その構造上、櫓を回る通常の盆踊りスタイルではなく、ステージを組んだコンサートに近い形式で行なわれる。広場の後方はダンス・スペースとなっていて、踊り手たちは輪になってグルグルと回り続ける。先述したラ・プラッサ・デ・ラ・パスの光景を観て、僕はすぐさまこの錦糸町の踊りの輪を想起したのだった。 二〇一〇年に高円寺と錦糸町で体験した2つの夏祭りによって、日本のフォークロアに対する僕の偏見はいとも容易く溶解してしまった。世界各地で体験してきたエネルギー渦巻く音楽の場というものが、自宅からもそう遠くない東京の片隅にあったことをそのとき初めて知ったのである。それは簡単に言えばカルチャーショックのようなもので、大袈裟に言うならば自分のアイデンティティーを揺さぶるものでもあった。*
僕はその後コロンビアのカルナバルに触れ、タガンガのゲストハウスでハンモックに揺れている間にあの忌まわしい3・11が起きた。旅から帰国した僕は、いくつかの縁があって日本各地へと足を運んだ。新潟、金沢、京都、大阪、徳島、山口。東京生まれ・埼玉育ちの僕は、関東以外の地域のことをあまり知らない。そんな僕にとって、この二〇一一年夏の旅は“ディスカヴァー・ジャパン”の旅でもあった。各地の仲間たちと酒を酌み交わし、原発やこれからの日本について話した。そして、僕の知らない日本があることを彼らに教えてもらったのだった。 一〇代の頃、ニューヨークかロンドンへの移住を結構本気で考えたこともあった。三〇代になり、それなりに世界の成り立ちを知ってからも、移住するならばイタリアのナポリかチリのサンチアゴか?などと夢見ていたし、正直なところ、何かのきっかけさえあれば日本を脱出したって構わないと思ってきた。だが、僕は今のところ、放射能が降り注ぐ東京に留まり続けている。その理由のひとつには、東京を離れてもなお現在の仕事を続けるメドが立たなかったこともあるし、もうひとつには、日本という国に対して今まで感じたことのない感情を感じつつあることも影響している。それを愛国心などと言うべきではないかもしれないけれど、少なくとも愛着とは言えるのだろう。そして、その感情は日本のフォークロアに対する好奇心と少しずつ結びついていった。 気づけば、僕はレゲエやクンビアのシングルを買い集めるように民謡の7インチ・シングルをコレクションするようになっていた。二年前までの僕には想像もできなかったであろう展開である。そして、無意識に集めていたそれらのレコードのうち、およそ半分が東北地方に伝わるものだった。これまた全然知らなかったのだが、東北は民謡の一大産地だったのだ。 そうして集めたシングルのうち、津波で大きな被害を受けた福島県相馬地方に伝わる「相馬盆唄」は特に僕の心を打った。伸び伸びとしたメロディーには南米のフォルクローレと同じように人々の生活が刻み込まれていて、大らかなリズムには70年代のルーツ・レゲエのようなウネリがあった。歌詞はこんな感じだ。ハァイヨー今年ゃ豊年だよ/穂に穂が咲いてヨ/ハァ道の小草にも/ヤレサ米がなるヨ/ハァイヨーそろたそろたヨ/踊子がそろたヨ/ハァ秋の出穂より/ヤレサよくそろたヨ豊作を祝う歌詞のなかには、相馬の人々の日常が描かれている。米どころである相馬の豊かな秋。それは相馬のコミュニティーを描写したものであり、人と人の繋がりを歌ったものである。津波と放射能は、そのすべてを奪い去っていってしまった。相馬ではこの「相馬盆唄」以外にも「相馬流れ山」や「新相馬節」「相馬二編返し」など数多くの民謡が歌われてきたが、そのなかでどれだけの歌が3・11以降失われていってしまうのだろうか。そのことを考えると、新米民謡リスナーである僕の心は痛んだ。 高速バスや新幹線で日本各地を移動する際、窓の外にはいつも青々とした水田が広がっていた。モロッコを旅していたとき、僕の目にはいつも乾燥した大地が映っていたし、南仏ではヒマワリ畑が、ペルーではアンデス山脈が映っていた。それらの風景がそれぞれの国を象徴するイメージだとすれば、日本の場合は青々とした水田がそれにあたるはずで、煌々と輝くネオンサインや高層ビルはその一部でしかない。そんな風景を見つめながら、広大な水田を大津波が次々に呑み込んでいくニュース映像を僕は思い出していた。 人々の生活。暮らし。絆。現在の日本ではそれがズタズタに切り裂かれようとしている。いくつかの出会いと体験をきっかけにして日本という国そのものに対して〈心が開いた〉僕は、それを繋ぎ合わせるヒントがこの国のフォークロアにあるような気がしている。まだひどく曖昧なイメージではあるけれど、決して漠然としたナショナリズムに繋がるものではなく、より根源的な野性や無意識を刺激する“何か”がそこにはあるのではないか──。 こうして、日本のフォークロアを巡る僕の旅が始まった。