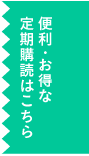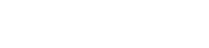カメラを携えて“音楽の発火点”を求める旅は、東西間の「壁」が崩れる直前、1989年初頭のベルリンに始まり、パリ、 キューバ、エルサレム〜ガザ地区へ、さらにシリア、ダブリンへと続く。

PROFILE
石田昌隆
フォトグラファー
いしだ・まさたか:フォトグラファー。1958年、千葉県生まれ。“音楽の発火点”を求めて、これまでに世界50ヵ国以上を旅している。著書に『ソウル・フラワー・ユニオン 解き放つ唄の轍』(河出書房新社、2014)、『オルタナティヴ・ミュージック』(ミュージック・マガジン、2009)、『黒いグルーヴ』(青弓社、1999)がある。CDジャケットの撮影も多数。
第1回 ベルリンの壁が崩壊して、U2は『アクトン・ベイビー』を作り、タラフ・ドゥ・ハイドゥークスは西欧に登場した。
[caption id="attachment_709" align="alignnone" width="500" class="full"] 西ベルリン側から見たベルリンの壁。右奥に監視塔が見える。壁を越えて亡命しようとして命を落とした人は、少なくとも一三六人。最後の犠牲者は、八九年二月六日に壁を越えようとして射殺された二一歳の青年だった。八九年一月七日に撮影。[/caption]
西ベルリン側から見たベルリンの壁。右奥に監視塔が見える。壁を越えて亡命しようとして命を落とした人は、少なくとも一三六人。最後の犠牲者は、八九年二月六日に壁を越えようとして射殺された二一歳の青年だった。八九年一月七日に撮影。[/caption]
 ルーマニアのクレジャニ村で、〇〇年一二月二六日に撮影したタラフ・ドゥ・ハイドゥークス。一番前でヴァイオリンを弾いているのは、今は亡きニコラエ爺さん。〈独裁者のバラード(Balada Conducatorolui)〉という曲で「(チャウシェスクが失脚した八九年一二月)二二日という日に生きた時間が戻ってきた」と歌った。[/caption]
ルーマニアのクレジャニ村で、〇〇年一二月二六日に撮影したタラフ・ドゥ・ハイドゥークス。一番前でヴァイオリンを弾いているのは、今は亡きニコラエ爺さん。〈独裁者のバラード(Balada Conducatorolui)〉という曲で「(チャウシェスクが失脚した八九年一二月)二二日という日に生きた時間が戻ってきた」と歌った。[/caption]
 西ベルリン側から見たベルリンの壁。右奥に監視塔が見える。壁を越えて亡命しようとして命を落とした人は、少なくとも一三六人。最後の犠牲者は、八九年二月六日に壁を越えようとして射殺された二一歳の青年だった。八九年一月七日に撮影。[/caption]
西ベルリン側から見たベルリンの壁。右奥に監視塔が見える。壁を越えて亡命しようとして命を落とした人は、少なくとも一三六人。最後の犠牲者は、八九年二月六日に壁を越えようとして射殺された二一歳の青年だった。八九年一月七日に撮影。[/caption]
一九八九年一月 東西ベルリン~プラハ
八九年一月二日の夕刻、ぼくはアエロフロート機でベルリンに降り立った。 航空券にも、モスクワで乗り換えたときの空港の案内板にも、行き先は、単に「Berlin」と書いてあった。だから飛行機は西ベルリンに着くものだとばかり思っていた。様子がおかしいと気がついたのは、着陸してターミナル・ビルに入ったときである。そこはシェーネフェルト空港という、ベルリン郊外の東ドイツ領に位置している空港なのだった。 ベルリンの壁が崩壊したのは、八九年一一月九日である。この日をもって東西冷戦の終結が決定的になったわけだが、このときは、わずか一〇ヵ月後にそのような劇的変革が起こるなんて、まだ誰も予想すらしていなかった。 当時、ドイツは、西ドイツ(ドイツ連邦共和国)と東ドイツ(ドイツ民主共和国)に分断されていた。そして、ベルリンもまた壁を隔てて東西に分断されていた。 しかしベルリンは、東西ドイツの国境線上に位置していたわけではない。東ドイツのほぼ真ん中に位置する大都市だった。つまり西ベルリンは、東ベルリンに隣接しているということ以前に、東ドイツの中にすっぽり入っている西ドイツの飛び地のような場所だった。 入国審査で、パスポートに東ドイツのトランジット・ヴィザのスタンプが押された。速やかに第三国へ出国しなければならないという意味だ。 すでに、とっぷりと闇に包まれていた。シェーネフェルト空港の外に出ると、広場を突っきった先に鉄道の駅があった。とにかく一刻も早く西ベルリンに入ってホテルを探さなくては、という思いに駆られていた。 西ベルリンには我々と価値観を共有する自由主義陣営の人々が住んでいる。しかし東ベルリンとその背後に広がる共産圏の国の人々は、些細なことで密告され、秘密警察の拷問を受け、粛正されてしまうのではないかという恐怖に怯えながら、古びたアパートのなかで息を潜めて暮らしている。そんなイメージがまとわりついていた時代である。 ところが駅へ行ってみると、西ベルリンとは逆方向の、チェコスロバキアのプラハへと向かう夜行列車がほどなくやって来ることに気がついた。シェーネフェルトはベルリンの南側の郊外に位置していて、そこはベルリンからプラハへと向かう国際列車が最初に止まる駅でもあった。 ベルリンに行くついでに、場合によってはプラハへも行けるようにと、チェコスロバキアのヴィザは取得しておいた。「プラハの春」の時代を描いた映画『存在の耐えられない軽さ』(八八年。フィリップ・カウフマン監督。原作は八四年にミラン・クンデラが書いた同名の小説)を見て、いつか行ってみたいと思っていたのだ。 この際いきなりプラハに行ってみようと思いたち、切符を買おうとした。しかし外国人は、長距離の切符はライゼビューローという国営旅行社で買うことが原則になっていて、駅では売ってもらえなかった。それでも、ヨーロッパの駅では普通のことだが、切符を持っていなくてもプラットホームに入ることはできる。ぼくは意を決して、その夜行列車に飛び乗った。 深夜、列車は東ドイツ南部の街、ドレスデンに滑り込んだ。第二次大戦の末期、連合軍の空爆によって一夜にして灰燼に帰した街だ。ここを発車して、まもなくチェコスロバキアとの国境へとさしかかるところで、車掌が検札にやってきた。ぼくはちょっとドキドキしていたが、列車の中で知り合った人が「この人はドレスデンから乗ってきたんですよ」と言ってくれて、わずかなお金で切符を手に入れることができた。このような場合に対処できるように、少額ドル紙幣や西ドイツのマルクを用意していたが、シェーネフェルト空港で強制両替させられた東ドイツのマルクで足りた。 翌朝プラハ本駅に降り立った。まだ夜は明けていない。夜霧のなかで中世のヨーロッパがそのまま息づいているようなプラハの街を、オレンジ色の街灯がボワッと照らし出していた。その幻想的なまでに美しい街並みのなかを、多くの人々が足早に歩いていた。彼らは出勤途中の労働者たちだった。 このときの旅行は、その後、プラハに三日間滞在してから、夜行列車で西ベルリンに行き、東ベルリンも観光して、シェーネフェルト空港からアエロフロート機に乗って一月一一日に帰国するという経過をたどった。 昭和天皇の崩御(八九年一月七日)は、東ベルリンで見たテレビのニュースで知った。帰国したら、テレビからお笑い番組が消え、コンサートやイヴェントの中止が相次ぎ、東京の中心部は警察官だらけになっていた。 そんなおり、一月一六日のことだが、普通に見ていたテレビのニュースに思いもよらない映像が流れてきて、ぼくの目は釘づけになってしまった。オレンジ色の街灯がボワッと照らし出す古い街並みのなかを、群衆が何やら叫びながら練り歩いている様子を映し出していたのである。プラハで、プラハの春以来となる民主化を求める大規模なデモが起こり、後に大統領になる劇作家のヴァーツラフ・ハヴェルを含む多数の逮捕者が出たのだった。 このニュースは、ぼくにとって二つの意味で衝撃的だった。まず、わずか二週間前に歩いていたプラハの街は穏やかな印象でまったく気づかなかったが、実際には、見えないところで民主化を求める民衆の思いがじわじわと高まっていたのだということが判った驚き。それから、プラハの春はぼくが小学校五年生のときに起こった事件だが、二一年を経て、それが最新のニュースに繋がっていたのだという驚きである。 プラハの春とは、このような事件だった。 六八年一月、チェコスロバキアで、人間の顔をした社会主義という考え方を唱えていたアレクサンドル・ドプチェクが共産党第一書記に就任した。それはチェコスロバキアに民主化への機運が芽生え始めたことを意味していたので、ソ連は不快に思った。 ドプチェクは、当時ソ連の首脳だったレオニード・ブレジネフ共産党第一書記とアレクセイ・コスイギン首相に対して「われわれの政策は基本的に社会主義であり、ソ連との友好は絶対に壊れない」と説明したが、ソ連は納得しなかった。「チェコスロバキアは、西ドイツとの国境の防衛が十分でない。西部国境はあなたがたの国境ではない。我々の国境なのだ」と応じたという(六八年七月二九日から八月一日にかけて行なわれたチェルナ会談)。 六八年八月二〇日、ソ連は大規模な軍事介入を行ない、ドプチェクは失脚した。そしてソ連の承認を得た保守派のグスターフ・フサークがチェコスロバキアの共産党第一書記に就任して、反革命分子、あるいは修正主義者とみなされた者には激しい弾圧が加えられることとなった。以来、チェコスロバキアは、再び長い沈黙の時代に入っていった。 プラハの春以来となるこのときの大規模なデモは、八九年一月一五日から二一日にかけて行なわれた。デモの名目は六九年一月一九日にソ連の侵攻および占領に抗議してヴァーツラフ広場で焼身自殺した大学生、ヤン・パラフを追悼するということだった。しかしこのとき、フサークから権力を継承してチェコスロバキア共産党書記長になっていたミロシュ・ヤケシュは、旧来の保守強硬路線を踏襲して民衆を弾圧したのである。 東ドイツでは、七一年にドイツ社会主義統一党中央委員会第一書記に就任して以来、東ドイツの最高実力者であり続けたエーリヒ・ホーネッカー国家評議会議長が、一月一八日の時点で、このような発言をしていた。 「壁の存在理由が除去されないかぎり、壁は五〇年後、一〇〇年後も存続するだろう」 ベルリンの壁の存在理由が除去されることなどありえないと、ホーネッカーは確信していたわけである。 事態が大きく動いたのは、八九年八月に「汎ヨーロッパ・ピクニック」という事件が起こったときである。ハンガリーのショプロンという地理的にオーストリア領に突き出ている町で政治集会が開かれ、その場に集まっていた千人ほどの東ドイツ市民がゾロゾロとオーストリア側に越境して、そのまま西ドイツへと集団で亡命したのだ。 このあたりから自由を求める民衆の気持ちが膨らみ、変革の機運が、あれよあれよという間に大きくなっていった。ライプツィヒや東ベルリンで大規模なデモが行なわれるようになり、ホーネッカー国家評議会議長は、一〇月一八日にすべての役職を解任された。 そしてついに、八九年一一月九日にベルリンの壁が崩壊。変革の波は、ドミノ倒しのように周辺の国々に伝わっていった。一九八九年一一月 東京
一一月二五日に、ぼくは東京ドームで〝ラヴ・カムズ・トゥ・タウン・ツアー〟と題されたU2のライヴを見た。ゲストにB・B・キングを迎えたそのライヴは、『焔』(八四年)、『ヨシュア・トゥリー』(八七年)、『魂の叫び』(八八年)とアルバムをリリースして、アメリカ音楽を探訪していた時代のU2を締めくくるに相応しい壮大なものだった。 U2はこの次のアルバム『アクトン・ベイビー』で大きな変貌を遂げるのだが、ライヴの最中に、それを予感させるシーンがあった。 どの曲を歌う時だったかは忘れてしまったが、ボノが突然、「チェコスロバキア~」と叫んだのである。 その前日、八九年一一月二四日に、ビロード革命と呼ばれることになるチェコスロバキアの民主化運動の成功を決定づける出来事があった。プラハのバーツラフ広場に集まった群衆を前にしたバルコニーに、プラハの春の立役者で、すでに老齢に達していたアレクサンドル・ドプチェクが姿を現わして健在ぶりをアピールしたのだ。その日の夜、守旧派のミロシュ・ヤケシュ書記長が辞任した。 ボノは、宿泊していたホテルオークラ東京の部屋で、このニュースを伝えるテレビを食い入るように見ていたに違いない。〝ラヴ・カムズ・トゥ・タウン・ツアー〟には似つかわしくないこの叫び声を、ぼくは今でもはっきりと覚えている。一九八九年一二月~一九九〇年一月 ブダペスト~ブカレスト
八九年一二月二一日に、ぼくは成田空港から再びアエロフロート機に乗り、モスクワのトランジット・ホテルで一泊して、翌二二日にトルコのイスタンブールへと飛んだ。それからブルガリアのソフィアを経て、ハンガリーのブタペストへと向かった。 ちょうどその頃、ルーマニアは大変なことになっていた。一二月二一日にブカレストの共産党本部のバルコニーで行なわれたニコラエ・チャウシェスクの最後の演説をきっかけに、群衆は蜂起した。翌二二日に共産党本部の屋上から逃亡するニコラエ・チャウシェスクを乗せたヘリコプターが飛び立ち、一二月二五日にチャウシェスクが処刑されたことが大々的に報道されるまでの間、ブカレスト市内で銃撃戦が起こって数多くの犠牲者が出たのだ。二四年間続いた独裁政権の末路は悲劇的だった。 九〇年一月一日の夜、ブダペスト東駅から夜行列車に乗って、ぼくはルーマニアのブカレストへと向かった。乗客はまばらで、乗っていた車両は暖房がほとんど効いていなかった。アラドからブラショフに向かう途中で夜が明けると、一面の銀世界だった。冬のトランシルヴァニア地方の風景の美しさに見とれていた。 一月二日の昼過ぎ、ブカレスト北駅に到着。まずは駅の近くでいちばん安いセカンドクラスのホテルに宿を決めた。ルーマニアのホテルはすべて国営で、デラックス、ファーストクラス、セカンドクラスとランクづけされている。宿泊した部屋は、バス、トイレ共同というのはともかく、夜中は暖房が切られ、持参した寝袋がなかったら凍死してしまいそうな寒さだった。 さっそく街の中心部に出て、共産党本部、テレビ局、大学などが集まっている一帯を歩いた。銃撃戦で多数の市民が犠牲になったところだ。市民を無差別に銃撃したのは、チャウシェスク派の秘密警察(セクリタテア)である。建物のあちこちに真新しい銃痕があり、ほとんど廃墟になったビルもあった。汚れて固まった雪の上には、銃弾の薬きょうがバラバラ落ちていた。ぼくはそれを一〇個ほど拾い、ポケットに入れた。 街のあちこちでロウソクの炎が揺れ、道ばたのところどころに花束と十字架とイコンが供えられていた。まさにそこで、銃弾に倒れた人がいたのである。ロウソクの炎を囲んで、その場で亡くなった人の遺族や友達と思われる人や通行人が入り交じって、興奮して何かを話していた。 共産党本部の前には装甲車が並んでいた。国軍はチャウシェスクから離反して、市民に銃口を向けることはなかった。 共産党本部の中にはルーマニア救国戦線のイオン・イリエスク議長がいるはずだ。チャウシェスク時代のルーマニアの国旗は、青、黄、赤の三色が縦に並び、中央に共産党の紋章が描かれていたが、共産党本部の入口の上に掲げられていた国旗は、共産党の紋章の部分を丸くくり抜いてあった。チャウシェスク時代は終わったという主張である。 要所には自警団のような人たちが配置されていて、ものものしい警備体制が敷かれていた。地下鉄に乗るときも厳しいボディー・チェックを受けなければならなかった。秘密警察の残党を見つけ出そうとしていたのだ。 ブカレストでいちばん高級なホテル、インターコンチネンタルにプレスセンターができていて、世界中から報道陣が集まっていた。チャウシェスクが処刑されてからすでに一週間経っていたが、街はまだピリピリした雰囲気に包まれていた。 それでも街の中心部にあったレコード屋が営業を再開していたので覗いてみる。輸入盤はまったく取り扱っていなくて、売っているのはすべて国営レーベル、エレクトレコード(Electrecord)のものだった。ルーマニア人によるタンゴとかインド歌謡みたいなもの、出所不明(キューバ?)の黒人グループが畑のなかに立っているジャケットのラテン音楽などもあったが、ほとんどがルーマニア音楽のレコードである。ハンガリーではローリング・ストーンズなども普通に売られていたが、西側の音楽は一切なかった。 このときぼくが知っていたルーマニア音楽のミュージシャンは、ナイというパン・フルートを奏でるゲオルグ・ザムフィル(Gheorghe Zamfir)ぐらいで、実際、巨匠らしく扱われていた。しかし一般に人気があるのは歌ものの民謡で、マリア・シオベヌ(Maria Ciobanu)、ソフィア・ヴィコヴィアンカ(Sofia Vicoveanca)などがよく売れているようだった。ジャケットを見ると二人ともけっこう綺麗なオバサンだけど、独特のちょっと怒っているような感じの歌いかたをする。ヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネット、アコーディオン、ツィンバロムなどからなるアンサンブル(オルケストラ)がバックを務めている。このときはまだ、ルーマニアにジプシー音楽が存在することをまったく知らなかった。 一月四日になると、突然、自警団によるボディー・チェックはなくなり、ピリピリした状態は収束した。ルーマニア革命の真相は未だにナゾが多いのだが、とにかくこの日を境に、市民の間には革命に勝利したという安堵感が広まった。 そしてこの日から、街のあちこちでカオマの〈ランバダ〉が大音量で流れだした。レコード屋では西側の音楽はまったく売っていなかったが、ダビングにダビングを重ねた〈ランバダ〉のカセット・テープは密かに出回っていたのである。 このときの旅行の記憶は〈ランバダ〉と切り離すことができない。日本でも同じ頃、ちょっと下品でエッチなダンス・ミュージックとして〈ランバダ〉が流行していた。しかしルーマニアでは、カオマの〈ランバダ〉は、ニコラエ・チャウシェスクの圧政から解放された民衆の歓喜を表す歌として流れていたのだった。 この後、ヴァーツラフ・ハヴェルが大統領に就任した(八九年一二月二九日)ばかりでビロード革命の熱気に沸いていたプラハ、壁が崩壊してブランデンブルク門からも東西を行き来できるようになっていたベルリンへと旅行を続けた。 U2は、東西ドイツが統合した日、九〇年一〇月三日にベルリンに入り、ハンザ・スタジオで『アクトン・ベイビー』のレコーディングを開始した。 九一年は湾岸戦争の勃発で幕を開けた年で、CNNが連日、テレビ・ゲームのような戦争を実況中継していた。『アクトン・ベイビー』が完成してリリースされたのは九一年一一月。このアルバムには、ベルリンの壁の崩壊以後の混沌とした世界観が深く投影されていた。 一曲めに収録された〈ズー・ステーション〉は、既存のU2の音楽とはかけ離れていた。ノイジーなギターと金属質なリズムの奥で奇妙に歪んだヴォーカルが被さってくる。ズー・ステーションとは、西ベルリンの繁華街、クーダムに近い駅である。ベルリンの壁が崩壊したとき、東ベルリンの若者たちが、目と鼻の先にあった自由と豊かな物質を享受するために真っ先に駆けつけたところだ。 三曲めの〈ワン〉は、いかにもU2らしい壮大な曲で、アントン・コービンによるMVには、東ドイツを象徴する車、トラバントが登場してくる。トラバントの写真はブックレットの中にも何枚も出てくるが、とりわけ、タヘレスという、第二次大戦末期に空爆で建物の半分が破壊されたデパートがそのまま置き去りにされていた廃墟といっしょに写っている写真は、東ベルリンのどんよりした空気を伝えていた。 ソ連でゴルバチョフ大統領が辞任して、連邦が崩壊したのは『アクトン・ベイビー』が出た翌月、九一年一二月のことである。二〇〇〇年一二月 ブカレスト~クレジャニ
二〇〇〇年一二月一〇日、アエロフロート機でブカレストに降り立った。ほぼ一一年ぶりのルーマニアである。ジプシーのバンド、タラフ・ドゥ・ハイドゥークスを撮影するために再訪したのだった。 ベルリンの壁が崩壊して、音楽はいかに変容したか。ぼくはそのことについて考え続けていた。 タラフ・ドゥ・ハイドゥークスを〝発見〟したのは、ステファン・カロというベルギー人だ。八八年にフランスのオコラから、後にタラフ・ドゥ・ハイドゥークスのメンバーとなるラウターリ(ジプシーの楽師)による演奏が収録されたレコードが出た。それを聴いたステファンは、チャウシェスク政権下のルーマニアを訪ねた。そしてラウターリが多く住むクレジャニ村を探し当てて彼らに接したのだった。ステファンは、村を出るとき車からふりかえって、子供が追いかけてくるのを見て思った。彼らは海外に進出すべきだ。有名になれるはずだと。でもそのときは何かをなす術はなかった。ところが八九年一二月に、多くの民衆の血と引き替えにチャウシェスク政権は崩壊した。そのときステファンは、今週中にでも行かなくてはと思った。そして旧知の友人、ミッシェル・ウィンターとルーマニアに向かった。ぼくがブカレストを訪ねていた、まさにその頃の話である。 ステファン・カロとミッシェル・ウィンターの尽力で、クレジャニ村のラウターリたちはタラフ・ドゥ・ハイドゥークスとして西欧に売り出された。それは、ベルリンの壁の崩壊とドミノ倒しのように波及した東欧の民主化という歴史と密接に関連していた。 タラフ・ドゥ・ハイドゥークスは、トニー・ガトリフ監督の映画『ラッチョ・ドローム』(九三年)に出演したころから西欧で人気が出てくるようになったが、ジプシーへの差別意識が強いルーマニア本国では表立った活動はできなかった。しかし西欧での人気から逆輸入されるように認められて、二〇〇〇年一二月一四日と一五日にブカレストのホールで初めてコンサートを行なった。ぼくはそれを撮影して、一二月一六日と一七日にクレジャニ村に彼らを訪ねた。このとき撮影した写真が『バンド・オブ・ジプシーズ』(〇一年)のジャケットに採用され、ヨーロッパではクラムド・ディスク、アメリカではノンサッチ、日本ではワーナーからリリースされた。 [caption id="attachment_711" align="alignnone" width="500"] ルーマニアのクレジャニ村で、〇〇年一二月二六日に撮影したタラフ・ドゥ・ハイドゥークス。一番前でヴァイオリンを弾いているのは、今は亡きニコラエ爺さん。〈独裁者のバラード(Balada Conducatorolui)〉という曲で「(チャウシェスクが失脚した八九年一二月)二二日という日に生きた時間が戻ってきた」と歌った。[/caption]
ルーマニアのクレジャニ村で、〇〇年一二月二六日に撮影したタラフ・ドゥ・ハイドゥークス。一番前でヴァイオリンを弾いているのは、今は亡きニコラエ爺さん。〈独裁者のバラード(Balada Conducatorolui)〉という曲で「(チャウシェスクが失脚した八九年一二月)二二日という日に生きた時間が戻ってきた」と歌った。[/caption]
*
ということで、今回は、ベルリンの壁が崩壊して、U2は『アクトン・ベイビー』を作り、タラフ・ドゥ・ハイドゥークスは西欧社会にデビューすることができたという話で誌面がつきた。でもこれは、ベルリンの壁が崩壊したことと音楽の関連を示すふたつの例にすぎない。話はまだ延々と続くので、次回以降もぜひお付き合いください。第2回 ワールド・ミュージックとは、非西欧圏のミュージシャンが 西欧の都市に出てくることによってスパークする火花のような音楽だった。
[caption id="attachment_888" align="alignnone" width="500"] マヌ・チャオが率いていたバンド、マノ・ネグラ。モロッコのシャアビ(大衆歌謡)のカヴァーを含む代表作『Puta's Fever』をリリースした直後のツアーのとき。90年1月17日にロワール川沿いの街、オルレアンで撮影。[/caption]
マヌ・チャオが率いていたバンド、マノ・ネグラ。モロッコのシャアビ(大衆歌謡)のカヴァーを含む代表作『Puta's Fever』をリリースした直後のツアーのとき。90年1月17日にロワール川沿いの街、オルレアンで撮影。[/caption]
 ユッスー・ンドゥール。ベルリンの壁の崩壊によって、東西冷戦という二項対立の時代から、プルーラリズム(多元主義)の時代に移行した。ちょうどその頃、存在感を増してきた。90年1月20日にカンヌで撮影。[/caption]
ユッスー・ンドゥール。ベルリンの壁の崩壊によって、東西冷戦という二項対立の時代から、プルーラリズム(多元主義)の時代に移行した。ちょうどその頃、存在感を増してきた。90年1月20日にカンヌで撮影。[/caption]
 マヌ・チャオが率いていたバンド、マノ・ネグラ。モロッコのシャアビ(大衆歌謡)のカヴァーを含む代表作『Puta's Fever』をリリースした直後のツアーのとき。90年1月17日にロワール川沿いの街、オルレアンで撮影。[/caption]
マヌ・チャオが率いていたバンド、マノ・ネグラ。モロッコのシャアビ(大衆歌謡)のカヴァーを含む代表作『Puta's Fever』をリリースした直後のツアーのとき。90年1月17日にロワール川沿いの街、オルレアンで撮影。[/caption]
一九八九年九月二三日 パリ〜ロンドン
八九年九月二三日の夜、ロンドンのヴィクトリア・コーチ・ステーションから、パリ行きの夜行バスに乗った。バスは日本と同じく右ハンドル、左側通行の道を走り、深夜、海峡の港町、ドーヴァーに着く。そこでバスごとフェリーに乗り込んだ。 フェリーが航行している間はキャビンに移動して時間を過ごす。ぼくはカフェテリアに行き、スライ&ロビーにサポートされたレゲエのコーラス・トリオ、ブラック・ウフルーの『アンセム』というアルバムのライナーを書いていた。八四年にアイランドからレコードでリリースされた音源に一曲追加したものが八九年にCD化されたのである。八四年にロンドンのレゲエ・サンスプラッシュで『アンセム』収録曲を歌ったブラック・ウフルーを撮影した。そのときの感覚をたぐり寄せながら書いていたのだが、没頭するあまり、フェリーがフランス側の港町、カレイに着いたとき、バスに戻るのが微妙に遅れてしまった。すると、乗っていたバスはすでにパリに向かって走り去っていたのだった。 ロンドンからパリへの夜行バスは客の数に応じて複数台出る。後続のバスがまだフェリーの中にいたので運転手に事情を話したら乗せてもらえた。バスはフランスに入ると右側通行の道をひた走り、朝、パリに着いた。ターミナルは北東部の郊外、ポルト・ドゥ・ラ・ヴィレットにあった。到着すると、運転手はトランクから乗客の荷物をばんばん降ろして行ってしまう。乗客たちは自分の荷物を間髪入れずに確保する。本来ぼくが乗っていたはずのバスは、同じ場所に一〇分前ぐらいに着いたはずだ。しかし同じようにトランクから降ろされたであろうぼくの荷物、ミレーの黄色いバックパックはどこにもなかった。 このときが初めてのパリである。現金やパスポート類、標準レンズつきのカメラ一台だけは持ち歩いていたので助かったが、いきなり手ぶらに近い状態になってしまった。警察署に行って盗難証明書を書いてもらって、メトロでパリ一八区のほうに向かい、PLクリシーでモダン・ホテルという安宿に部屋を見つけた。バックパックに入れてあったカメラ機材を失ったことによる金銭的ダメージは小さくないが、歯磨きや最低限の着替えを買い、ライナーを仕上げてファックスで送り、街を歩いて一台のカメラで写真を撮ればよいわけである。そう思うと、さばさばした気持ちになった。 パリ一八区といえば、サクレ・クール寺院があるモンマルトルの丘や、キャバレー、ムーラン・ルージュがあるピガール界隈の歓楽街が有名だが、道一本隔てるだけで、風景はがらりと変わる。メトロをバルベス・ロッシュシュアール駅で降りて、ガードの北側に出て、バルベス通りの東側に位置する一帯を歩けば、そこはもう、本当にパリなのかと思うほど、アルジェリア、チュニジア、モロッコなど、マグレブの国から移民してきたアラブ人やカビール人の街になっていた。 バルベスのカフェではオヤジたちがドミノに興じていた。近くに寄ってしばらく眺めていると、こっちを見る。ぼくは眉毛を動かして挨拶する。道行く女性にはスカーフを被っている人がけっこういた。 クスクスを食べたり、ミント・ティーを飲んで異郷の雰囲気に接したり、ライやシャアビなどアラブ音楽を売るカセット屋に入って、推薦してもらったカセットを適当に買ってみたりした。 アフリカ系の黒人もよく見かけた。ザイロワ(ザイール人。現コンゴ民主共和国人)はなんとなく判る。「ンボテ・ミンギ(いっぱい、こんにちは)」と、唯一知っているリンガラ語の挨拶をしてみる。 ほとんどの時間を一八区で過ごしたのだが、パリ中心部、ポンピドー・センターやレ・アールのフナック(大型CD店と家電量販店を合わせたようなチェーン店)などには行ってみた。フナックにはワールド・ミュージックのCDもたくさん売られていたが、バルベスのカセット屋に売っているようなアラブ人社会向けのローカルな音楽は見あたらなかった。バルベスとレ・アールはメトロでわずか七駅の距離だけど別世界である。 ピガールの街角で、フランスパンにはさんだドネル・ケバブを売っていた。フランスと移民文化が折衷したようなこの食べ物は、ワールド・ミュージックに似た発想だと思った。 初めてのパリはわずか二泊三日の滞在で、凱旋門やエッフェル塔は遠目に見ることさえなく、帰路も夜行バスでロンドンへと向かったのだった。 ロンドンは、西部のサウソールがインド/パキスタン人街になっている。テムズ川南岸のブリクストンはジャマイカ人街になっている。 サウソールでは、七九年に反人種差別デモに参加していたブレア・ピーチという男性教諭が警官に襲われて死亡する事件が起こった。ブリクストンでは、八一年に大規模な暴動が起こった。在英ジャマイカ人ミュージシャン/詩人のリントン・クウェシ・ジョンソンは、アルバム『Bass Culture』(八〇年)に収録されている〈Regga Fi Peach〉でブレア・ピーチについて歌い、『Making History』(八四年)に収録されている〈Di Great Insohreckshan〉で八一年のブリクストン暴動について歌った。 イギリスではその後も、八五年、九五年、二〇一一年に暴動が起こったが、移民と国家との軋轢が顕在化する転換点は、七〇年代末から八〇年代前半にあったと思う。 イギリスではジャマイカ本国よりも人気があったブラック・ウフルーが『アンセム』で〈Solidarity〉という曲を歌っていたのも、この時代の世相を反映している。 一方フランスでは、〇五年に、パリ北東部の郊外、セーヌ=サン=ドニ県で、警察に追われたチュニジア系の少年とマリ系の少年が変電所に逃げ込み、感電死した事件をきっかけに大規模な暴動が起こったわけだが、この暴動に繋がる原点と言える事件が、ぼくが初めてパリに行ったのとちょうど同じ時期に起こっていた。 八九年九月、パリの北に位置するオワーズ県クレイユの公立中学で、フランスで生まれたモロッコ系とチュニジア系の女子生徒が教室でスカーフを外すことを拒否したため退学させられる事件が発生した。モスリムの女子生徒が教室でスカーフを着用したまま授業を受けるというのは、それまでは普通に行われていて、特に問題視されるようなことではなかったという。宗教を学校に持ち込むことの是非とか、スカーフは女性を抑圧している象徴だとか、さまざまな理由づけがなされたが、この事件が大きく注目されたのは、この時期に移民と国家との軋轢が顕在化し始めたからにほかならない。 フランス国内で最も多い移民はアルジェリア系である。イギリスで最も多いのは南アジア(インド/パキスタンなど)系だが、次いで多いのはジャマイカ系だ。フランスとアルジェリア、イギリスとジャマイカは、それぞれ旧宗主国と旧植民地の関係であり、両国とも六二年に独立した。 フランスにおける移民の比率は、INSEE(フランス国立統計経済研究所)のデータによれば、九九年には七・四%だったが、暴動が起こった〇五年には八・一%に上がっていた。しかし意外なことに、六〇年代には高度経済成長を支える労働力として移民が増えたが、七五年から九九年までは七・四%のままで変化していない。イギリスにおける移民の比率はONS(イギリス国家統計局)のデータによれば戦後一貫して右肩上がりで増えている。フランスで移民と国家との軋轢が顕在化するのがイギリスより遅かったのは、そのためかもしれない。 それでも、八九年が転換点となったことに注目しないわけにいかない。なぜなら、八九年は、ベルリンの壁が崩壊した年であり、ワールド・ミュージックという概念が浸透した年でもあるからだ。 ベルリンの壁の崩壊によって、東西冷戦という二項対立の時代から、プルーラリズム(多元主義)の時代に移行した。それは新たな民族紛争の時代の幕開けにもなってしまったが、まさにそのタイミングでワールド・ミュージックという概念が実態を持ったことについて、ぼくは考え続けている。 〝ワールド・ミュージック〟という言葉は、八七年六月二九日にイギリスで生まれた。日付まではっきりしているのは音楽業界の関係者が集まった会議で決まった言葉だからだ。レゲエやサンバなどと違っていかにもマーケティング用語の匂いがして好きになれない言葉だったし、日本でよく使われていた〝パリ発ワールド・ミュージック〟という言葉はさらに胡散臭く響いた。 その一方で、セネガルのユッスー・ンドゥール、マリのサリフ・ケイタ、アルジェリアのシェブ・ハレドらがパリで活動することにより、パリという街の構造が見え、ワールド・ミュージックという音楽の実態が伝わってくるようになってきたのである。一九九〇年一月一三日 パリ〜オルレアン〜カンヌ
二回めにパリに行ったのは、九〇年一月一三日。前夜にアムステルダムから夜行バスに乗り、朝、ポルト・ドゥ・ラ・ヴィレットのバス・ターミナルに到着。メトロで二〇区へ向かい、ベルヴィルでホテル・アトラスという安宿に部屋を見つけた。このあたりはベトナムや中国からの移民が多い。 一月一六日に、パリの南一二〇キロのところに位置するロワール川沿いの街、オルレアンに行き、マヌ・チャオが率いていたバンド、マノ・ネグラのライヴを見た。代表曲〈King Kong Five〉やモロッコのシャアビ〈Sidi H’bibi〉のカヴァーを含む『Puta’s Fever』(八九年)のリリースに伴うツアーの最中だった。 マヌ・チャオは、フランコ独裁下のスペインからパリに逃れてきたガリシア人の父とバスク人の母のもとで生まれた。非西欧圏からの移民ではないし、マノ・ネグラの音楽はパンクやレゲエの要素も強かったので、ワールド・ミュージックというより、ワールド・ミュージックに対するフランスからの返答と言ってもよかったが、この時代ならではのミクスチャーで、ライヴは圧倒的なパフォーマンスだった。 翌朝、彼らが泊まっていたホテルに行き、駐車場でグループ・ショットを撮らせてもらった。 それからすぐ鉄道でパリに戻り、ワールド・ミュージックのレーベル、コバルトの事務所に行き、所属アーティストのうち、ハイチの女性歌手エムリーヌ・ミッシェル、ギニアの女性歌手ジャンカ・ジャバテ、マリのソリ・バンバらを撮影した。ぼくは未だにマリやギニアに行ったことはないが、ハイチはこの一四年後、〇三年の暮れから〇四年の年明けにかけて訪ねた。そのときエムリーヌ・ミッシェルの故郷、ゴナイーヴにも行き、ジャマイカの首都キングストンのゲットー、トレンチタウンをもっと貧しくしたような生活ぶりに衝撃を受けた。ワールド・ミュージックは、遠くで聴いていればエキゾチックな音楽だが、移民街のあるパリではリアルな都市の音楽であることを実感する。しかし彼らの故郷まで遡って行ってみれば、同胞たちの多くには手の届かないパリでの生活によって得た意識が刻み込まれている音楽なのかもしれない。 一月一九日、パリ一八区、ピガールにある劇場、ラ・シガールでレ・ネグレス・ヴェルトのライヴを見た。デビュー作『Mlah』(八八年)に収録されているフラメンコや東欧のジプシー音楽を織り交ぜたメランコリックな旋律の曲に引き込まれた。ヴォーカルのエルノは前歯が一本欠けていて、酔っぱらいのようにふらふら歩きながら歌う。この時代に一瞬だけ存在した美しい音楽である。終演後、楽屋で集合写真を撮らせてもらった。 一月二〇日。高速列車TGVでカンヌへ。映画祭でおなじみの地中海に面した町だ。パリより物価が高くてびっくりした。 翌二一日、コンベンション・センターで行われているMIDEM(国際音楽産業見本市)へ行く。業界人ばかりだし、こういう場所で音楽の存在理由に触れることはできないが、どうしても撮りたいミュージシャンが来ているのだ。 楽屋へ入っていくと、一ヵ月ちょっと前、八九年一二月一四日に渋谷クラブ・クアトロで撮影したばかりのマハラティーニ&ザ・マホテラ・クイーンズがいたので挨拶した。その先に、お目当てのユッスー・ンドゥールがひょろっと佇んでいた。『ザ・ライオン』(八九年)が出て『セット』(九〇年)が出る前という、ワールド・ミュージックの絶頂期と言ってよいタイミングである。 その晩、カンヌからクシェット(寝台車)に乗って、一月二二日の朝、パリに戻った。この日は、パリ東駅のメトロに通じる通路で、レ・ネグレス・ヴェルトのエルノ、マノ・ネグラのガルバンシートらを含むミュージシャンたちが集まってバスキングをするというので駆けつけたのだ。 そして一月二五日にシャルル・ド・ゴール空港からアエロフロート機に搭乗して帰国した。 [caption id="attachment_889" align="alignnone" width="500"] ユッスー・ンドゥール。ベルリンの壁の崩壊によって、東西冷戦という二項対立の時代から、プルーラリズム(多元主義)の時代に移行した。ちょうどその頃、存在感を増してきた。90年1月20日にカンヌで撮影。[/caption]
ユッスー・ンドゥール。ベルリンの壁の崩壊によって、東西冷戦という二項対立の時代から、プルーラリズム(多元主義)の時代に移行した。ちょうどその頃、存在感を増してきた。90年1月20日にカンヌで撮影。[/caption]
一九九〇年一一〜一二月 パリ
三回めのパリは、九〇年一一月二一日から二六日まで。ファンハウスから出た『Kiss me again 世界でいちばん美しい』(九一年)というレーザーディスクのジャケット撮影の仕事だったので、シンプルに成田から飛行機で往復。パッシー・エッフェルというホテルに泊まり、初めてエッフェル塔を見た。パリの街角でカップルがキスしている写真を撮るために、オーディションでモデルを選び、ロケハンして、スタッフを乗せたロケバスで撮影に向かうというスタイルだ。ぼくの主張が通り、ロケはバルベスからモンマルトルの一帯で敢行することになった。移民がいるからではなく、古びたアパルトマンが建ち並んでいる感じとか壁の質感とかがフォトジェニックだったからである。 この滞在中、一一月二三日の夜、ひとり抜け出してピガールのラ・シガールに行った。レ・テット・ブリューレという、独特のボディ・ペインティングを施してカメルーンの音楽ビクツィ・ロックを演奏するバンドのグループ・ショットを、レ・ネグレス・ヴェルトのときと同じく床がタイルの楽屋で撮らせてもらった。この日のもうひとりの出演者、フランスの海外県グアドループ出身のダンスホール・レゲエのDJ、キング・ダディー・ヨードの写真も撮った。パリは生牡蠣が美味しかった。 その翌月、九〇年一二月二二日の朝、フランクフルトからの夜行列車でパリ東駅に到着した。四回めのパリである。ベルヴィルのホテル・アトラスに投宿した。 さっそくバルべスに行くと、ピガールへと向かう道路に挟まれた普段は何もないところに、メリーゴーランドとか射的のテントとか、妖しい彩りの電飾に包まれた建物がいくつも特設されて、縁日のような賑わいを見せていた。プロレスのテントがあったので中に入り、覆面レスラーの写真を撮った。モンマルトルに登ってゆく坂道には豆電球が飾られていて、七面鳥がたくさんぶらさがっている肉屋の軒先と、バンパーがくっつくように路上駐車している車の列のわずかな隙間を、タチ・デパートの袋を持った買物客などが忙しく歩きまわっていた。クリスマスが間近なのである。 しかし、バルべスのアラブ人街のほうにはクリスマスらしい雰囲気はなかった。色彩の乏しい雑踏に、爪切とかビニール鞄などを売っている露店や、魔法の水だという怪しげな液体を売っている香具師、路上のサイコロ賭博などが出没していた。そこをいつもと同じようにマグレブからの移民たちが行き交い、肉屋はいつものようにマトンのハラル肉をぶらさげていたのだった。 ピガールのほうに行ってみたら、九〇年八月にパルコのポスターの撮影で行ったチェコのプラハで出会ったトーゴ人留学生とばったり出くわして互いに驚いた。 このあと、マルセイユ、アルジェリアのオラン、アルジェと旅行して、九一年一月七日にエールフランス機でパリに戻ってきた。 翌日の朝、ポルト・ドゥ・ラ・ヴィレットのターミナルからロンドン行きのバスに乗った。ドーヴァー海峡はすごい風が吹いていてフェリーはけっこう揺れた。午後、イギリス側のドーヴァーの港に着いたとき、フェリーは岸壁にぶつかってしまい、すこし右に傾いた。海難事故は交通事故と違って、どの程度深刻なのか判りずらい。大した事故ではないような感じだったが、なかなか下船できなかった。とりあえず飲み物は無料になるとアナウンスされたので、カフェテリアでカフェオレを飲んだ。しばらくして食物も無料になったので、チリビーンズとライスを食べ、肉入りブラウン・シチューとポテトフライを食べ、林檎ジュースとオレンジジュースを飲み、ストロベリームースを食べ、カフェオレを飲んだ。しかしいっこうに下船できなかった。夕方までにはロンドンに到着するはずだったのに、下船できたのは、深夜一時三〇分。港に着いてから一一時間後だった。下船する場所にテレビカメラが何台も来て撮影していた。ロンドンのヴィクトリア・コーチ・ステーションにバスが到着したのは夜中の三時三〇分だった。 外国に行くと、ぼくはときどき、移民としてその街に住んでいる自分の姿を想像してみる。帰りの飛行機のチケットを持って出かけているから所詮ただの旅行者にすぎないことは判っているけど、移民になった気分を想像することによって、その街に潜む物語を身近に引き寄せようとする。 ワールド・ミュージックという言葉は、現在はほとんど、単に非西欧圏の音楽全般を指す言葉になっていて、ワールド・ミュージックという概念について考える機会はなくなった。今となっては、音楽だけを聴くなら、ユッスー・ンドゥールはワールド・ミュージックの時代の作品よりセネガルにいた七九年頃の作品のほうが好きだったり、サリフ・ケイタなら、悠久の時間を感じさせるワールド・ミュージックの時代の作品より、マリのバマコやコートジヴォワールのアビジャンで活動していた八〇年代半ばまでの、アフリカの都市と一体化した音楽のほうが面白いと思ったりする。 音楽は残るけど、街の雰囲気は日々更新され、記憶は薄らいでいく。改めて振り返れば、八九年頃のワールド・ミュージックは、時代との相関関係がとりわけ強い音楽だったと思う。第3回 ソ連の崩壊とアメリカによる制裁で経済的苦境に立たされたキューバ。 九四年には多くの難民がイカダでフロリダ半島に漂着したが、その後キューバは持ち直し経済を成長させていく。
[caption id="attachment_890" align="alignnone" width="500"] ハバナの旧市街[/caption]
ハバナの旧市街[/caption]
 96年12月23日にメキシコ・シティで撮影した路上のアコーディオン弾き。右後方に見える建物は革命記念塔。キューバへ行くには、今はカナダ経由が簡単だが、当時はメキシコ経由が安かった。[/caption]
そして夜になると、ホテル・カールトンのひなびたバーは、常連らしいオジサンたちやワケありふうのオバサンたちで賑わっていた。ハス向かいの床屋の前では街灯の下にいつも娼婦が立っていて、ぼくも「オラ」と声をかけられたりしたのだが、彼女たちもよくこのバーに出入りしていた。ギターを抱えた流しのミュージシャンがふらっと入ってきたりもする。だいたい一曲一〇ペソだったが、巧い人は連続して頼まれていた。こういう場合、ランチェーラ(メキシコの歌謡曲・演歌のようなもの)っぽい曲を弾き語りで歌い上げることが多くて、それが場末の雰囲気を盛り上げるのだった。
メキシコ・シティに一週間ほど滞在して、その間に旅行代理店で、ハバナ往復の航空券と六泊分のホテルとビザの代行取得のセットを五四八ドルで手に入れた。
一九九六年一二月二五日、ついにキューバの土を踏んだ。空港の入国審査に一時間ぐらいかかり、バスで指定されたホテルへと向かう。ハバナ新市街、ベダド地区の海岸通りに面したリビエラ・ホテルに着いたのは夕方。なかなかの高級ホテルで、ここに六泊するだけで五四八ドルの価値はあるように思えた。
キューバはドルとペソの二重経済になっていた。観光客向けのドル払いのカフェではコーヒー一杯が一ドルはするけど、地元民が集まるペソ払いのカフェでは一ペソ(一ペソは約五円)以下のようである。しかし観光客がペソを手に入れても、ペソで支払う場所で何かを買ったり食べたりする機会はなかなかなく、バスとか公共交通機関に乗るのも難しそうだ。
リビエラ・ホテルの地下はパラシオ・デ・ラ・サルサというホールになっていて、着いた日にいきなり、アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのライヴを見ることができた。前座の演奏が終わって登場してきたのは深夜一時三〇分で、三時まで演奏した。しかし、若手シンガーをフロントに立てているとはいえ、この日のアダルベルト・アルバレスにはバンマスとしての威厳が足りないように見えた。客席最前列で踊っていたのはお洒落な若いキューバ人女性たちだが、観客はだいたい観光客のようだし、やや期待はずれだったという印象が残っている。アダルベルト・アルバレスは、八〇年代のキューバ音楽に息を吹き込んだ重要人物なのだが。
翌二六日はまず、タクシーでハバナ中心部の旧市街、ビエハ地区に行ってみた。古い街並みがひときわ美しいビエハ地区では、タイム・スリップしたように五〇年代のアメ車が普通に走っていた。しかしそこは観光客だらけで、みんな写真やビデオを撮りまくっていた。無遠慮に構えた観光客のカメラに、キューバ人は笑顔をふりまいている。観光客は、メキシコ、スペイン、カナダ、ベネズエラなどからの団体が多いようだった。ハバナのビエハ地区はフォトジェニックで、観光客のイメージどおりに作られたテーマ・パークのようである。治安はジャマイカなどとは比べものにならないほど良い。なんとなく出来すぎていて、違和感を抱きつつ夕方ホテルに戻ったら、隣のホテルでシンクロナイズド・スイミングのショーをやっているのが見えた。
夜一〇時過ぎ、ホテルからタクシーでカサ・デ・ラ・ムジカというライヴハウスへと向かった。エネヘ・ラ・バンダのライヴがあることを知ったのだ。
入場料は一五ドル。前座のバンドや、いかにも社会主義国っぽいサーカス芸のパフォーマンスに続き、エネヘが登場したのは夜中の一時過ぎだった。入場料をどうやって払ったのか、あるいは払わずに入ったのか知らないが、お洒落した若い女性たちがいつのまにかダンス・フロアの前の方に集まってきて踊っている。
『エネヘ・ラ・バンダ・ライブ・イン・ジャパン』(九三年)ではジャズ/フュージョンっぽさが鼻についたけど、そのようなよそ行きの展開にはならずに、地元ならではの猥雑さとセンティミエントがあふれ出す演奏でぐいぐい攻めてくる。リーダーのホセ・ルイス・コルテスがすぐフロントに出てきて、ちょっとエッチなオヤジぶりを発揮しつつ煽るため、フルートを吹きすぎないのも良い。
最後の曲〈コンガ・デル・ネグロ・カンサード〉では、客の女性がひとりずつステージに上がってダンス・コンテスト状態に突入。むき出しの快楽が炸裂しているのを、ぼくは呆然と眺めていた。タクシーでホテルに帰ったのは夜中の三時三〇分ごろだった。
[caption id="attachment_894" align="alignnone" width="500"]
96年12月23日にメキシコ・シティで撮影した路上のアコーディオン弾き。右後方に見える建物は革命記念塔。キューバへ行くには、今はカナダ経由が簡単だが、当時はメキシコ経由が安かった。[/caption]
そして夜になると、ホテル・カールトンのひなびたバーは、常連らしいオジサンたちやワケありふうのオバサンたちで賑わっていた。ハス向かいの床屋の前では街灯の下にいつも娼婦が立っていて、ぼくも「オラ」と声をかけられたりしたのだが、彼女たちもよくこのバーに出入りしていた。ギターを抱えた流しのミュージシャンがふらっと入ってきたりもする。だいたい一曲一〇ペソだったが、巧い人は連続して頼まれていた。こういう場合、ランチェーラ(メキシコの歌謡曲・演歌のようなもの)っぽい曲を弾き語りで歌い上げることが多くて、それが場末の雰囲気を盛り上げるのだった。
メキシコ・シティに一週間ほど滞在して、その間に旅行代理店で、ハバナ往復の航空券と六泊分のホテルとビザの代行取得のセットを五四八ドルで手に入れた。
一九九六年一二月二五日、ついにキューバの土を踏んだ。空港の入国審査に一時間ぐらいかかり、バスで指定されたホテルへと向かう。ハバナ新市街、ベダド地区の海岸通りに面したリビエラ・ホテルに着いたのは夕方。なかなかの高級ホテルで、ここに六泊するだけで五四八ドルの価値はあるように思えた。
キューバはドルとペソの二重経済になっていた。観光客向けのドル払いのカフェではコーヒー一杯が一ドルはするけど、地元民が集まるペソ払いのカフェでは一ペソ(一ペソは約五円)以下のようである。しかし観光客がペソを手に入れても、ペソで支払う場所で何かを買ったり食べたりする機会はなかなかなく、バスとか公共交通機関に乗るのも難しそうだ。
リビエラ・ホテルの地下はパラシオ・デ・ラ・サルサというホールになっていて、着いた日にいきなり、アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのライヴを見ることができた。前座の演奏が終わって登場してきたのは深夜一時三〇分で、三時まで演奏した。しかし、若手シンガーをフロントに立てているとはいえ、この日のアダルベルト・アルバレスにはバンマスとしての威厳が足りないように見えた。客席最前列で踊っていたのはお洒落な若いキューバ人女性たちだが、観客はだいたい観光客のようだし、やや期待はずれだったという印象が残っている。アダルベルト・アルバレスは、八〇年代のキューバ音楽に息を吹き込んだ重要人物なのだが。
翌二六日はまず、タクシーでハバナ中心部の旧市街、ビエハ地区に行ってみた。古い街並みがひときわ美しいビエハ地区では、タイム・スリップしたように五〇年代のアメ車が普通に走っていた。しかしそこは観光客だらけで、みんな写真やビデオを撮りまくっていた。無遠慮に構えた観光客のカメラに、キューバ人は笑顔をふりまいている。観光客は、メキシコ、スペイン、カナダ、ベネズエラなどからの団体が多いようだった。ハバナのビエハ地区はフォトジェニックで、観光客のイメージどおりに作られたテーマ・パークのようである。治安はジャマイカなどとは比べものにならないほど良い。なんとなく出来すぎていて、違和感を抱きつつ夕方ホテルに戻ったら、隣のホテルでシンクロナイズド・スイミングのショーをやっているのが見えた。
夜一〇時過ぎ、ホテルからタクシーでカサ・デ・ラ・ムジカというライヴハウスへと向かった。エネヘ・ラ・バンダのライヴがあることを知ったのだ。
入場料は一五ドル。前座のバンドや、いかにも社会主義国っぽいサーカス芸のパフォーマンスに続き、エネヘが登場したのは夜中の一時過ぎだった。入場料をどうやって払ったのか、あるいは払わずに入ったのか知らないが、お洒落した若い女性たちがいつのまにかダンス・フロアの前の方に集まってきて踊っている。
『エネヘ・ラ・バンダ・ライブ・イン・ジャパン』(九三年)ではジャズ/フュージョンっぽさが鼻についたけど、そのようなよそ行きの展開にはならずに、地元ならではの猥雑さとセンティミエントがあふれ出す演奏でぐいぐい攻めてくる。リーダーのホセ・ルイス・コルテスがすぐフロントに出てきて、ちょっとエッチなオヤジぶりを発揮しつつ煽るため、フルートを吹きすぎないのも良い。
最後の曲〈コンガ・デル・ネグロ・カンサード〉では、客の女性がひとりずつステージに上がってダンス・コンテスト状態に突入。むき出しの快楽が炸裂しているのを、ぼくは呆然と眺めていた。タクシーでホテルに帰ったのは夜中の三時三〇分ごろだった。
[caption id="attachment_894" align="alignnone" width="500"] 96年12月26日。カサ・デ・ラ・ムジカで行われたエネヘ・ラ・バンダのライヴ。入場料は15ドルだった。[/caption]
一二月二七日は、革命広場に面した内務省ビルに描かれているチェ・ゲバラの有名な壁画を見て、カフェ・カンタンテというライヴハウスに入ってみた。一瞬、地元の人で満員かと思ったら、ほぼ全員ベネズエラからの団体客だった。
二八日は再びハバナ中心部の旧市街ビエハ地区のほうを歩き回った。
二九日は早朝にホテルを出て、四〇人乗りぐらいのアントノフのプロペラ機に乗って、キューバ中央部サンクティ・スピリトゥス州の町トリニダを訪ねる日帰りツアーに参加した。ユネスコの世界遺産にも登録されている古都で、フォトジェニックだし、観光客向けのインフラも整備されているので、ここもまたテーマ・パークのように見えてしまう。
ここまでを振り返っても、キューバ人の素顔が垣間見えた気がしたのは、エネヘ・ラ・バンダのライヴのときぐらいしかない。ただしライヴで踊っていたお洒落した若い女性たちがどういう素性の人なのかは判らない。アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのときも何人かいたけど、庶民には見えなかった。
あっという間にキューバ滞在の最終日、一二月三〇日になった。この日はなんとかして普通のキューバを見たくて、白タクを三五ドルでチャーター。ハバナの南東五〇キロほどのところに位置するグイネスへ行ってみた。観光客はまったく来ない普通の町だ。しかし、人を乗せた馬車が通り過ぎたりするが、カフェらしいところも見つからず、商店をのぞいてもコーラさえ置いていなかった。町はずれに製糖工場があり、サトウキビ畑から通じているナロー・ゲージの線路が引き込まれていた。一月下旬から三月上旬の収穫期には小さな蒸気機関車が走っているはずだが、この時期、工場は閉まっている。
結局とっかかりがつかめないままハバナに戻った。白タクの運転手が、うまいレストランがあるというので連れて行ってもらった。そこは民家がやっているパラダール(個人経営のレストラン)。キューバでは庶民が入る街のレストランのようなものが見あたらなくて、観光客向けのレストランであまり美味しくないイタリア料理などを食べていたのだが、ここで食べた一〇ドルのグリル・フィッシュは、キューバに来て一番美味しい食べものだった。社会主義の最大の欠点は外食産業の質が宿命的に低くなることだと思うが、ドルの個人所有が認められたことによって張り切っている姿が見えて、やっと実状に接することができた気がした。
一二月三一日に、ハバナの空港の免税店でチェ・ゲバラのTシャツを買ってメキシコ・シティに飛び、バスでテキサスのサンアントニオまで戻り、九七年一月八日に帰国。
九四年には多くのバルセーロスを生んだキューバだが、経済的に回復しつつあったことは、パラダールのグリル・フィッシュの味に象徴されている。こういうところに見える変革の波は、音楽にも反映されないわけがない。この時代のエネヘ・ラ・バンダには、ポスト冷戦時代の困窮を突き破ったところで生まれた快楽がみなぎっていたと思う。
96年12月26日。カサ・デ・ラ・ムジカで行われたエネヘ・ラ・バンダのライヴ。入場料は15ドルだった。[/caption]
一二月二七日は、革命広場に面した内務省ビルに描かれているチェ・ゲバラの有名な壁画を見て、カフェ・カンタンテというライヴハウスに入ってみた。一瞬、地元の人で満員かと思ったら、ほぼ全員ベネズエラからの団体客だった。
二八日は再びハバナ中心部の旧市街ビエハ地区のほうを歩き回った。
二九日は早朝にホテルを出て、四〇人乗りぐらいのアントノフのプロペラ機に乗って、キューバ中央部サンクティ・スピリトゥス州の町トリニダを訪ねる日帰りツアーに参加した。ユネスコの世界遺産にも登録されている古都で、フォトジェニックだし、観光客向けのインフラも整備されているので、ここもまたテーマ・パークのように見えてしまう。
ここまでを振り返っても、キューバ人の素顔が垣間見えた気がしたのは、エネヘ・ラ・バンダのライヴのときぐらいしかない。ただしライヴで踊っていたお洒落した若い女性たちがどういう素性の人なのかは判らない。アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのときも何人かいたけど、庶民には見えなかった。
あっという間にキューバ滞在の最終日、一二月三〇日になった。この日はなんとかして普通のキューバを見たくて、白タクを三五ドルでチャーター。ハバナの南東五〇キロほどのところに位置するグイネスへ行ってみた。観光客はまったく来ない普通の町だ。しかし、人を乗せた馬車が通り過ぎたりするが、カフェらしいところも見つからず、商店をのぞいてもコーラさえ置いていなかった。町はずれに製糖工場があり、サトウキビ畑から通じているナロー・ゲージの線路が引き込まれていた。一月下旬から三月上旬の収穫期には小さな蒸気機関車が走っているはずだが、この時期、工場は閉まっている。
結局とっかかりがつかめないままハバナに戻った。白タクの運転手が、うまいレストランがあるというので連れて行ってもらった。そこは民家がやっているパラダール(個人経営のレストラン)。キューバでは庶民が入る街のレストランのようなものが見あたらなくて、観光客向けのレストランであまり美味しくないイタリア料理などを食べていたのだが、ここで食べた一〇ドルのグリル・フィッシュは、キューバに来て一番美味しい食べものだった。社会主義の最大の欠点は外食産業の質が宿命的に低くなることだと思うが、ドルの個人所有が認められたことによって張り切っている姿が見えて、やっと実状に接することができた気がした。
一二月三一日に、ハバナの空港の免税店でチェ・ゲバラのTシャツを買ってメキシコ・シティに飛び、バスでテキサスのサンアントニオまで戻り、九七年一月八日に帰国。
九四年には多くのバルセーロスを生んだキューバだが、経済的に回復しつつあったことは、パラダールのグリル・フィッシュの味に象徴されている。こういうところに見える変革の波は、音楽にも反映されないわけがない。この時代のエネヘ・ラ・バンダには、ポスト冷戦時代の困窮を突き破ったところで生まれた快楽がみなぎっていたと思う。
 00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。[/caption]
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。
最終的にはアメリカの司法長官ジャネット・レノの判断で、エリアン・ゴンサレスくんをキューバの父の元に返すことが決まったが、亡命キューバ人社会に支えられた叔父はあくまでもアメリカに留めようとした。そのため四月二二日にSWAT(アメリカの警察に設置されている特殊部隊)が叔父の家に踏み込んでエリアン・ゴンサレスくんを引き剥がし、キューバの父の元に送還させるという事態になり、帰国したエリアンくんは国家的英雄として迎え入れられた。
エリアン・ゴンサレスくん事件は、オリヴァー・ストーンがフィデル・カストロを取材したドキュメンタリー映画『コマンダンテ』(〇三年)でも取り上げられている。カストロはここで「あの少年の誘拐を機に、市民運動が発生しはじめた。その規模は革命直後のものよりも大きい」と語っている。意外にもアメリカの良識によって実現したエリアンくんの帰国を、勝利と宣伝することなく、時代の変わり目で起こった象徴的な事件と捉えているようだった。
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。[/caption]
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。
最終的にはアメリカの司法長官ジャネット・レノの判断で、エリアン・ゴンサレスくんをキューバの父の元に返すことが決まったが、亡命キューバ人社会に支えられた叔父はあくまでもアメリカに留めようとした。そのため四月二二日にSWAT(アメリカの警察に設置されている特殊部隊)が叔父の家に踏み込んでエリアン・ゴンサレスくんを引き剥がし、キューバの父の元に送還させるという事態になり、帰国したエリアンくんは国家的英雄として迎え入れられた。
エリアン・ゴンサレスくん事件は、オリヴァー・ストーンがフィデル・カストロを取材したドキュメンタリー映画『コマンダンテ』(〇三年)でも取り上げられている。カストロはここで「あの少年の誘拐を機に、市民運動が発生しはじめた。その規模は革命直後のものよりも大きい」と語っている。意外にもアメリカの良識によって実現したエリアンくんの帰国を、勝利と宣伝することなく、時代の変わり目で起こった象徴的な事件と捉えているようだった。
 ハバナの旧市街[/caption]
ハバナの旧市街[/caption]
一九九四年六月〜八月 新宿〜キューバ
一九九四年六月一六日、村上龍に話を聞きに行った。指定されたホテル、センチュリーハイアット新宿(現ハイアットリージェンシー東京)の部屋に入っていくと、昼間だったがすでにちょっと酔っぱらっていた。 村上龍は、短編小説『トパーズ』(八八年)を、自ら監督となって九一年に映画化した。そのとき、デヴィッド・バーンが設立したレーベル、ルアカ・ボップが出していたコンピレーション『Cuba Classics 2: Dancing With the Enemy』に入っていたロス・バンバンの〈ジェゲ・ジェゲ〉という曲を聴いて「何かコレいいな」と思い、サウンドトラックに使用した。以来キューバとキューバ音楽が好きになり、たびたび現地を訪れるようになった。そしてソニー・レコード内にMURAKAMI’sレーベルを作り、ロス・バンバンの〈ジェゲ・ジェゲ〉のオリジナルが入っていた『ロス・バン・バン1974』(七四年)の再発盤や、サルサ・ドゥーラあるいはティンバと呼ばれる音楽で当時特に人気があったエネヘ・ラ・バンダを日本に招聘してコンサートを行って、そのとき独自にレコーディングした音源など、キューバ音楽のCDを果敢にリリースしていた。 「ベンチャーズに3か月で飽きた後、やっぱりビートルズやストーンズに行ったわけ。で、ブルースのジョン・メイオールを聴いて、ギターの音がベイ~ンって伸びるのね、あの音が新しいロックの音だと思った。それからドアーズとかね」 村上龍は、音楽遍歴をざっくり話した後、キューバにのめり込んでいった理由をこのように説明した。 「ベルリンの壁が崩れて、ヨーロピアン・クラシックとアメリカン・ポップスの違いとかが無意味になったときに、新世界の音楽の中で、唯一、クラシックやジャズやロックに変わる、ある可能性を持った音楽のある国に行ったと、そういうことにしておいて下さい」 キューバを「唯一」とするのは、もちろん村上龍ならではの嗜好があるからだ。 「アフリカものとか、中近東ものとか、アジアものとか、僕は嫌いなの。旅行でモロッコとか行くと、坂本(龍一)が好きそうな、アッア~とかいうようなやつ、買ってくるけど結局聴かないもん。ただブラジルでサンバのレコードをたくさん買ったんですけど、それは結構聴きましたね」 と言っていた。それでも、ベルリンの壁が崩壊したことと非西欧圏の音楽に接するようになった経緯を関連づけて受け止めていたわけで、大いに刺激的な話だった。 村上龍に話を聞いた直後の九四年八月、キューバから手作りのイカダ(バルサ)に乗って脱出する難民が爆発的に増えてアメリカのフロリダ半島にたどり着いているというニュースが、日本のテレビでも大きく報道された。 ハバナからフロリダ半島沿岸までは最短で一六〇キロ。バルセーロスと呼ばれる彼ら難民は、海の藻屑となってしまう危険を犯してアメリカに渡り、〝亡命キューバ人(Cuban exile)〟になる道を選んだわけである。 アメリカで亡命キューバ人として生きていくためには、アメリカにとっての正義に忠誠を尽くすことを示す踏み絵を踏まなくてはならない。じつのところ経済難民であっても、キューバのカストロ社会主義政権を打倒する側に立つという意志を示すことと引き替えに、後ろ指を指されずにアメリカで生活できるのだ。亡命キューバ人とは、そもそもキューバを否定することを前提とした政治的な言葉であり、彼らは十把一絡げに親米反カストロと見なされている。それが、アメリカがメキシコから越境してくる人を厳しく取り締まる一方でキューバ人の〝亡命〟は受け入れてきた理由でもある。 もちろん実際には人の数だけ物語がある。九四年にキューバとアメリカ両方で撮影されたバルセーロスの映像と、彼らのその後を追った映像からなるドキュメンタリー映画、カーロス・ボッシュとジョセフ・マリア監督の『キューバン・ラフターズ』(〇二年。原題は〝Balseros〟)には、キューバを出航する前に残していく家族とハグしたり、米国に渡ってから望郷の念にさいなまれたりする様子が描かれている。 アメリカの沿岸警備隊の報告によれば、九三年のバルセーロスは三六五六人だったが、九四年はその一〇倍、三万七一九一人に膨れあがった。このうち二万人が八月に集中している。 そのような事態に至ったのは、八九年にベルリンの壁が崩壊して、九一年にキューバが経済的に大きく依存していたソビエト連邦が解体したことにより苦境に陥り、追い打ちをかけるように九二年にアメリカによる経済制裁が強化(トリチェリ法の施行)されたからだ。 九四年八月の報道に接したときは、さすがにもう、キューバのカストロ社会主義政権は持たないのではないかと思った。八九年には一人当たり三〇〇〇ドルあったGDPが九四年には一八〇〇ドルまで激減していた(それでもハイチの倍以上だが)。九二年一月から二月にかけて日本武道館でキューバン・ミュージカル・レビュー『ノーチェ・トロピカール』が上演されて、来日したオマーラ・ポルトゥオンドやカルロス・エンバーレのポートレイトを撮影する機会があったのだが、このときの来日メンバーは皆、少しでも多くのお金を持ち帰るため食事代を節約し、滞在先のホテルの近くのコンビニでサンドイッチなどを買って凌いでいると聞いたことを思い出した。 ところがキューバは持ち直して、九五年以後、経済成長していくのである。 アメリカは増えすぎたバルセーロス対策として、沿岸警備隊の追跡をかいくぐって上陸した人にはアメリカへの移住を認めるが、海上で捕まえた人はキューバに送還するというルール(Wet Foot, Dry Foot Policy)を九五年に作った。しかしキューバは送還されてきた人を罰しない方針に改めていたため、バルセーロスにとって航海の途上でイカダが難破してしまうこと以外のリスクはなくなっていた。 アメリカは九六年に新たな経済制裁(ヘルムズ・バトン法)を課したが、キューバ経済はそれでも上向き続けていた。その要因はまず、九三年にキューバ人のUSドルの所持が解禁されたのだが、ちょっと間を置いて経済が動き出して効果が現われ始めたこと。それから、東西冷戦の時代は砂糖が外貨を得る最大の産業だったが、外国人観光客が年々増えて観光が最大の産業になってきたからである。一九九六年一二月〜九七年一月 メキシコ〜キューバ
そのころ、日本からキューバへ行くのはメキシコ・シティから飛ぶのが最も安かった。ぼくもまずメキシコ・シティに行って、それからキューバへと向かう旅行に出た。 一九九六年一二月一六日に成田から飛行機に乗り、ロスアンジェルスとシカゴで飛行機を乗り継いで、同日午後一一時、テキサス州サンアントニオに着いた。その日はホテル代を節約するために空港のロビーで仮眠して、翌朝一番の市バスで街中にあるグレイハウンド・バス・ディーポへと向かった。そこからメキシコ国境の街ラレドまでバスで三時間。さらに夕方出発するバスに一六時間揺られてメキシコ・シティ(メキシコDF)までやって来た。 まずは革命記念塔の北側に位置する安宿が多い一帯を重いバックパックを背負ってフラフラ歩き、何軒か覗いた末、一泊八〇ペソ(一ペソは約一五円)で小さな公園に面していたホテル・カールトンにチェック・イン。一二月一八日の真昼、この旅行で初めてありついたベッドにゴロンと転がった。メキシコ・シティまでの格安チケットが取れなかったので、ここまで六〇時間ほどかかってしまった。 メキシコ・シティはラテンの街だ。何から何までスペイン語で、英語はほとんど通じない。ホテル・カールトンのフロントなどでは、ワン、ツー、スリーも通じない。ラジオから流れてくる音楽はメキシコ産クンビアが最も多く、ロスアンジェルス・アズールズの〈Como Te Voy A Olvidar〉というロマンティコたっぷりの曲が特に耳に残った。次に多かったのはちょっと粋な外国の音楽としてのサルサ。ソナ・ロッサの洒落たレストランなどでも英語の曲が流れてくることはほとんどなかった。 メキシコ・シティの歓楽街といえば、マリアッチの楽団が集まり、近所にはサルサのクラブやポルノ・ショップ、ルチャ・リブレの会場などがあるガリバルディ広場界隈が有名だが、ぼくはむしろ、街の中心部にありながら割とひっそりしていたホテル・カールトンの周りが好きだった。 このあたりでは昼間、どこにねぐらがあるのか、アコーディオンを抱えたインディオ系の子供のストリート・ミュージシャンがよく出没していた。 [caption id="attachment_891" align="alignnone" width="388"] 96年12月23日にメキシコ・シティで撮影した路上のアコーディオン弾き。右後方に見える建物は革命記念塔。キューバへ行くには、今はカナダ経由が簡単だが、当時はメキシコ経由が安かった。[/caption]
そして夜になると、ホテル・カールトンのひなびたバーは、常連らしいオジサンたちやワケありふうのオバサンたちで賑わっていた。ハス向かいの床屋の前では街灯の下にいつも娼婦が立っていて、ぼくも「オラ」と声をかけられたりしたのだが、彼女たちもよくこのバーに出入りしていた。ギターを抱えた流しのミュージシャンがふらっと入ってきたりもする。だいたい一曲一〇ペソだったが、巧い人は連続して頼まれていた。こういう場合、ランチェーラ(メキシコの歌謡曲・演歌のようなもの)っぽい曲を弾き語りで歌い上げることが多くて、それが場末の雰囲気を盛り上げるのだった。
メキシコ・シティに一週間ほど滞在して、その間に旅行代理店で、ハバナ往復の航空券と六泊分のホテルとビザの代行取得のセットを五四八ドルで手に入れた。
一九九六年一二月二五日、ついにキューバの土を踏んだ。空港の入国審査に一時間ぐらいかかり、バスで指定されたホテルへと向かう。ハバナ新市街、ベダド地区の海岸通りに面したリビエラ・ホテルに着いたのは夕方。なかなかの高級ホテルで、ここに六泊するだけで五四八ドルの価値はあるように思えた。
キューバはドルとペソの二重経済になっていた。観光客向けのドル払いのカフェではコーヒー一杯が一ドルはするけど、地元民が集まるペソ払いのカフェでは一ペソ(一ペソは約五円)以下のようである。しかし観光客がペソを手に入れても、ペソで支払う場所で何かを買ったり食べたりする機会はなかなかなく、バスとか公共交通機関に乗るのも難しそうだ。
リビエラ・ホテルの地下はパラシオ・デ・ラ・サルサというホールになっていて、着いた日にいきなり、アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのライヴを見ることができた。前座の演奏が終わって登場してきたのは深夜一時三〇分で、三時まで演奏した。しかし、若手シンガーをフロントに立てているとはいえ、この日のアダルベルト・アルバレスにはバンマスとしての威厳が足りないように見えた。客席最前列で踊っていたのはお洒落な若いキューバ人女性たちだが、観客はだいたい観光客のようだし、やや期待はずれだったという印象が残っている。アダルベルト・アルバレスは、八〇年代のキューバ音楽に息を吹き込んだ重要人物なのだが。
翌二六日はまず、タクシーでハバナ中心部の旧市街、ビエハ地区に行ってみた。古い街並みがひときわ美しいビエハ地区では、タイム・スリップしたように五〇年代のアメ車が普通に走っていた。しかしそこは観光客だらけで、みんな写真やビデオを撮りまくっていた。無遠慮に構えた観光客のカメラに、キューバ人は笑顔をふりまいている。観光客は、メキシコ、スペイン、カナダ、ベネズエラなどからの団体が多いようだった。ハバナのビエハ地区はフォトジェニックで、観光客のイメージどおりに作られたテーマ・パークのようである。治安はジャマイカなどとは比べものにならないほど良い。なんとなく出来すぎていて、違和感を抱きつつ夕方ホテルに戻ったら、隣のホテルでシンクロナイズド・スイミングのショーをやっているのが見えた。
夜一〇時過ぎ、ホテルからタクシーでカサ・デ・ラ・ムジカというライヴハウスへと向かった。エネヘ・ラ・バンダのライヴがあることを知ったのだ。
入場料は一五ドル。前座のバンドや、いかにも社会主義国っぽいサーカス芸のパフォーマンスに続き、エネヘが登場したのは夜中の一時過ぎだった。入場料をどうやって払ったのか、あるいは払わずに入ったのか知らないが、お洒落した若い女性たちがいつのまにかダンス・フロアの前の方に集まってきて踊っている。
『エネヘ・ラ・バンダ・ライブ・イン・ジャパン』(九三年)ではジャズ/フュージョンっぽさが鼻についたけど、そのようなよそ行きの展開にはならずに、地元ならではの猥雑さとセンティミエントがあふれ出す演奏でぐいぐい攻めてくる。リーダーのホセ・ルイス・コルテスがすぐフロントに出てきて、ちょっとエッチなオヤジぶりを発揮しつつ煽るため、フルートを吹きすぎないのも良い。
最後の曲〈コンガ・デル・ネグロ・カンサード〉では、客の女性がひとりずつステージに上がってダンス・コンテスト状態に突入。むき出しの快楽が炸裂しているのを、ぼくは呆然と眺めていた。タクシーでホテルに帰ったのは夜中の三時三〇分ごろだった。
[caption id="attachment_894" align="alignnone" width="500"]
96年12月23日にメキシコ・シティで撮影した路上のアコーディオン弾き。右後方に見える建物は革命記念塔。キューバへ行くには、今はカナダ経由が簡単だが、当時はメキシコ経由が安かった。[/caption]
そして夜になると、ホテル・カールトンのひなびたバーは、常連らしいオジサンたちやワケありふうのオバサンたちで賑わっていた。ハス向かいの床屋の前では街灯の下にいつも娼婦が立っていて、ぼくも「オラ」と声をかけられたりしたのだが、彼女たちもよくこのバーに出入りしていた。ギターを抱えた流しのミュージシャンがふらっと入ってきたりもする。だいたい一曲一〇ペソだったが、巧い人は連続して頼まれていた。こういう場合、ランチェーラ(メキシコの歌謡曲・演歌のようなもの)っぽい曲を弾き語りで歌い上げることが多くて、それが場末の雰囲気を盛り上げるのだった。
メキシコ・シティに一週間ほど滞在して、その間に旅行代理店で、ハバナ往復の航空券と六泊分のホテルとビザの代行取得のセットを五四八ドルで手に入れた。
一九九六年一二月二五日、ついにキューバの土を踏んだ。空港の入国審査に一時間ぐらいかかり、バスで指定されたホテルへと向かう。ハバナ新市街、ベダド地区の海岸通りに面したリビエラ・ホテルに着いたのは夕方。なかなかの高級ホテルで、ここに六泊するだけで五四八ドルの価値はあるように思えた。
キューバはドルとペソの二重経済になっていた。観光客向けのドル払いのカフェではコーヒー一杯が一ドルはするけど、地元民が集まるペソ払いのカフェでは一ペソ(一ペソは約五円)以下のようである。しかし観光客がペソを手に入れても、ペソで支払う場所で何かを買ったり食べたりする機会はなかなかなく、バスとか公共交通機関に乗るのも難しそうだ。
リビエラ・ホテルの地下はパラシオ・デ・ラ・サルサというホールになっていて、着いた日にいきなり、アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのライヴを見ることができた。前座の演奏が終わって登場してきたのは深夜一時三〇分で、三時まで演奏した。しかし、若手シンガーをフロントに立てているとはいえ、この日のアダルベルト・アルバレスにはバンマスとしての威厳が足りないように見えた。客席最前列で踊っていたのはお洒落な若いキューバ人女性たちだが、観客はだいたい観光客のようだし、やや期待はずれだったという印象が残っている。アダルベルト・アルバレスは、八〇年代のキューバ音楽に息を吹き込んだ重要人物なのだが。
翌二六日はまず、タクシーでハバナ中心部の旧市街、ビエハ地区に行ってみた。古い街並みがひときわ美しいビエハ地区では、タイム・スリップしたように五〇年代のアメ車が普通に走っていた。しかしそこは観光客だらけで、みんな写真やビデオを撮りまくっていた。無遠慮に構えた観光客のカメラに、キューバ人は笑顔をふりまいている。観光客は、メキシコ、スペイン、カナダ、ベネズエラなどからの団体が多いようだった。ハバナのビエハ地区はフォトジェニックで、観光客のイメージどおりに作られたテーマ・パークのようである。治安はジャマイカなどとは比べものにならないほど良い。なんとなく出来すぎていて、違和感を抱きつつ夕方ホテルに戻ったら、隣のホテルでシンクロナイズド・スイミングのショーをやっているのが見えた。
夜一〇時過ぎ、ホテルからタクシーでカサ・デ・ラ・ムジカというライヴハウスへと向かった。エネヘ・ラ・バンダのライヴがあることを知ったのだ。
入場料は一五ドル。前座のバンドや、いかにも社会主義国っぽいサーカス芸のパフォーマンスに続き、エネヘが登場したのは夜中の一時過ぎだった。入場料をどうやって払ったのか、あるいは払わずに入ったのか知らないが、お洒落した若い女性たちがいつのまにかダンス・フロアの前の方に集まってきて踊っている。
『エネヘ・ラ・バンダ・ライブ・イン・ジャパン』(九三年)ではジャズ/フュージョンっぽさが鼻についたけど、そのようなよそ行きの展開にはならずに、地元ならではの猥雑さとセンティミエントがあふれ出す演奏でぐいぐい攻めてくる。リーダーのホセ・ルイス・コルテスがすぐフロントに出てきて、ちょっとエッチなオヤジぶりを発揮しつつ煽るため、フルートを吹きすぎないのも良い。
最後の曲〈コンガ・デル・ネグロ・カンサード〉では、客の女性がひとりずつステージに上がってダンス・コンテスト状態に突入。むき出しの快楽が炸裂しているのを、ぼくは呆然と眺めていた。タクシーでホテルに帰ったのは夜中の三時三〇分ごろだった。
[caption id="attachment_894" align="alignnone" width="500"] 96年12月26日。カサ・デ・ラ・ムジカで行われたエネヘ・ラ・バンダのライヴ。入場料は15ドルだった。[/caption]
一二月二七日は、革命広場に面した内務省ビルに描かれているチェ・ゲバラの有名な壁画を見て、カフェ・カンタンテというライヴハウスに入ってみた。一瞬、地元の人で満員かと思ったら、ほぼ全員ベネズエラからの団体客だった。
二八日は再びハバナ中心部の旧市街ビエハ地区のほうを歩き回った。
二九日は早朝にホテルを出て、四〇人乗りぐらいのアントノフのプロペラ機に乗って、キューバ中央部サンクティ・スピリトゥス州の町トリニダを訪ねる日帰りツアーに参加した。ユネスコの世界遺産にも登録されている古都で、フォトジェニックだし、観光客向けのインフラも整備されているので、ここもまたテーマ・パークのように見えてしまう。
ここまでを振り返っても、キューバ人の素顔が垣間見えた気がしたのは、エネヘ・ラ・バンダのライヴのときぐらいしかない。ただしライヴで踊っていたお洒落した若い女性たちがどういう素性の人なのかは判らない。アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのときも何人かいたけど、庶民には見えなかった。
あっという間にキューバ滞在の最終日、一二月三〇日になった。この日はなんとかして普通のキューバを見たくて、白タクを三五ドルでチャーター。ハバナの南東五〇キロほどのところに位置するグイネスへ行ってみた。観光客はまったく来ない普通の町だ。しかし、人を乗せた馬車が通り過ぎたりするが、カフェらしいところも見つからず、商店をのぞいてもコーラさえ置いていなかった。町はずれに製糖工場があり、サトウキビ畑から通じているナロー・ゲージの線路が引き込まれていた。一月下旬から三月上旬の収穫期には小さな蒸気機関車が走っているはずだが、この時期、工場は閉まっている。
結局とっかかりがつかめないままハバナに戻った。白タクの運転手が、うまいレストランがあるというので連れて行ってもらった。そこは民家がやっているパラダール(個人経営のレストラン)。キューバでは庶民が入る街のレストランのようなものが見あたらなくて、観光客向けのレストランであまり美味しくないイタリア料理などを食べていたのだが、ここで食べた一〇ドルのグリル・フィッシュは、キューバに来て一番美味しい食べものだった。社会主義の最大の欠点は外食産業の質が宿命的に低くなることだと思うが、ドルの個人所有が認められたことによって張り切っている姿が見えて、やっと実状に接することができた気がした。
一二月三一日に、ハバナの空港の免税店でチェ・ゲバラのTシャツを買ってメキシコ・シティに飛び、バスでテキサスのサンアントニオまで戻り、九七年一月八日に帰国。
九四年には多くのバルセーロスを生んだキューバだが、経済的に回復しつつあったことは、パラダールのグリル・フィッシュの味に象徴されている。こういうところに見える変革の波は、音楽にも反映されないわけがない。この時代のエネヘ・ラ・バンダには、ポスト冷戦時代の困窮を突き破ったところで生まれた快楽がみなぎっていたと思う。
96年12月26日。カサ・デ・ラ・ムジカで行われたエネヘ・ラ・バンダのライヴ。入場料は15ドルだった。[/caption]
一二月二七日は、革命広場に面した内務省ビルに描かれているチェ・ゲバラの有名な壁画を見て、カフェ・カンタンテというライヴハウスに入ってみた。一瞬、地元の人で満員かと思ったら、ほぼ全員ベネズエラからの団体客だった。
二八日は再びハバナ中心部の旧市街ビエハ地区のほうを歩き回った。
二九日は早朝にホテルを出て、四〇人乗りぐらいのアントノフのプロペラ機に乗って、キューバ中央部サンクティ・スピリトゥス州の町トリニダを訪ねる日帰りツアーに参加した。ユネスコの世界遺産にも登録されている古都で、フォトジェニックだし、観光客向けのインフラも整備されているので、ここもまたテーマ・パークのように見えてしまう。
ここまでを振り返っても、キューバ人の素顔が垣間見えた気がしたのは、エネヘ・ラ・バンダのライヴのときぐらいしかない。ただしライヴで踊っていたお洒落した若い女性たちがどういう素性の人なのかは判らない。アダルベルト・アルバレス・イ・ス・ソンのときも何人かいたけど、庶民には見えなかった。
あっという間にキューバ滞在の最終日、一二月三〇日になった。この日はなんとかして普通のキューバを見たくて、白タクを三五ドルでチャーター。ハバナの南東五〇キロほどのところに位置するグイネスへ行ってみた。観光客はまったく来ない普通の町だ。しかし、人を乗せた馬車が通り過ぎたりするが、カフェらしいところも見つからず、商店をのぞいてもコーラさえ置いていなかった。町はずれに製糖工場があり、サトウキビ畑から通じているナロー・ゲージの線路が引き込まれていた。一月下旬から三月上旬の収穫期には小さな蒸気機関車が走っているはずだが、この時期、工場は閉まっている。
結局とっかかりがつかめないままハバナに戻った。白タクの運転手が、うまいレストランがあるというので連れて行ってもらった。そこは民家がやっているパラダール(個人経営のレストラン)。キューバでは庶民が入る街のレストランのようなものが見あたらなくて、観光客向けのレストランであまり美味しくないイタリア料理などを食べていたのだが、ここで食べた一〇ドルのグリル・フィッシュは、キューバに来て一番美味しい食べものだった。社会主義の最大の欠点は外食産業の質が宿命的に低くなることだと思うが、ドルの個人所有が認められたことによって張り切っている姿が見えて、やっと実状に接することができた気がした。
一二月三一日に、ハバナの空港の免税店でチェ・ゲバラのTシャツを買ってメキシコ・シティに飛び、バスでテキサスのサンアントニオまで戻り、九七年一月八日に帰国。
九四年には多くのバルセーロスを生んだキューバだが、経済的に回復しつつあったことは、パラダールのグリル・フィッシュの味に象徴されている。こういうところに見える変革の波は、音楽にも反映されないわけがない。この時代のエネヘ・ラ・バンダには、ポスト冷戦時代の困窮を突き破ったところで生まれた快楽がみなぎっていたと思う。
一九九九年〜二〇〇〇年 マイアミ
九九年一二月五日、ジャマイカから帰国するとき、経由地のマイアミで一泊した。マイアミには、サンテリアの神様を祀っている店などもあるリトル・ハバナと呼ばれる地区がある。せっかくなのでタクシーを走らせてご飯を食べに行った。 このときニュースになっていた記憶はないのだが、九九年一一月に、アメリカへの亡命を企てたキューバ人が乗った船が嵐にあって難破して、一一人が亡くなるという事件があった。母親に連れられてその船に乗っていた当時六歳のエリアン・ゴンサレスくんは、このとき母親を亡くしたものの本人は救助されて、いったんはマイアミ在住の叔父に引き取られた。 〇〇年三月二九日から四月二日まで、グロリア・エステファンの撮影でマイアミに行った。五九年のキューバ革命の時に二歳だったグロリアは、家族に連れられてマイアミに亡命した。その後ポップ・スターとして大成功するわけだが、それは同時に、反カストロを標榜する亡命キューバ人社会のオピニオンを代弁する立場を宿命的に背負うことでもあった。 このときマイアミでは、エリアン・ゴンサレスくん問題が大きな関心を集めていた。 キューバにいる父がエリアンくんの送還を要求したことから、キューバと、マイアミの亡命キューバ人社会による綱引きが始まり、政治問題化していたのだ。三月三〇日に、キューバ政府がアメリカの法廷で争うために父を渡米させることを決めたことが大きなニュースになった。 [caption id="attachment_893" align="alignnone" width="500"] 00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。[/caption]
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。
最終的にはアメリカの司法長官ジャネット・レノの判断で、エリアン・ゴンサレスくんをキューバの父の元に返すことが決まったが、亡命キューバ人社会に支えられた叔父はあくまでもアメリカに留めようとした。そのため四月二二日にSWAT(アメリカの警察に設置されている特殊部隊)が叔父の家に踏み込んでエリアン・ゴンサレスくんを引き剥がし、キューバの父の元に送還させるという事態になり、帰国したエリアンくんは国家的英雄として迎え入れられた。
エリアン・ゴンサレスくん事件は、オリヴァー・ストーンがフィデル・カストロを取材したドキュメンタリー映画『コマンダンテ』(〇三年)でも取り上げられている。カストロはここで「あの少年の誘拐を機に、市民運動が発生しはじめた。その規模は革命直後のものよりも大きい」と語っている。意外にもアメリカの良識によって実現したエリアンくんの帰国を、勝利と宣伝することなく、時代の変わり目で起こった象徴的な事件と捉えているようだった。
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。[/caption]
00年3月30日にマイアミで撮影した新聞の自動販売機。『The Miami Herald』紙と、スペイン語の『Diario Las Américas』紙。いずれもエリアン・ゴンサレスくん関連のニュースが1面トップだった。
最終的にはアメリカの司法長官ジャネット・レノの判断で、エリアン・ゴンサレスくんをキューバの父の元に返すことが決まったが、亡命キューバ人社会に支えられた叔父はあくまでもアメリカに留めようとした。そのため四月二二日にSWAT(アメリカの警察に設置されている特殊部隊)が叔父の家に踏み込んでエリアン・ゴンサレスくんを引き剥がし、キューバの父の元に送還させるという事態になり、帰国したエリアンくんは国家的英雄として迎え入れられた。
エリアン・ゴンサレスくん事件は、オリヴァー・ストーンがフィデル・カストロを取材したドキュメンタリー映画『コマンダンテ』(〇三年)でも取り上げられている。カストロはここで「あの少年の誘拐を機に、市民運動が発生しはじめた。その規模は革命直後のものよりも大きい」と語っている。意外にもアメリカの良識によって実現したエリアンくんの帰国を、勝利と宣伝することなく、時代の変わり目で起こった象徴的な事件と捉えているようだった。 第4回 イスラエル兵が通り過ぎざま、「ファック・ユー」と言い捨てた ──1993年12月、オスロ合意直後のエルサレム〜ガザ地区への旅
[caption id="attachment_895" align="alignnone" width="500"] 1993年、和平に最も近づいた時代のパレスチナ、ガザ中心部の風景[/caption]
ヤセル・アラファト・PLO議長とイツハク・ラビン・イスラエル首相との間で、パレスチナ暫定自治に関する歴史的合意、いわゆるオスロ合意が結ばれ、ワシントンで署名式典が行われたのは、一九九三年九月一三日のことだった。ビル・クリントン米大統領をはさんで、アラファトとラビンが握手する映像をテレビで見て、ベルリンの壁の崩壊以来となる感動を覚えたものだ。
オスロ合意は、イスラエルを国家として、PLO(パレスチナ解放機構)をパレスチナの自治政府として相互承認すると謳っていた。これにより、当時チュニジアのチュニスにあったPLO本部がパレスチナの地に帰還して、暫定自治が始まることになったわけである。
パレスチナの占領地に作られた入植地から撤退する気のないユダヤ人や、イスラエルの存在自体を認めないパレスチナ人は、当然のようにオスロ合意を粉砕しようと気炎を上げたが、当初は、ぼくの印象では、イスラエル人の六割、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の八割、ガザ地区のパレスチナ人の五割ぐらいの人たちが、オスロ合意に和平への希望を抱いていた。
1993年、和平に最も近づいた時代のパレスチナ、ガザ中心部の風景[/caption]
ヤセル・アラファト・PLO議長とイツハク・ラビン・イスラエル首相との間で、パレスチナ暫定自治に関する歴史的合意、いわゆるオスロ合意が結ばれ、ワシントンで署名式典が行われたのは、一九九三年九月一三日のことだった。ビル・クリントン米大統領をはさんで、アラファトとラビンが握手する映像をテレビで見て、ベルリンの壁の崩壊以来となる感動を覚えたものだ。
オスロ合意は、イスラエルを国家として、PLO(パレスチナ解放機構)をパレスチナの自治政府として相互承認すると謳っていた。これにより、当時チュニジアのチュニスにあったPLO本部がパレスチナの地に帰還して、暫定自治が始まることになったわけである。
パレスチナの占領地に作られた入植地から撤退する気のないユダヤ人や、イスラエルの存在自体を認めないパレスチナ人は、当然のようにオスロ合意を粉砕しようと気炎を上げたが、当初は、ぼくの印象では、イスラエル人の六割、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の八割、ガザ地区のパレスチナ人の五割ぐらいの人たちが、オスロ合意に和平への希望を抱いていた。
 サンタクロースになっているパレスチナ人、ムスタファ[/caption]
一二月二五日。安息日でイスラエルは静まりかえっているなか、アラブのバスで西岸地区のアリーハ(ジェリコ)へと向かった。
パレスチナは、地中海沿いでエジプトと国境を接していて人口が密集しているガザ地区と、ぱらぱらと村が点在するヨルダン川西岸地区に分かれている。オスロ合意に基づく暫定自治は、ガザと、西岸地区のごく一部だがアリーハ(ジェリコ)から始めることになっていた。
パレスチナ人がアリーハと呼ぶ街をイスラエル人はジェリコと呼んでいる。ただしイスラエル人と一般の観光客にとってのジェリコは、アリーハの街から二キロ北にあるテル・エッスルタンの遺跡を意味する。そこには遺跡とレストランとみやげもの屋があるだけだが、ジェリコに行く観光客を乗せたイスラエルのバスは、パレスチナ人の街、アリーハに立ち寄ることなく遺跡に直行する。東エルサレムとアリーハの街を結ぶのはアラブのバスで、これにイスラエル人が乗ってくることはない。
アリーハは砂漠のオアシスのような街である。どちらに歩いても一〇分ほどで通り抜けてしまう。唯一の大きな建物はヒシャム・パレス・ホテルで、当時はこの建物が暫定政府になると言われていた。一泊六〇USドルと高かったがここに泊まった。庭には、オレンジとレモンとブドウの木があり、ブーゲンビリアやカンナの花が咲いていた。
アメリカのテレビがホテルの支配人にインタヴューしているところを見た。「アラファトがいつやって来るかは判らない。でも近い将来、かならずここに入城するはずだ。その日は歴史的な一日になるだろう」と語っていた。
実際は、九四年五月にガザ・ジェリコ暫定自治協定が調印されて、同年七月にヤセル・アラファト・PLO議長はガザの方に帰還して先行自治が始まった。しかし九三年一二月の時点では、アラファトはアリーハに入城してくるものだと思われていて、ヒシャム・パレス・ホテルの近くに早くも公然とPLOの事務所が開設されていた。
アリーハは、アラファトをリーダーとするPLO主流派でイスラエルとの和平をめざしているグループ、ファタハの支持者が大勢を占める街だった。赤、黒、白、緑のパレスチナの旗がはためき、あちこちの壁にアラファトの似顔絵が描かれていた。
PLOの事務所にいた人たちはだいたいインティファーダでイスラエルの牢屋に入れられた経験があり、「俺は三年」、「私は五年」と歴戦の闘士のように言うが、いたって普通のパレスチナ人にしか見えない。
英語の先生と大学生がお茶を飲んでいるところでは「パレスチナが独立したらコーゾー・オカモト(七二年にテルアビブの空港で銃の乱射事件を起こした日本赤軍の岡本公三)の銅像を造りたい」と言われた。
裏道を歩いていたら子供が何人か遊んでいたので「サラーム・アレイコム。アナ・ヤパーニ(こんにちは。日本人です)」と言ってみた。すると子供たちのお母さんが「家に遊びに来なさい」と言うのでついて行く。ソフィアという三二歳の女性で九人も子供がいるそうだ。瓜の中に米を詰めてトマトで煮込んだ料理をごちそうになった。中学生の長女が英語でいろいろ説明してくれる。家族の写真を撮り、送る約束をしてメモ帳に住所を書いてもらった。
サンタクロースになっているパレスチナ人、ムスタファ[/caption]
一二月二五日。安息日でイスラエルは静まりかえっているなか、アラブのバスで西岸地区のアリーハ(ジェリコ)へと向かった。
パレスチナは、地中海沿いでエジプトと国境を接していて人口が密集しているガザ地区と、ぱらぱらと村が点在するヨルダン川西岸地区に分かれている。オスロ合意に基づく暫定自治は、ガザと、西岸地区のごく一部だがアリーハ(ジェリコ)から始めることになっていた。
パレスチナ人がアリーハと呼ぶ街をイスラエル人はジェリコと呼んでいる。ただしイスラエル人と一般の観光客にとってのジェリコは、アリーハの街から二キロ北にあるテル・エッスルタンの遺跡を意味する。そこには遺跡とレストランとみやげもの屋があるだけだが、ジェリコに行く観光客を乗せたイスラエルのバスは、パレスチナ人の街、アリーハに立ち寄ることなく遺跡に直行する。東エルサレムとアリーハの街を結ぶのはアラブのバスで、これにイスラエル人が乗ってくることはない。
アリーハは砂漠のオアシスのような街である。どちらに歩いても一〇分ほどで通り抜けてしまう。唯一の大きな建物はヒシャム・パレス・ホテルで、当時はこの建物が暫定政府になると言われていた。一泊六〇USドルと高かったがここに泊まった。庭には、オレンジとレモンとブドウの木があり、ブーゲンビリアやカンナの花が咲いていた。
アメリカのテレビがホテルの支配人にインタヴューしているところを見た。「アラファトがいつやって来るかは判らない。でも近い将来、かならずここに入城するはずだ。その日は歴史的な一日になるだろう」と語っていた。
実際は、九四年五月にガザ・ジェリコ暫定自治協定が調印されて、同年七月にヤセル・アラファト・PLO議長はガザの方に帰還して先行自治が始まった。しかし九三年一二月の時点では、アラファトはアリーハに入城してくるものだと思われていて、ヒシャム・パレス・ホテルの近くに早くも公然とPLOの事務所が開設されていた。
アリーハは、アラファトをリーダーとするPLO主流派でイスラエルとの和平をめざしているグループ、ファタハの支持者が大勢を占める街だった。赤、黒、白、緑のパレスチナの旗がはためき、あちこちの壁にアラファトの似顔絵が描かれていた。
PLOの事務所にいた人たちはだいたいインティファーダでイスラエルの牢屋に入れられた経験があり、「俺は三年」、「私は五年」と歴戦の闘士のように言うが、いたって普通のパレスチナ人にしか見えない。
英語の先生と大学生がお茶を飲んでいるところでは「パレスチナが独立したらコーゾー・オカモト(七二年にテルアビブの空港で銃の乱射事件を起こした日本赤軍の岡本公三)の銅像を造りたい」と言われた。
裏道を歩いていたら子供が何人か遊んでいたので「サラーム・アレイコム。アナ・ヤパーニ(こんにちは。日本人です)」と言ってみた。すると子供たちのお母さんが「家に遊びに来なさい」と言うのでついて行く。ソフィアという三二歳の女性で九人も子供がいるそうだ。瓜の中に米を詰めてトマトで煮込んだ料理をごちそうになった。中学生の長女が英語でいろいろ説明してくれる。家族の写真を撮り、送る約束をしてメモ帳に住所を書いてもらった。
 94年1月1日のインティファーダ。左端が連行される少年[/caption]
94年1月1日のインティファーダ。左端が連行される少年[/caption]
 1993年、和平に最も近づいた時代のパレスチナ、ガザ中心部の風景[/caption]
ヤセル・アラファト・PLO議長とイツハク・ラビン・イスラエル首相との間で、パレスチナ暫定自治に関する歴史的合意、いわゆるオスロ合意が結ばれ、ワシントンで署名式典が行われたのは、一九九三年九月一三日のことだった。ビル・クリントン米大統領をはさんで、アラファトとラビンが握手する映像をテレビで見て、ベルリンの壁の崩壊以来となる感動を覚えたものだ。
オスロ合意は、イスラエルを国家として、PLO(パレスチナ解放機構)をパレスチナの自治政府として相互承認すると謳っていた。これにより、当時チュニジアのチュニスにあったPLO本部がパレスチナの地に帰還して、暫定自治が始まることになったわけである。
パレスチナの占領地に作られた入植地から撤退する気のないユダヤ人や、イスラエルの存在自体を認めないパレスチナ人は、当然のようにオスロ合意を粉砕しようと気炎を上げたが、当初は、ぼくの印象では、イスラエル人の六割、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の八割、ガザ地区のパレスチナ人の五割ぐらいの人たちが、オスロ合意に和平への希望を抱いていた。
1993年、和平に最も近づいた時代のパレスチナ、ガザ中心部の風景[/caption]
ヤセル・アラファト・PLO議長とイツハク・ラビン・イスラエル首相との間で、パレスチナ暫定自治に関する歴史的合意、いわゆるオスロ合意が結ばれ、ワシントンで署名式典が行われたのは、一九九三年九月一三日のことだった。ビル・クリントン米大統領をはさんで、アラファトとラビンが握手する映像をテレビで見て、ベルリンの壁の崩壊以来となる感動を覚えたものだ。
オスロ合意は、イスラエルを国家として、PLO(パレスチナ解放機構)をパレスチナの自治政府として相互承認すると謳っていた。これにより、当時チュニジアのチュニスにあったPLO本部がパレスチナの地に帰還して、暫定自治が始まることになったわけである。
パレスチナの占領地に作られた入植地から撤退する気のないユダヤ人や、イスラエルの存在自体を認めないパレスチナ人は、当然のようにオスロ合意を粉砕しようと気炎を上げたが、当初は、ぼくの印象では、イスラエル人の六割、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の八割、ガザ地区のパレスチナ人の五割ぐらいの人たちが、オスロ合意に和平への希望を抱いていた。
ファタハ支持者の街、アリーハ
九三年一二月二三日、ぼくはヨルダンの首都アンマンから、ヨルダン川西岸地区を通過して、陸路イスラエルのエルサレム(アル・クドゥス)へと向かった。 朝、国境となっているヨルダン川に架かるアレンビー橋(キング・フセイン橋)まで行くバスに乗る。 ヨルダン川西岸は、六七年の第三次中東戦争でイスラエルに占領されたが、ヨルダンは九四年にPLOが暫定自治を始めるまで領有権を主張していたので、国境でパスポートに出国スタンプを押されることはなく、内務省で取得した西岸地区入域許可証を提出する仕組みになっていた。 橋の手前で小銃を携えたイスラエル兵がバスに乗り込んできて、川幅わずか一〇メートルほどのヨルダン川を渡る。西岸地区に入ったところにイスラエルのイミグレーションの建物があり、入国手続きを行う。イスラエルは西岸地区を実効支配しているが、入国スタンプは希望すればパスポートではなく別紙に押してもらえる。パスポートにイスラエルに入国した形跡が残ると入国できなくなるイスラム圏の国が多いから配慮しているのだ。カメラを天井に向けてシャッターを押せと言われたので従った。カメラの形をした銃の持ち込みを警戒していたのだろうか。 イミグレーションの建物を出ると、乗り合いタクシーでエルサレムへと向かう。オリーブの木が生えた砂漠を走り、死海の近くにある世界一低い海抜マイナス三五〇メートルの町、ジェリコを通過して長い坂道を登り始める。途中で海抜〇メートルの標識を見てさらに登り、丘の上に白い壁とオレンジ色の屋根の家々が並ぶ明らかに国連決議に違反した入植地の風景なども見えて、海抜八〇〇メートルのエルサレムに到着する。当時は検問所は一か所もなかった。 一二月二四日は金曜日でクリスマス・イヴだ。イスラエルでは金曜日の夕方から土曜日の夕方までが安息日(シャバット)で、ほとんどの店が閉まるだけでなくバスも止まるのでまったく何もできない。ただしその間でも、東エルサレムのイスラム教徒地区の店は営業しているし、ダマスカス門のすぐ外にあるバス・ターミナルから西岸地区へと向かうアラブのバスはいつも通りに走っている。 ユダヤ教徒はクリスマスにまつわることは一切やらないが、イスラム教徒のパレスチナ人は、キリスト教徒でない日本人でもクリスマスを祝うのに近いことをする。サンタクロースの衣装を着たパレスチナ人が、友達から「ムスタファ!」と呼ばれているところを見た。 [caption id="attachment_896" align="alignnone" width="396"] サンタクロースになっているパレスチナ人、ムスタファ[/caption]
一二月二五日。安息日でイスラエルは静まりかえっているなか、アラブのバスで西岸地区のアリーハ(ジェリコ)へと向かった。
パレスチナは、地中海沿いでエジプトと国境を接していて人口が密集しているガザ地区と、ぱらぱらと村が点在するヨルダン川西岸地区に分かれている。オスロ合意に基づく暫定自治は、ガザと、西岸地区のごく一部だがアリーハ(ジェリコ)から始めることになっていた。
パレスチナ人がアリーハと呼ぶ街をイスラエル人はジェリコと呼んでいる。ただしイスラエル人と一般の観光客にとってのジェリコは、アリーハの街から二キロ北にあるテル・エッスルタンの遺跡を意味する。そこには遺跡とレストランとみやげもの屋があるだけだが、ジェリコに行く観光客を乗せたイスラエルのバスは、パレスチナ人の街、アリーハに立ち寄ることなく遺跡に直行する。東エルサレムとアリーハの街を結ぶのはアラブのバスで、これにイスラエル人が乗ってくることはない。
アリーハは砂漠のオアシスのような街である。どちらに歩いても一〇分ほどで通り抜けてしまう。唯一の大きな建物はヒシャム・パレス・ホテルで、当時はこの建物が暫定政府になると言われていた。一泊六〇USドルと高かったがここに泊まった。庭には、オレンジとレモンとブドウの木があり、ブーゲンビリアやカンナの花が咲いていた。
アメリカのテレビがホテルの支配人にインタヴューしているところを見た。「アラファトがいつやって来るかは判らない。でも近い将来、かならずここに入城するはずだ。その日は歴史的な一日になるだろう」と語っていた。
実際は、九四年五月にガザ・ジェリコ暫定自治協定が調印されて、同年七月にヤセル・アラファト・PLO議長はガザの方に帰還して先行自治が始まった。しかし九三年一二月の時点では、アラファトはアリーハに入城してくるものだと思われていて、ヒシャム・パレス・ホテルの近くに早くも公然とPLOの事務所が開設されていた。
アリーハは、アラファトをリーダーとするPLO主流派でイスラエルとの和平をめざしているグループ、ファタハの支持者が大勢を占める街だった。赤、黒、白、緑のパレスチナの旗がはためき、あちこちの壁にアラファトの似顔絵が描かれていた。
PLOの事務所にいた人たちはだいたいインティファーダでイスラエルの牢屋に入れられた経験があり、「俺は三年」、「私は五年」と歴戦の闘士のように言うが、いたって普通のパレスチナ人にしか見えない。
英語の先生と大学生がお茶を飲んでいるところでは「パレスチナが独立したらコーゾー・オカモト(七二年にテルアビブの空港で銃の乱射事件を起こした日本赤軍の岡本公三)の銅像を造りたい」と言われた。
裏道を歩いていたら子供が何人か遊んでいたので「サラーム・アレイコム。アナ・ヤパーニ(こんにちは。日本人です)」と言ってみた。すると子供たちのお母さんが「家に遊びに来なさい」と言うのでついて行く。ソフィアという三二歳の女性で九人も子供がいるそうだ。瓜の中に米を詰めてトマトで煮込んだ料理をごちそうになった。中学生の長女が英語でいろいろ説明してくれる。家族の写真を撮り、送る約束をしてメモ帳に住所を書いてもらった。
サンタクロースになっているパレスチナ人、ムスタファ[/caption]
一二月二五日。安息日でイスラエルは静まりかえっているなか、アラブのバスで西岸地区のアリーハ(ジェリコ)へと向かった。
パレスチナは、地中海沿いでエジプトと国境を接していて人口が密集しているガザ地区と、ぱらぱらと村が点在するヨルダン川西岸地区に分かれている。オスロ合意に基づく暫定自治は、ガザと、西岸地区のごく一部だがアリーハ(ジェリコ)から始めることになっていた。
パレスチナ人がアリーハと呼ぶ街をイスラエル人はジェリコと呼んでいる。ただしイスラエル人と一般の観光客にとってのジェリコは、アリーハの街から二キロ北にあるテル・エッスルタンの遺跡を意味する。そこには遺跡とレストランとみやげもの屋があるだけだが、ジェリコに行く観光客を乗せたイスラエルのバスは、パレスチナ人の街、アリーハに立ち寄ることなく遺跡に直行する。東エルサレムとアリーハの街を結ぶのはアラブのバスで、これにイスラエル人が乗ってくることはない。
アリーハは砂漠のオアシスのような街である。どちらに歩いても一〇分ほどで通り抜けてしまう。唯一の大きな建物はヒシャム・パレス・ホテルで、当時はこの建物が暫定政府になると言われていた。一泊六〇USドルと高かったがここに泊まった。庭には、オレンジとレモンとブドウの木があり、ブーゲンビリアやカンナの花が咲いていた。
アメリカのテレビがホテルの支配人にインタヴューしているところを見た。「アラファトがいつやって来るかは判らない。でも近い将来、かならずここに入城するはずだ。その日は歴史的な一日になるだろう」と語っていた。
実際は、九四年五月にガザ・ジェリコ暫定自治協定が調印されて、同年七月にヤセル・アラファト・PLO議長はガザの方に帰還して先行自治が始まった。しかし九三年一二月の時点では、アラファトはアリーハに入城してくるものだと思われていて、ヒシャム・パレス・ホテルの近くに早くも公然とPLOの事務所が開設されていた。
アリーハは、アラファトをリーダーとするPLO主流派でイスラエルとの和平をめざしているグループ、ファタハの支持者が大勢を占める街だった。赤、黒、白、緑のパレスチナの旗がはためき、あちこちの壁にアラファトの似顔絵が描かれていた。
PLOの事務所にいた人たちはだいたいインティファーダでイスラエルの牢屋に入れられた経験があり、「俺は三年」、「私は五年」と歴戦の闘士のように言うが、いたって普通のパレスチナ人にしか見えない。
英語の先生と大学生がお茶を飲んでいるところでは「パレスチナが独立したらコーゾー・オカモト(七二年にテルアビブの空港で銃の乱射事件を起こした日本赤軍の岡本公三)の銅像を造りたい」と言われた。
裏道を歩いていたら子供が何人か遊んでいたので「サラーム・アレイコム。アナ・ヤパーニ(こんにちは。日本人です)」と言ってみた。すると子供たちのお母さんが「家に遊びに来なさい」と言うのでついて行く。ソフィアという三二歳の女性で九人も子供がいるそうだ。瓜の中に米を詰めてトマトで煮込んだ料理をごちそうになった。中学生の長女が英語でいろいろ説明してくれる。家族の写真を撮り、送る約束をしてメモ帳に住所を書いてもらった。
ガザでインティファーダに遭遇
一二月二七日。朝、バスでエルサレムに戻り、セルビス(七人乗りのパレスチナの乗り合いタクシー)で一気にガザへ行く。オスロ合意の効果なのか、北部の境界にあるエレツ検問所でのイスラエル軍によるチェックは拍子抜けするほど甘く、難なくガザに入ることができた。 ガザは全体が金網のフェンスやコンクリート壁でふさがれて、五か所ある検問所のいずれかを通らないと入ることができない。東西冷戦時の西ベルリンと似た構造だが、イスラエルの一方的な都合で封鎖して兵糧攻めにすることがしばしばあり、こちらは本当に巨大な刑務所のような状態になっていた。 当時、ガザの人の多くはイスラエルへ出稼ぎに行っていた。ガザからイスラエルで最大の都市テルアビブまでは片道一〇シェケルのセルビスで一時間ほど。それで通勤して工事現場などで働いていた。携帯を義務づけられた身分証明書を持ってパレスチナからイスラエルに出稼ぎに行くさまは、南アのアパルトヘイトと同じだ。 ガザには地中海沿いにホテルが三軒建っていた。そのうちのひとつ、アダム・ホテルに泊まることにした。ホテルのまわりは紛争がなければビーチ・リゾートとして発展していたと思える環境で快適だった。ホテルの支配人は和平が実現することを期待していて「日本からも新婚旅行客が来るようになればよいのですが」と話していた。 しかしジャバリヤ難民キャンプが近くにあるガザの中心部は、インティファーダを伝えるニュース映像で見慣れていたガザの風景そのものだった。ロード・ブロックに使うコンクリート詰めのドラム缶、閉鎖された映画館、ときおり通りすぎていくイスラエル兵を乗せたジープ。それでも市場があり、ロバの荷車が行き交い、日用雑貨を売る店が開いていて人々の日常的な生活が営まれていた。 カセット屋ではパレスチナの音楽もけっこう売られていた。現地の人がいつもまっ先に推薦するのが、ヒッシャー・マサロフという歌手のカセット。音楽的にはエジプトのシャアビ(大衆歌謡)のような曲や、行進曲みたいな曲が入っている。どうも歌詞のメッセージがパレスチナ人を勇気づける内容のようで、支持されているらしい。他にはトラディショナルな結婚式の歌のカセットが何種類もあったりして、民族のアイデンティティーと係わる部分を大切にしているようだ。当時はまだ独自にヒップホップをやるグループは見あたらなかった。 ガザの住民はファタハとハマスに分かれていて、互いに牽制しあっていた。ハマスは、イスラム復興運動の観点から、アラファトがイスラエルと共存する道を選択したことを裏切りと捉えていた。パレスチナという国家はあくまでもアル・クドゥス(エルサレム)を首都に樹立されなくてはならないと考えている。ガザ地区では支持者が多く、ファタハと拮抗する勢力になっていた。 一二月三一日に、ファタハの集会があった。広場に五〇〇人以上集まっていて、西欧人ジャーナリストも二〇人ぐらい来ていた。特設ステージができていて、まずは、ウード、ダルブッカ、キーボード、ドラムによる演奏でパレスチナの国歌斉唱。続いてインティファーダのリーダーだったアブ・ジハードをはじめとする死んでいった英雄たちの名前を呼ぶ。次にハマスからのものも含めた祝電が紹介され、集会のハイライトに、パレスチナ人による軍隊の行進が行われた。軍隊といっても自警団のようなものだが、そのなかの数人が銃を持っていて、空に向けてパンパンと撃った。 その翌日、九四年一月一日。ガザ中心部で、突然始まったインティファーダに遭遇した。オマール・ムクタール通りに出ていた大勢の人が突然こっちに向かって走ってきて何事かと思ったら、三〇〇メートルほど先に、自動小銃を携えたイスラエル兵が横一列に並んでこちらに向かって歩いてくる姿が見えた。距離はどんどん狭まってくる。すると、若い男のパレスチナ人の何人かが、あらかじめ集めてあったいくつもの握り拳大の石をどこからともなく出してきて、イスラエル兵に向けて投げ始めた。イスラエル兵は、銃を水平に構えたり、何発か空に向けて威嚇射撃したりして近づいてきて、あっという間に一帯を制圧してしまった。道の向こう側でなにやらイスラエル兵に抗議しているパレスチナ人の男がいて、何だろうと思って見ていると、彼は突然走って逃げ出した。その直後、彼は足を撃たれてしまった。なぜ突然イスラエル軍がこのような行動に出たのかは判らないが、とにかく制圧して、イスラエル兵は四~六人のグループに分かれて街を捜索し始めた。ひとりの少年が連行されていくところが見えた。まわりのパレスチナ人たちは、ぼくに「写真を撮れ」と言う。外国の人にこの現実を知ってもらいたいからだ。ぼくはそのシーンを写真に撮った。すると、イスラエル兵が通り過ぎざま、ぼくに向けて「ファック・ユー」と言い捨てた。 [caption id="attachment_897" align="alignnone" width="500"] 94年1月1日のインティファーダ。左端が連行される少年[/caption]
94年1月1日のインティファーダ。左端が連行される少年[/caption]
アシュケナージとオリエンタル
ガザに滞在している途中、一二月二九日の朝から三一日の朝までイスラエルに行っていた。テルアビブまでセルビスで行き、イスラエルのバスで北部の町アフラへ。イスラエル人がファラフェル発祥の地と主張している町だ。イスラエル人とパレスチナ人は、ファラフェルとかホンモスを好んで食べることとか、じつは食文化の多くが共通している。アフラではまず、ファラフェルを高く投げてピタパンでキャッチして素早くタヒニソースをかけて作るファラフェル屋で腹ごしらえをして、近くにあるキブツ・イファット(Kibbutz Yifat)を訪ねた。東京で知り合ったイスラエル人ヒラの父がそこで生活しているのだ。 広河隆一は『パレスチナ』(八七年)で、初めはキブツという「理想の共同体」に強く惹きつけられてイスラエルに行ったと書いている。そしてある日、キブツがパレスチナ人の村を破壊した跡に作られたことを知って後の活動を起こすようになるのだが、ぼくも七〇年代末に「理想の共同体」としてキブツを知り、興味を抱いていた。 ヒラの父がキブツ・イファットを案内してくれた。敷地内に開墾当初の建物と生活用具を展示してある博物館もあり、本当に「理想の共同体」のように見える。 ヒラの父は、元はドイツに住んでいたが、ホロコーストを逃れて南米に移り住み、七〇年代になってからイスラエルに帰還したアシュケナージ(東欧系ユダヤ人)だ。今でもドイツ人には抵抗があること、ソ連崩壊後にロシアから帰還してきたユダヤ人が大勢いるけど彼らはヘブライ語をなかなか覚えなくてロシア風の生活をそのまま続けるので困惑していることなどを語ってくれた。 ヒラは日本にいたときは、東京でトワイライトゾーンというテクノのパーティーをオーガナイズしていたのだが、この頃はイスラエルに戻って、テルアビブに住んでいた。ガザを一月二日に出て、テルアビブのカルメル・マーケットの近くでヒラに再会した。 テルアビブは、エルサレムとは違って日常的な都市である。カルメル・マーケットの周辺は、セファルディー(環地中海系ユダヤ人)やミズラヒーム(アラブ系ユダヤ人)が多く住む地区で、テルアビブのなかでも古い街並が残っているところだ。 イスラエルでは、欧米の音楽や、クレツマーを含むアシュケナージによる音楽が主流で、テルアビブのタワーレコードにはそういう音楽のCDが並んでいた。しかしカルメル・マーケットのあたりには、それとはまったく別の種類のオリエンタルと呼ばれる音楽のカセットを売っている屋台がいくつかあった。当時日本でも知られていたイエメン系イスラエル人の歌手、オフラ・ハザがメイン・ストリームにいたのはあくまでも例外的で、オリエンタルのカセットは、モロッコ(特にマラケシュ)系、トルコ系などセファルディーや、イエメン系のミズラヒームによる音楽で、案の定、アシュケナージからは低く見られていた。ところがこちらのほうが、ギリシャのブルースとも言われるレンベーティカや、イエメン系ユダヤ人の音楽ディワンの影響はもとより、濃厚なアラブの臭いがするものも多く刺激的だ。まさに環地中海音楽の十字路なのである。オリエンタルのカセット屋では、アルジェリアのライの帝王ハレドのヒット曲〈Didi〉をカヴァーした曲が入ったものや、ギリシャの歌姫ハリス・アレクシウのカセットなども売られていた。ただしアラビア文字が書かれているものはなく、モロッコ系のものもすべてヘブライ語で表記されていた。 ユダヤ人といっても、さまざまである。ファラシャというエチオピア系の黒人のユダヤ人も見かけた。その一方で、パレスチナ人とイスラエル人の骨格が似ていると思うことがしばしばあった。同じような顔立ちで同じようなものを食べている。しかし、宗教が違う。ライフ・スタイルが違う。この近くて遠い双方の日常生活を均等に覗ける日本人という立場の不思議さを噛みしめた。 九四年一月五日、テルアビブのベン・グリオン国際空港。出国審査で荷物はほとんど見られなかったが、滞在中何をしたかという口頭試問とメモ帳のチェックを三〇分近くかけてやられた。アリーハでソフィアがメモ帳に書いた住所がアラビア語だったため問い詰められたりしたが何とか切り抜けて、エジプトのカイロへと飛んだ。*
その後九四年二月二五日に、ヘブロン虐殺事件が起こった。ヨルダン川西岸地区、ヘブロンにあるマクペラの洞窟で礼拝していたパレスチナ人に向けて、カハというユダヤ教過激派のメンバーが銃を乱射して二九人が死亡したのだ。同年一〇月一九日には、テルアビブで自分の体に爆弾を巻き付けた人によってバスが爆破されて二二人が死亡。ハマスが犯行声明を出した。イツハク・ラビンとヤセル・アラファトはノーベル平和賞まで受賞したが、ラビンは九五年に和平反対派のユダヤ人青年に暗殺された。暫定自治が始まってからのアラファトの周辺は汚職にまみれていると指摘されることが増えた。パレスチナ情勢はじりじりと悪化していき、〇〇年にアリエル・シャロンが岩のドームを訪問したことをきっかけに第二次インティファーダが始まり、和平へのプロセスは脆くも崩壊してしまったのである。