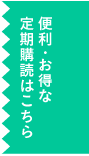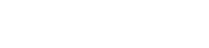「洋楽」と「邦楽」のあわいに生きる「ウナギイヌ」たる「カタコト歌謡」こそが、日本近代大衆歌謡の主流だったのではないか?! ──『創られた「日本の心」神話「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』でサントリー学芸賞を受賞した気鋭の音楽学者が、そんな新たな視点から歌謡史を洗い直す注目の連載。

PROFILE
輪島裕介
大阪大学准教授
わじま・ゆうすけ:1974年金沢生まれ。大阪大学准教授。専攻はポピュラー音楽研究・民族音楽学・大衆文化史。著書『創られた「日本の心」神話―「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』(光文社新書)で2011年度サントリー学芸賞を受賞。共著に『クラシック音楽の政治学』(青弓社)、『事典世界音楽の本』(岩波書店)、『拡散する音楽文化をどうとらえるか』(勁草書房)がある。
第1回 カタコト歌謡への道
これからしばらく「カタコト歌謡」について考えてみたい。
これをテーマとして論じた文章が公になるのはおそらくこれが史上初だろう。というより、「カタコト歌謡」とは、近代(とりわけ昭和以降の)日本歌謡史をある視点から見通すために筆者が案出した分析カテゴリーである。その限りにおいて「カタコト歌謡」の発明者は私だ、といっても過言ではない。ドーダ(©東海林さだお)。
しかし私が思いつくようなことはすでに誰かが言っているに違いない、と慣れない「ドーダ」でにわかに不安になり、Googleで「カタコト歌謡」を検索してみる(国会図書館や大宅文庫や新聞データベースでは引っかからない)。二〇一一年九月二一日現在、ヒットは約二三万一〇〇〇件。むう。気をとり直して内容を見る。ざっと見る限り「カタコト」「片言」と「歌謡」「歌謡曲」を共に含むサイトが表示されているようで、「カタコト歌謡」そのものズバリは少ない。安堵。
トップは「カタコト。」と題された個人ブログのエントリー、「【明星@SJ】060305人気歌謡!」(二〇〇六年三月五日)、内容は韓国の歌謡番組のレビュー。「カタコト歌謡」という用法ではない。「片」さんが台湾・韓国アイドルについて「ひとりごと」をつづるページで、略して「カタコト。」だそう。次はツイッターのログ、「ヤバい!カタコト日本語歌謡曲大好きな人には、超ツボな番組が日テレで今やってます。のどじまんTHE!ワールド(*_*)」というもの(二〇一一年六月二五日 174.36.45.50/5gh5yr)。
次に示されたのがタワーレコードの商品紹介ページ。モノはKARAのCD『ガールズトーク(通常版)』だ。
スリー・ディグリーズの『Internation』がリイシューされて、細野晴臣のペンによる〝ミッドナイト・トレイン〟などの日本語曲をちょうど聴いて思ったんですが、日本にはアグネス・チャンの昔からチリアーノとか初期マルシアとか初期BoAやらココナッツ娘。―と連綿と紡がれてきた〈カタコト歌謡〉の歴史があります。ただ、KARAの日本語曲には言葉の違和感が希薄なので、片言マニア(?)には満足度が低いかもしれません
出嶌孝次 - bounce vol.327(二〇一〇年一一月二五日発行号)掲載(タワーレコード)
ビンゴ! 「カタコト歌謡」の語が特定の音楽群を指示するために用いられている。そのことでこの語が筆者の独創ではないことが証明されたのは残念だが、この評言は本論考で扱うべきテーマの、少なくともある重要な一面を言い当てている。つまり「外国人」(日本語を母語としない人)が日本語の楽曲を歌うのが「カタコト歌謡」であり、その「マニア」にとっては、「言葉の違和感」こそが魅力となる、という洞察である。しかし、この種の歌謡がアグネス・チャンどころではない「昔」から連綿と続いてきたことは、本論考のなかであきらかになるだろう。
さらに興味深い事例に行き当たった。TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル」の番組サイトだ。二〇一一年四月二七日にサタデーナイトラボ「輝け!〈裏PRAY FOR JAPAN〉歌謡祭!」が放送されている。曰く「世界のミュージックシーンで活躍するトップアーティストたちが『親切にも!』『カタコトの日本語で!』歌ってくれた曲だけをまとめてお届けする〈親切な歌の祭典です〉」(「カタコト歌謡」の語は用いられていない)。曲がカットされた(生殺し!)ポッドキャストを聴いてみたところ、ポリス、デヴィッド・ボウイ、フィル・コリンズ、ニュー・オーダーなど、いわゆる「洋楽」(つまり英語圏のポップ/ロック)の錚々たるミュージシャンたちが日本語で歌う楽曲が紹介されている。「親切」というキーワードは、趣味のヒエラルキーの上位者である「洋楽」のアーティスト様が、ありがたくも「われわれ下々」の日本のファンのために日本語で歌ってくださっている、という構図を強調するために用いられているようだ(もちろんこの企画ではそのような構図自体を問題化しているのだが)。
さすが天下のGoogle様、検索トップページだけで、これから試みる考察の叩き台を見事に提供してくれた。「カタコト歌謡」という語自体はあまり用いられていないにせよ(筆者にはむしろ好都合)、その言葉で筆者が指示しようとする音楽的対象とその社会的・美的な含意については、音楽関係者の間で相当明確に認識されていることがわかる。
それだけではない。前者のように「邦楽」(日本の芸能界)の文脈で語られる場合と、後者のように「洋楽」の文脈で語られる場合では、なんとなく意味合いが異なっている、という気配も感じられる。つまり、前者では、「言葉の違和感」自体が、感覚的な魅力として言及されているのに対して、後者では、日本の音楽好きが有している(いた)「洋楽」と「邦楽」の優劣関係が、「洋楽アーティストのたどたどしい日本語歌唱」によって不安定にさせられる不自然さや居心地の悪さが、「親切」という皮肉なキーワードに焦点化されているといえる。
さらにいえば、前者と後者の「邦楽/洋楽」対立は、かなりの程度ジェンダー化されていそうだ。前者では、チリアーノ(私の世代にとってテレビドラマ『特捜最前線』のエンディングテーマ〈私だけの十字架〉の物悲しさはほとんどトラウマと言ってもいい)を除き、女性の、特に「アイドル」的な傾向を帯びた歌手が列挙されるのに対し、後者では男性の自作自演のロック・アーティストが並ぶ。そして、前者にはアジア系の出自を持つ人々が多く含まれるのに対して、後者はほとんどアングロ・サクソンだ。ここには近現代日本における、ジェンダー、エスニシティ、言語の秩序やヒエラルキーの感覚に関して相当に厄介な問題が含まれていそうだ。
ところで、Google検索の五ページ目では、「【芸能】「少女時代」の魅力は片言の日本語…岡村隆史も彼女達がコンサートで言った「あちゅいでしゅね〜」をずっと真似していた★3」という2ちゃんねるの過去ログが引っかかった。ご想像の通り、「少女時代の片言の日本語が魅力である」とする発言(これはナイナイ岡村ではなくCOWCOW多田のブログがソースなのだが)を非難する、目を覆いたくなる差別的な言辞が並ぶのだが、その「魅力」として「あちゅいでしゅね〜」という、幼児語めいた発音が強調されていることは考えさせられる。カタコト歌謡の魅力は、エスニック・ステレオタイプや偏見、矮小化と結びつきうる、かなり危ういものでもあることは認めざるをえない。
つまり「カタコト歌謡」は「洋楽」と「邦楽」のあわいに生きる「ウナギイヌ」のようなもの、といえるかもしれない。このすっとぼけた、とらえどころのない(なにしろウナギだ)、喜劇的でもあり悲劇的でもある(大抵バカボンのパパに食べられる)、両義的な存在について考えることで、「ウナギ」と「イヌ」のそれぞれに関しても新たな洞察が得られるのではないか。
というだけでは収まらない。というのは、筆者は、この「ウナギイヌ」たる「カタコト歌謡」こそが、実は近代日本の大衆歌謡の主流だったのではないか、少なくとも「カタコト歌謡」の系譜として日本の大衆歌謡史を語ることができるのではないか、と考えているのだ。速水健朗が「タイアップ」という分析視角から一つの近代日本歌謡史を見事に描き出したように(速水健朗『タイアップの歌謡史』洋泉社、二〇〇七)、「カタコト歌謡」という観点からみた近代日本歌謡史が可能であり必要だろう、と本気で思っている。
ただし、そのためには「カタコト歌謡」概念をもう少し拡張する必要がある。「日本語を母語としない歌手による日本語歌唱楽曲」のみならず「非日本語話者の日本語のように歌う歌謡」、あるいは端的に「日本語を英語っぽく発音する歌謡」まで含めることを提案したい。ディック・ミネ、坂本九、キャロル、サザン、ゴダイゴ、佐野元春、Boφwy。ここにトニー谷や内田裕也の英語交じりトークや日本語ラップ及びラップ歌謡を付け加えてもいい。
こう並べると、いわゆるJ−POPとはおしなべて日本語を英語っぽく歌う「カタコト歌謡」なのではないか、という気がしてくるだろう。そしてあの「養老の星☆幸ちゃん」の歌唱は、J−POPの「カタコト性」を暴露し、言語としてほとんど理解不能なレヴェルまで脱構築(書いててちょっと恥ずかしい)するきわめて批評的な実践だったのではないか、とさえ思えてくる。
*
賢明なる読者はもうお気づきだろう。この試みは、昨年上梓した拙著『創られた「日本の心」神話―「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』(光文社新書)と対をなしている。拙著では、一般的に日本的、伝統的と考えられている(いた?)「演歌」が、明示的なジャンルとしては非常に新しく成立したものであること、そのジャンル化が、きわめて特異な思想的アクロバットによってなされたものであることを論じた。その過程で、現在では「演歌」に包摂されがちな「日本調」歌謡(小唄調、民謡調、浪曲調その他)の変遷を、特に歌唱法や「声の肌理」に着目して、ある程度通時的に記述した。それに対して本連載でこれから試みる考察は、「日本調」と対比される「洋楽調」の系譜を、同様の観点から辿ろうとするものである。 もうひとつ、前著執筆時点では、具体的な歌手や楽曲への言及は、あくまでも「演歌のジャンル化」という主題を語るための前提と考えていたのだが、読まれる文脈では、幸か不幸か(どういう形であれ読んでいただければありがたいのだが)、これが一種の通史と捉えられている節がある。そこで前著では扱えなかった、しかも私自身としてはむしろ日本のレコード歌謡の「本流」なのではないかと考えている側面について論じ、本格的な通史とはゆかずとも、まがりなりにも筆者の歴史的な見取り図を提示することが必要だろうと考え、この主題に着手するに至った、というわけである。 「カタコト歌謡」への注目は、事例のレヴェルで前著の「演歌」と対をなすだけではない。むしろ演歌の国民文化化を促進したロジックを内在的に批判する、という意図もある。というのは、演歌ジャンル成立後に、それが当初の対抗文化的性質を喪失し、「伝統」と密着した「国民文化」に成り上がって(成り下がって?)ゆく時期に、演歌に代表される近代日本の大衆歌謡は、「正しく美しい」日本語を保持しているという美点を持つがゆえに「西洋かぶれ」の芸術歌曲や学校唱歌よりも真正である、という趣旨の発言がしばしばなされた。民族音楽学者の小島美子は、日本語の発音が不自然な日本のクラシック声楽家を批判して次のように述べる。 歌謡曲などの人びとは、むしろ歌詞から歌に入ってゆく。まず詩をなんども読んで、その意味や感じなどがよくわかり納得したら、初めてメロディを覚えるのである。歌詞の表そうとしているものを伝えることのできないような歌は、歌謡曲の分野ではまったく通用しないからだ。だから歌謡曲の歌手の日本語はよくわかり、そのデリケートな語感さえも巧みに表している人が少なくない。とくに演歌の歌手がそうだ。日本語の発音のおかしな歌謡曲歌手といえばウェスタン調の尾崎紀世彦か、かけ出しの人びとぐらいだが、その尾崎よりもちゃんと日本語が歌えるクラシック歌手が、いったい何人いるだろうか。(小島美子『日本の音楽を考える』一九七六年、音楽之友社、一七頁)*
小島の場合、日本におけるクラシック至上主義の批判という意図に基づき、それとの対比において「演歌」をはじめとする「歌謡曲」歌手の日本語歌唱を高く評価しているわけだが、近年でも、クラシックの声楽家である藍川由美が、『これでいいのか、にっぽんのうた』や『「演歌」のススメ』(ともに文春新書)といった著書で従来の日本歌曲における日本語の「間違い」を激しく批判しつつ、中山晋平や古賀政男や古関裕而の楽曲を、彼女が考える「正しく美しい」日本語および「正確な」楽譜に基づいて録音している(彼女が『「演歌」のススメ』の中で「ススメ」ている大衆歌曲のほとんどは「演歌」というジャンルが確立する以前のものであり、楽譜や日本語発音の「正確さ」へのあくなき探究心に比して、用語法の歴史的な変遷についての「正確さ」にはまるで無頓着なことが伺えるのは興味深い)。 それに対して、演歌に代表される大衆歌謡の中には正しく美しく伝統的な日本語が息づいている、という幻想とも願望ともつかない考えを、「カタコト歌謡」という観点から相対化することが本論の目論見の一つである。藍川の「これでいいのか、にっぽんのうた」という問いかけに対して、「これでいいのだ」と断言すること、ではないかもしれないが、少なくとも、「いいか悪いかの前に、ほんとにそうなのか、だとしたらなんでそうなのか考えてみましょうよ」ともぐもぐと応えるようなものではあるだろう。 さらに大風呂敷を広げれば、「母語を正しく美しく歌う」ということが、歌を歌い、聴くという行為にとってどの程度重要なのか、もっといえば「歌」と「言語」はどのように関わる(べきな)のか、といった問題に、新たな光を投げかけるような、これは相当に壮大なテーマであると、本気で考えている。*
前口上が長くなってしまった。今回は日本の流行歌/歌謡曲はそもそもカタコト歌謡として始まったのかもしれない、という話をしよう。取り上げるのは記念すべきカタコト・レコード歌手第一号、バートン・クレーンである(『バートン・クレーン作品集』NEACH RECORDS NEACH-0123、山田晴通「バートン・クレーン覚書」 http://camp.ff.tku.ac.jp/yamada-ken/y-ken/fulltext/02BC.htmlを参照されたい)。〈酒がのみたい〉(一九三一)は大衆音楽史に興味のある方なら絶対に聴いておかねばならない一曲。サトウハチローをして「歌そのものが既に酔っ払っている」といわしめた奇天烈なカタコト歌詞と歌唱だ。ほかにも「太郎は一番のアホですよ」(〈コンスタンチノープル〉)や「ポクポク仔馬」(〈ニッポン娘さん〉)など、破壊力満点のパンチラインが次々繰り出される。 クレーンは英字新聞『ジャパン・アドバタイザー』の特派員で、東京の花柳界で夜な夜な酔っ払って外国曲に適当な日本語詞をつけて歌っている「ヘンなガイジン」がいる、との噂を日本コロムビアの社長ホワイト氏が聞きつけて、録音させたところ大ヒット、という。実際のところどうだったのかは知る由もないが、ちょっと引っかかりはしないか? 確かに彼の歌はこの上なく素っ頓狂で愉快なシロモノには違いないにせよ、なぜズブの素人のアメリカ人の歌を録音しようと思ったのか、そしてなぜそれが図にあたったのか。 そこにはこの時期の、外資系の参入によるレコード産業の大転換という事件が影を落としている。そしてそれは、本誌の今号のテーマに絡めて言えば、「震災後」という条件に深く規定されていた。 こういうことだ。関東大震災からの復興のために贅沢品の輸入に多額の関税がかけられ、蓄音機とレコードもそこに含まれていた。そこで、すでに日本を大きなマーケットとしていたビクター、コロンビア、ポリドールといったレコード産業の世界的メジャーは、国内の輸入代理店を通すのではなく日本法人を開設し、原盤を輸入し日本でプレスして販売するようになった。さらに、輸入原盤のプレスばかりでなく、海外で開発された録音技術(折しもマイク録音が発明されたばかり)や最新流行の音楽スタイルを用いて日本国内でもレコード制作してみるか、となるのも不自然ではない。 そこで最初に当たったのが、浅草オペラ出身でエノケンの盟友、二村定一が歌った〈青空〉と〈アラビアの歌〉という二曲のティン・パン・アレイ楽曲の日本語盤である(この二曲については三井徹「企画流行歌の誕生期―〈アラビアの唄〉/〈青空〉再考」、三井徹監修『ポピュラー音楽とアカデミズム』[音楽之友社、二〇〇五年]を参照されたい)。前者〝My Blue Heaven〟はいうまでもなく世界中でヒットしたスタンダード中のスタンダードだが、後者〝Sing Me a Song of Araby〟は本国ではどこの誰が録音していたのかもわからない謎の楽曲だ。日本限定で人気の洋楽、いわゆる「ビッグ・イン・ジャパン」のハシリともいえ、これも「カタコト歌謡」と同様、日本における「洋楽」の大衆的受容のきわめて重要な側面だ。 〈青空〉〈アラビアの唄〉(つまりティン・パン・アレイ)のフォーマットを模した国産楽曲として初の大ヒットとなったのが佐々紅華作詞作曲、二村定一歌〈喜味こいし〉もとい〈君恋し〉(一九二八)である(寒い冗談だが、漫才師の芸名に使われるほど流行した、ということだ)。それに続いたのが西條八十作詞中山晋平作曲佐藤千夜子歌〈東京行進曲〉(一九二九)。マイク録音を生かしたフルバンド伴奏を伴うティン・パン・アレイ式の楽曲、という新機軸は、これらが先鞭をつけたと言っていい。ここで、既に別の文脈で流行している曲をレコードに録音するのではなく、レコードとして発売することを前提に新曲が企画・制作される、という転換が起こる。その過程で、制作から流通、小売店までを抱え込む垂直統合方式を導入し、国内の都市部各地に点在していた地場産業的な国産レコード会社を買収・駆逐してゆく。現代のJ−POPまで続く、「レコード発売を前提に企画・制作される欧米フォーマットに則った日本製歌謡」という意味における流行歌/歌謡曲(本稿ではこれを「レコード歌謡」と呼ぶことにする)の産業的な基盤がここにおいて確立した、といってもよい。 さてそれがバートン・クレーンのカタコト歌謡と何の関係が? ポイントは上記のレコードはすべて日本ビクターから発売された、ということだ。ティン・パン・アレイのノックダウン生産というべき日本製ジャズ・ソングで快進撃を続けるビクターへの対抗上、日本市場では日蓄以来の大先輩でもあるライバル会社のコロムビアが面子をかけて見出したのが、夜の巷でカタコトの酒呑みソングを歌う日本駐在アメリカ人、バートン・クレーンであった、というわけだ。ビクターのティン・パン・アレイ式日本語ヒットソングに対抗するために、クレーンの珍妙な「カタコト歌謡」が選ばれ、しかも実際に相当ヒットしたということは、当時のレコード歌謡の位置づけを推測する上でも興味深い。つまり、ここ四〇年ほど「ナツメロ」という括りにがっちり組み込まれている〈君恋し〉や〈東京行進曲〉も含め、当時においてはレコード歌謡というものそれ自体が、「横のものをむりやり縦にした」ような違和感を伴う新奇な舶来風文化であったのではないか。端的に言えば、二村定一も佐藤千夜子も、ひょっとしたら当時の耳には「カタコト的」に聞こえていたんじゃないの? ということだ。 そしてそれは、主に都市の新興中間層と結びついたモダンな夜の巷の享楽、はっきり言えば「酒と女」を歌う、「エロ・グロ・ナンセンス」文化でもあった(〈青空〉の家庭志向は異なるが、新興中間層の生活を歌ったものとして相補的である)。佐々紅華や西條八十が文学的なオブラートにくるんで表現した主題が、非母語話者のクレーンにかかると「酒がのみたい」、「酒と女とは一番よいものだ、これさえ手に入れりゃ現世の極楽だ」(〈おいおいのぶこさん〉)とミもフタもなく言いきられてしまう。過剰なインチキ臭さで酒色の享楽を謳歌する道化、という意味で、たとえばあやまんJAPANとチャラ男藤森の日本語破壊パフォーマンスの中にバートン・クレーンの遠い反響を見出すこともあながち不可能ではない。 なお、旧来の流行歌史では、昭和三〜四年の〈青空〉〈アラビアの唄〉〈君恋し〉〈東京行進曲〉のビクターの快進撃に対し、昭和六年以降コロムビアは「古賀メロディー」で反撃した、といわれる。事実としてはその通りにせよ、これは「洋風」から「和風」への転換と解釈されることが多いが果たしてそうか。クレーンの〈よういわんわ〉(盤面には「ナンセンス小唄」と記されている)は、東京のカフェーの女給との掛け合い仕立て(相手役は淡谷のり子!)で「よういわんわ」をキーワードに大阪の夜の街事情(?)を描くものだが、「あなたが大阪にいらしたとき一番流行の歌はなんでしたでしょう」という問いに対して〈酒は涙かため息か〉を「商売は涙かため息か」と換えて歌いこんでいる。もちろんこの一事をもって、クレーンも「古賀メロディー」も同じだ、ということは到底できないにしても、どちらも都会の夜の「酒と女」に関わるモダン文化として位置づけられていたことがうかがえる(都市モダン文化としての「古賀メロディー」に関しては、映画『東京ラプソディー』(一九三六年)が非常に参考になる)。と、〈よういわんわ〉をYouTube検索すると、関連動画で、日系二世でカリフォルニアから来日したジャズ歌手・森山久(良子の父、直太朗の祖父、そしてムッシュかまやつの叔父)と思しき歌手による〈酒は涙かため息か〉英語版ジャズ編曲がアップされていた(動画タイトルでは「藤山一郎」となっていたが)。和製ジャズ・ソングと「古賀メロディー」の距離の近しさを示す好例といえる。この音源の素性の追及は私の手には余るものだが、この事例は、次回テーマへの絶好の橋渡しでもある。 ということで、次回は「二世歌手とニセ二世」でお会いしましょう。それではビールをくれたまえ!第2回 二世歌手とニセ二世
戦前日本ジャズのリバイバル・ブーム
このところ、戦前日本ジャズの研究・復刻が大変な活況を呈している。今回のテーマは、その蓄積に大幅に依拠しているため、まずは簡単に言及しておきたい。 学問研究の文脈では、合衆国の歴史学者による通史、Taylor Atkins, Blue Nippon(2001)や、マイク・モラスキー『戦後日本のジャズ文化』(二〇〇五)が日本ジャズへの注目を高めたことは間違いない(これらも含むジャズ研究の最新動向は、意欲的なアンソロジー『ニュー・ジャズ・スタディーズ』にまとめられている。さて、版元はどこだったか)。 しかし、音楽好きの広範な関心を集めるようになったのは、この分野の第一人者・瀬川昌久氏の名著『ジャズで踊って』(初刊一九八三)が二〇〇五年に復刊され、翌二〇〇六年には前回取り上げたバートン・クレーンの復刻CDが『レコード・コレクターズ』誌のリイシュー・アルバム「日本のロック/歌謡曲/芸能」部門第一位に選ばれたあたりがきっかけだろうか。同年には同盤の配給会社であったブリッジが自社レーベルから『日本のジャズ・ソング』(これは一九七六年のLPセットの再復刻)を発表し、その後もハタノ・オーケストラや、後に触れる童謡ジャズ、服部良一未復刻曲集など、きわめて意義深い復刻を数多く行っている。 二〇〇九年には、大谷能生による瀬川昌久の聞き書き『日本ジャズの誕生』が刊行されており、これは菊地成孔と大谷が進めてきた「ジャズ史の書き直し」の一環に戦前日本を位置づけるものといえる。 さらに、直近の動きとして、二〇一〇年に刊行された毛利眞人『ニッポン・スウィングタイム』をうけて、レコード会社をまたいだ大規模な復刻CD企画『ニッポン・モダンタイムス』が昨年末よりスタートしている。各盤の詳細には立ち入らないが、このケッタイな連載を楽しんでくださるほどの風流な方であれば問答無用でコンプリートすべき驚くべき内容、とだけ申し上げておく。普段ならまったく面白味に欠けるいけすかない堅物のイメージしかない(注・個人の感想です)藤山一郎でさえ愛らしく思えるような絶妙の選曲で楽しませてくれる*
戦前日本ジャズの一種の「ブーム」ともいうべき状況は、今回が初めてではない。一九八〇年代にも若干似た動きはあった。その中心はいうまでもなく、先日逝去した斎藤燐の戯曲『上海バンスキング』(一九七九年初演)であった。オンシアター自由劇場のロングラン公演のほか、二度にわたる映画化がなされた。同作のための取材がもとになった戦前のジャズ・ミュージシャンの聞き書き『昭和のバンスキングたち』が『ミュージック・マガジン』に連載され、若い音楽ファンの注目を集めた。 さらには主演女優・吉田日出子のヴォーカル・アルバムも大成功を収め、〈林檎の木の下で〉〈ウェルカム上海〉などは、一種スタンダード・ナンバー的な地位を獲得した(なお、浅草オペラ、アーニー・パイル劇場、ムーラン・ルージュを題材にした戯曲、西條八十や藤原義江を扱った「昭和不良伝」シリーズなど、近代日本の大衆文化における「西洋」の光と影を鋭く描いた斎藤燐の仕事については別の機会に(もっと修行を積んだ後に)論じてみたい。ご冥福をお祈りする)。川畑文子―全米のスターが日本デビュー
さあ、ようやく今回のお題に辿り着いた。勘の良い方はおわかりだろう。吉田日出子のちょっと舌足らずで甘ったるくねばっこいあの独特のヴォーカル・スタイルは、日系アメリカ人歌手として最初に来日し、昭和八年からのわずか数年の間にめざましく活躍し多くのフォロワーを生んだ川畑文子の歌唱法を真似たものだったのである(以下、本稿では戦前の「日系アメリカ人歌手」を「二世歌手」と称する)。 たどたどしい日本語発音で歌われる川畑の歌唱は、音楽学校出身者のベル・カントとも、芸者歌手ののどを閉めた発声とも全く異なるもので、当時「マレーネ・ディートリッヒのような」としばしば形容された。連想を逞しくすれば、こちらが吉田日出子のフィルターを通して聴いてしまうせいもあり、音程の微妙な不安定さや棒読み風のアーティキュレーションも含めて一九八〇年代ニューウェーヴ的レトロ趣味とも親和的である。バンドブーム前夜のインディーズ・バンドの女性ヴォーカルというか、昔の清水ミチコが真似しそうな感じ、というか。さらに勝手な連想を重ねれば、この川畑文子=吉田日出子のラインは、若干のアストラッド・ジルベルト風味を加えて、現在でも小野リサ、クレモンティーヌ、アン・サリーといったあたりにまで引き継がれているのではないだろうか。 アリス・フミコ・カワハタは一九一六年に日系一世の父、二世の母の間にハワイで生まれた。三歳で転居したLAでダンスを学びはじめ、一三歳にしてニューヨークに移り、映画・放送・興行にまたがる一大メディア・コングロマリットとして一九二九年に設立されたばかりのRKOと専属契約を交わし全米を公演するスター・ダンサーとなった。「琥珀色のジョセフィン・ベイカー」の異名を取ったという彼女が日本を訪れた事情は、管見の限りはっきりしない。ディック・ミネは「奇術師の[松旭斎]天勝が世界をまわってアメリカでひろって連れて来たんだから」と述べている。彼女の生涯を小説として描いた乗越たかお『アリス ブロードウェイを魅了した天才ダンサー 川畑文子物語』によれば、目を患っていた母方の祖母を生まれ故郷に連れて帰るために強引に休暇をとっての「お忍び」であったという。 いずれにせよ、一九三二年九月に来日した彼女は、翌年二月になって日本コロムビア社と専属契約を結び日本での芸能活動を開始する。RKOとの専属関係を重視するならば日本コロムビアではなく、RKO系列のRCAを親会社に持つ日本ビクターと契約するのが自然な流れなのだが、このことは、彼女の日本での芸能活動が、少なくとも日系スターを売り込むために米メディア企業によって仕組まれたというようなものではなかったことを示しているだろう。むしろ「お忍び」で来日した彼女の日本での芸能活動は、日本のショービジネスの側からの要求に基づくものだったと考えられる。 日本コロムビアが専属契約を結ぶにあたっては、同社のカタコト歌手バートン・クレーンの成功が当然念頭にあっただろう。川畑の歌うジャズ・ソングの日本語訳詞を行ったのは、クレーンと同様、後の東宝重役・森岩雄だった。瀬川昌久は、「異色外人、バートン・クレーンによって始められたタドタドしい日本語と本場の英語ジャズを唄うパターンが、彼女のユニークな発声と唱法によって更に確立され、一世を風靡した」と述べ(『日本のジャズ・ソング 二世ジャズシンガー川畑文子』解説)、その理由の一端を次のように説明している。 デビュー曲「三日月娘」の「何たる今宵は、暗い夜でしょ」の「何たる」というところが、文章としてはおかしいのに、ぴったりと節にあって、魅力にさえなった。このところがこの歌の大ヒットだと、藤浦洸がほめている。森岩雄自身は、「泣かせて頂戴」という曲の訳詞がいちばん気に入った、といっている。大胆な自由訳でぎこちない日本語になったが、それがまた川畑がうたうとなんともいえない魅力になって、新橋あたりで大いに流行して森も得意になったそうである。(『ジャズで踊って』一六六頁) 残念ながら、藤浦の発言の出典をつきとめることはできなかったのだが、「何たる」という文法的な破格や「ぎこちない日本語」、本稿の言葉でいえば「カタコト」性を積極的な魅力とする見方がすでに同時代に存在していたことがわかる。「ザッツ・オーケー」が流行語に
ところで、話題は遡るが、昭和初期の日本コロムビアにおける「カタコト」企画の誕生に関して興味深い資料を入手したので、ぜひとも見せびらかし、もとい紹介しておきたい。大正一四年に日本コロムビアの前身、日本蓄音機商会に入社し、後にテイチクに転じたレコード・ディレクター川崎清の回想録『レコード盤と共に』(私家版)である(明治大学在学中の学生社長ならぬ社長学生、平川亨氏が発見されたものを譲っていただいた。記して感謝申し上げたい)。 川崎は、昭和五年に〈ザッツ・オーケー〉を企画している。同曲はクレーンの〈酒が飲みたい〉(一九三一)に一年先立つものであり、レコード会社企画の日本製楽曲としてはおそらく初めて英語フレーズをタイトルに冠したものである(もちろん、「ジャズで踊ってリキュルで更けて」の〈東京行進曲〉からも明らかなように、日本語化された英単語の使用はこの時点で既に珍しいものではなく、その気になれば明治の〈ダイナマイトどん〉まで遡りうる。英語フレーズを用いた歌も、大正期の書生節〈アイドントノー節〉などがあり、〈ザッツ・オーケー〉が全く初めてというわけではないが今回は問題にしない。本連載の中で「レコード以前のカタコト歌謡」についても扱う機会が持てればと考えている)。 川崎によれば、昭和四年に新社長に就任したL・H・ホワイトの下で日本蓄音器商会から日本コロムビアと社名変更し、外資導入、電気録音などの一大改革が断行された結果「従来のようにただ名人の芸を選んで録音するという時代は次第に過去のもの」となり、「代わって会社自身が新しい企画をたて、購買者の需要に応えるべく広いアイデアのもとに意欲的な制作に努力を傾け」るようになった、という(六二頁)。川崎は、そこでのレコード・ディレクターの仕事を映画監督に比較してもいる(ただし、その「権威」の違いを自嘲しながらではあるが)。 このような企画重視の流れの中で、従来から「英語万能で、重要書類や支払伝票などすべて英語」(六一頁)であった同社では「OK」や「NG」という言葉が日常的に用いられており、川崎はその点に注目して「ザッツ・オーケー」という言葉を流行歌に取り入れ流行語にしようと考えた、という。それを松竹宣伝部長に相談したところ、同宣伝部嘱託の明治大学講師・畑耕一を作詞家として紹介され、これを主題歌にした映画『いいのね誓ってね』ともども流行した。川崎は、「自分の企画によって『ザッツ・オーケー』という言葉が一般人の流行語になったことは喜びにたえませんでした」と誇らしげに記している(七二〜七五頁)。もちろん、〈ザッツ・オーケー〉だけが、クレーンから川畑文子に至るカタコト・ジャズ・ソングを準備した、と主張するつもりは全くないが、レコード制作における社員ディレクターの中心的役割、外資系レコード会社の英語万能の風潮、映画産業とのタイアップ、という、昭和初年のレコード歌謡草創期の、やや軽薄でハイカラな雰囲気がうかがえる。その中で、レコード向きの新ジャンルとして「カタコト歌謡」が作られたのである。「子供らしさ」の商品化
話を戻そう。川畑文子の成功をうけて、昭和九年から一一年ごろの間、二世歌手が続々と登場する。ベティ稲田、リキー宮川・宮川はるみ兄妹、森山久とティーブ釜范の義兄弟(妻同士が姉妹)、灰田晴彦(のち由紀彦)・勝彦兄弟などだ。特に、チェリー・ミヤノ、リラ・ハマダとニナ・ハマダ姉妹、ヘレン隅田、二世ではないが日英ハーフのマーガレット・ユキといった年若い少女歌手が多く、しばしば童謡風の楽曲を録音していることは興味深い(コンピレーションCD『オ人形ダイナ』にまとめられている)。 こうした企画は二世歌手のロール・モデルとなった川畑が一〇代の少女であったことや、子役映画スターのシャーリー・テンプルの人気にあやかった部分も多いと思われるが、たどたどしい日本語を話す者(特に女性)が、未熟で不完全な(それゆえ「無垢」で「天然」な)「子ども」として商品化・フェティッシュ化する、という、「カタコト歌謡」のネガティヴな(とあえて言い切ってしまおう)側面が、この時点で既にあらわれている、と考えられる(例えばビビアン・スーやBoAは、日本の芸能界では年齢や能力や個性にかかわらず未成熟で無垢な「子ども」のように扱われていたといえるだろう)。 さらにいえば、レコードとして商品化された童謡自体、「子どもらしさ」のフェティッシュ化と不可分に結びついた存在であった。ここでいう「童謡」とは、大正期以降のプチ・ブルジョア的な「家庭」をターゲットとした文芸運動に起源を持ち、昭和以降、「家庭向きレコード」として商品化されることで、特定の声の質が喚起する「子供らしさ」と結びついていった音楽ジャンルである(周東美材「「令嬢」は歌う」『思想』二〇〇八年五月)。 文学研究者の坪井秀人は、戦前の「童謡」歌唱において顕著に見られる少女の甲高く扁平な発声が、知識人によって理想化された透明で無垢な「少女」イメージの強制と結びついていると指摘し、「レコードの歌声の中で、平べったく透明な物言わぬ彼女たちは、大人や男性への批判の視点を持たぬ、極めて安全で好都合な置物、高級なインテリアとなりおおせている」と論じている(『感覚の近代』(名古屋大学出版会、二〇〇六、三六一頁)。 翻って〈お人形ダイナ〉〈お人形の結婚式〉(いずれもチェリー・ミヤノ)といった楽曲は、彼女たち自身が、洋風で英語もタップダンスもできる舶来の、しかし当時の和洋折衷の文化住宅の応接間に置いても違和感のない「置物」であり「高級なインテリア」とみなされる文脈があったことを示唆しているだろう。もちろんその一方で彼女たちは、いわゆる「令嬢」のイメージを前面に出し、実際にそうした出自を持つ者が多かった日本人童謡歌手とは異なり、はるばる海を渡ってやってきたショービジネスの「プロ」でもあり、性急な一般化は慎むべきだが、二世少女歌手の歌う童謡ジャズの「可愛らしさ」が孕む問題は案外根深いだろう。ディック・ミネ──方法としての「カタコト歌唱」
一方、こうした「少女」のイメージの対極にあるのが、数々の「性豪伝説」に彩られた「ニセ二世」ディック・ミネだ。帝大出の厳格な中学校長(一種の文部官僚)を父に持ち、立教大学でバンドマンとして鳴らした三根徳一は、卒業後は逓信省に勤務していた(「おやじが無理矢理、役所に入れちゃったの。あの頃は就職難でね、〝大学は出たけれど〟だったから、その年に逓信省に入ったのは、東大出と僕の二人だけ。もちろん僕は裏口」(『昭和のバンスキングたち』六二頁))。その傍ら、各レコード会社でスチール・ギター奏者として活躍し、昭和九年末に新興レコード会社のテイチクで歌手として吹き込んだ(発売は翌年)〈ダイナ〉が大ヒットする。 つまり、彼は特権的なエリートであるブルジョア大学生の軟派文化の一貫としてジャズにどっぷり浸かった人物であり、もちろん日系アメリカ人ではない。「ニセ二世」は筆者の造語だが、芸名の付け方や歌唱法など、当時の二世歌手を強く意識していたことは疑いない。戦後のインタビュー記事になるが、「僕は名前のせいで二世だと思われるんですが、全々外国へ行ったことはありません。純粋のタクアンですよ。しかし二世のリキー・宮川だの灰田勝彦だのの方がタクアン臭いものを唄いますね」(『占領期雑誌資料大系・大衆文化編Ⅲ アメリカへの憧憬』一四八〜一四九頁 ディック・ミネ「僕のジャズ談義」『音楽之友』4巻5号、日本音楽雑誌(東京)、一九四六年五月)と述べている。 二世よりも二世らしい、この「ニセ二世」ディック・ミネこそは、現在のJ―POPのメインストリームともいえる日本語を英語風に歌う「カタコト歌唱」の発明者である。クレーンや二世歌手にとってむしろ言語能力による表現上の「制約」であったかもしれないカタコト歌唱は、ミネによって「方法」として再定義された、といえるかもしれない。 ミネは、斉藤燐による聞き書き『昭和のバンスキングたち』のなかで次のようにその秘密を開陳している。[歌詞を]正確に日本語でやるとどうもブルースにならない。そこで思いついたのが、外人の喋る日本語。LとR、SにしてもTにしても全然違う。だから日本語の歌詞をいったんローマ字にしてね、アメリカ人だったらどう発音するか考えたわけ。(六〇頁)この発言をうけて斎藤は、「おそらく、ディック・ミネによって創られたジャズ・ソングの日本語の発音方法は川畑文子やベティ稲田に伝えられ、五〇年後の吉田日出子の歌い方に引き継がれていったのだろう」と記している。 先述のように川畑もベティ稲田も、ミネのデビュー以前からコロムビアで多くの録音を行なっており、テイチク専属である三根徳一訳詞・編曲楽曲の録音は彼女たちが同社に移籍した昭和一〇年以降である。それゆえ「ミネの発音方法が川畑やベティに伝えられた」というのは時系列的には正しくないのだが(これは斎藤が同書で述べるように、『上海バンスキング』構想時の一九七七年にテイチクの『SP原盤による日本ジャズ/ポピュラーの歩み』に深く影響され、その収録曲を劇中で多く用いているためであろう)、少なくとも『上海バンスキング』の作者が意識していたのが、ディック・ミネから川畑文子、ベティ稲田へ(そして吉田日出子へ)という影響関係であったことは非常に興味深い。 ミネはまた、後の自伝『あばよなんて、まっぴらさ!』(東京書房、一九八六)でも、「日本語の歌詞をいったんローマ字にして英語のように歌う」方法に言及し、「いま、〈サザンオールスターズ〉の桑田佳祐をはじめとする若い歌手の、国籍不明風日本語の歌い方がヤングに好まれているけど、ナニ、あれは五十年以上も前に、ぼくがとっくにやっているんだよ」(五二頁)と胸を張っている。 しかしこの方法は、実はサザンではなくキャロルが用いているのだ。ジョニー大倉『キャロル夜明け前』には「矢沢節、誕生秘話」として、レコード・デビューに際して、もともと適当な英語で歌われていた矢沢永吉のオリジナル曲〈ルイジアンナ〉にジョニー大倉が日本語歌詞をつけ、日本語で歌ったことのない永ちゃんのためにローマ字や英語で発音の仕方を書いて渡した、というエピソードが記されている(一七八〜一八〇頁)。 もちろんジョニーや永ちゃんや桑田がディック・ミネを意識していたとは考えにくく(ただし桑田に関しては、弘田三枝子や飯田久彦や前川清など、少なくとも戦後日本のカタコト歌唱の系譜は意識していたともいえる)、彼らの直接の「ルーツ」がミネであった、などと言いたいわけではない。むしろ「本場」たるアメリカ音楽と英語への眼差しのありかたにおいて、ある種の相同的な関係が見いだせる、というべきだろう。内田裕也とはっぴいえんどの間の「日本語ロック論争」をなし崩し的に終焉させたキャロルやサザンについては、もちろん本連載でも何回か後に主題的に扱うことになるが、ここではひとまずミネに戻ろう。
歌詞はデタラメでも大丈夫
ディック・ミネがなぜこうした方法を思いついたのかは定かではないが、そのための補助線になりそうなエピソードがいくつかある。まずは、まだ学生時代に「シャムの貴公子バロン・ディック・マーラー」を詐称してバンド仲間と温泉旅行に行った話を紹介しよう(なお、俳優の「ディック・パウエル」と「魔羅」を合わせたこの偽名が、芸名「ディック・ミネ」の語源になったという)。主人夫婦が改めて挨拶に来てね。ぼくは笑なぞ浮かべて鷹揚に、 「チーサンニマスナリワセシクヨロ」 これを友だちの一人が通訳するわけだ。吹き出したいのを必死にこらえた顔で。 「二、三日お世話になります、よろしく、と閣下はおっしゃってます」 いまでもミュージシャンは、言葉を逆さにした符丁で喋るけど、これはぼくらが遊びでやりはじめたのが最初でね。これがいまだにえんえん続いているわけだ。たとえば 「バンコンネカリアロウジョイコカイ チャンカーショナイバッハナーネカギ」 なんて仲間同士で喋っていると、まるで国籍不明語だからさ。〈どこの人間だろう?〉って顔でみんな見るわけだ。それで得意になっているんだから、世話ァないけどね。 さっきのは、 「今晩金借りて女郎買いに行こう。カァちゃんには内緒だよ、幅がきかねーな」 って意味だけどね。 (『あばよなんて、まっぴらさ!』一四一〜一四二頁)バンドマンからテレビ業界人に流れてゆく逆さ言葉は、戦後占領の産物だろうと勝手に思い込んでいたのだが、ミネの証言が正しければ、戦前ジャズの射程は予想以上に広い。次の例を見よう。 英語の歌詞なんて、どうせわかりゃしないからね。こっちは毎晩、同じ曲やってんだから飽きるよね。そこで即興で替え歌にしてやっちゃうの。もっともらしく舌を丸めた発音で、適当に、
「グッド ケツ パイパイ」 「ヌレテ ヨク シマル」 「イクイク アハン」 ハワイアンなんかは、こういうデタラメ入れてもわかんないの。だいたいがカタカナ英語なんだから、意味なんてない詞が多いから、大丈夫。 (『八方破れ言いたい放題』一九九頁)話題が必ず下半身方面に収束するのは、晩年の彼が世間で持たれていたステレオタイプによるものか、これがまさに戦前ジャズメン気質というものなのか、おそらくはその両方だろうが、ともあれ、これらのエピソードに即して考えると、彼の発明した「カタコト唱法」も、お坊ちゃん大学生の仲間内の隠語や替え歌のような悪ふざけ、遊びの一種だった、といえるのではないか。たとえば、彼のカタコト・ジャズ・ソングには「美人」の意味で「シャン」という「モダン語」が頻出するが、これは英語ではなくドイツ語のschönが語源であり、「仕事」を「アルバイト」、「お金」を「ゲル」、「女の子」を「メッチェン」という類の、旧制高校のドイツ語教育に由来する隠語である。 つまり、彼の「カタコト唱法」は、「アメリカ人になりたい」という類の、文化的な優位者への皮相な憧憬というよりはむしろ、ブルジョア遊び人の余裕に裏打ちされた言葉遊びの感覚と、「歌詞はデタラメでも大丈夫」というバンドマン気質が合わさったところで生れたのではないか。そうであればこそ、傑作オペレッタ映画『鴛鴦歌合戦』で好色な「バカ殿」を演じ、「和製ジャズ・ソング」である〈青い空僕の空〉の「丘を越えてはるばる 口笛も高らか」という歌詞を「ぼーくはわかーいとーのさーまー、けらいどーもーよろこーべー」とお気楽に替え歌にするような離れ業を演じられたように思える。
〈ダイナ〉から古賀メロディーへ
自覚的な「方法」としての「カタコト歌謡」の端緒ともいえるディック・ミネ〈ダイナ〉についてもう一つ興味深いのは、これが新興レコード会社のテイチクから発売されており、また同社は作曲家の古賀政男が取り仕切る、事実上「古賀商店」だったことである。もともと奈良で蚊帳を作っていた問屋の副業として昭和六年に設立されたテイチク(帝国蓄音機)は、昭和九年に東京進出を試みる際に古賀政男を重役待遇で迎え入れ、古賀が昭和一三年にコロムビアに復帰するまでの間に、同社は外資系メジャー及び大日本雄弁会講談社系列のキングに匹敵する全国区の大手レコード会社に急成長している(古賀は、昭和六年にコロムビア専属として〈酒は涙か溜息か〉〈影を慕いて〉〈丘を越えて〉でブレイクしているが、コロムビア専属となる際にも、「文芸部員」つまり社員ディレクターとしての待遇を要求しており、古賀のビジネスマインドと、専属制度における社員ディレクターの権限の強さをふたつながら物語っている)。 ミネは、渋る文芸部長に対して、古賀の鶴の一声で〈ダイナ〉の録音が決まった、としばしば古賀への恩義を強調している(ただし、その文芸部長であったはずの川崎清の前掲書では「たまたまこの[〈ダイナ〉の]演奏を聞いた文芸部員一同が「これはいけるじゃないか」と期せずして意見一致、そこで早速吹き込みをした」(一四二頁)とされている。また、昨年末に発売された『ディック・ミネ エンパイア・オブ・ジャズ』(傑作!)では、〈ダイナ〉以前の録音も収められており、この「古賀の鶴の一声で〈ダイナ〉誕生」というエピソードの真偽は定かではない)。 テイチク最初の大ヒットとなった〈ダイナ〉の後、ミネは外国曲のみならず〈二人は若い〉や〈人生の並木路〉といった「古賀メロディー」をも、もちろんお得意のカタコト歌唱で多く録音している。レコードが売れて金になればジャズじゃなくても結構、というミネの鷹揚さと遊び人気質と、主力商品のほとんどを古賀自身が手がける「個人商店」テイチクの社風が交差するところで、二世風カタコト発音による日本製流行歌、というスタイルが生まれたのである(ミネ以前に二世歌手が国産楽曲を歌う例があったかについては調べがついていないので軽々しくは言えないが)。 そして、そのスタイルは他社にも飛び火し、「ホンモノ」の二世歌手にも影響を与えてゆく。服部良一作曲による「和製ブルース」の記念すべき第一作〈霧の十字路〉(一九三七)は、二世歌手兼トランペッターの森山久が歌っている。あくまでも私見だが、ミネ以前の二世歌手が概して「カタコト性」を隠すために結果として単調な歌唱になっているのに対し、森山の場合は一種の美的な効果を狙って「カタコト歌唱」を強調しているようにさえ思える。*
とりとめがなくなってしまった。服部良一や、古賀のテイチク退社後ミネの楽曲を多く作った大久保徳二郎、あるいは戦中に「南洋もの」を多く手がけた佐野鋤といったジャズ・プレイヤーあがりの作曲家について、またディック・ミネの立教の後輩で、「ハワイ生まれの江戸っ子」と呼ばれた灰田勝彦について、もちろん戦時中の「大陸」のジャズについて、まだまだ述べるべきことは多いが、現在の筆者の能力ではおぼつかない。 ともあれ今回は、二世歌手・川畑文子の成功をうけて、「ニセ二世歌手」であるディック・ミネによって自覚的な「方法」としての「カタコト歌唱」が発明され、「古賀商店」において商品化されたことを確認して、次回はもう一人のニセ二世、トニー谷を生みおとす戦後占領期に話を進めよう。 それでは、林檎の木の下でまた逢いましょう。第3回 トニー谷のインチキ英語は戦後アメリカニズムのB面だった
日本のコミックソングの金字塔
レディスアンドヂェントルメン、おとっさん、おっかさん。グッドアフタヌーン、おこんにちは。グッドイヴニング、おこんばんは。ジスイズナンバーワンストレンジ怪しい連載オンジスマガジン。メイドインジャパン、チンジャラパチンコカントリーのピジンイングリッシュソング、カタコト歌謡のお時間ざんす。ざんすざんすさいざんす。そう、今回の主役はトニー谷。細い口ヒゲにフォックス型のメガネの出で立ちで、一九五〇年代のジャズ・コンサート・ブームの司会者として登場、やがて司会者の枠を大きく逸脱する「ゲテモノ芸人」として、実演、ラジオ、映画に出演し、果てはレコードまで吹き込んでいる。「さいざんす」「馬っ鹿じゃなかろか」「家庭の事情」といった数々の流行語を生み出しているが、本稿の最大の関心は、「トニー・イングリッシュ」、つまり英語(時には中国語)を江戸前の七五調のリズムで立て板に水でまくしたてる語り口である。一部のインテリからは「植民地的」と軽蔑・嫌悪されながらも一世を風靡したこの外国かぶれのいやったらしいキャラクターは、後に赤塚不二夫『おそ松くん』の「イヤミ」のモデルとなり、また、マンガで頻出する「ざあます」言葉の有閑夫人(典型的には『ドラえもん』のスネ夫のママなど)の造形にも影響を及ぼしてゆくことになる。 インチキ英語を駆使して彼が人気絶頂期の一九五三〜四年ごろに残した幾つかの録音は、本人にとっては単なる余技にすぎなかったのかもしれないが、結果的に「カタコト歌謡」の戦後における端緒となり、のみならず日本のコミックソングの金字塔となった(というよりも、トニー谷が死去した一九八七年に大瀧詠一がNHK―FMで放送した追悼コミックソング特番によって「刷り込み」を受けた筆者にとっては、「日本のコミックソング」とはトニー谷とクレージーキャッツにほかならない)。 日本もアメリカも小馬鹿にし倒す悪意に満ちた「トニー・イングリッシュ」や、「二世」風のいでたちは、ポスト占領期の日本における「アメリカ」への両義的な感情をある仕方で代表するものといえ、同時期に米軍キャンプという同じ文脈から登場しながらアメリカへの憧憬を比較的ストレートに表現する江利チエミや雪村いづみらとは好対照をなす。芸能の「戦後アメリカニズム」の「A面」であるチエミやいづみに対して、「B面」を担ったのがトニーであったといえるかもしれない。 「戦後アメリカニズム」が彼らから始まった、という評言はいささか奇異に思われるかもしれない。明朗快活な〈リンゴの唄〉や笠置シヅ子の〈東京ブギ〉、あるいは笠置の物真似でデビューし、笠置に先駆けてアメリカ公演を行った(そのことで笠置の逆鱗に触れ、ブギの歌唱を禁じられた)初期の美空ひばりこそが「戦後」を代表するのではないか、と。 しかし私見では、敗戦直後の日本で流行した国産楽曲は、その担い手も曲調も、戦前・戦中をそのまま引き継ぐものであり、新たな時代の開始というよりも、おおむね日米開戦ごろから断絶していたものの復活と考えるべきである。〈リンゴの唄〉が主題歌となった映画『そよかぜ』は、敗戦前に制作されているし、しばしば敗戦後のアメリカニズムの象徴のように考えられている服部良一・笠置シヅ子による一連のブギも、受容の文脈はともかく、少なくとも曲調においては戦前の〈ラッパと娘〉などの傑作ジャズ・ナンバー群の系譜にあり、日米開戦以前に目覚ましい成熟を見せていたジャズ文化が復活したものにすぎないともいえる。 それに対して、占領終結後、米軍キャンプに出自を持つ音楽家や芸能プロダクションが台頭し、やがて、民放ラジオやテレビといった新メディアと結びついて、日本の大衆文化環境を根本的に変化させてゆくことになる。こうした過程を、芸能における「戦後アメリカニズム」と仮に呼んでおきたい(もちろん敗戦直後の大衆音楽状況が単なる戦前の回帰にすぎない、ということではないが、この問題については別稿を期したい)。
トニー・イングリッシュ「開花」の瞬間
トニー谷こと大谷正太郎(しばしば谷正を自称)の経歴は一九四六年、二九歳にしてアーニー・パイル劇場(GHQに接収された東京宝塚劇場)に事務員として就職したことから始まる。それまでの経歴は謎に包まれている。戦時中は上海で従軍していたとも民間人として放浪していたともされる。村松友視は伝記『トニー谷、ざんす』(毎日新聞社、一九九七)において、彼自身の複雑な「家庭の事情」を強調しているが、確証はない。つまりトニー谷の経歴には「戦後」しか存在しないのだ。 アーニー・パイル劇場での演出助手を経て、アメリカ赤十字クラブに移籍。そこでのあだ名「トニー」がのちの芸名となる。つまりは「谷」の英語読みと日本語読み。同義の英語と日本語を並べるトニー・イングリッシュの基本法則が芸名にも貫徹されていることになる。ちなみに江利チエミはキャンプ回り時代のあだ名、「エリー」に本名のチエミをくっつけたもの。こちらはファーストネームの日米併記ということになる。 赤十字クラブでキャンプ慰問芸能人の手配・斡旋を行っていたトニーだが、副業に精を出してクラブを留守にした際に小火を起こす不始末であえなくクビ。赤十字時代のコネを活かして食いつなぐうち、司会者として舞台に立つようになる。 転機となったのは一九四九年一〇月のプロ野球チーム、サンフランシスコ・シールズの来日だった。英語に堪能な弁士出身の漫談家・松井翠声の代役として急遽歓迎会の司会に立ったのがトニー谷。村松友視は「トニー・イングリッシュ」の「開花」の瞬間をドラマティックに記している。「レディス・エンド・ジェントルメン、グッド・イブニング」 とスポーツ・センターの中央に立って喋り始めたら、 「何いってんだか分らねえぞ」 と野次がきた。これに対して反射的に、 「何言ってやがんだい」 と怒鳴り返したら、ワッと笑い声が起った。これは、トニー谷にとって天の啓示のようなものだった。これはいける……そのときトニー谷は瞬間的にそう感じた。いや、感じたばかりでなく、即座にそこで芸風を確立してしまったのだった。 「レディース・アンド・ジェントルメン」 と声を大きくして言い、さらに、 「アンド・ミーチャン・ハーチャン」と付け加えた。するとこれまたドッと受けた。そこから流れるように吐き出されたのが、トニー・イングリッシュの開花だった。 (『トニー谷、ざんす』六六―六八頁)この記述自体は作家・村松の想像力の賜物と思われる(別の可能性についてはあとで検討する)が、シールズ歓迎会をきっかけにトニーが注目を集め始めたことは間違いない。広告も検索できる読売新聞データベースで調べると、一九五〇年以降、日劇の司会者として頻繁に広告に名前が載るようになっている。 ところでシールズの来日はトニーにとってのみならず、戦後日本の大衆文化にとってもひとつの転機だった。『占領期雑誌資料大系 大衆文化編Ⅲ アメリカへの憧憬』(岩波書店、二〇〇九)ではこのイヴェントに一章を割いて詳細に当時の記事を紹介している。谷川建司による解説は、球場でコカ・コーラとペプシ・コーラの日本人向け発売が試験的に行われ、パンフレットにもコカ・コーラの広告が大々的に掲載されたことを強調し、「占領期における日米野球の復活という檜舞台が、同時にアメリカ流食文化のお披露目の舞台でもあったことは象徴的な事実だ」と述べ(一八一頁)、「日本人にとってシールズ来日が持っていた最も大きな意味とは何か」と問い、「戦後の日本がアメリカという国の強大な力の庇護の下で、アメリカナイズされた形でしか存在し得ないことが改めて示された機会でもあったろう」と結論する(一八一―一八二頁)。 もうひとつ、トニー谷売り出し中の仕事としてもう一つ特筆すべきは、ケニー・ダンカン来日公演の司会だ。「拳銃の曲打ちと投げ縄が得意なハリウッドの西部劇スター」という触れ込みで来日した彼は、アメリカでは全く無名のエキストラ俳優で、曲打ちやロデオはおろか、単なる乗馬さえもまったくできなかったという。 とんだ食わせ物ケニー・ダンカンはしかし、トニー谷や笠置シヅ子といった共演者、そして空砲にあわせて的に穴を開け風船を割る「標的持ち」の妙技によって、化けの皮を剥がされずに「スター」のままで帰国した。広島公演では駅長が白手袋で出迎え、市長以下お歴々が立ち並ぶ中をオープンカーでパレードしながら会場入りしたという。その堂々たる(?)スター姿は、笠置シヅ子主演映画『女次郎長ワクワク道中』に収められており、筆者は未見だが後にこの顛末自体『はったり二挺拳銃』として映画化されている。 この「ニセ・ハリウッドスター」が鳴り物入りで来日する裏では、軍属の二世プロモーターや伝説の興行師・永田貞雄が暗躍しているのだが、いずれにせよこれが戦後における来日タレントの「呼び屋」ビジネスの事実上の(米軍慰問の一環ではなく、日本の聴衆向けという意味での)端緒となったことは厳然たる事実である(猪野健治『興行界の顔役』ちくま文庫)。戦後の「外タレ」は「ドシロウトのアメリカ白人」から始まっているのだ。単なる「ホンモノのアメリカ人」でしかないケニー・ダンカンと、したたかな「ニセ二世」芸人トニー谷の邂逅。戦後日本において「外タレ」(来日タレントのみならず「ガイジン」であることを唯一最大のセールスポイントとする日本の芸能人も含め)とは何だったのかを考えさせる出来事ではある。
ジャズ・コン・ブームで大ブレイク
シールズ来日、ケニー・ダンカン騒動という、よくも悪くも戦後のアメリカ化の象徴的なイヴェントに立ち会っていたトニー谷だが、大ブレイクを果たすのは占領終結後のジャズ・コン(サート)・ブームにおいてである。それまで米軍キャンプの中だけで演奏されていたジャズ(アメリカ的軽音楽全般、という意味での)が、占領終結と朝鮮戦争休戦によるキャンプの縮小にともなって、続々と「フェンスの外」に流れでてくるのだ。映画『ベニイ・グッドマン物語』でのドラム・ソロが日本の観衆に強い印象を残していたジーン・クルーパや、ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニーが来日公演を行うのもこの頃だ。江利チエミや雪村いづみを筆頭に、ジョージ川口とビッグフォー、渡辺晋とシックス・ジョーズ、与田輝雄とシックス・レモンズといった本格的コンボから、フランキー堺とシティ・スリッカーズ(植木等と谷啓もメンバー)、ペギー葉山、ナンシー梅木などが多く登場し、彼らは実演、レコード、映画に加え、民放ラジオ(一九五一年放送開始)やテレビ(一九五三年放映開始)といった新メディアでも積極的に活躍しはじめる。これらの新メディアが、その草創期には、すでに地位を確立したレコード歌手や映画スターにはまったく魅力のないものであったこともキャンプ出身者に幸いした。これらの人々にトニー谷同様、「カタカナ名前+漢字苗字」の芸名が多いのはもちろん、キャンプでの通り名をそのまま用いたためだ。 ホールや大学講堂でのジャズ・コンにおいてトニーは、そろばんをリズム楽器として鳴らし、出番に関係なく勝手に出てきて歌い、踊り、さらには歌手やミュージシャンに悪態をつく、といった司会にあるまじきアクの強いパフォーマンスを行っていた。小林信彦は「そんなことがなぜ許されたかというと、トニー谷の人気が六・四か五・五ぐらいで大きくなっていたからである」(『ジス・イズ・ミスター・トニー谷』解説)とし、「司会者を見るために、客が集ったというのは、空前といえるのではないか」(『日本の喜劇人』八七頁)と指摘する。なお、人気絶頂期の彼の司会ぶりは映画『アジャパー天国』(一九五三)で見ることができる。身体化されたみごとな七五調のリズム
さあ、ようやく「トニー・イングリッシュ」で歌われる彼の傑作コミック・ソング群の検討に入ろう。 初録音の〈レディス&ヂェントルメン&おとっさん、おっかさん〉(一九五三)は前年にヒットしたバラード‘You Belong to Me’のカヴァー。二番冒頭の歌詞、See the market placeを江戸弁で「しーざまーくーらで」と空耳アワー的に替え歌するセンスが冴える。ロマンティックな歌(案外真面目に歌っているのがまた可笑しい)の前にはもちろんたっぷりとトニー・イングリッシュの口上が入り、間奏では「イーハン、リャーハン、チャーハン」といった麻雀式中国語や「二一天作、二進が一進、三五のひだちが悪かった」といったそろばん用語のもじり(銀座の「歌舞伎座のそば」で生まれたトニーは下町では有名なそろばん塾に通っており、同じ塾に後年小林信彦も通ったという)が用いられ、「トニー・イングリッシュ」が単なる米日カタコトのチャンポン以上に多様な出自をもつ混淆的な話芸であることをうかがわせる。 カップリングの〈さいざんす・マンボ〉は宮城まり子との共演。「家庭の事情」がモチーフとなっている。多忠修(雅楽の家系から戦前にジャズに転じた人物)による本格的なマンボ編曲が施されており、ジャズ・コン・ブームとマンボ・ブームの同時性に改めて気付かされる。なんといっても聞きどころはソロバンによる見事なソロ。グルーヴィ! そして最高傑作の〈チャンバラ・マンボ〉。無粋ながら簡単に絵解きをしながら見てゆこう。 まずは〈マンボNo. 5〉そのままのイントロから、当時誰でも知っていた月形半平太の名台詞がトニー・イングリッシュで炸裂する。マウント・イースト・東山、サーティーシックス・三十六峰、クワイエット・スリーピング・タイム、ここ三條ブリッジ・イン・ザ・京都シティ、幕末勤王佐幕・タイム。 突然サドンリー・ハップン起るはチャンバラサウンド。 (S.E.)「御用、御用」 来たなオッサン チョイキタホイ! 寄らば斬るワョ、サアーイラッシャイ!無声映画伴奏の和洋合奏風旋律が入り、それが〈マンボ・ジャンボ〉を半分に端折ったテーマにスムーズに移行する。多忠修の面目躍如。「チャンバラ・マンボ」を「ケンゲキ・マンボ」、「フェンシング・マンボ」と言い換えてゆくセンスも素晴らしい。さらに「チャンバラ屋」から連想でカントリー&ウエスタンの「ジャンバラヤ」の一節が挿入される。ちなみにカントリー&ウエスタンは、戦前日本の都市モダン文化であったジャズのレパートリーにはほとんど入っておらず、田舎出身の若い占領軍兵士がもちこんだ、まさしく戦後的な「アメリカの音」だった。さて、ここでようやく主役・月形半ペン太と雛菊の登場と相成る。
ミスター・ムーン、月形様。アイ・ドン・ライクのトラブル事。 早くハバハバゴー・バック・ホーム カモナ・マイ・ハウス「ハバハバ」は語源不詳の占領軍スラングで「早く」の意味。〈カモナ・マイ・ハウス〉はローズマリー・クルーニーが歌った当時のヒット曲だが、日本では〈テネシー・ワルツ〉と並ぶ江利チエミの代表曲。そして決め台詞「月様、雨が」の後に挿入されるは〈雨に唄えば〉! しごく真面目に二枚目然と歌われる一節をはさんで「ヂイス・イズ・スプリング・レイン 春雨。アイ・ドン・ケアー 濡れて行こう」でバチリンコンと決める。大仰に見得を切る姿が目に浮かぶ。 〈チャンバラ・マンボ〉の名調子が示すように、トニー・イングリッシュは一面ではみごとにこなれた七五調のリズムに基づいている。語彙の選択こそ相当にトリッキーであっても、銀座生まれに相応しい、由緒正しい江戸前の話芸といえる。本連載でここまで扱ってきた(そして基本的にこれからも扱うことになる)、英語風に日本語を発音する、という方向とは正反対に、トニー・イングリッシュは日本語の統語法と語調の中に英語の語彙を割り込ませる形で成立しているといえるかもしれない。実は、今回この原稿をトニー・イングリッシュで書くことを試みたのだが、七五調が決まらないとどうにもそれらしくならない。ルー大柴の「ルー語」をさらに間延びさせたようなシロモノにしかならず、身体化された韻律の差を痛感した次第。 そう考えると、特に〈チャンバラ・マンボ〉に顕著な、ヴァラエティ・ショーをそのまま切り取ってきたような録音は、戦前のあきれたぼういず(トニーのソロバン演奏は元は坊屋三郎の持ちネタで、パクられた坊屋は憤慨していたという)や、さらに遡って「話芸」としての映画説明レコードやバスガイドの名所説明レコードからその連続性を見出しうる、つまり舶来のポピュラー・ソングの意匠を巧みに用いた「語り物」の一種とみることができるだろう(やや余談になるが、先頃『ニッポンジャズ水滸伝』と題した四枚組CDが発売された。主に関西の非外資系レーベルに残された戦前のジャズ録音を集めたもので、それだけでも堪らない企画だが、特に興味深いことに演歌師や活動弁士出身者によるジャズ録音が多数収められている。お馴染みの〈青空〉や〈アラビアの唄〉のなかにも当然のように朗々たる語りが入り込んでおり、舶来要素の「語り物化」とでもいうべき過程を考える上できわめて示唆に富んでいる)。
鏡としてのニセ二世
では彼の言語的実践はどのように機能したのか。池内紀は「一つの言語的事件」と呼び、次のように述べる。トニー谷とともに異様なものが登場した。それはキザを絵にかいたような衣装や、楽器としてのソロバンといった突飛な着想にとどまらない。トニー・イングリッシュをまじえた奇妙な日本語は、思想・信条から食べ物や風俗まで、あわただしくころもがえしてアメリカかぶれした人と世相を辛辣に戯画化していた。彼のセリフが、一度聞いたら忘れられない強烈さをもち、しばしば流行語になったのは、時代に対する鋭い批判を含んでいたからにちがいない。 (『地球の上に朝がくる』河出書房新社、一九八七、五二〜三頁)ことばの奇妙な働き、その本来のいかがわしさ。トニー谷は、それを肉声でもって示してくれた。「ざんす」や「ざあます」言葉が、トニー以降、急速にすたれたのをご存知だろう。トニー谷は一人の風変わりな芸人というよりも、一つの言語的事件であった(同五四頁)。 「言語的事件」としてのトニー谷のブームは、いうまでもなく占領終結前後という時代に深く規定されていた。再び小林信彦御大を引こう。
進駐軍の占領時代に、なにがイヤがられたといって、アメリカの威光を背負った二世通訳ぐらい、イヤなものはなかった。そのくせ、日本の若者はサングラスをかけ、アロハシャツを着、ラバーソールをはいて、キザな二世の真似をした。こうした日本人の矛盾と屈折をテコにして、トニー谷は登場した。(CD『ディス・イズ・ミスター・トニー谷』解説)また、フィクションではあるが、斎藤憐『アーニー・パイル劇場』(ブロンズ新社、一九九八)にも同様の「矛盾と屈折」の感情を描いた一節がある。
「支配人、なんて言いましたっけねえ、あの通訳」 「さあて、なんて名前だったかなあ」 「あっしは、ああいう奴の面見ると、虫酸が走るんですよ。日本人のくせに、アメリカの腰巾着になり下がりやがって……」 「まあ、そう怒るな、あの人は国籍がアメリカなんだから」 (略) 「…国籍がアメリカだろうと元は日本人だろうが、日本人のくせして、チューインガムをくちゃくちゃやりやがって…(略)肉をたんまり食ってるアメリカに敗けたなあ、しょうがない…しかし、あの黄色い顔の男が、俺らの前ででかい面しやがるのが気に食わない…」(一六頁)特に最後の台詞からは、「アメリカ」(おそらく白人)を優位に、「黄色い顔」を劣位に置く人種主義的偏見が内面化されていることがわかる。その上で「人種(民族)」的には「日本人」でありながら、(「日本人」にとっては不当にも)占領者の側にある「二世」に対する、理不尽かつ身勝手な嫌悪感と羨望が表明されているのである。 翻って、グロテスクなまでにいかがわしい「ニセ二世」を演じるトニー谷は、当時の日本人が抱いていた「二世」への、ひいては「二世」に投影された「アメリカ」への両義的な感情を戯画的に可視化し、逆撫でする存在であった。そしてそれは不可避的に占領者の姿をも歪んだ鏡に映しだすことになるだろう。 村松友視は次のように述べる。
トニー・イングリッシュは、たしかに日本人観客の野次を舞台上から言い返したところからスタートした。したがって、トニー・イングリッシュは日本人を揶揄しているように思えるのだが、その半面には占領軍たるアメリカの言葉をもてあそんでいるという要素があった。いや、むしろそこのところに、実はトニー谷という存在の真髄があったのではないだろうか。それは、トニー谷自身の自覚を越えて、あの時代全体を揶揄しているという構造を、トニー・イングリッシュがもっていたからなのだ。そして、トニー谷の躯の奥底にそのような毒がひそかに息づいていたという気がするのだ。 それは、もしかしたら暗い過去をもつ者が、明るい世界へ向ける怨念の矢であったのかもしれない。明るい世界には、戦勝国アメリカも入っていたが、そのアメリカに馴染んでゆく戦後日本のありさまも入っていたし、戦争をはさみながら悠々と暮す[ざんす言葉のヒントとなった]芦屋夫人も入っていた。(『トニー谷、ざんす』、七三頁)アメリカ/日本、戦後/戦前という対比重ね合わされる明るさ/暗さの感覚とその交錯への視線は、トニー谷に固有のものというより、むしろ書き手としての村松友視の核心に関わるものかもしれない。力道山(『力道山がいた』)にせよ、水原弘(『黒い花びら』)にせよ、村松が伝記を手がける人物はことごとく、ある「暗さ」を背負っている。もちろんそれは、彼を世に出したプロレス論における、「善玉」「悪玉」を超えた「凄玉」に通じるものだろう。そういえばカタカナ名前+漢字苗字は「昭和プロレス」の定番の命名法でもあった。
新たな芸能界形成の中で
ところで村松は「トニー・イングリッシュは、たしかに日本人観客の野次を舞台上から言い返したところからスタートした」としているが、池内はトニー・イングリッシュの成立について別の可能性を示唆している。池内が紹介するところでは、一九六九年頃のラジオ録音でトニーはシールズ来日歓迎会について次のように話している。「レディース・アンド・ジェントルメン!」 とやりました。自分だけは発音が正確だろうと思っていました。うしろの舶来が聞いてて全然わからない顔をしてる。しょうがないから、 「アンド・おとっつァん・おっかさん!」 それからトニー・イングリッシュがはじまったんざんす― (『地球の上に朝がくる』、四一〜四二頁)もし「舶来が聞いてて全然わからない顔をしてる」ために、さらに日本語でたたみかけて煙に巻いた、というのが事実であるならば、むしろ村松の「占領軍たるアメリカの言葉をもてあそんでいる」という洞察を裏付けるものといえる。これはまったくの推測だが、トニーは実際は英語がほとんどできなかったのではないだろうか。謎に包まれた彼の経歴の中に、戦時中に大陸で英語、中国語を身につけた、という話が含まれているが、もともと英語ができた人間が、トニー・イングリッシュのような批評性(または悪意)を持つことはむしろ困難であるように思える。村松のように想像の翼を広げることが許されるならば、戦後ベストセラーとなった簡易教本『日米会話手帳』程度の知識と強心臓のみを頼って占領軍に入り込み、甘い汁を吸いながらボスを嘲笑する狡猾でしたたかな日本人、と見立てるほうがトニーのキャラクターを理解しやすいように思える。 占領者を揶揄する、というきわめて危険なパフォーマンスは、菅見の限り占領期日本には見いだせない。激しい政府批判で鳴らしたラジオ番組『日曜娯楽版』においても占領軍批判だけはご法度だった。というよりも、最高権力者たる占領軍の存在を意識させない限りにおいて、政府権力への「健全で民主主義的な」批判が奨励されていたといえる。 翻って、占領末期から直後のジャズ・コン・ブームは、音楽的な魅力というよりも、占領期には手が届かなかった「フェンスの向こうのアメリカ」への憧憬に動機づけられる部分が大きかっただろう。司会者としてそのブームの一端を担ったトニー谷は、憧憬の裏側、つまり抑圧されていた「二世」や「アメリカ」への嫉妬や反発といった感情を露悪的に戯画化し、それを解放することで人気を獲得したといえるのではないか。 もしそうした見立てが可能であるならば、トニー谷の存在は、彼に対する批判の紋切型であった「植民地的」というよりむしろ、「ポスト植民地的」(ちょっと面映い……)というべきなのではないか。被占領者による占領者(ただし「人種」的には被占領者と同じ、と想定される「二世」という両義的な存在)の模倣が、それを見る被占領者と占領者の双方にもたらす「居心地の悪さ」の効果について、ホミ・バーバの「植民地的擬態 colonial mimicry」の概念を用いて分析することは可能であり必要だろう(筆者には到底ベリベリノーキャンドゥーざんすが……)。 そのように考えると、彼の人気の凋落も説明がつくかもしれない。一般に彼の人気衰退の理由とされる一九五五年に起こった子息の誘拐事件の以前から、その人気にはすでに陰りが見えていたという。「アメリカ」と「日本」の屈折した関係を暴露し揶揄する彼の芸風は、占領軍という「日本の中のアメリカ」が「日本」に還流してゆく、その流れがどこに向かうのかまだわからない最初の段階でのみ、一種の異化効果を伴って熱狂的に受け入れられたと考えたほうがよいのではないか(もちろん、彼の性格的な問題によって「干された」という側面は多々あるのだろうが)。 トニー谷のブレイクにおいて決定的な役割を果たしたジャズ・コン・ブームもまた、早々と沈静化する。ある者は既存の映画やレコードの世界に居場所を見つけ、また少数の者は芸術志向のモダン・ジャズへと向かっていった。そして、新たな芸能界秩序の形成に向かう動きも現れる。その中心はシックス・ジョーズの渡辺晋が設立した渡辺プロダクションであり、テレビという新メディアだった。この「魔法の箱」を通じて全国の「お茶の間」に広がった消費主義的な「豊かなアメリカ」の雰囲気は、「アメリカ」と「日本」の不均衡な関係を可視化し、両者のアイデンティティを撹乱し蹂躙し嘲笑するトニー谷の芸風とは相容れないものだっただろう。 ややしんみりしたところで次回のお題はロカビリー・ブームとテレビの音楽ヴァラエティで賑やかに参りましょう。トニー谷によって日劇出入りの電気工からコメディアンに転身させられた「ヘンな外人」E・H・エリックも登場予定ザンス。それではレディース・アンド・ジェントルメン、おさいなら!
第4回 ジェリー藤尾のやけっぱちソングは占領者アメリカへの対抗的実践だった!?
「ギャップ萌え」シングルの傑作
ハオ ハオ ハオ/バーバリスト バーバリスト ハオ ハオ ハオ ツイスト/インディアン インディアン ハオ ハオ ハオ ツイスト/ナパホ キッカポ スー シャイアン/アパッチ コマンチ ハオ ハオ ハオ/ジュゲムジュゲム ゴコオノスリキレ/オッペケレツのウパッパ/ヤーレンソーラン ソラキタドッコイ/オッペケレツのウパッパのパ今回のテーマ曲、ジェリー藤尾〈インディアン・ツイスト〉(一九六二)の歌詞〝全文〟だ。 「インディアン」の部族名と雄叫び、落語由来のフレーズ、民謡の囃子言葉をごちゃまぜにした歌詞は限りなくオノマトペに近く、意図的に無意味に聴こえることを狙っているとしか思えない。当時の彼の「危険」なイメージと考え合わせると、ここまで本連載で扱ってきた、戦前日本のモダニズムを背景にした「英語風日本語発音」や占領期のトニー谷のピジン言語パフォーマンスに比して、格段にアナーキーでやけっぱち、あえて問題のある言い方をすれば「野蛮」な性格を有している。決して有名な曲ではないが、いくつかのコンピレーションCDに収められており、また歌唱シーンを含んだ映画『若い季節』もDVD化されているため、入手困難というわけではない。 ジェリー藤尾はロカビリー・ブームにのって登場し、当時「ケンカ最強」と謳われた日英ハーフの歌手。テレビ・映画でも活躍し、黒澤明監督が『用心棒』でそれまでの時代劇映画の約束事を破壊した、腕が飛び血しぶきが上がる殺陣シーンで「斬られ役」を演じてもいる(ちなみに彼自身、歌手になる前は新宿の愚連隊の用心棒だった)。『地平線がギラギラッ』や『偽大学生』といった主演作でも鬼気迫る魅力を振りまいているが、どちらも見る機会が極めて限られているのが残念だ。 この曲は、ジェリー藤尾の代表曲にして日本のスタンダード〈遠くへ行きたい〉のB面に収められており、作詞・作曲はA面と同様、永六輔・中村八大による。〈遠くへ行きたい〉は、この「六・八コンビ」の〈上を向いて歩こう〉〈こんにちは赤ちゃん〉と同様、NHKテレビの音楽ヴァラエティ番組『夢であいましょう』の「今月の歌」として作られた。当時テレビで〈遠くへ行きたい〉を気に入ってレコードを買った善良なリスナーがこの曲を耳にしたときの驚きは想像するに難くない。かまやつひろし〈我が良き友よ/ゴロワーズを吸ったことがあるかい〉と並ぶ、AB面の「ギャップ萌え」シングルの傑作といえよう。 今回は、ジェリー藤尾とこの曲を、単なる「名曲の迷B面」としてだけでなく、一九五〇年代末のロカビリー・ブームを端緒とする日本の大衆音楽文化の大規模な変容と、そこで突出する「アメリカ」の表象の編制を、別な仕方で(いわば「B面」において)象徴する存在として位置づけ、「インディアン」という「他者」の記号作用について、若干の検討を行ないたい。