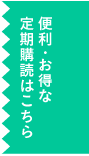大の音楽好き、とくにブルース・ギターの大ファンでもあるデザイン史家の柏木博さんの連載エッセイ。音楽をめぐる交友、あこがれのブルースマン、日常生活をいろどる音、ギターをはじめとする音楽の道具たちのデザインについて……さまざまな話題が次々に登場します。

PROFILE
柏木博
武蔵野美術大学教授(近代デザイン史)
1946年神戸生まれ。武蔵野美術大学教授。近代デザイン史専攻。デザイン評論家。武蔵野美術大学卒業。著作:『家事の政治学』『モダンデザイン批判』『「しきり」の文化論』『探偵小説の室内』『わたしの家』『日記で読む文豪の部屋』ほか多数。展覧会監修:『田中一光回顧展』(東京都現代美術館)、『電脳の夢』(日本文化会館パリ)ほか多数。
音楽批評家「とうよう」さんのこと
ロバート・ゼメキス監督の映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』(1985)には、主人公の少年が1955年にタイムスリップし、ロックを演奏する場面が出てくる。50年代のチャック・ベリーのロックンロールから、次々にロックの変遷をなぞり、最終的には、いわゆるハード・ロックの演奏になっていくシーンである。ロックの歴史が一気に展開される、なかなか面白い場面だ。この場面は、ロックンロール以前のブルースを想起させもした。ブルースこそが、ロックの起原であることがわかる。
いまではよく知られているように、アメリカの音楽は、白人のカントリー・ミュージックと黒人のブルースのふたつが、大きな位置を占めている。このことは映画『ブルース・ブラザーズ』で面白おかしく描かれている。
ぼくは、どちらの音楽も好きだ。とはいえ、カントリーにかんしては、新しいものは、「どうも……」という感じだ。古いものは、たとえば、パッツィ・クラインのナンバーなどは、ノラ・ジョーンズやダイアナ・クラールなどによって、ジャズのスタンダード・ナンバーのようにアレンジされているので、美しいと思う。カントリーは、ジャズにアレンジしやすいのかもしれない。
一方のブルースについては、ぼくは70年頃に、その魅力を知り、ヴィクトリア・スピヴィーのレーベル(スピヴィー・レコード)や、アリゲータ、あるいはアーフーリーなどのレーベルのレコードで聴いていた。けれども、そうしたブルースの演奏を直接聴く機会はなかった。そうしたなかで、突然、「ブルース・フェスティバル」と題するブルースのコンサートがシリーズで開催されることになった。74年の第1回は、たしか、スリーピー・ジョン・エステスのコンサートで、ハミー・ニクソンがジャグ・バンドのようにポリ・タンクを使って共演したと記憶している。エステスはひさしく忘れられていたブルース・マンだが、ブルース研究者たちによってすでに60年代(おそらく62年)に再発見されていた。少年期に右目を失明していた彼は、再発見時にはすでに左目も失明し盲目の状態だった。この一連のコンサート(フェスティバル)を監修していたのが中村とうようさんだった。
ブルース・フェスティバルの舞台に登場する中村とうようさんは、ぼくにとってははるかに遠い存在だった。第2回のフェスティバルは、ジュニア・ウェルズとバディー・ガイのコンサートだった。2人ともシカゴ・ブルースのスターである。ウェルズはその後、亡くなった。ガイは、シカゴにクラブを持ち、もちろん現在もスーパースターとして活動している(そのクラブに2008年に行ったが、残念ながらすでにブルース界の巨匠ということなのか、本人の演奏はなかった)。エリック・クラップトンは、彼のギターにはかなわないとまで言っている。
ウェルズとガイの東京コンサートのとき、1曲終わるごとに拍手があるわけだが、どうしたわけか、そのときに、「イエィ(yes)」にまざって「バカヤロー」という声が、たったひとつだったけれど聞こえた。すべての演奏が終わり、会場からアンコールの拍手が続くなか、舞台の袖から、中村とうようさんが出てきた。とうようさんは「さっき、バカヤローと言ったのがいた。言葉はちがっても、差別や悪い言葉は、わかるんだ。きょうはアンコールはなしだ」ときっぱりとした語調で語った。なんと素敵な人だろうと思った。
80年代半ばに入ってからのことだったと記憶する。東京の中野駅で地下鉄東西線に乗った。午後の時間で、ほとんど乗客がいない。車内を見回すと、熱心に読書をしている人がいる。なんと、とうようさんである。もちろん、声をかけるにはあまりにも遠い存在だ。のちに、とうようさんから聞いたのだが、仕事場にしている『ミュージック・マガジン』の編集室が神田神保町にあり、そこに行くのに便利なので東西線を使っていたとのことだった。
その後、90年代にNHKの「ナイト・ジャーナル」という番組で、ぼくはキャスターをすることになった。番組のなかで、とうようさんに音楽情報を紹介していただくことになった。ここではじめて、あの遠い存在だったとうようさんに直接お話しすることがかなった。それで、「バカヤロー」事件のことを話すと、「よくそんなことを覚えていたね」とうれしそうにされた。
当時、ぼくの母の体調がすぐれなかった。そこで、そうした人におすすめの音楽があったら教えてくださいと、とうようさんに聞いた。とうようさんはすぐに、メモを手渡してくれた。なんとやさしい人だろうと思った。この印象は鮮やかで、いまも変わりない。
その後もとうようさんはていねいな手紙をくださったり、戦前のSPレコードの紙袋を送ってくれたりしていたが、2006年にとつぜん、所有している4万枚ほどのレコード、書籍、楽器を引き取ってくれないかと連絡してきた。ぼくの勤務する武蔵野美術大学に寄贈というかたちで「中村とうよう文庫」をつくった。2011年、すべてが完成し、展覧会を開催して特別コンサートも終わらせた2日後、とうようさんは、いきなり逝ってしまった。自死だった。
翌朝とうようさんが発見されたと連絡があり、死を確認しに行った。帰宅すると、とうようさんからの手紙が郵便受けに入っていた。開くと「これは遺書です」とあった。
とうようさんが、なぜすべてのコレクションをぼくに託したのかは、いまだに謎である。
スリーピー・ジョン・エステスをめぐるいくつかのこと
1970年代、ブルースのレコードを入手するのは、さほど困難ではなかった。レコードのチェーン店であるディスク・ユニオンがかなりの数のブルースのレコードを置いていた。
シカゴ・ブルースあるいはモダン・ブルースはもちろん、カントリー・ブルースあるいはルーラル・ブルースと呼ばれている、多くはアコースティック楽器を使ったブルースのレコードも、当時はすでに容易に入手することができた。けれども、そうしたブルースの本格的なコンサートとなると、おそらく中村とうようが企画した1974年の「ブルース・フェスティバル」を待たなければならなかった。
「ブルース・フェスティバル」の第1回目は、スリーピー・ジョン・エステスのコンサートだった。ブルース・ハープ奏者のハミー・ニクスンが、ジャグ・バンドがやるようにポリ・タンクに息を吹きこんでリズムをとった。ともあれ、これがわたしのカントリー・ブルースを見た初めての体験だった。
ここでは、そのエステスをめぐるいくつかのことにふれておきたい。エステスの亡くなった年が1977年ということは、はっきりしているのだけれど、生年は1899年、1904年といった説があり、はっきりしない。
中村とうようの監修した『Sleepy John Estes 1935-1940』(MCVA)の中村自身によるライナー・ノーツには、来日したときの入国申請の書類などでは1900年となっていたが、人名辞典での1899年にしたがうのが最善だと思う、とある。子どものころ野球で遊んでいたときに、けがをして右目を失明したとされる。12歳のときに父が買い与えたギターを弾き始めたといわれている。
中村によれば、エステスは、1929年から41年までにヴィクターとデッカに約50曲を録音しており、この時期にメンフィスで活動していたブルース・ミュージシャンのなかでもきわだっていた。その後、あまり目立った活動はなく、1953年頃、ビッグ・ビル(ウィリアム)・ブルーンジーが、エステスが生きているとしたら87歳くらいになっているだろうと発言したことで、すでに生存はしていないと考えられていた。
ついでながら、ブルーンジーもエステスと同じ1920年代末あたりからブルース・シンガーとしての活動をしていた。アメリカのスミソニアン博物館は、古いブルースのCDを刊行しており、ブルーンジーのブルースもスミソニアンのCDで聴くことができる。彼の作曲でもっともよく知られている〈キー・トゥー・ザ・ハイウェイ〉は、1945年頃につくられている。この曲は、クラプトンがデレク・アンド・ザ・ドミノスとして、1970年のフィルモアのライヴでカヴァーして以来たびたび取り上げているために、よく知られるようになったのだろう。
エステスは、62年に極貧生活の状態で再発見されたときには、左目も失明していた。エステスの再発見以降、70年代にかけてカントリー・ブルースがふたたび注目されるようなる。
エステスのブルースは、さまざまな人々にインスパイアを与えているように思える。たとえば、1963年にジェフ・マルダーのアルバム『Sleepy Man Blues』がつくられているが、このなかでマルダーは、エステスの〈Everybody Oughta Make A Change〉をカヴァーしている。再発見の翌年だから、早い時期にマルダーは、エステスのこの曲を演奏しているといえる。
エステスはキーをCにしている。12小節の典型的なブルース構成である。スケール(音階)はもちろんペンタトニックで動いていく。マルダーは、キーをAに変更しているけれど、基本の構成はまったく同じだ。マルダーのギター演奏と歌い方には、エステスを意識していることがはっきりとうかがえる。
さらにずっとあとになるが、エリック・クラプトンが1983年のアルバム『マネー・アンド・シガレッツ』の冒頭でカヴァーしている。キーはマルダーと同じAだが、エステスの痕跡はまったく感じられない。エステスの痕跡は消えているが、すばらしくエレガントで速度感のある仕上がりになっている。
「天気は変わる、海は変わる、帰ってきてよベイビー、おまえは俺が変わったのがわかるはずだ。誰だって、いつか変わるはずだ。だって、早かれ遅かれ、俺たちは寂しい土の下に行かなくっちゃいけないんだから」
以下、「おれはスーツを変えた、おれはシャツを変えた、おれは変わった……」と続いていく。メロディとコード進行は、同じエステスの〈Easin' Back to Tennessee〉とほぼ変わらない。こうしたことはブルースでは、めずらしくない。この曲は35年から40年あたりにつくられているから、〈Everybody Oughta Make A Change〉もほぼ同じ時期につくられているのだろう。カントリー・ブルース(ルーラル・ブルース)の作曲年を正確に確定することはなかなかむずかしいようだ。
ジェフ・マルダーの『Sleepy Man Blues』がつくられた同じ年の1964年、エステスは、再発見後デッカから2枚目のアルバム『Broke And Hungry』を出している。興味深いのは、このアルバムにマイク・ブルームフィールドが参加していることだ。このアルバムの裏面にあるボブ・コスターによるライナー・ノーツには、ブルームフィールドは、「ロックンロールからブルースにやってきた、ブルース・リヴァイヴァリスト(復興論者)のメンバー」だと記している。「ブルース・リヴァイヴァリスト」というのは、おそらくマルダーをふくめたカントリー・ブルースにふたたび目をむけた動きのことで、エステス再発見の時代のことだったということだろう。
ブルームフィールドは、エステスのアルバム参加の時期では、ほとんど知られていないブルース・ミュージシャンで、このLPにつけられた中村とうようのライナー・ノーツによれば、まだシカゴ大学在学中の学生だったのではないかという。
その後、1968年にブルームフィールドは、〈アルバートのシャッフル〉を発表している。美しいというと平凡な形容詞だが、そうとしかいいようのないブルースである。薬物による陶酔をどこかに感じさせもする。エレクトリック・ギターがこれほど深く染み入る音色が出せるのだということに気づかせる演奏だ。この曲は、アル・クーパーとの有名なセッション『Super Session』の冒頭でも演奏されている。
エステスの『Broke And Hungry』では、ブルームフィールドはアコースティック・ギターを使っている。〈3:00 Morning Blues〉と〈Beale Street Sugar〉の2曲にブルームフィールドの名前がクレジットされている。どちらの曲もキーはA。ペンタトニックの音階を使ったシンプルな演奏である。ヤンク・レイチェルがフラット・マンドリンでリードを担当しており、ギターに関しては、エステスとブルームフィールドの音が鮮明には聴き分けられない。つまり、ブルームフィールドは、控えめなカントリー・ブルースのスタイルで演奏していたということだ。
『Broke And Hungry』が発表された同じ年の1964年、ブルース・ハープ奏者のポール・バターフィールドがポール・バターフィールド・ブルース・バンドを結成している。ブルームフィールドは1965年にこれに参加する。ここでは、ブルームフィールドはエレクトリック・ギターを使っている。彼らは、いわゆるエレクトリック・ブルースと呼ばれる演奏スタイルを代表するバンドのひとつとなった。
1965年におこなわれた「ニュー・ポート・フォーク・フェスティヴァル〉でポール・バターフィールド・ブルース・バンドが演奏すると、それまでアコースティック楽器が中心だったフォーク・ファンからの反発があった。しかし、このライヴを聴いたボブ・ディランが、このフェスティヴァルの自分のライヴで彼らをバックに使った。したがって、ディランがエレクトリック・ギターを使ったことへの反発も引き起こされたことはよく知られている。しかし、このライヴをジェフ・マルダーと一緒に聴いていた彼の妻で歌手のマリア・マルダーは強くインスパイアされたといわれている。
●声
高く張り上げるエステスの歌声は、とても特徴的である。このことは、ブルースやその後のロックにも共通していることなのだが、いわゆる美しい声である必要はない。むしろ、歌い手の身体の固有性のほうが、意味をもつ。このことについては、ロラン・バルトが「息」と「きめ」による声のちがいとしてとらえようとしていたように思える。 「音楽教育全体が、声の《きめ》の文化ではなく、発声の情緒的様式を教えている」「それは息の神話なのだ。歌の芸術というものは、息の抑制、息の上手な扱いにあると、歌の教師たちが御託を並べるのをわれわれは聞いたではないか」「もっぱら息だけに頼る芸術というものは秘められた芸術になりやすい」「肺というのは間の抜けた器官だ(猫の餌だ)」「意味形成が炸裂し、魂ではなく悦楽を出現させるのは、喉、すなわち、音声の金属が硬化し、輪郭が形づくられる場所においてであり、顔面においてである。フィッシャー=ディスカウにおいては、私には肺しか聞こえず、決して、舌、声門、歯、口内壁、鼻は聞こえないように思う」とバルトは述べている。 ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウはドイツの代表的なバリトンのオペラ歌手であるが、バルトは、その声からは歌手の固有な声の「きめ」は感じられないという。バルトは、むしろそうしたクラッシックの歌手の声ではく、いわば大衆音楽の歌声に魅力を感じていたことが、このエッセイから伝わってくる。そして、大衆音楽の歌では歌い手の「舌、声門、歯、口内壁、鼻」などの複雑な器官によって生まれる声こそが、魅力であり、聴くべきものなのだとバルトは感じている。 バルトの指摘にしたがえば、エステスの歌はまさに彼の「舌、声門、歯、口内壁、鼻」によっているといえる。 同じことが、ギターという楽器の音質についてもいえる。エステスが残したレコードから、彼のギターの音を聴くかぎり、それはくぐもったものだ。現在の良質なギターの音質とされているクリアな音質ではない(あえていえば安価なつくりのギターの音色である)。しかし、それは声と同様、バルトがいう「きめ」として受け取れば、エステスのギターの特性だといえる。その音が魅力的な音色だと感ずるのであれば(じっさい魅力的なのだが)、実のところギターもまた、かならずしも特定のメーカーによる音色が絶対的に良いものだとは、一概にはいえなくなることがわかる。悪声の魅力があるとすれば、悪い音色のギターの魅力もあるということだ。●再発掘
ジェフ・マルダーが、エステスの曲を取り上げたのは、やがてはじまる60年代から70年代にかけてのアメリカのフォーク・ミュージックの圧倒的な広がりへとつながるものだった。けれども、そうした流れのなかでは、ボブ・ディランの影にかくれて、マルダーはマイナーな存在になってしまったのかもしれない。 マルダーは70年代に『Is Having a Wonderful Time』というアルバムで、ブルースをふくめた古いアメリカのポピュラー音楽をカヴァーしている。たとえば、ケニー・バレルやダイアナ・クラールなど多くのアーティストがカヴァーしているドン・レッドマン作曲、アンディ・ラザフ作詞による〈Gee Baby, Ain't I Good to You〉といったスタンダードな曲を扱っている。この曲がつくられたのは、1929年。マルダーは、そうした古いアメリカの音楽を好んでいるようだ。そうした好みによって、エステスのブルースも取り上げられたのだろう。 古い音楽を再発掘するということでは、キューバのブエナ・ビスタ・ソーシャル・クラブを1990年代に再発掘したライ・クーダーにも共通した面があるように思える。ヴィム・ヴェンダース監督の映画『パリ・テキサス』のサウンドトラックで、クーダーは、1920年代に活動したブラインド・ウィリー・ジョンソンによるブルース(ゴスペルというべきか)〈Dark Was the Night〉を演奏している。ジョンソンは、スライド・ギターを弾きながらハミングを入れているが、クーダーはスライド・ギターの演奏のみにアレンジしている。そして、クーダーは1972年のアルバム『Boomer's Story』では、エステスと共演している。1曲はエステスの〈Ax Sweet Mama〉。ここでは、クーダーがヴォーカルを入れている。そして、もう1曲〈President Kennedy〉はエステス自身がギターとヴォーカルを担当している。この曲には次のように歌われる。 「ある金曜日の夕暮れ、みんな悲しんだ、わたしたちはこれまでのなかの最良の大統領を失った。けれども、彼は家にもどったんだ、家にもどったんだ。彼はとても長い間、留守をしているんだ」 ここでは、エステスの声が柔らかなものに聞こえるから不思議だ。キーはDの単純なスリーコードによる構成になっている。エステス自身が亡くなる5年前のレコーディングである。ギターをめぐるいくつかのこと(上)
20世紀の後半以降の世界中の音楽を支配した楽器がギターであることには、おそらく異論はないだろう。それは、ヨーロッパのクラシック音楽に代わって、ブルース、カントリー、フォーク、ジャズ、そしてロックなどアメリカの音楽が世界を制覇したことと無縁ではない。また、それはアメリカの政治経済そして美術をふくめた文化全般が世界に大きな影響を与える力をもったことと重なり合っている。
ヨーロッパ起源のギターはガット弦を使っており、さほど大きな音を出すことはできなかった。したがって、そのなかでは金属弦のおかげで大音響を出すことができるバンジョーが、アメリカの音楽ではメインの弦楽器として使われていた。しかし19世紀半ば頃、金属弦を張ったギターが使われるようになる。それ以降、しだいにギターが大衆にとってメインの楽器となりはじめた。その証拠に、この時代に現在につながるアメリカのギター・メーカーが登場している。たとえば1833年以来生産しているマーティン、19世紀末から楽器生産をはじめ、1902年に会社を設立したギブソンなどである。
さらに決定的だったのは、電気信号の増幅により大音響を実現したエレクトリック・ギターの出現である。これは、アメリカ独自の楽器だった。
エレクトリック・ギターの最初の製作は、カリフォルニアのアドルフ・リッケンバッカー(Adolph Rickenbacker)とジョージ・ビーチャム(George Delmetia Beauchamp)との協働によるものだと言われている。1931年にフライング・パン(フライパン)というエレクトリック・ギターを製作した。このギターは、現在のエレクトリック・ギターの形状とは異なり、フライパン、つまりバンジョーのような形状のものだった。また、フレットは25もあった。ちなみに、現在ではソリッド・タイプのエレクトリック・ギターとしてもっともよく使われているフェンダーでは、21から22フレットである。リッケンバッカーは現在もエレクトリック・ギターのメーカーとして知られる。
1936年、ギブソンがエレクトリック・ギターのES-150を制作している。このギターはようするに、アコースティック・ギターにピックアップをつけたものである。表面の板がギターの中心にむかって盛り上がったアーチトップ(archtop)になっていて、そこにはfホールが空いている。そのようなアコースティック・ギターにピックアップを付けたものだった。いわゆるピックギターとよばれるギターだ。ギブソンではf字のサウンド・ホールをもつギターを1920年代に製作していた。ヴァイオリンをはじめとするクラシックの弦楽器と同じように、表面が盛り上がったアーチトップは、鉋(かんな)で削り出して作られたものだ。いわゆるフォーク・ギターのような平板のフラットトップよりも手間がかかっている。ES-150は、ジャズ・ギターの奏法の基本をつくったといわれるチャーリー・クリスチャン(Charlie Christian,1916-42)が使ったことで知られる。
アーチトップの初期のギターは、ギブソンが1903年に製作しているが、1916年には「スタイル0」というアーチトップのギターも出している。このギターのサウンド・ホールはf字形ではなく、楕円形だ。形状は、ブルーグラスのビル・モンロウ(Bill Monroe)が演奏したフラット・マンドリンに似ている。このギターは『Country Blues Project: All by Myself』(Shamrock Record, 1996)というアルバムで使われているので、そこでその柔らかい音色を聴くことができる。ついでながら、このアルバムのH.Blessingによる「National」のリゾフォニック・ギターの演奏は秀逸である。スライド奏法でのGuitar Ragでは、カントリーの名曲Steel Guitar Ragをアコースティックで聴くことができるし、フラットピッキング奏法でのTuff Luck Bluseでは、このリゾフォニック・ギターの音色の特徴を聴くことができる。
リゾフォニック・ギター(リゾネイター・ギター)というのは、ボディ内部にコーン・スピーカーの形状をしたアルミニウムの共鳴器(resonator)を入れることで、通常のギターよりもいちだんと大きな音量を実現したギターだ。
ジョン・ドペラ(John Dopyera)、ルウディ・ドペラ(Rudy Dopyera)兄弟とジョージ・ビーチャムはナショナル・ストリング・インストルメンツ・コーポレーション(National)を1925年に設立した。ここで、リゾフォニック・ギターが製作された。製作は1926年といわれている。ビーチャムは、すでにふれたように、リッケンバッカーと協働してエレクトリック・ギターを開発したひとでもある。
その後1928年にドペラ兄弟はナショナルから離れ、ドブロ社(Dobro)を設立する。その結果、ナショナルとドブロは、リゾフォニック・ギターの2大メーカーとなった。
ビーチャムがその後、リッケンバッカーとともにエレクトリック・ギターを開発していることからもわかるように、アメリカの音楽は、大音量を可能にするギターを求めていたのである。
ヨーロッパで力をもっていたクラシック音楽は、オーケストラという編成で、たとえば複数のヴァイオリンを使うことで、大音響を実現した。またコンサート・ホールそのものが、巨大な共鳴空間であった。その大音響の音は、また世界を支配する文化の力と深くかかわっていた。したがって、アメリカが大音響の楽器としてギターを開発していったことは、世界に拡大していったアメリカの力と無縁ではない。逆にいえば、現在でもマイノリティが使う楽器のほとんどが弱音楽器である。
ギターをめぐるいくつかのこと(中)
スライド奏法とギター
ところで、リゾフォニック・ギターは、一般的にスライド奏法が使われる。つまり、弦の上をガラス管や金属管を滑らせる奏法によって演奏される。ブルーグラスやカントリー・ミュージックで使われるリゾフォニック・ギターは、弦高が高く、指でフレットを押さえることができない。したがって、フレットはいわば目印で、演奏は金属のバーをスライドすることでおこなわれる。また、ギターはひざの上に載せて演奏する。あるいは首からストラップで吊って、ボディを水平にして演奏する。ハワイアン音楽で使われるスティール・ギターの奏法にちかいといえる。
リゾフォニック・ギターは、ブルースにも使われる。ブルースに使われるリゾフォニック・ギターは、やはり弦の上をガラス管や金属管を滑らせるスライド奏法で演奏される。しかし、ブルーグラスのときとは異なって、ガラス管や金属管は一般的にはフレットを押さえる手の小指に装着され、それをスライドするとともに、場合によっては管を装着していない指でフレットを押さえて演奏する。
弦の上をガラス管や金属管で滑らせる演奏法はリゾフォニック・ギターで使われるのだが、リゾフォニック・ギターでのみおこなわれるわけではない。たとえば、エリック・クラプトンのアルバム『Me and Mr. Johnson』をはじめとして、多くのミュージシャンにカヴァーされているロバート・ジョンソンは、金属弦のアコースティック・ギターをスライド奏法で演奏している。
スライド奏法による演奏は、ぴったりとフレットの上の音を出すだけではなく、バーがフレットからフレットへとスライドしていくので、そこを経過していく音(グリッサンドあるいはポルタメントとよばれる奏法による)を出すことになる。また、きわめてあいまいな音ではあるが、微妙な音程を出すことができる。また、バーを振るわせることでヴィブラートを出すこともできる。したがって、演奏効果として少なからず使われてきた。楽譜の記譜としては音符の上に波状の線を引き、弾き方は演奏者の判断にまかせることになる。
この演奏方法がいつごろ誰によって生み出されたのかはわからないが、ガット弦のギターではその効果はほとんど期待できないので、金属弦ギターの出現以降に考案されたのだろう。
しかし、同時にスライド奏法は、その初期においては複雑なコードを使えない奏者、あるいは、精度の低いギターしか持てない奏者のかかえる問題を解決してくれるものであった。まず、複雑なコードを使えない奏者の問題であるが、スライド奏法をおこなう場合、フレットを押さえなくともよいように、いわゆるオープン・コードに調弦する。一般的には、GやE、あるいはDに調弦される。
この開放弦を和音とする調弦はバンジョーの調弦法から来ているともいわれている。ちなみに、バンジョーは、一般的に、開放弦でGの和音が出るように調弦している。
ギターの通常の調弦では、1弦の高いほうからE・B・G・D・A・Eとなっている。ドレミファで表記すると、ハ長調のミ、シ、ソ、レ、ラ、ミとなる。これをオープンGに調弦するには、1弦を1音下げてDに、5弦を1音下げてGに、さらに6弦を1音下げてDにする。つまり、D・B・G・D・G・Dとなる。これを開放で鳴らすとGのコードになる。5フレットにバーを移動するとCになる。さらに7フレットにバーを持っていくとDになる。したがって、バーを平行移動するだけで、G、C、Dといういわゆる3コードを出すことができる。複雑なコードを使えない奏者にも、じつに簡単にギターの演奏をすることができるようになる。
とはいえ、1930年代に活躍したロバート・ジョンソンのスライド・ギターの演奏は、高度なテクニックを使ったものだった。また、ジョンソンとも共演したエルモア・ジェイムズの1950年代の演奏は、ピックアップを取り付けたアコースティック・ギターを使い、ポルタメントとヴィブラートを多用したテクニカルな演奏をしている。
すでにふれたように、クラプトンもリゾフォニック・ギターを使っているが、当初は、スライド奏法で自在な表現はむつかしいと考えていたようだ。しかし、アルバム『いとしのレイラ(Layla)』(1970)で、デュアン・オールマンとのセッションをし、スライド奏法で自在な表現ができることを認識したようだ。「ドブロの演奏で初めて自在な表現力を感じたのがデュアンの演奏だった」「そのとき初めてカントリー・ドブロ――つまり膝の上に乗せて演奏するスタイルに限定されない、抑制の効いたドブロというものを聴いたんだ」(マーク・ロバティ『エリック・クラプトン/イン・ヒズ・オウン・ワーズ』中川晴子訳、キネマ旬報社)とクラプトンは語っている。つまり、スライド奏法は、現在では複雑な奏法と認識されているということだ。
さて、もうひとつの「精度の低いギター」という問題である。これは、リゾフォニック・ギターではなく、ふつうのアコースティック・ギターといっていい。廉価の、時として通信販売などで手に入れたギターは、製品として精度が低い。そうしたギターは、弦の張力などでしだいにネックに歪みが生じる。その結果、フレットを押さえても正確な音程が実現できないという問題が出てくる。しかし、フレットを押さえずにガラス管や金属管で音程を出すスライド奏法では、ネックの歪みにかかわりなく演奏が可能になる。
初期のブルースを演奏する黒人たちは、マーティンやギブソンといったギター、あるいはナショナルやドブロといったリゾフォニック・ギターなどの高価なものを手にすることはまれであったろう。多くが安価なギターを使っていたと思われる。そのギターのネックが狂ってしまうことはじゅうぶんにありうることだ。
弦高調整
ところで、ギターのネックの歪みのほとんどは、いわゆる「反り」である。一般的には、弦の張力によって、弦の張ってある側に反っていく。これによって、音程にも狂いが出てくるが、弦とネックとの間隔が広がり、フレットを押さえにくくなる。このネックの反りは、ネックの内部に金属のロッドを入れ、このロッドを引っぱるか緩めるかで調整することができる。この調整システムは、アジャスタブル・ロッドとよばれ、1921年にギブソン社が特許をとった。特許権が切れたころから、さまざまなギターにこのシステムが導入されていった。マーティン社では1985年に導入された。
アジャスタブル・ロッドは、サウンド・ホール側から六角レンチで調整するタイプと、ペグ(弦巻)のつけられたヘッドストック側からソケットタイプのレンチで調整するタイプの2種類がある。時計回りにレンチを回すと、いわゆる逆反り方向にネックが動き、反りが調整できる。
弦の高低の異常は、ネックばかりではなくボディが原因でも起こりえる。弦楽器は、乾燥した状態のほうが好ましいと思われがちだが、かならずしもそうではない。アコースティック・ギターの場合、ボディの天板にはスプルース材が一般的に使われている。ヴァイオリンなどにも使われる材料で、軽く乾燥しやすい特性がある。
ギターの天板[註:おもて面の板]は、乾燥しすぎるとサドル(ブリッジ)とよばれる弦の端のあたりが沈む。それによって弦高が下がり、押さえなくても弦がフレットについてしまう。その結果、音が出なくなってしまう。この現象は、エレクトリック・ギターを中心に演奏しているプロフェッショナルのギタリストにも認識されていないことがある。
このトラブルは、ギターに湿度を与えることで解決できる。良いか悪いかはわからないが、短時間で解決するには、スプレーで細かい霧を与えるという方法もある。
ギターのネックの反りともかかわるのだが、弦高が高くなると、演奏がしにくくなる。弦高が下がりすぎると弦がフレットにふれてしまう。弦高の調整は演奏のしやすさと深くかかわっている。
弦高は、ギター上部のナットから下部のサドルにいたる領域における、ネックと弦の距離である。弦の始まりのところにはナットとよばれるプラスティック製(象牙製)の弦の受けがある。そして弦の終わりのところにやはりプラスティック製(象牙製)のブリッジとよばれる受けがある。これらの受けは弦の振動をボディに伝えるので、音響に少なからぬ影響を与える部品だ。
弦高は低いほうが演奏しやすい。また、通常ナットからブリッジに向かって弦高は高くなっていくのだが、たとえば、クラプトンはこれを同じ高さに調整している。クラプトンが多用しているフェンダーのストラトキャスターなどのエレクトリック・ギターの場合、アコースティック・ギターよりも比較的弦高が低く設定されている。フェンダーのストラトキャスターの場合、サドル部分につけられているネジで弦高を調整できるように設計されている。しかも、1本ずつの弦高調整が可能である。アーチトップのギターの多くは、ブリッジの両端にナットがついており、これを回すことで弦高を変更することができる。現在のオヴェイションなどのギターには、ブリッジの下にプラスティック板が重ねられているので、この板を増減することで弦高の設定を変更することができる。
問題は、マーティンに代表されるアコースティック・ギターである。これは、すでにふれた、(本来の機能である)ネックの反りを調整するアジャスタブル・ロッドを使って、ある程度、弦高の調整が可能になる。ロッドを時計回りにまわすと、ネックが逆反りの傾向になり、弦高がいくぶん低くなる。
弦高を低くすれば弦を押さえる力は少なくてすむので演奏はしやすくなる。しかしアコースティック・ギターの場合、ブリッジを下げると、音響は明らかに衰える。したがって、アコースティック・ギターの演奏よりも弦高の低いエレクトリック・ギターのほうが、はるかに運指が楽になる。さらにいえば、フェンダーのストラトキャスターなどのエレクトリック・ギターは、ネックがアコースティック・ギターにくらべて細く、演奏しやすいようにデザインされている。
ギターをめぐるいくつかのこと(下)
ロボット・ギターとロック
弦高が低く調整され、ネックの細いストラトキャスターに代表されるエレクトリック・ギターは、高速度の演奏もしやすい。アンプリファイアを使うことで、エレクトリック・ギターは、地響きがするほど巨大な音を出すことも可能だ。クラシックのオーケストラのように複数の同一楽器と巨大なホール空間を必要とせず、エレクトリック・ギターは、単一で巨大音を出すことができる。
20世紀後半の文化を特徴づけてきたロックは、エレクトリック・ギターとわかちがたく結びついていた。エレクトリック・ギターの開発が、新しい音楽としてのロックを生み出すことへとつながっていったといえるだろう。それは、20世紀後半以降のアメリカ文化の世界的な影響力、あるいは資本主義のシステムと無縁ではない。資本主義は、単に経済のシステムであるだけではなく、文化の様式ともかかわっている。
実際、ティモシー・W. ライバック『自由・平等・ロック』(水上はるこ訳、晶文社)は、社会主義圏におけるロックについて、興味深いエピソードを数多く紹介している。それによれば、1960年代にソヴィエトでは、ロックを演奏しようとしても、エレクトリック・ギターがなかなか手に入らなかった。66年に東ドイツ製のエレクトリック・ギターを扱う店ができたが、10本ほどしかストックがなく、開店後、たちまち売り切れてしまった。69年、「エレクトリック・ギターのピックアップは電話につけられているピックアップを改造することで作ることができる」ということを、ある若者が新聞で説明したため、モスクワ中の公衆電話が破壊された。一時は、モスクワ中の公衆電話が1台も使えなくなるほどにまで破壊しつくされたという。
ロックは、社会主義圏の旧ソヴィエトにもさまざまなかたちで流れ込み、若者たちに聴かれていたが、それを演奏する楽器が当初なかったのである。それを演奏するには、社会主義圏ではなく、それはとりもなおさず、アメリカで生み出された楽器、エレクトリック・ギターが必要だった。
ところで、さきのリゾフォニック・ギターのところで、調弦についてふれた。一般的には、高いほうからE・B・G・D・A・Eというレギュラー(ノーマル)・チューニングをする。ロックを演奏するためのエレクトリック・ギターは、これ以外にも、6弦だけをEから1音下げてDにするダウン・チューニングがよくおこなわれている。もちろん、スライド奏法を使うことも多く、GやEやDのオープン・コードのチューニングもめずらしくない。
現在では、スイッチひとつで複数の調弦に変更できるエレクトリック・ギターがつくられている。たとえば、ギブソン社は、自動的にチューニングをするロボット・ギター(Gibson Robot Guitar, GOR)を2007年に製作した。いくつかの型が存在するが、その基本は、レス・ポール・モデルにしている。ちなみに、オリジナルのレス・ポール・モデルは1952年、ギタリストのレス・ポール(Les Paul, Lester William Polfuss)とギブソンが共同開発したものである。そして2011年に、FirebirdXというさらに新しいGORを製作した。このロボット・ギターは、2011年には、Firebird Xというさらに新しいシリーズを追加した。これは、1963年に生産されたエレクトリック・ギター、ファイアバードをモデルにしている。そのデザインは、クルマのデザイナー、レイ・ディートリヒ(Raymond H. Dietrich)の協力によっていた。レス・ポールなどのモデルを平行四辺形にずらしたような形状で、いわゆる「オッドシェイプド・ギブソン(odd-shaped Gibson)」、つまり「変形」と呼ばれているものである。
Firebird Xは、ボディにトネリコ材を使い軽量化している。通常のピックアップのセレクターのようなボタンがあり、エフェクト・レヴェル、ピエゾ・ピックアップ(piezoelectric pickup。電圧素子を使ったピックアップ。ピックアップには磁石を使ったマグネティック・ピックアップも使われる)の調整などができる。アコースティック・ギターのJ-45のサウンドを出すことも可能になっている。そして、チューニング選択のトグルがついている。弦の圧力をセンサーで読みとり自動チューニングを調整するしくみになっている。機械的に弦を巻き取り調整するのでペグが回転する。7つのプリセット・チューニングができ、そのうち6つの編集も可能になっている。もちろん、スイッチ(トグル)ひとつで、すぐにレギュラー・チューニングにもどすことができる。
高速度で調弦を変化させ、高速度で演奏することができ、大音量を出す。多くの弦楽器がそうであるように、ギターはもともとそれぞれの個体の音の差異がある。高速度とパワー(力)、そして音の差異、これは、ロックという音楽の特性に見合っている。また、力と差異による更新の運動は、資本主義のシステムに見合っている。
けれども、だからといって、ロックが市場経済のシステムや論理に全面的に回収されているわけではない。そうしたシステムや論理をすり抜けていくことがまた、ロックというサウンドの力でもあるからだ。この点に関連してサイモン・フリスは名著『サウンドの力』(細川周平、竹田賢一訳、晶文社)の中で、「ロックこそは資本主義の形態であるが、その資本主義文化こそは我々が理解し、利用し、ひっくり返し、楽しもうとしているものなのである」と述べている。フリスの言う「ひっくり返し」や「楽しみ」とはまた、かつてテオドール・W. アドルノとは逆に、ヴァルター・ベンヤミンが大衆文化の中に見た、いわばシステムとの文化的闘争なのだと言い換えることもできるだろう。
痛みをやり過ごす──モーツァルト
作家の桐山襲(きりやまかさね)に生前、わたくしはたった一度しか会う機会にめぐまれなかったが、亡くなる少し前、彼が新聞に近況を書いていたのが印象深かった。いま、その切り抜きがないので正確な文章をここに引くことはできないが、それは、病院で一日中点滴をつけたまま生活しているため、点滴をぶらさげたポールのキャスターが歩くたびにゴトゴトという音をたて、それが自らの身体に固有の音であるかのように思えてくるといったような意味のことを語っていた。痛みが去ったときには、少しは院内を散歩するらしく、病院の屋上に立つと、頭をなでる風の寒さが、制癌剤のせいでほとんど髪が抜け落ちたことを意識させるという。そして、癌の激痛と制癌剤の副作用の苦しみをベッドでじっとこらえるには、モーツァルトを聴くしかないと書いていた。それからしばらくして桐山は亡くなった。
亡くなったのは、1992年の春先のことだったから、上記の新聞でのエッセイは1991年だったのかもしれない。作家としての活動は、8年ほどの短いものだったが、芥川賞に二度、そして野間文芸新人賞に一度ノミネートされている。活動期間の短さに比例して、作品はけして多くはない。したがって、桐山の名を記憶している人が、いまではどれほどいるかはわからないし、わたくし自身、ほんのいくつかの作品しか読んではいない。しかし、闘病生活を語った新聞でのエッセイの、モーツァルトを聴くしかないというくだりに、長く忘れがたい印象を受けた。
嵐のような激痛を耐えるには、身体を動かさずに、じっとモーツァルトに耳をすませるしかなく、痛みが通り過ぎていくのを待つ。絶望の中で、気分がそれ以上落ち込まないように、とりあえず神経を鎮静させるためにモーツァルトを流し続けたのだろう。
もし、わたくしが激痛に襲われ、いつ終わるともしれない不安のなかで、痛みが和らぎ、凪のくるのを待つために音を流し続けるとしたら何を選ぶだろうか。ロックやジャズやブルースではないだろう。そうしたものは健康なとき(決定的な痛みを感じていない日常というべきか)にはいい。とりわけ、ブルースやジャズは好きだ。けれども、ぎりぎりに追い詰められた中では、わたくしも、モーツァルトを流してくれるように頼むかもしれない。
では、モーツァルトの中で何がいちばん好きかといわれて、次々に作品と演奏を思い浮かべつつ即座にこたえられるほど、わたくしはモーツァルトを聴き込んでいるわけではない。手もとには、さまざまな演奏家による10枚ほどのCD、それと内田光子の8枚組のCD『Mozart――The Piano Concertos』(PHILIPS)がある程度だ。したがって、なぜモーツァルトなのかと問われると、モーツァルトの音が織りなす空間に身を包まれることの心地よさといえばいいのか──。ここでいう空間はまさに建築的空間といっていいかもしれない。
音においても建築的空間を構成したのはやはり、ヨーロッパのバロック以降の音楽であるように思える。旋律がつくりだす物語性とテーマ性、和音の構造、音階(スケール)による遠近法そして様式、楽器による内部空間のテクスチュア。ついでながらふれておけば、クラヴサンやハープシコードといった楽器が家庭の中で聴かせる程度の小さな音量しかもたない楽器であったのに対し、ピアノの音量はコンサート・ホールに対応している。ヨーロッパの楽器はバロック時代以降、ひたすら巨大な建築空間に対応するように改造されていった。また、オーケストラ形式で、同一の楽器を複数使うことでアンプの効果を出す。逆にマイノリティの楽器は、口琴に代表されるように、いかにも、恋人にひそかなメッセージを伝えるほどの音量しかない。現代の支配的資本主義が、人間の身体を吹き飛ばすほどの出力をもったエレクトリック・ギターを中心的な楽器としたロックを生み出したことはいかにも象徴的である。
ヨーロッパの音楽が建築的空間を構成し、物質的にも巨大なコンサート・ホールを生み出したという事情は、書物においてもあてはまる。ヨーロッパにおいては書物は、建築と同じように構成されてきた。煉瓦や石のブロックのように文字を集めてページや章を構成し、やがて1冊の書物を組み上げる。それは棚に収められ、やがて巨大な図書館を生み出していった。たとえば18世紀末、フランスの建築家エティエンヌ・ルイ・ブーレの一連のメガロマニアックな図書館構想にそれを見ることができる。それは、20世紀のパリの新国立図書館建設にまでつながっている。そこでは、書庫(マガザン)の棚の長さはなんと500キロメートルに及んでいる。東京から新大阪までの長さだ。
モーツァルトを楽しむこととは、モーツァルトがつくりだした華麗な空間に身を包まれる快楽にほかならない。たとえば、ピアノ協奏曲第21番ハ長調(K467)。この作品の第1楽章「アレグロ」はCメジャー(C-Dur、ハ長調)で始まる。そして第2楽章「アンダンテ」の部分がとりわけポピュラーである。この出だしはコントラバスがくっきりと、静かにFメジャー(F-Dur、ヘ長調)の和音で始まることを伝える。ゆっくりとヴァイオリンの旋律が始まる。やがて、ピアノの三連符の和音と、ゆっくりとした旋律が始まっていく。F-C7-F-F7-B♭とあたりまえの和音で進行していく。こうしたあたりまえの構成をとっているということは、演奏(解釈)の仕方によってそれぞれ異なったものとなるはずだ。わたくしは、内田光子の演奏(解釈)が美しいと思う。この曲は、彼女の8枚組CDの5枚目に入っている。
モーツァルトは、基本的な構造体に愛らしい旋律をつける。それは装飾であり様式でもある。こうした音の空間はロココの快楽的建築空間に対応している。
いつ終息するのかわからない、たどりつく彼岸の見えないような痛みの中でじっと身を包んでもらうとしたら、やはり、そうしたモーツァルトの建築空間かもしれないと思う。
ここでピアノ協奏曲第21番について記述したのは、たまたまのことである。それがモーツァルトのなかでとりたてて好きというのではない。聴きたいものはその時々で変化する。ピアノ協奏曲第21番を使った映像作品で美しかったのは、ポーランドの映像作家ズビグニュー・リプチンスキーの『オーケストラ』であったことを付け加えておきたい。
あいまいな音の魅力
記譜できない音
以前(第4回参照)、リゾフォニック・ギターとスライド奏法にふれた。経過音を使ういわゆるグリッサンド(滑奏法)である。もちろん、リゾフォニック・ギターだけではなく通常のアコースティック・ギター、エレクトリック・ギター、あるいはハワイアン・ギター、スティール・ギターなどでも同じ奏法が使われる。この場合、音を楽譜では示せないので、音符の上に波状の線を引き、あとは演奏者の判断にまかせることになる。
音符として記譜できない音という意味では、この奏法は、いわゆる無調律(nontempered)的なものだともいえるだろう。音楽のジャンルとしてはブルース、カントリー、ブルーグラス、そしてハワイアンやロックなどでさかんに使われる。中世ヨーロッパ音楽でもどうやら無調律的な楽器が中心だったようだ。
かつてボストン交響楽団のベース奏者だったオーティツ・ウォールトンによれば[註1]、「中世の音楽のほとんどは、ほんらい声楽であった。用いられた楽器は、コンティヌオ[continuo。通奏低音]と呼ばれる演奏に適したヴィオール[viol。ヴァイオリンの前身]型のものや、バルブやキーのない、いろいろな管楽器だった。ヴィオール類はフレットのないもので、アフリカの弦楽器に似ていた。それらは無調律で、メロディの演奏も、オスティナート(ostinato)とよばれる反復単音の音列も、メロディからあらかじめアレンジした音列のコードを伴奏するベースとしても、演奏することができた」のだという。したがって、「無調律、そして機械化されていない楽器の演奏者の技術能力は、たしかにそうとうなものであり、したがって、無調律楽器のために書かれたコンチェルトやソナタの多くは、新しい楽器にとっても難しいものだった」という。つまり、フレットが付けられた弦楽器や、ヴァルヴやキーあるいはピストンがつけられた、いわば機械化された新楽器でも、無調律楽器のために書かれた曲は演奏しにくいものだった。
楽器の機械化とJ.S.バッハの登場は無縁ではない。このことは、記譜法ともかかわっている。ウォールトンは、次のように述べている。
中世初期に、ネウマ(neumes)とよばれる記譜法[グレゴリオ聖歌に用いられる]がすでに作られていたが、しかしそれは単にピッチの上がり下がりを示しただけで、上下の音階度(ディグリー)を示すものではなかった。最終的にコントロールされなければならないのは、ピッチの変化であった。記譜のシステムの確立によって決定されたにもかかわらず、多様な音のピッチは定まらず、また、音と音の間の振動の比率は、オクターブごとに変化した。
バッハは、《平均律クラヴィーア曲集(The Well-Temered Clavier)》において、“平均律”の効果的価値をはじめて完璧に論証した。1オクターブは、他のオクターブに似るように人為的に調整された。また、G♭はF♯とは元来異なっていたのだが、いまや同一のサウンドに調整されたのである。しかし、このプロセスは、さまざまな音程を、“不調和(out of tune)”に調整した結果なのだ。無調律の教会の旋法(モード)から全音階(ダイアトニック)にとって変えられ、合理性と断定性の要素を増していったのである。平均律の普及によって、ヨーロッパの楽器制作者は、調律楽器を作るようになっていった。他方では、「音楽の完璧な合理化を目指すことの頂点の達成は、交響楽団の発達だった。ここに、専門化はそのピークに達し、演奏家たちは、そのたびに常に同じやり方で演奏するための明確な楽譜を持つようになった。メロディ、ハーモニーそしてリズムの変更は許されず、操作の流れ作業(アッセンブリー・ライン)型のものが、指揮者の監督によって動き出したのである。それぞれの演奏者は、流れ作業の労働者のように、完成品のために貢献する負担を求められた。交響楽団は、各セクションに分かれ、さらにはセクションの監督あるいはリーダー(指揮者)、そしてサイドマン(主演奏者を補助する奏者)といった階級制によって、最大の効果をあげる集団(ライン)にそって組織された」のだとウォールトンは述べている。 まるで、流れ作業の工場労働者あるいは戦場の兵士のように、規律にしたがって、正確にそして精密に演奏することが、クラッシク音楽の領域ではおこなわれるようになったのだというのだ。ウォールトンがここで使う「ライン」という言葉には、実際、軍隊の戦闘部隊という意味もある。 ジャズやブルースあるいはカントリーやハワイアンなどの大衆音楽では、演奏は演奏者あるいは歌手のみずからの解釈であるていど、自由に演奏の変更ができる。また、そのアレンジが演奏や歌唱の評価にかかわる。したがって、楽譜どおりに指揮者の監督のもとに演奏するクラッシク音楽の奏者にくらべてその演奏は難しいと、傍目には思える。しかし、事態は逆だといえるだろう。正確な機械のように作業することがいかに困難であることか。 バッハにしてもモーツァルトにしても、クラシック音楽の美しさは、そうした精密なメロディ、和音、リズム、楽器の強弱によっている。もちろんわたくしも、それをじゅうぶんに美しいと思うし、好ましく思っている。 しかし、クラシック音楽からみれば大衆音楽(ポピュラー・ミュージック)とされるジャズやブルース、あるいはカントリーやハワイアン、さらにはロックでは、フレットを無視したギターのスライド奏法が使われている。つまりこちらではあいかわらず、その不安定な音が、わたしたちの感覚を捉えているということだ。楽器そのものの構造でいうなら、クラシックでは、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスといったフレットをもたないヴィオール型の楽器が使われているにもかかわらず、音を歪めるような奏法はほとんどおこなわれない。グリッサンドにしても、正確な経過音を出している。ギターのスライド奏法のように、演奏者の判断にまかされているわけではない。 語ることと歌うこと、抑揚 ポピュラー・ミュージックにおけるいわゆる無調律とも思える音の不安定さは、楽器演奏だけではなく、どうやら歌声にも共通しており、それが魅力をつくっているように思える。 ハワイアン音楽の女性歌手、イローディア・カーネの歌声と唱法は、そうした特徴をあらわしているひとつの例である。20世紀前半のハワイアンの作曲家で歌手のレナ・マシャード(1903-1974)へのトリビュート・アルバム『Tribute to Lena Machado』(RESPECT RECORD Ltd, 1999)での彼女の歌声と唱法の魅力は、その不安定さにある。消え入りそうなほどに弱い高音の歌声。時として音程があやふやになる。なかでも、〈Holau〉は、スライド奏法のハワイアン・ギターをバックに、ファルセットと思えるほどに高く、しかもか細い声で歌っており、正確なメロディがどういうものなのか、にわかにつかめない。たゆたうように歌っている。けれどもその不安定な歌唱は、どこまでも人を引きつける魅力に富んでいる。ついでながら、この曲の基調コードはGである。 オリジナルのほうのレナ・マシャードは、やはりファルセット唱法で、ハワイアンの女性歌手として中心的存在であった。しかし、カーネのトリビュートと聴きくらべると、マシャードは音程がしっかりしている。したがってマシャードのほうが歌手としての力量は高いのだが、とはいえ、音程が心許なくなるカーネのほうが、かえってどこかしら魅力的に聞こえるのは、その抑揚にあるように思える。 この種の魅力についてロラン・バルトは、ジュリア・クリステヴァが使った、テクストについての二項対立的な分析的用語を援用して語っているように思える[註2]。その二項対立的用語とは、「フェノ・テクスト(現れとしてのテクスト)」と「ジェノ・テクスト(発生としてのテクスト)」というものだ。バルトは、その用語になぞらえて、現れとしての歌(フェノ・シャント:pheno-chant)と「発生としての歌(ジェノ・シャント:geno-chant)」という造語をおこなっている。 「現れとしての歌」は、歌われた言語の構造、ジャンルの法則、メリスマ(melisme)のコード化された形式、作曲家の個人的言語(イディオレクト)などの特徴である。それは文化的価値の織物を組織するものだとも、バルトは説明している。つまりいいかえれば、それは社会や時代の文化的枠組みの中にあるともいえるだろう。 それに対して「発生としての歌」、それは「歌い、かつ、語る声の量(ヴォリューム)である」とバルトはいう。それは「能記=音の官能」(la volupte de ses sons-signifiants)なのだとも述べている。「それは、きわめて単純な一語、しかし、真面目に取らなければならない一語で表せば、言語の語り口(ディクシオン)なのだ」という。それは、身体が発する語り口の抑揚といったものにかかわっている。ディクシオン(diction)には発声法、話し方、朗読法、歌い方、といった意味がある。 歌うことと話すこと、朗読あるいは語ることが、ほんらい同じものであったという認識は、きわめて重要な視点である。バルトは「歌は語らなければならない。さらにいえば〈書く〉ことが必要である」とまでいう。それは、話し書くことの官能的身体性にかかわっている。 このことはこんにち、多くの指摘がなされている。たとえば、イギリスの社会人類学者、ティム・インゴルド[註3]は、祈りに没頭するひとりの修道士について、12世紀のペトルス・ウェネラビリスの「休むことなく、彼の口は聖なる言葉を反芻した」という記述を引いている。ウェネラビリスは、フランスのクリュニー修道院の修道院長をつとめ、『コーラン』の最初のラテン語訳発案者であった。インゴルドは、「少なくとも西洋では、発話[スピーチ]と歌[ソング]は異なる領域に区分されていなかった」と指摘している。 このことは、日本においても同様である。ちなみに「ギリシャ人は彼らの『音楽』をあらわす適切な表記法に到達しなかった。彼らは言葉から離れた音楽を想像することができなかったので、言葉の記述と音楽の記譜とを分離する理由がなかったのだ」とインゴルドは述べている。 さきにウォールトンによるネウマについての記述を引いたが、インゴルドによればネウマがアクセント記号であったいう。
ギリシャ・ローマの文献[リタラチュア]は紀元前200年頃、アレクサンドリア図書館長、ビザンティウムのアリストファネスによって発展させられた。それらは〈ネウマ〉[neuma]とよばれ、「合図[サイン]」、「身振り[ノッド]」という意味のギリシャ語に由来する。揚音[acute]と抑音[grave]というふたつの基本的なアクセントがあり、それぞれピッチの上げ下げを示した。それらはしばしば結合されて、たとえばVやNといった印で、より複雑な声の抑揚[inflection]をあらわした。[註4]これがグレゴリオ聖歌のための「ネウマ譜」とよばれるものであった。したがって、言葉を表記することと音を表記することは、その考え方において重なり合っていたといえるだろう。そして、言葉を発することと歌うことは分離されてはいなかった。それは、キリスト教の聖歌だけではなく、コーラン、仏教の声明などにも共通してみられることだ。 インゴルドは、したがって歌詞テクストに「〈マーキング〉する方法は、雄弁[oratory]の分野でも広く用いられた」のだと指摘している。語ることも歌うことも、声の「抑揚」によって、表現するということでは共通するものであった。 どちらが音痴か 話すことと歌うことの関連でいうと、アフリカの言語は、どうやら特徴的な言語のようだ。ウォールトンは、次のように述べている。
アフリカの音楽的感性は、彼らの言語の広範囲の使用をとおして、動かされ強化されている。その言語とは「声調的[tonal]」なものである。声調的な言語においては、同じ単語が、単語のピッチによって複数の意味を持つことができる。ヨルバ[Yoruba]語における、foやdaを例にとれば、すなわち、 Lo fò awo nyen(あの皿を洗いに行きなさい)は、foのアクセント変えることで、 Lo fó awo nyen(あの皿を壊しにいきなさい)になる。 また、Olorun lo dà mi(神がわたしを作った)は、daのアクセントを変えることで、 Olorun lo dá mi(神はわたしを裏切った)となる。 多くのアフリカ人は、子どもの頃から、ピッチの違いを弁別するように注意深く教育される。ピッチの鋭さや差異が、言語の固有性とリズミックなアクセントと結びついて、アフリカ言語に固有な音楽性を与えている。[註5]ウォールトンはfoやdaのアクセントに、フランス語で使うアクサン=テギュとアクサン=グラーヴの記号を使っているが、じっさいにどのように発音するのかは、わからない。これはすでに紹介した、インゴルドによるネウマのアクセント記号を想起させる。いずれにせよ、アフリカの言語においては声調性が重要であり、それによって意味が変化してしまうということなのだ。そして、それが音楽にも共通しているということだ。 このことについては、情報理論の領域でも指摘されている。ジェームズ・グリックは、「アフリカの言語」は「声調言語であり、母音や子音の差異によってだけではなく、ピッチの上下によっても意味が決定される」と述べている。また、この特徴は、「英語をふくむインド・ヨーロッパ語から消えている」という。そしてアフリカの言語を習い覚えたヨーロッパ人が、「耳にしたその単語をラテン・アルファベット[ローマ字]に翻訳するときに、ピッチに注意をはらわなかった。彼らはいわば先天的な音痴[color-blind、色覚異常の意味だがここでは音痴とした]だったのである」[註6]と指摘している。 アフリカの言語そして歌が声調つまり抑揚によっていることに注意をはらえなかったヨーロッパの人々を「音痴」とまでグリックはいっている。アフリカの音楽だけではない、ハワイアン、あるいはアフリカ音楽に少なからずつながっているブルースなどのいわゆる大衆音楽では、声調、抑揚が重要な要素となっており、それが魅力ともなっている。 音程があやふやで、ときに消え入りそうなハワイアンのイローディア・カーネの唱法に、話をもどそう。それは音程があやふやであるがゆえに「音痴」なのか。情報理論の見地からいえば、むしろ、平均律による全音階(ダイアトニック)の音を中心としていったヨーロッパのほうが「音痴」ということになる。はたして、どっちが「音痴」なのか。 歌や楽器演奏が官能的に感じられるのは、ある時期のヨーロッパ人が無視してしまった、あいまいな抑揚をもつときだ。これは、わたくしの個人的な好みともかかわっている。けれどももちろん、わたしはバッハも好きだ。疲れたときには、カナダのグレン・グールドのピアノによる演奏を聴きたくなる。ついでながら、カナダのトロントにあるグールドのグランド・ピアノの形をした墓にお参りをしたことがあるけれど、一説では、正式な墓はほかにもあるとのことだ。