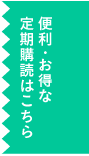近藤秀秋
ギター奏者、音楽ディレクター、録音エンジニア、ビショップレコーズ主宰、即興音楽アンサンブル「Experimental improvisers’ association of Japan」リーダーなど。主な作品としてCD『アジール』(PSF Records, PSFD-210)など、近日中に書籍『音楽の原理』(アルテスパブリッシング)刊行予定。
喜多直毅クアルテット「挽歌─沈黙と咆哮の音楽ドラマ─」
2016年3月31日 東京・ティアラこうとう小ホール
演奏)喜多直毅クアルテット:喜多直毅(vln)、北村聡(bdn)、三枝伸太郎(pf)、田辺和弘(cb)
演目)鉄条網のテーマ(喜多直毅)/燃える村(喜多直毅)/影絵遊び(喜多直毅)/月と星のファンタジー(喜多直毅)/峻嶺(喜多直毅)/アンコール:残された空(喜多直毅)
──────────タンゴ云々より先に、音楽として最大価値に達しうる領域で挑まれた音楽。そのうえで、学習期を過ぎ自分の声を持ち始めた日本タンゴ界の近年の芸術的躍進をさらに印象づけたパフォーマンス。この日の喜多直毅クアルテットのコンサートを音楽史上で位置づければ、このようなものであったのではないだろうか。
3月末、美しい緑に囲まれた東京のティアラこうとう小ホールで行われた喜多直毅クアルテットのリサイタルの客席には、ラテン音楽関係の批評家はもちろん、ジャズや現代音楽の批評家、音楽サロン運営者、さらにミュージシャンの顔などが確認できた。一昨年に発表されたライヴ録音盤『幻の冬』の成果や、喜多をはじめこの楽団のメンバー個々の近年の目覚しい活躍など、これが音楽界にとって重要なコンサートになることを予感した音楽人は多かったかもしれない。そして喜多直毅クアルテットは、その期待に充分に応えた。

喜多直毅はタンゴから活動を始めたヴァイオリニストである。しかし最初に結成したタンゴ・バンドを解体後はすぐに次のタンゴ・バンド結成には進まず、アラブ音楽や即興音楽などさまざまな音楽を吸収してから、現在の喜多直毅クアルテット結成に踏み込んだ。それは単純なタンゴへの帰還ではなかった。良くも悪くも優秀なタンゴ・ヴァイオリニストに留まる可能性もあった喜多にとって、現クアルテットの存在は大きい。この四重奏団の音楽をタンゴの範囲で語ることはもちろん可能だろうが、実際にはより普遍的な音楽領域に踏み込んでいる。
この日のコンサートで披露された音楽の特徴をひとつ挙げるとすれば、強さへのこだわりである。音楽を構成する内観や外観は、それぞれカラーや強度を持っているが、このコンサートでの喜多クアルテットは、そのどちらに対しても強靭さを求めていたように感じる。むろん、フォルム面も表現面もけっして一辺倒ではないのだが、本筋として判断の基準においているものが強さなのではないか、という意味だ。まず外観(わかりやすく多少の語弊を避けずにいえば、作曲的所為)。巨大な音楽劇が多く(この日最長となった「峻嶺」は約21分)、タンゴ以上に西洋芸術音楽の影響を感じさせる。楽式は明らかに西洋芸術音楽に由るもので、なかでも目立ったのは複合形式やロンド形式という変化しながら横に繋がる音楽の様相で、これがこのコンサートの「音楽ドラマ」というサブタイトルに繋がっているのだろう。 各楽節は、技法の創造や特定技法内の作曲ではなく、さまざまな音楽から断片的に援用される。これは音楽の価値を(発明や実験ではなく)具体的な効果や強度に見出しているがゆえ、と感じた。ハバネラ、ピアソラ、ストラヴィンスキー、バッハ、インプロヴィゼーション……さまざまな音楽を俯瞰して一本にまとめ上げる所作は、喜多がポスト・モダンの視点を持つ作曲家であり、その課題局面を正確に把握している証でもあるだろう。これだけの音楽要素に一貫性を持たせてまとめ上げたスコアはみごとだった。また、まとめ上げの難しいこれらの楽式を、起承転結のドラマとして提示した三枝伸太郎の演奏は特筆に値する。ソルフェージュ能力の高さから来たのであろう三枝の演奏プランのみごとさが、この音楽劇を劇的かつ一貫性あるものにした。 内観(言い換えれば音から受ける刺激、情動喚起、あるいは演奏表現)。これも徹底して強さに向かっていたように感じた。作曲には複雑性を求めずにデザインの明確さだけを求めて音楽を安定させ、そのうえで演奏家が暴れまわる。演奏が複雑な方向に走っても音楽が崩壊することのないこの構造が、バンドに強い表現に走ることを許し、これが苛烈な演奏を特徴とする喜多クアルテットの魅力を引き出す。音をどれだけ血肉化できるか、ここに向かう姿勢は実にタンゴ的であった。このあたりは、一歩引いて本質としてタンゴを見つめることのできる日本人タンゴ楽団の強みだろう。しかし具体的な表現の表象自体は、すでにタンゴの範疇にない。この日の喜多の演奏の一部を切り取ってみれば、バッハ解体からそれを演奏表現の机上に還元し直したような演奏、呼吸やルバート感覚に透けて見える日本音楽の様相……挙げればきりがないが、演奏表現は何かの模倣ではなく、自己の内部に血肉化されたもののように感じた。これは、フリー・インプロヴィゼーションや地域音楽など、音楽の色々な局面を螺旋状にめぐった経験が生きているのかもしれない。
近現代の日本音楽史の特徴のひとつは、外文化受容史という側面だろう。これは現代に政治的風下に立った周縁地域の多くが経験してきたことで、タンゴを育んだブエノスアイレスもラテン・アメリカも、ヨーロッパ音楽の模倣に覆いつくされた時代がある。そのまま同化吸収されて消えた文化も少なくないが、強い音楽文化を創出しえた文化圏では、西洋音楽と自文化を跨いで弁証法的還元を成功させて現状を作り出している。タンゴもフラメンコもこうした側面を持っており、日本でも戦後現代音楽や黎明期フリー・ジャズにはそういう側面があった。そして今度は日本のタンゴがこの局面を迎えている。喜多直毅クアルテットの音を聴いて感じるのは、喜多やそのメンバー、さらに現在の日本タンゴ界の前線に立つ音楽家たちが、この役割を果たす最初の世代になるという予感だ。喜多クアルテットはすでに大きな成果をあげている。場合によっては、歴史というコンテクストの脈絡に左右されない点をして、ブエノス以上にタンゴや音楽の本質に近づいたサウンドを奏でているとすらいえるかもしれない。日本の音楽史上で重要な意味を持つコンサートのひとつであったと感じる。 音楽が人間に対して果たすことのできる最大価値を狙うことが、最大価値を持つ音楽の条件であり、そこに挑むことこそが最大価値を持つ音楽家の創作姿勢であると信じて疑わない。音楽に癒しや楽しみを求める傾向のますます強まる現状で、強い音楽を狙いにいった姿勢に拍手を送りたい。