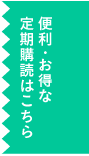東日本大震災で被災した福島から、Twitter上でその混乱と恐怖を「詩」として言葉で発信し続けた詩人・和合亮一。その数々の詩(詩集『詩の礫』[徳間書店/2011年]にまとめられた)に共振し、震災の記憶を呼び起こす「歌」=《つぶてソング》として詩を新たな次元に導いた作曲家・新実徳英。二人の対談は、お互いの創作活動を真摯に見つめ、共作となる《つぶてソング》を発信源にこれからの福島、日本の展望を描き出す。全7回。(2014年7月4日、鎌倉芸術館にて。構成:zoSoh)

PROFILE
新実徳英
作曲家
東京大学工学部卒、東京藝術大学作曲科卒、同大学院修了。作品にオペラ《白鳥》、管弦楽曲《風神・雷神》ほか多数あり、国内外で演奏されている。 《協奏的交響曲~エラン・ヴィタール~》で尾高賞。ほかに中島健蔵音楽賞、文化庁芸術祭大賞などを受賞。谷川雁との共作《白いうた 青いうた》(全53曲)、東日本大震災後、和合亮一の『詩の礫』に作曲した《つぶてソング》(全12曲)は幅広く歌われている。 桐朋学園大学院大学特別招聘教授、東京音楽大学客員教授。 (撮影:近藤篤)

PROFILE
和合亮一
詩人
1968年8月18日生まれ。 中原中也賞、晩翠賞などを受賞。東日本大震災の直後からツイッター上で『詩の礫』を発表。詩集やエッセイ集、絵本の制作、作詞や講演・朗読活動など。新しい国語や音楽の教科書・準教科書などに、震災以降の作品が掲載される予定。吉永小百合さんの新朗読CD「第二楽章」に作品がおさめられたことで話題に。NHK復興サポーター。福島県教育復興大使。フランス「ZOOM JAPON」誌にて震災後に期待する日本人のひとりに選出。
現在進行形の《つぶてソング》
新実(N) 最近《つぶてソング》がどこでどのように歌われているのか、自分がやっているところを除けば、あまり知らないんです。
和合(W) そうなんですか? 私のところには全国、いろいろな演奏会の招待状をたくさんいただきます。感謝いたしております。
N あらら、なんでウチに来ないんだろう(笑)。ともあれ、この歌集の「寄り添う気持ち」というのに共感して、それを表明できるということで、皆さん歌われるのでしょう。どういった演奏会で歌われているのですか?
W 多種多様ですね。コンサート・ホールでのものもあれば、学校で歌っているだとか。今度私の赴任先の学校でも歌って下さる予定です。福島では、合唱の好きな方々が《つぶてソング》の中の1曲を、演奏会や発表会の中で取り上げるということもあるようです。YouTubeで「つぶてソング」と検索するとかなりの数の動画があって、それだけ歌ってくれる方々が多いというわけですよね。この夏休みにも「演奏しました」というお便りを何枚もいただきましたし、今もなお多くの方が歌ってくれているということを、実際に肌で感じています。あと、実は私、学校ではバレー・ボール部の副顧問をやっているのですが(笑)、その練習試合でお会いした相手の中学校の方が「自分の学校でも歌っている」と教えてくれました。
《つぶてソング》自体がもう一人歩きをしているというか、皆が共有しているという印象で……、新実先生には本当に感謝しています。
N 教育出版さんが作っている高校2年生の音楽の教科書に、《つぶてソング》の中の1曲〈あなたはどこに〉を掲載してくれたんです。そういうことも、この歌が広がっていく機会になればいいですね。
W 私は特に、いわゆる「言葉に関わっている」ひと以外の方々の反応が返ってくるということが実に新鮮で、自分が何か教わっているような感じがするんです。歌を歌う方々の、作品や言葉への向き合い方というのは、文学の人間のそれと全然違います。あるいは、演劇をやっているひとのそれとも違う。そうした言葉との「未知の距離感」を新たに教えていただいているんですね。
N 言葉は言葉、音は音でそれぞれあるわけだけど、言葉と音が一体化して、つまり「歌」になったときに、1+1=2ではない、何か別なものになるんです。それが大きなポイントですよね。以前和合さんとお話させていただいたとき、「(旋律が付くと)言葉に翼が生えて飛んでいくみたいな気分ですね」と仰いましたが、なるほどと思いました。
W 色々な方の《つぶてソング》を聴いていると、自分が届けたいと思ったものが様々に変容してくるし、あるいは新実先生が数多くの『詩の礫』の詩からこれを選ばれたのはどういうことなのか、ということをじっくりと考えさせていただく時間ができますね。
N 例えば〈あなたはどこに〉の「あなたはどこに居ますか。」という言葉はひとつの詩から選んだんだけど、中間部に出てくる「命を賭けるということ。」というのは全く別な詩の言葉であったりして……、『詩の礫』の中の詩を自由に組合わさせてもらいました。これらはTwitter上で綴られたために短いこともあって、柔軟に組み合わせることが可能で、なおかつその方が面白いと思ったわけです。あと和合さんにも了解をいただけましたので。
W ある時、新実先生から歌詞の状態になったものを読ませていただいたのですが、流れがまったく自然で、どこをどのように先生が「編集」したのか、自分でも分からないくらいだったんですよ(笑)。《つぶてソング》の以前にも、私の現代詩に曲をつけていただいてます(《宇宙になる 三つの愛のかたち》[混声合唱とピアノのための作品/2010年])。初めてお会いしてからもう7、8年になりました。
N あの曲はたしか『地球頭脳詩篇』[思潮社/2005年]の中の詩でしたね。
W その通りです。《宇宙になる》の初演を大阪のシンフォニー・ホールに聴きにいきました。自分の作品が合唱曲になってそれを実際に聴いた初めての体験だったんですが、ナマの合唱の肉感と言いますか、底力と言いますか、すごく巨大なエネルギーを感じて、心臓が痛くなってしまうような気がするほどでした。
[続く]
創作、「闇」の世界
和合(W) 新実先生が書かれた《風神・雷神》[和太鼓とオルガンとオーケストラのための作品/1997年]のCDを以前から聴かせていただいていまして、今回お会いするのに際して聴きなおしてみました。ちょうど梅雨時の福島の風景を見ながらだったこともあってか、自然の深淵さ、それへの畏怖を強く感じました。ちょっと分かりやすい例えで言うと、私の大好きな宮崎駿の映画『もののけ姫』の最後の場面で荒ぶるシシ神のような。あるいは、これはいま特に強く感じるのですが、幼少の頃、外で友達と遊んだ帰り道に降られた雨や、燃え上がるような夕焼け、捕まえてあやまって死なせてしまった昆虫や魚、そういったかつて自分が体感していた福島の自然、畏怖のような郷愁のような……、そうしたものをこの曲の旋律に感じたんですね。
私は萩原朔太郎[詩人/1886〜1942]の『月に吠える』[1917]と『青猫』[1923]という詩集が大好きで、大学の卒業論文もこれがテーマだったんです。その中で彼は「ふるえる」世界を書いている。竹の葉がふるえる、何かの線がふるえる、心がふるえる――その「ふるえる」という言葉がたくさん使われています。それにはどこか、身近な自然への生理的な恐怖心が根っこにあって、そこから突き動かされる新鮮なイメージが不可分に結びついていると思うんですね。それと同じような印象を、新実先生の作品にも持たせていただいたんです。
新実(N) 朔太郎は不思議な感覚の持ち主ですよね。いやあ、比較してもらっちゃって光栄です(笑)。
仰った「自然への畏怖」ということについては、一つ、この曲に使われる和太鼓が大きな役割・意味を持っているのではないかなと思います。太鼓のひと打ちが何か神々しい、自然への畏敬の念のようなものを想起させる力を働かせるのかもしれないですね。あと、もう一つ大きい役割を担っているのはオルガンでしょう。まさしく大地の霊が湧き上がるような、地底から声が響いてくるような、なにか迫ってくるものがあると思います。でも、それは僕の力では決してなくて、楽器そのものの持っている生命力が、僕の曲の中でその在り処を求めて動き回った結果なのでしょう。
W 例えば、その他の文学作品では、高校生が必ず読む中島敦[小説家/1909〜1942]の『山月記』[1942]や芥川龍之介[小説家/1892〜1927]の『羅生門』[1915]などに朔太郎の作品との共通性を見出すことができるのですが、それは「闇の世界」だと思うんです。「闇の世界」とは決して薄気味悪くて暗いという印象ばかりではない。どちらの作品でも、主人公に「闇」の中で転機が訪れます。この「闇」への眼差しと言うのは、可視を見る、可聴を聞くのではなく、不可視を探し、不可聴のなかで見えざるもの、聞こえざるものを探り当てるという意味合いが強いと思うんです。そこにこそ、なにか本質的なものがあるという。新実先生の作品には、積極的にこうした「闇」を招くようなエネルギーを感じました。そこでは音が等速で進んでいくのではない、独特の滞空時間があって、時には逆戻りしたりする自由さがあるような気がします。
N フラフラしてますからねえ(笑)。
先ほど「闇」という言葉が出てきましたが、私は作曲する段階で「全ての音をいったん音の闇に返す」、周りから音を消してしまうことを意識しています。その音のしじまから何が聴こえてくるだろうと耳を澄ます、という姿勢でいるわけです。《風神・雷神》はそうした過程で生まれたのかな。でも一方で、同時に明るい大自然から何かを受け取りたいところもある。黎明の森や山、夜の星空から何かが降ってくるような感じ。
「音の闇」とはとても思念的なもの、抽象的な観念だけど、全ての音を闇に預けると一度浄められるような感じがしますね。宮沢賢治[詩人・童話作家/1896〜1933]の短編『狼森と笊森、盗森』[1924]にも似たようなエピソードがありましたが、ある種の浄め、そこから何を捉えることができるか、ということ。作曲、イメージのはじまりはこういうことなのかと、しきりに思ったこともあります。現代はなにしろ周りに音が溢れていますから、こうしたことを念頭におくのはとても大事なことなんだと思います。
W 御自身のエッセイ『風を聴く 音を聴く ――作曲家がめぐる音宇宙』[音楽之友社/2002]というタイトルにも、そうした思いが込められているのでしょうか?
N そうですね。
[続く]
閃き――音/言葉が「降ってくる」とき
和合(W) 私の場合、毎日必ずやっていることは、朝起きて、そこで最初に浮かんだ言葉をそのまま書き留めるということです。一番最初に自分の頭に「降ってくる」言葉ですね。谷川俊太郎[詩人/1931〜 ]さんは、自分には無意識しかなく、無意識のうちに浮かんできた言葉を書く、それを待っているしかないんだ、というようなことを仰っています。
現代はあまりに音に溢れている、言葉に溢れている、つまり記号、情報に溢れている。そんな中で書きとめられた音、旋律というのを、先生はどうやって見つけることができたのでしょう? 例えば、どこか特定の場所、空間をテーマにした曲の場合、その場所に実際に行かないと見つからないのか、あるいは例えば新宿の人ごみの雑踏の中にいてもイメージが立ち上がるものなのか……。
新実(N) それは音も同じ、「降ってくる」のを待つものなのかもしれません。私も朝起きてぱっと浮かんだ音をメモしたりします。そうしたきっかけがないと、先が始まらない。ただ、面白いことに、その先をどうしようか色々考えて煮詰めていくと、何か生まれることもあるけど、生まれないことの方が多い。そこで、いったん距離を置いて放っておいて、頭の中を空っぽにする。すると、いきなり閃いたりするわけです。僕はそれを「空(くう)の器」と言っています。一度空っぽにしないと何も降ってこないんだと思うわけです。
W 以前、先生は合唱曲について「子供たちがすぐ覚えて歌えるようなものがよい」ということを仰っていて、私の詩に耳なじみの良い旋律をつけてくださいました。一方、現代曲を書かれるときは、現代詩の言葉で言うと「読み手を裏切る」ような、あえて聴き手がイメージしやすいものと違う方向に持っていくようなことを強く意識されているのでしょうか? また、その旋律というのは、先生のどこからやってくるものなのでしょうか? これはつまり、個人の生む音楽とは何なのかということに繋がっていくと思うのですが。
N 音楽の創作はやはり、人それぞれの体験が根幹にありますよね。一度体に入ったものが、どのようなかたちで体から出ていくのかということです。だけど、それを“意識的に自分の中から探す”よりも、やはりそれが「降ってくるの」を待つ、閃きを待たなくてはなりません。だから、それがないと曲は書けません。以前、谷川雁[詩人/1923〜1995]さんと《白いうた青いうた》[ピアノ伴奏による53曲の歌集/1989〜1995]を作った時は、《つぶてソング》とは逆で、詩が先にあるのではなく、曲が先行して作られました。
書こうとする、つまり企んでいる間は、神様は何もくれないんですよ。そこで先ほど言った「空の器」。無心でいると、神様がご褒美をくれるのか、どこかから音が湧いて出てくる、そんな感じなんです。特にメロディ・ライティング。ソングや合唱曲の旋律を書くときは、それが降ってこないと困っちゃうんですね。詩が先にある場合は前もってイメージをもらえるわけですが、先に旋律を書く場合は、逆にそちらがどんどんできてしまって、あとでどの詩が当てはまるだろうと考えなくてはならない作業になることもあります。他の作曲家の方もやはり音が「降ってくる」んだと思うんですが・・・・・・モーツァルトみたいに次から次に降ってくればいいんですがね(笑)。
W 「空の器」のお話で思い出したのですが、小室等[フォークシンガー/1943〜 ]さんはギターをとても練習する方で、一度イヤになるほど練習して、しばらく楽器から離れて、それでもう一回楽器を練習しなおして、ようやく人前にたてる、ということを対談させていただいた際に仰っていました。つまり、演奏家の方の場合は、一度できあがったものをクールダウンさせて、空っぽの状態でもう一度向き合ったときに新たなインスピレーションが「降ってくる」のかなと思ったのです。別な意味での閃きと言えるでしょうか。先生は一度降ってきた音について、それをそのまま「完成形」とされるのでしょうか?
N いえ、推敲を重ねますよ。ピアノで弾くと納得がいくけど、自分の声で歌ってみると納得いかない、ということがあります。声という肉体そのものの生理とうまく符号しない場合は、それを受け止めてあげないといけない。谷川さんと曲を作っていったときは、そうして作った音にこんな詩が乗るのかという驚きばかりで、とても勉強になりましたね。
[続く]
「霊性」の在り処
和合 私はそうした閃きというものが、何かこう生きている証そのもののように思えるんです。萩原朔太郎はそれをドストエフスキーから学んだのですが、そうした閃きを「霊性」なのだと言っています。モノを書く「霊性」というのは、私としては、それこそが生命の証、躍動感を伝えるための何かに有機的に繋がっていると思うんです。先生は「霊性」という言葉にどのようなことを感じられますか?
新実 かつて鈴木大拙[仏教学者/1870〜1966]が「日本的霊性」という言い方をしていましたね。
私は「自分は縄文神道です」と嘯くこともあるのですが、すべてに生命が宿っているという感覚は、自分自身に強くあることを自覚しています。年に2〜3ヶ月を蓼科に住むようになってからは、それが特に強くなりました。それまでは、音楽というものは自分で作らなくてはいけない、という観念が強かった。頑張らなくてはいけないという。でも違った。「もらうもの」なんだと思うようになりました。自分の周りにこれだけたくさんの生命がいて、それぞれに霊性があって、そういうところに住んでいるんだから、そちらから多くのことをもらうことができると思ったんです。霊性という言葉だけとると少しオドロオドロしいかもしれないですが、もっとシンプルな、みんな生きているんだというところから立ち上ってくるもの、そうした賑やかなものに「霊性」をイメージしますね。喜びが溢れて楽しい感じですよ。
和合さんの詩というのは、解説しろと言われても僕にはまるでできないのだけど(笑)、なにしろ言葉が踊っている。大自然の中であらゆる生物が躍動するように、言葉が踊っているんですね。初めて詩を読ませてもらったときは「これはとんでもない詩人がいるぞ」と思ってね、これをぜひとも音でつかまえたいなと。
[続く]
「3・11」以前と以後の変化
新実(N) 福島市の市制100周年の記念讃歌を作った際に、こうした曲の詩はみんなが歌っていて「いいな」と思える詩じゃなきゃいけないよと和合さんに言ったことがありましたが、《つぶてソング》にはこのことがどこか繋がっている気がするんですよ。震災以前の詩には、記念讃歌のようなやわらかい詩をあまり書かれなかったのではないですか?
和合(W) そうですね。どちらかというと文語体のものが多かったかもしれません。やわらかな言葉、例えば「雲のあしあと」という言葉に、新実先生が「こういうのがいいんだよ」と仰ってくださったのを今でも覚えていますね。それから多くの場面で皆さんがその曲を歌われているシーンに立ち会って、こうした言葉が「伝わる言葉」なんだなと強く認識するきっかけになったんです。実際にたくさんの子供たちが喜んで歌ってくれているわけで。
N その曲から3・11までの創作活動においては、現代詩を中心に執筆されていたんですか?
W はい。エッセイはずっと書いていましたが、つまりは現代詩の読者に向けて書いていたわけです。ただ、『詩の礫』以降の口語体の作品とそれまでの現代詩は、自分の中では変わらず存在し続けていたものなのですが、周囲の人からの反応を多くいただくようになりましたね。
N 僕の中でも合唱曲と現代曲が並存するそのスタンスのようなものは変わらないんだけど、3・11の時に取りかかっていた弦楽四重奏曲第2番‐Asura‐[2011]という曲は、ずっとテレビをつけっぱなしにしながら作曲作業を続けるというちょっと特殊な体験から生まれた曲で、次々に流される被災地の映像、被害状況や様々なコメント、原発に全然対応できていない、隠し事がたくさんあることへの驚き、恐怖、怒り、悲しみ、そうした感情が一気にこの曲を書き上げたんです。そうした人間の心の奥底にある辛いものとか暗いものを描かないといけない、ということは以前から思っていて、私の現代曲作品には通底しています。曲のスタイルも変わりませんし。3・11を契機とするならば、やはりよりわかりやすいところで《つぶてソング》のようなものが生まれたということでしょうか。
そういう意味でスタンスに変わりはないのですが、3・11以降、震災によるあれこれを意識せずに作品を作ることが難しくなったというか……、この曲を聴いた人の心が少しでも穏やかになればいいなとか、どこかそういうことを思うようになりました。そうしたことは無関係に、芸術至上主義的に美しいものを追い求めるのもよいと思うんですが、自分はそれができなくなってしまって、いつも「思う心」がどこかに入り込んでくる、それが一番大きな変化なんじゃないかな。
和合さんは『詩の礫』から『廃炉詩篇』[思潮社/2013年]を書かれるまで結構時間がかかったのではないですか?
W 3年たっていますね。それまでに『詩の邂逅』[朝日新聞出版/2011]『詩ノ黙礼』[新潮社/2011]の2冊、その翌年にまた2冊の詩集を出版したのですが、『廃炉詩篇』はずっとそれらと同時に取り組み続けていて、震災前の2年間と震災後の3年間、計5年かけて編んだ現代詩集です。最後に『誰もいない福島』を載せています。震災後の3年間で、ようやく現代詩を書く器が自分の中に形成されてきたと思うんです。現在は『孤独詩篇』というものに取りかかっています。孤独、孤独死をテーマに短い詩を集めて1冊にしたいと考えています。
[続く]
福島の現在――「風化」との闘い
和合(W) TwitterやFacebookに書く詩は、書けばすぐに読める人は読めるものなんですが、考えてみると毎日締め切りがあるような感じがして(笑)。最近やっと、すぐに詩をリリースするのと、自分の中で詩を寝かせるのと、二つのバランスをとることができてきました。自分の中でこれからよりはっきりしてくると思うのですが、「作品とは時間という比喩を込めること」だと最近自覚してきたんです。
新実(N) 目の前に葡萄を差し出して食べさせるのと、熟成してワインにして飲ませるのと、ちょっとそれに似てるような印象を覚えました。時間を込めることとは、自分のなかで熟成させることですよね。
W ええ、そうですね。あと、先ほど先生がご自身の作品のスタンスについて仰られたように、自分の作品のテーマはつねに「福島」なんです。福島の自然にある。一部の批評家の方には「売れようとしてやってる」みたいなことを言われましたけど(笑)、そうではなくて一貫したテーマなんですね。そこが偶然にも、史上最悪の原発事故の舞台となってしまい、今日まで様々な問題が一向に解決されない地域として存在しているわけです。現在も被災された方々にインタヴューして回っているのですが、震災直後のときとは変わった別の問題が顕著になってきたと思うんですね。それを象徴するのが「孤独死」です。
もう一度、いまものを作る人間として、その熟し方が「試される」時を迎えているのだと思います。熟し方が震災前と同じじゃないかと言われてしまうのか。自分としては、震災前と何が変わって何が変わらないのかもっと見極めたいんです。
新実先生の《つぶてソング》というのは、自分のそうした疑問を数え切れないくらい解決して導いてくれた存在の歌なのですが、その中で最も先生から教わったことは、「風化」との闘い方です。例えば、ある大臣の「最後は金目でしょ」という発言は象徴的で、福島の人をもう一度傷つけた言葉でした。ただ福島の中においても、当時のことを忘れたいという人と、忘れたくない、忘れられないという人の温度差がかなりあります。どちらかというと若い方々は新しいところに住んでそこを故郷とするんだと言うけれど、その親は以前いた場所に戻りたいという。そこで対立が生まれているんです。一方、仮設住宅には1ヶ月1度も家から外出しないというご老人たちがたくさんいらっしゃったりするんですよ。
福島の内側でも外側でも、こうした温度差はどんどん鮮明になっていくことでしょう。そんな中で、先生が作ってくださった《つぶてソング》は、震災直後の我々の気持ちを新鮮なまま作品の中に宿してくれて、それをいつも目の前に置いておくことが出来る。何度でもその作品の力を信じることができると思うんですね。
N 僕はとにかく風化させてはならない、エールを、寄り添う気持ちを送り続けたいということで動いたんです。最初はちょっと悩んだんですね。一作曲家としてこうした歌をつくるということはどういう意味があるのか、ということ。何かの役には立つかもしれないが。でも、どうしてもいたたまれなくて、やらずにはいられないという気持ちの方が勝っていきました。この《ソング》がマルかペケかなんてことは超えてしまって、もうやるっきゃないんだと思ってやったんです。
でも、正直なことを言えば、早くこの歌が笑い話になればいいなと思うんです。復興が進んで、そういえばこんな曲もあったねといって歌ってくれるような。いまのままだと、あと何十年かかるかわからないですが。では、どうやって風化する現実と闘っていくか。
若い人が「福島」を忘れたいと思うのは、よくわかります。しかし、同時にやはり忘れてはいけないと思うのが、あの大惨事です。それにしっかりと向き合っているものをちゃんと残していくのが、それを体験した大人としての責任なんじゃないかなと。どんな形でもいいからそれをやっていかなくてはいけないというのが僕の考えです。
[続く]
タブーを打破し、未来への舵をとる
新実(N) 実はいま、2016年が震災から5周年ということで、震災をテーマにした交響詩のようなものを作曲する予定なんです。仮のタイトルは《祈ル・祀ル・鎮メル》。第1章には《風神・雷神》を持ってきて、それに続く形で合唱とオーケストラの曲、さらにそこに岩手の伝統芸能「鬼剣舞」を盛り込んで、あわせて50分くらいの交響的作品を作ろうと思っています。《風神・雷神》はすでにある曲ですが、これは神様を呼ぶ音楽。その中で人が祈る、鎮める、舞う。復興を祈念する、未来への力をもらえるような作品にしたいと思うんです。
和合(W) 私が『廃炉詩篇』で震災前の作品を組み込んだのは、「その時点ですでに何かが起こりそうな兆しが見えるから」と周囲の人や編集者の方に言われたこともあったからなんです。この1冊の中で、震災前と震災後も変わらないものというのが描けたかもしれません。先生のその作品を聴いて《風神・雷神》に同じような「兆し」を聴き取る方もいらっしゃるかもしれませんね。
N なるほど。そうかもしれません。あと、やっぱり僕はこの新しい曲で「破壊」を描かなくてはいけない。
W よく分かります。私は震災直後、放射能と余震に不安を抱いて毎日過ごしていたなか、部屋でテレビを見ることしかできなかったときに、ベートーヴェンの《第9》を…、来日したズービン・メータの指揮による演奏を観て、涙が止まりませんでした。その後『詩ノ黙礼』にそのことも書かせてもらいましたが、津波の映像と《第9》の映像がシンクロして、「破壊と再生」が言葉を超えて迫ってきたんです。
いま現在、福島についてもっとも書かれ描かれていることは「復興」なんですけど、津波や地震といった「破壊」をもっと描いてよいと思うんです。それらが描かれることで、我々はより強くその惨事を受け止めることが出来るのではないかと思います。これは震災後、ずっと言い続けていることなんですが、受容しないでそのまま進んでいくのが、日本の慣習的な文化なのかもしれないなと。
N 無責任文化、といえるかもしれませんね。
W 日本には鎮魂の文化、レクイエムの文化が乏しすぎるんです。震災直後、《つぶてソング》の中の〈放射能が降っています 静かな静かな夜です〉を福島の方々は「あの歌はつらすぎて歌えない」と仰っていました。ただ一方で、現在でもあの詩について、「書いてくれてありがとう」といってくれる人がとても多いんですね。それと同じことが、先生が歌にしてくれたことで起こっていまして、現在あの歌は福島でもたくさんの方に歌われていますし、いまあの歌を「辛い」と感じる人は少なくなったと思うんです。もっと言えば、あの歌を歌うことではじめて、今の自分、今の福島をありのまま受け止めることができ、新しい扉を開くことできるのではないのでしょうか。タブーとされているものほど、不条理な現実に立ち向かえる力を持っていると思うんです。タブーを何かの形で、歌や言葉の力で打ち破ることで、はじめて明るさをもたらせる、未来を明るい方向に導くことができると思います。これは『詩の礫』を書いていてそう思いましたし、《つぶてソング》となってからは、新実先生の音楽にそうした力があるんだと思うようになったんです。
N いや、それは『詩の礫』にこそ、そういう力があったんだと思います。あの歌は本当にその情景が浮かんできますよね。目の前の辛いこと、苦しいことに対して、目を逸らすのではなくてすべてを見ること。天災と人災、そして、何が辛いのか、何が苦しいのか、その正体はこれなんだと突き詰める。そこを通らないと、次の明るい方向にきちんと向いて進んでいくことができないと思うんですよ。音楽でそれがどこまでできるのかまだわからないけれど、辛い部分を描かなくてはいけない。《第9》ではないけれど、歓喜に向かうためには、やはり苦悩と向き合わなくては。
W 福島の小学生が書いた作文で「この震災の問題は自分が大人になっても、自分の子供の代になっても、孫の代になっても、解決できないかもしれない。だったらそれを孫の代にまで伝えていかなくてはいけない。そのために自分は勉強をしたい」という内容のものがありました。この《つぶてソング》は、そうして次代にも引き継いでいける「震災の記憶」になったと思います。だから、ぜひ子供たちに歌い続けて欲しいですね。そうした力を、この歌は大きく宿していると思います。
[了]