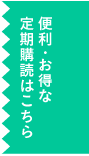「今世紀最大の発見!?」──今年9月、モーツァルトの作品の自筆譜がハンガリーの図書館で発見されたというニュースが全世界を駆けめぐりました。大作曲家の自筆譜が見つかることじたいはそれほど珍しいことではありませんが、今回は発見されたのが《トルコ行進曲付き》の通称で知られるモーツァルトのもっとも有名なソナタといっていい作品だったため、一般の音楽ファンを巻きこんで大きな話題となっています。
10月初旬におこなわれた「国際モーツァルト会議」での発見者バラージュ・ミクシ氏による報告を、ベルリン在住の音楽学者・畑野小百合さんが要約してくれました。

畑野小百合
国立音楽大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了。東京藝術大学大学院音楽研究科音楽文化学(音楽学)専攻博士後期課程を経て、ベルリン芸術大学大学院博士課程在学中。ドイツ学術交流会(DAAD)奨学生(2009年、2012~2013年)、公益財団法人ローム ミュージック ファンデーション奨学生(2014年)。訳書にJ. オッテン『ファジル・サイ─―ピアニスト・作曲家・世界市民』(アルテスパブリッシング)。
発見者による国際モーツァルト会議での報告(要約)
2014年10月、ザルツァッハ川が翡翠色を深める秋のザルツブルクで、「国際モーツァルト会議(Internationaler Mozart-Kongress)」が開催された。
ザルツブルク・モーツァルテウム財団のモーツァルト研究アカデミーが主催するこの大会は、近年は隔年のペースで開催されている。今年は、10月2日から5日までの4日間に、23の研究発表と1つのレクチャー・コンサート、そして、すべての発表を締めくくるラウンド・テーブルが一般公開された。会場となったモーツァルテウムのウィーン・ホールには、欧州本土のみならず、アメリカやイギリスからも錚々たるモーツァルト研究者たちが集結し、ただでさえ眩い会場の内装が、それ自身の内に熱を宿し、光を放っているようにも思われた。
しかし、あれほどの華やいだ雰囲気が、毎度この大会の開催を祝しているわけでもないだろう。直前に発表されたブダペストでのモーツァルトの自筆譜発見のニュースは、この作曲家に対する愛と情熱に駆られて音楽祭期間外にこの田舎町を訪ねてきた変わり者の音楽関係者すべてにとっての吉報であった。さらに、約1週間前のブダペストでのプレゼンテーションに続き、この会議の最終日に自筆譜のお披露目とそれにかんする発表がなされるとあっては、変わり者たちの心は浮き立たずにはいられないのだった。
以下は、この新史料にかんするバラージュ・ミクシ氏(ハンガリーの国立セーチェーニ図書館音楽部門主任)による発表を要約したものである。内容は、2014年10月5日に「国際モーツァルト会議」内でミクシ氏が行った約30分間(質疑応答を含む)の英語の口頭発表にもとづいているが、本稿は第三者による速報的な報告にすぎず、ミクシ氏が挙げた例をすべて扱っているわけでもない。ミクシ氏の発表内容の典拠として用いられるべきは、『モーツァルト年鑑(Mozart-Jahrbuch)』、もしくは別の媒体に掲載されるであろう発表者自身の文章であることは、念のため強調しておきたい。なお、畑野による若干の補足情報は、〔 〕(亀甲括弧)内に記した。
*
1.資料状況
今回発見されたのは、モーツァルトのピアノ・ソナタK.331の自筆譜の一部。「トルコ行進曲」という通称でお馴染みの楽章を含む、演奏機会の多いイ長調のソナタである〔成立年代は、ヴォルフガング・プラートの筆跡研究によって1780年夏以降、アラン・タイソンの紙と漉かしの研究によって1783年と推定されている〕。これまでこの作品については、第3楽章、いわゆる〈トルコ行進曲〉の第90小節以降の終結部分を記した1葉の自筆譜〔1992年よりモーツァルテウム財団モーツァルト図書館所蔵〕しか知られておらず、20世紀のモーツァルト研究の集大成である『新モーツァルト全集(Neue Mozart-Ausgabe)』(以下、『新全集』)をはじめとして、楽譜校訂にあたっては、1784年にウィーンのアルタリア社から出版された初版が基本資料として用いられてきた。しかし、このアルタリア版のテクストには疑問がとなえられる箇所も多く、モーツァルト作品にみられる音楽語法や同時代の様式にかんする研究、音楽理論的見地からの推測、初期の他の出版譜や筆写譜の参照など、互いに異なる方針に依拠する校訂者によって、相違するエディションが数多く生み出されてきた。このような経緯から、今回ブダペストの国立セーチェーニ図書館で発見され、鑑定の結果モーツァルトの自筆と認められた手稿譜は、きわめて重要性の高い史料として注目に値するのである。
今回発見された自筆譜は2葉4ページからなり、一枚の紙の左右の角を合わせるように折って2葉とした横長の「バイフォリオ」である。ページの構成は、次に示すとおり:
第1葉recto(表):【第1楽章】第3変奏第1小節~第4変奏第14小節
第1葉verso(裏):第4変奏第15小節~第5変奏第16小節
第2葉recto:第5変奏第17小節~第1楽章最終小節(ページ下部にて複縦線で終結)
第2葉verso:【第2楽章】メヌエット全体およびトリオの第10小節まで
このバイフォリオと以前から確認されていた1葉の自筆譜には共通する点が多く、紙の漉かし模様も一致することから、かつては同じ手稿譜の部分であったものと考えられる〔以前から確認されていた1葉の自筆譜は、タイソンによる漉かしの目録で第67番に分類されており、新たに発見されたバイフォリオにも同じ漉かし模様が確認されたとのこと〕。また、推測の域を出ないものの、がんらいはもう1枚のバイフォリオがこのバイフォリオを外側から覆うように重ねられ、その第1葉には第1楽章の第2変奏までが、第2葉には第2楽章のトリオの第11小節以降と第3楽章の途中までが書かれていたと想像できる。そして、2枚のバイフォリオで曲の終わりに到達しなかったモーツァルトが追加で用いた1葉が、これまで知られていた自筆譜ではないだろうか〔なお、発表会場の後方には、今回発見された自筆譜と、以前から知られていた1葉の自筆譜、さらに初版のアルタリア版がガラスケースに入れられて展示されていた〕。
2. 自筆譜発見にいたる経緯
モーツァルトの自筆譜は、国立セーチェーニ図書館所蔵の手稿資料を整理する過程で発見された。このバイフォリオが含まれていたフォルダーは、RISM〔国際音楽資料総目録〕の目録作成に従事していたロバート・ムラニが1970年代から1990年代中頃までこの図書館内で使用していたものである。ムラニの退職後、彼のポストは廃止され、彼が用いていた資料は放置されたままになっていた。
この自筆譜がどのような経緯で国立セーチェーニ図書館にいたったのかは判明しておらず、図書館の記録の状況からして、今後明らかになる見込みもない。第3楽章終結部の1葉の自筆譜がかつて作曲家自身の遺品に含まれていたことは周知の事実だが、アンドレの自筆譜目録からは、今回ブダペストで発見されたバイフォリオも、行方はわからないがかつて組になっていたと想像されるもう1枚のバイフォリオも、当時すでに別の者の手に渡っていたものと推測される〔1799年、オッフェンバッハで楽譜出版業を営んでいたヨハン・アントン・アンドレ(1775-1842)は、モーツァルトの未亡人コンスタンツェから、遺品となった273を超える自筆譜を買い取った。これらの自筆譜は、アンドレの生前はほぼ完全な状態で保管され、1841年にはアンドレ所有のモーツァルトの自筆譜目録が作成された〕。ハンガリーの貴族との親しい交流が来歴に関係している可能性もあるが、この自筆譜がどのようにしてセーチェーニ図書館に行きついたのか、はっきりとしたことはなにも言えない。
発見された自筆譜をよく見ると、このバイフォリオがかつて他の紙の束をあいだに挟み、それと結合されていたと思わせる形跡がある。以前この自筆譜を所有していた人物は、自分が何を手にしているのか、おそらく認識していなかったのであろう。
3.自筆譜から見えてくるもの
自筆譜の内容に話を進めるまえに、必ずしも自筆譜が初版のテクストより大きな重要性をもっているわけではないということを指摘しておきたい。自筆譜には詳細に書き込まれなかった強弱記号が、初版の出版準備の過程で作曲家自身によって付け加えられるということも確実にあったのだから。
3-1.第1楽章第5変奏第5、6小節たしかに、初版のアルタリア版には明らかな誤植もある。第1楽章の第5変奏、第5、6小節の右手のパッセージを見てみよう。それぞれの小節の6拍目は、今回発見された自筆譜においては、2つの64分音符と1つの32分音符、そして1つの16分休符からなり、勢いよく駆け上がるような動きを示している。ところが初版の同じ箇所には、2つの32音符と1つの16分音符、そして1つの16分休符が並び、小節全体の拍数の整合性がとれていない〔譜例1〕。
[caption id="attachment_2483" align="alignnone" width="640"] 譜例1 第1楽章第5変奏第4~6小節(初版=アルタリア版)[/caption]
この不合理を修正しようとしたのちの多くのエディションでは、この拍を3つの32分音符と1つの32分休符で構成する穏やかなヴァージョンが採用され、『新全集』もこれを踏襲している〔譜例2〕。
[caption id="attachment_2484" align="alignnone" width="640"]
譜例1 第1楽章第5変奏第4~6小節(初版=アルタリア版)[/caption]
この不合理を修正しようとしたのちの多くのエディションでは、この拍を3つの32分音符と1つの32分休符で構成する穏やかなヴァージョンが採用され、『新全集』もこれを踏襲している〔譜例2〕。
[caption id="attachment_2484" align="alignnone" width="640"] 譜例2 第1楽章第5変奏第5、6小節(『新モーツァルト全集』=NMA)[/caption]
初版の誤りに端を発して、この箇所がモーツァルトの本来の意図とは異なるかたちで伝承されてきてしまったことが、今回の自筆譜の発見で明らかになった。
譜例2 第1楽章第5変奏第5、6小節(『新モーツァルト全集』=NMA)[/caption]
初版の誤りに端を発して、この箇所がモーツァルトの本来の意図とは異なるかたちで伝承されてきてしまったことが、今回の自筆譜の発見で明らかになった。
以上は、自筆譜が新たな洞察をあたえてくれる良い例であったが、心得ておくべきは、アルタリア版におけるこの種の誤りはかなり稀だということだ。新たな史料との比較によって、これまでしばしばテクストの正誤が疑われていたこの初版が、かなり忠実に自筆譜を再現していることが確認された。
3-2.第1楽章第5変奏第16小節次に、第1楽章第5変奏の第16小節を見てみよう。初版では、小節後半の上声部が「ニ―嬰ロ―嬰ハ」音になっているが〔譜例3〕、平行8度が生じることから、『新全集』をはじめとする後の多くのエディションはこれを誤りととらえ、第1、2、4変奏の対応する箇所にならって「ロ―嬰ロ―嬰ハ」音を採用してきた〔譜例4〕。
[caption id="attachment_2485" align="alignnone" width="300"] 譜例3 第1楽章第5変奏第16小節(初版)[/caption]
[caption id="attachment_2486" align="alignnone" width="300"]
譜例3 第1楽章第5変奏第16小節(初版)[/caption]
[caption id="attachment_2486" align="alignnone" width="300"] 譜例4 第1楽章第5変奏第16小節(NMA)[/caption]
譜例4 第1楽章第5変奏第16小節(NMA)[/caption]
しかし自筆譜には、「ニ―嬰ロ―嬰ハ」音がはっきりと書き込まれている。おそらくモーツァルトは、「嬰ロ」音がじゅうぶんな存在感をもって平行8度をさえぎると考えたのだろう。ここでアルタリア版の製版者が過ちをおかしていることも、あわせて考慮するとよいかもしれない。というのも、アルタリア版は「ニ―嬰ロ」の音型に付点8分音符と16分音符をあてているが〔譜例3〕、モーツァルトはこの部分を複付点8分音符と32分音符で記しているのである。これは、初版のヴァージョンにくらべて、よりスパイスの効いた演奏効果をあたえるものだ。
3-3.第2楽章第3小節次は、第2楽章メヌエットの冒頭のテーマに注目してみよう。初版では、テーマの最高音として第3小節の3拍目に「2点イ」音が置かれているのに対し、メヌエットの後半でテーマが再帰するとこれが「3点嬰ハ」音となり(第33小節)、矛盾を見せていた〔譜例5〕。
[caption id="attachment_2487" align="alignnone" width="640"] 譜例5 第2楽章第1~4小節、および第31~34小節(初版)[/caption]
そして、『新全集』を含むのちのエディションは、このテーマの最高音を「3点嬰ハ」に統一し、オクターヴ跳躍を含む旋律を採用してきた〔譜例6〕。
[caption id="attachment_2488" align="alignnone" width="500"]
譜例5 第2楽章第1~4小節、および第31~34小節(初版)[/caption]
そして、『新全集』を含むのちのエディションは、このテーマの最高音を「3点嬰ハ」に統一し、オクターヴ跳躍を含む旋律を採用してきた〔譜例6〕。
[caption id="attachment_2488" align="alignnone" width="500"] 譜例6 第2楽章第1~5小節(NMA)[/caption]
譜例6 第2楽章第1~5小節(NMA)[/caption]
初版の矛盾は自筆譜の矛盾に由来するものと思われたが、じつはそうではなかった。モーツァルトは第3小節の3拍目に「2点イ」音を書き込み、メヌエット後半でテーマが再帰する箇所では楽章冒頭の7小節をそのまま演奏するように指示し、記譜を省略している。すなわち、この自筆譜に従うならば、メヌエットの前半でも後半でも「2点イ」音を最高音とするテーマが演奏されることになる。初版第33小節の「3点嬰ハ」音は、モーツァルトが右手パートをソプラノ譜表で記していることを失念した製版者が、加線2本の4分音符をそのまま写してしまった過失によるのではないか〔ソプラノ譜表で「2点イ」音を示す音符が、ト音記号を用いた高音部譜表では「3点ハ」音となるため。なお、発表に続く質疑応答では、この点についてフロアのロバート・レヴィン氏からの指摘があった。レヴィン氏によれば、モーツァルトの自筆譜には、五線の上の加線の本数が不足していることが多く(また、五線譜の下では加線の本数が過剰なことが多く)、この場合も作曲家自身の誤記の可能性があるとのこと〕。
3-4.第2楽章第24~26小節第2楽章メヌエットの第24小節から第26小節は、テクストの正誤が問われてきた箇所として有名だ。繰り返し記号の後、まずロ短調が現れ〔第19~22小節〕、第23小節でイ短調が示唆される。初版は、続く3小節〔第24~26小節〕をイ長調で記しているが〔譜例7〕、のちの多くのエディションがこれを誤りととらえ、この箇所をイ短調とする解釈を示してきた〔譜例8〕。
[caption id="attachment_2489" align="alignnone" width="640"] 譜例7 第2楽章第21~30小節(初版)[/caption]
[caption id="attachment_2490" align="alignnone" width="500"]
譜例7 第2楽章第21~30小節(初版)[/caption]
[caption id="attachment_2490" align="alignnone" width="500"] 譜例8 第2楽章第19~30小節(NMA)[/caption]
譜例8 第2楽章第19~30小節(NMA)[/caption]
今回の発見では、自筆譜でも第24小節から第26小節がイ長調で記されていることが明らかになり、初版のテクストの信憑性が高まってきた。さらに、イ長調への進行をモーツァルトがほんとうに意図していたという決定的な証拠が、自筆譜に見出されると思う。イ長調の調号をもつ譜面では、第26小節右手の1拍目に現れるシャープ記号が無意味なように思われ、それが初版のテクストに寄せられる不信の一因ともなっていた〔譜例7〕。しかし自筆譜を見てみると、このシャープ記号が狭い隙間に後から書き入れたような筆跡で記されていることがわかる。おそらくモーツァルトは、イ短調に転調した第27小節を書いたのちに、ここまでの部分がイ長調であったということを明確に示すために、第26小節のシャープ記号を遡及的に書き加えたのではないか。初版において無意味に思えた記号が、自筆譜ではきわめて有意味なものとして理解されるのである。
4.結語
自筆譜はこれまで知られていなかった重要な情報を豊富にあたえてくれるが、このソナタの演奏にかかわるすべての問題を解決してくれるわけでもない。研究者と演奏家がともにコンセンサスを求め、論議していく必要があるだろう。
このような貴重な発見を経験できたことは、たいへんに喜ばしいことだと思っている。しかし、この史料はわれわれの共有財産である。今後は、この4ページの自筆譜をファクシミリとして出版し、またウェブ上でも公開する意向だ。
〔以上、発見者バラージュ・ミクシ氏による報告を同氏の許可を得て要約。『新全集』の楽譜はベーレンライター社の許諾を得て掲載した(Abdruck mit Genehmigung des Bärenreiter-Verlages)〕