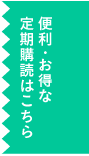アイルランドの打楽器バウロンのプレイヤー、トシバウロンさんによる世界のケルト音楽探訪記。〈アトランティック・カナダ編〉に続く第2弾は南半球に飛んで、オーストラリア編をお送りします。オーストラリアにケルト音楽? と怪訝に思う方も多そうですが、じつは日本と状況が似ている面もあるのです。3回に分けてお届けする現地からのレポート、どうぞご期待ください。
[連載記事一覧]
世界のケルト音楽を訪ねて〈アトランティック・カナダ編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈オーストラリア編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈スコットランド編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈ウェールズ編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈マン島編〉
世界のケルト音楽を訪ねてボーナストラック〈オーストラリア・バスキング事情 メルボルン編〉

PROFILE
トシバウロン
1978年、東京生まれ。日本では数少ないバウロン専門のプレーヤー。他の楽器と波長を合わせグルーヴを作り出すことに長けているが、首が曲がりメガネが弾け飛ぶほどダイナミックな動きには賛否両論がある。2000年冬アイルランド留学中にアイリッシュ音楽を始めパブセッションで研鑽を積む。現在東京にてJohn John Festivalを軸に多様な活動を展開中。2012年スペイン国際ケルト音楽フェスでHarmonica Creamsとして日本人初の優勝を果たす。葉加瀬太郎、鬼束ちひろのレコーディングにも参加。アイリッシュ・ミュージック専門イベント企画やCD販売レーベル「TOKYO IRISH COMPANY」を主宰している。http://www.t-bodhran.com/
第1回 移民の国のケルト音楽事情
 オーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンに着いたのは年の瀬も迫った2014年の12月25日。まさにクリスマス当日だったため、商店はすべて閉まっていて、街は閑散としていました。クリスマス自体は日本でも定着したとはいえ、みなが働くのをやめてしまうことはありえないので、やはり文化の違いを感じます。
日本と逆で、オーストラリアの季節は夏。ブリスベンでは日中は30度を越す暑さです。毎年この季節に訪れるようになって3回目ですが、今年は初めて調査のためにやってきました。
オーストラリアのケルト音楽、といってもピンと来ない人もおおいかもしれません。前回のカナダ調査時にも「オーストラリアでもアイリッシュ・ミュージックやスコティッシュ・ミュージックを演奏しているんですね」と驚かれます。実際オーストラリアではフォーク音楽シーンの人気があり、ケルト音楽はその一部として人々に親しまれています。
私は過去2回オーストラリアに滞在し、ミュージシャンと交流しセッションを楽しむなかで、ケルト音楽としては本場ではない日本と若干状況が似ているのではないか、と考えるようにもなりました。そこで関係者にインタビューをしたり、フェスやサマースクールを取材して、オーストラリアの事情を少し明らかにしてみたいと思ったのです。
オーストラリアのケルト音楽
オーストラリアへの入植は18世紀後半に始まりました。スコットランド人のジェームズ・クック James Cookが領有を宣言した後、イギリス本国から開拓のために多くの人々が送り込まれましたが、彼らは主に貧困層、政治犯といった人々で、アイリッシュ系やスコティッシュ系が多かったようです。2010年の国勢調査では全人口の74%がイギリスかアイルランドに先祖をもつというデータが出ています。そのため、彼の地でケルト音楽が盛んであるのは一見ごく自然な流れのように見えます。オーストラリアで最も人気のある歌〈ワルチング・マチルダ Waltzing Matilda〉のように、ケルト音楽の影響をうけたオーストラリアのフォーク・ソングは数多く存在します。それらはブッシュ・バラッド Bush Ballads、 ブッシュ・ミュージック Bush Musicとも呼ばれます。
♪Waltzing Matilda playing by the Bushwackers
http://youtu.be/dtgInNEuhbI
Bush Music(Wikipedia)
しかし、例えばカナダのケープ・ブレトン島のように、入植当時から移民の伝統音楽をずっと引き継いできた場所とは違い、オーストラリアには独自の事情があるようです。そのあたりを念頭に置きながら、まずはオーストラリア最大のフォーク・フェスティバルに向かいました。
ウッドフォード・フォーク・フェスティヴァル
オーストラリアでも最大級の音楽祭“ウッドフォード・フォーク・フェスティヴァル Woodford Folk Festival”にやってきたのは12月27日。会場は Woodfordiaという名のキャンプサイトで、ブリスベンから北西に1時間半ほど、電車とバスを乗り継いでたどりつきます。
年をまたいで6日間開催されるこのフェスは、毎年1回開催される国内最大級の音楽祭で、今年が29回目。フォーク・ミュージック以外にも様々なジャンルの音楽やパフォーマンスを観ることができます。延べ12万人もの人々がフェスを堪能し、481ものグループ、2500人にも及ぶアーティストが広大な敷地内で常時パフォーマンスを繰り広げています。国内外から様々なバンドが招聘されており、今年は日本からも Dachamboや Ichiが参加していました。
オーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンに着いたのは年の瀬も迫った2014年の12月25日。まさにクリスマス当日だったため、商店はすべて閉まっていて、街は閑散としていました。クリスマス自体は日本でも定着したとはいえ、みなが働くのをやめてしまうことはありえないので、やはり文化の違いを感じます。
日本と逆で、オーストラリアの季節は夏。ブリスベンでは日中は30度を越す暑さです。毎年この季節に訪れるようになって3回目ですが、今年は初めて調査のためにやってきました。
オーストラリアのケルト音楽、といってもピンと来ない人もおおいかもしれません。前回のカナダ調査時にも「オーストラリアでもアイリッシュ・ミュージックやスコティッシュ・ミュージックを演奏しているんですね」と驚かれます。実際オーストラリアではフォーク音楽シーンの人気があり、ケルト音楽はその一部として人々に親しまれています。
私は過去2回オーストラリアに滞在し、ミュージシャンと交流しセッションを楽しむなかで、ケルト音楽としては本場ではない日本と若干状況が似ているのではないか、と考えるようにもなりました。そこで関係者にインタビューをしたり、フェスやサマースクールを取材して、オーストラリアの事情を少し明らかにしてみたいと思ったのです。
オーストラリアのケルト音楽
オーストラリアへの入植は18世紀後半に始まりました。スコットランド人のジェームズ・クック James Cookが領有を宣言した後、イギリス本国から開拓のために多くの人々が送り込まれましたが、彼らは主に貧困層、政治犯といった人々で、アイリッシュ系やスコティッシュ系が多かったようです。2010年の国勢調査では全人口の74%がイギリスかアイルランドに先祖をもつというデータが出ています。そのため、彼の地でケルト音楽が盛んであるのは一見ごく自然な流れのように見えます。オーストラリアで最も人気のある歌〈ワルチング・マチルダ Waltzing Matilda〉のように、ケルト音楽の影響をうけたオーストラリアのフォーク・ソングは数多く存在します。それらはブッシュ・バラッド Bush Ballads、 ブッシュ・ミュージック Bush Musicとも呼ばれます。
♪Waltzing Matilda playing by the Bushwackers
http://youtu.be/dtgInNEuhbI
Bush Music(Wikipedia)
しかし、例えばカナダのケープ・ブレトン島のように、入植当時から移民の伝統音楽をずっと引き継いできた場所とは違い、オーストラリアには独自の事情があるようです。そのあたりを念頭に置きながら、まずはオーストラリア最大のフォーク・フェスティバルに向かいました。
ウッドフォード・フォーク・フェスティヴァル
オーストラリアでも最大級の音楽祭“ウッドフォード・フォーク・フェスティヴァル Woodford Folk Festival”にやってきたのは12月27日。会場は Woodfordiaという名のキャンプサイトで、ブリスベンから北西に1時間半ほど、電車とバスを乗り継いでたどりつきます。
年をまたいで6日間開催されるこのフェスは、毎年1回開催される国内最大級の音楽祭で、今年が29回目。フォーク・ミュージック以外にも様々なジャンルの音楽やパフォーマンスを観ることができます。延べ12万人もの人々がフェスを堪能し、481ものグループ、2500人にも及ぶアーティストが広大な敷地内で常時パフォーマンスを繰り広げています。国内外から様々なバンドが招聘されており、今年は日本からも Dachamboや Ichiが参加していました。



 今回のフェス出演者の目玉の一つは、スコットランドのバンド、ラウー Lau です。日本での公演も数度に渡り、世界のケルト音楽界でも最も注目されているバンドのひとつです。このフェスへの出演は初めてで、プログラムガイドの冒頭に取り上げられていました。
ラウーの他にもケルティック・ミュージック・バンドが複数ブッキングされていました。前回のカナダ調査時に出会ったプリンス・エドワード島のバンド、イースト・ポインターズ The East Pointers。ガット・ギターとアコーディオンの名手Tim Edeyが率いるTim Edey Trio。オーストラリアのフォーク・アワードを受賞したBlack Market Tune。
そして、7年ぶりにオリジナル・メンバーで活動を再開した地元オーストラリアのバンド、トラブル・イン・ザ・キッチン Trouble in the kitchen。ブランク明けとはいえ彼らの人気は非常に高く、客席も常に満席でした。
今回のリサーチは、まずトラブル・イン・ザ・キッチンの足跡をたどってみることにします。
豪アイリッシュ・シーンを代表するバンド、トラブル・イン・ザ・キッチン
[caption id="attachment_3295" align="alignnone" width="500"]
今回のフェス出演者の目玉の一つは、スコットランドのバンド、ラウー Lau です。日本での公演も数度に渡り、世界のケルト音楽界でも最も注目されているバンドのひとつです。このフェスへの出演は初めてで、プログラムガイドの冒頭に取り上げられていました。
ラウーの他にもケルティック・ミュージック・バンドが複数ブッキングされていました。前回のカナダ調査時に出会ったプリンス・エドワード島のバンド、イースト・ポインターズ The East Pointers。ガット・ギターとアコーディオンの名手Tim Edeyが率いるTim Edey Trio。オーストラリアのフォーク・アワードを受賞したBlack Market Tune。
そして、7年ぶりにオリジナル・メンバーで活動を再開した地元オーストラリアのバンド、トラブル・イン・ザ・キッチン Trouble in the kitchen。ブランク明けとはいえ彼らの人気は非常に高く、客席も常に満席でした。
今回のリサーチは、まずトラブル・イン・ザ・キッチンの足跡をたどってみることにします。
豪アイリッシュ・シーンを代表するバンド、トラブル・イン・ザ・キッチン
[caption id="attachment_3295" align="alignnone" width="500"] トラブル・イン・ザ・キッチン[/caption]
トラブル・イン・ザ・キッチンの活動は1997年に始まりました。フィドル&ヴォーカルのエイド・バーカー Ado Baker、フルート&バウロンのベン・ステファンソン Ben Stephenson、ギター&ヴォーカルのケイト・バーク Kate Burke、そしてブズーキのジョー・ファーガソン Joe Fergusonの4人で構成されているアイリッシュ・バンドです。彼らは、70年代のボシー・バンド Bothy Band やプランシティ Planxty、そして現役のダーヴィッシュ Dervishといったアイルランドのバンドから強く影響を受けた音楽スタイルをもち、本国のミュージシャン達からも高い評価を受けています。
メンバー全員の出身地であるキャンベラで結成された後、メルボルンに拠点を移して活動を続けます。その後2008年に休止するまで、オーストラリアのアイリッシュ・シーンを牽引してきました。休止直前には来日も果たしています。
今回初めて観ることのできた彼らのパフォーマンスは、とても素晴らしいものでした。彼ら独自のグルーヴがあり、これまで観てきたワールド・クラスのアイリッシュ・バンドと比べても遜色ありません。歌にはオリジナルやオーストラリアの伝統曲があり、アイリッシュ・バンドでありながらオージー・カラーを出しています。同世代や彼らより上の世代からもオーストラリアを代表するアイリッシュ・バンドとして敬意を払われ、また下の世代からはアイコニックな存在として慕われています。
新世代バンド、トルカ Tolka のフィドラー、ヒラリー Hilary は「彼らの影響力はとても大きいわ」とインタビューで語っています。
この取材では、非常に興味深いことが分かりました。卓越したアイリッシュ・ミュージックを演奏する彼らですが、実はアイリッシュ・ミュージックを学んできた過程はほぼ独学である、というのです。
「伝統音楽は家族の周りには一切なかった」エイド・バーカー(フィドル)
トラブル・イン・ザ・キッチン[/caption]
トラブル・イン・ザ・キッチンの活動は1997年に始まりました。フィドル&ヴォーカルのエイド・バーカー Ado Baker、フルート&バウロンのベン・ステファンソン Ben Stephenson、ギター&ヴォーカルのケイト・バーク Kate Burke、そしてブズーキのジョー・ファーガソン Joe Fergusonの4人で構成されているアイリッシュ・バンドです。彼らは、70年代のボシー・バンド Bothy Band やプランシティ Planxty、そして現役のダーヴィッシュ Dervishといったアイルランドのバンドから強く影響を受けた音楽スタイルをもち、本国のミュージシャン達からも高い評価を受けています。
メンバー全員の出身地であるキャンベラで結成された後、メルボルンに拠点を移して活動を続けます。その後2008年に休止するまで、オーストラリアのアイリッシュ・シーンを牽引してきました。休止直前には来日も果たしています。
今回初めて観ることのできた彼らのパフォーマンスは、とても素晴らしいものでした。彼ら独自のグルーヴがあり、これまで観てきたワールド・クラスのアイリッシュ・バンドと比べても遜色ありません。歌にはオリジナルやオーストラリアの伝統曲があり、アイリッシュ・バンドでありながらオージー・カラーを出しています。同世代や彼らより上の世代からもオーストラリアを代表するアイリッシュ・バンドとして敬意を払われ、また下の世代からはアイコニックな存在として慕われています。
新世代バンド、トルカ Tolka のフィドラー、ヒラリー Hilary は「彼らの影響力はとても大きいわ」とインタビューで語っています。
この取材では、非常に興味深いことが分かりました。卓越したアイリッシュ・ミュージックを演奏する彼らですが、実はアイリッシュ・ミュージックを学んできた過程はほぼ独学である、というのです。
「伝統音楽は家族の周りには一切なかった」エイド・バーカー(フィドル)
 フィドルのエイドは、子供の頃クラシック・バイオリンの教育を受けたと言います。アイリッシュ・ミュージックを学ぶ環境は当時はなく、たまたま路上でみたバスカーの影響からアイリッシュ・フィドルを志すようになりました。
彼の周囲には移民由来の音楽を伝える環境が整っていなかったので、もっぱら耳で聞いて曲を覚える方法で、セッションで教わったり、CDを聴いたりと、時々楽譜も読んではいたものの、基本はあくまで独学だったそうです。
祖先を辿ればアイリッシュ系やスコティッシュ系に行き着くのですが、両親や祖父母がアイリッシュ・ミュージックを演奏していた訳ではありません。例えば同じように移民が住むケープ・ブレトン島などとは、どうやら事情が違うようです。
エイドだけでなく、他のバンド・メンバーも同様の環境で音楽を修得していったといいます。現在オーストラリアでアイリッシュ・ミュージックを演奏している人の多くは、独学やセッションを通して学んでいて、先祖から伝えられた音楽をやっているわけではない、と口を揃えます。
またエイドは「アイルランド的なアイデンティティーに突き動かされて音楽を始めたわけでもないんだ。そういうものは家族の周りには一切なかった。でもアイリッシュ・ミュージックにはとても惹かれたんだ」と言います。とても興味深い話です。
エイドの話をまとめると
①移民における音楽伝統の断絶
②音楽と民族アイデンティティーの乖離
という2つのポイントが浮かび上がってきます。
これはオーストラリアのアイリッシュないしケルティック・ミュージック事情を読み解くうえで重要なキーワードとなりそうです。
都市によって違う、セッションの性質――ベン・ステファンソン(フルート&バウロン)に聞く
エイドに続き、フルート&バウロン奏者ベンに話を聞きました。ベンの場合、フォーク・ソング好きの母親の影響はあったが、基本的なアイリッシュ・ミュージックの習得はセッションを通してだったそうです。
「エイドも僕もとてもラッキーだった。当時のキャンベラはセッション・シーンがとても強かったからね」
たしかにどこの街でもセッションが盛り上がっていたり、その逆に少し静かになっていたりする時期があります。キャンベラでは現在も1週間に1度程度、セッションが行われているものの、以前ほどの勢いはないそうです。都市ごとにキャラクターがあって、セッション・シーンにも違いが出てくるのです。
なぜそういう現象が起きるのでしょうか? 例えばキャンベラに住む人の多くは政府関連の仕事をしているため、一定期間を終えると別の街に移ってしまうのです。長く定住する人が少ないため、当然セッション・シーンも、その時そこに住んでいる人によって雰囲気ががらりと変わるといいます。
一方、シドニーとメルボルンはオーストラリアでもアイリッシュ・ミュージックが一番盛んな都市で、常にセッションが行われています。しかしその性格には違いがあって、シドニーのシーンは外から来た人が多い、つまりアイルランドから来た人がリードしているといいます。対してメルボルンはローカルな人、つまりオーストラリア人でおもに構成されているといいます。
またベンはダンス・カルチャーと音楽の関係についても触れてくれました。元来アイリッシュ・ミュージックはダンスと分かちがたく結びついています。ダンスの伴奏音楽がアイリッシュ・ミュージックの本来の形だからです。しかしオーストラリアでは必ずしもダンスと音楽の結びつきは強くない、と言います。シドニーには Sydney Irish Ceilidh Dancersといった組織があり、定期的にケイリー(ダンス・パーティ)が企画されているものの、メルボルンに至ってはその機会はさらに少ないそうです。
(続く)
フィドルのエイドは、子供の頃クラシック・バイオリンの教育を受けたと言います。アイリッシュ・ミュージックを学ぶ環境は当時はなく、たまたま路上でみたバスカーの影響からアイリッシュ・フィドルを志すようになりました。
彼の周囲には移民由来の音楽を伝える環境が整っていなかったので、もっぱら耳で聞いて曲を覚える方法で、セッションで教わったり、CDを聴いたりと、時々楽譜も読んではいたものの、基本はあくまで独学だったそうです。
祖先を辿ればアイリッシュ系やスコティッシュ系に行き着くのですが、両親や祖父母がアイリッシュ・ミュージックを演奏していた訳ではありません。例えば同じように移民が住むケープ・ブレトン島などとは、どうやら事情が違うようです。
エイドだけでなく、他のバンド・メンバーも同様の環境で音楽を修得していったといいます。現在オーストラリアでアイリッシュ・ミュージックを演奏している人の多くは、独学やセッションを通して学んでいて、先祖から伝えられた音楽をやっているわけではない、と口を揃えます。
またエイドは「アイルランド的なアイデンティティーに突き動かされて音楽を始めたわけでもないんだ。そういうものは家族の周りには一切なかった。でもアイリッシュ・ミュージックにはとても惹かれたんだ」と言います。とても興味深い話です。
エイドの話をまとめると
①移民における音楽伝統の断絶
②音楽と民族アイデンティティーの乖離
という2つのポイントが浮かび上がってきます。
これはオーストラリアのアイリッシュないしケルティック・ミュージック事情を読み解くうえで重要なキーワードとなりそうです。
都市によって違う、セッションの性質――ベン・ステファンソン(フルート&バウロン)に聞く
エイドに続き、フルート&バウロン奏者ベンに話を聞きました。ベンの場合、フォーク・ソング好きの母親の影響はあったが、基本的なアイリッシュ・ミュージックの習得はセッションを通してだったそうです。
「エイドも僕もとてもラッキーだった。当時のキャンベラはセッション・シーンがとても強かったからね」
たしかにどこの街でもセッションが盛り上がっていたり、その逆に少し静かになっていたりする時期があります。キャンベラでは現在も1週間に1度程度、セッションが行われているものの、以前ほどの勢いはないそうです。都市ごとにキャラクターがあって、セッション・シーンにも違いが出てくるのです。
なぜそういう現象が起きるのでしょうか? 例えばキャンベラに住む人の多くは政府関連の仕事をしているため、一定期間を終えると別の街に移ってしまうのです。長く定住する人が少ないため、当然セッション・シーンも、その時そこに住んでいる人によって雰囲気ががらりと変わるといいます。
一方、シドニーとメルボルンはオーストラリアでもアイリッシュ・ミュージックが一番盛んな都市で、常にセッションが行われています。しかしその性格には違いがあって、シドニーのシーンは外から来た人が多い、つまりアイルランドから来た人がリードしているといいます。対してメルボルンはローカルな人、つまりオーストラリア人でおもに構成されているといいます。
またベンはダンス・カルチャーと音楽の関係についても触れてくれました。元来アイリッシュ・ミュージックはダンスと分かちがたく結びついています。ダンスの伴奏音楽がアイリッシュ・ミュージックの本来の形だからです。しかしオーストラリアでは必ずしもダンスと音楽の結びつきは強くない、と言います。シドニーには Sydney Irish Ceilidh Dancersといった組織があり、定期的にケイリー(ダンス・パーティ)が企画されているものの、メルボルンに至ってはその機会はさらに少ないそうです。
(続く) 第2回 ケルト音楽を学ぶ場としてのミュージックキャンプ
さてミュージシャン達はどのような過程を経て伝統音楽を習得しているのでしょうか? エイドやベンは、アイリッシュ・ミュージックを学ぶなら、セッションの他にミュージックキャンプというのがある、と教えてくれました。
元々アウトドアが好きなオージー達。サマースクールやミュージックキャンプは数多く存在します。週末だけの短いものから、1週間ほどの長さのものまで様々ですが、宿泊しながら楽器や歌、そしてダンスのレッスンを受けることのできる集中講座です。Woodford folk festival のブッキングを担当するクロエ・グッドイヤー Chloe Goodyearは「基本的にオージーは外で活動するのが好き。だからフェスも多いし、ミュージックキャンプも多いのよね」と言っています。
ケルティック・ミュージックキャンプとして大きなものは、新年明けにコロイト Koroit で開催されている Lake School と、メルボルン郊外の街カイントン Kyneton での Celtic Southern Cross Summer School のふたつです。後者は今年が最後の開催となってしまいましたが、幸運にも参加することができたのでレポートしたいと思います。
Celtic Southern Cross Summer School
キャンプの発起人であるベス・ソーター Beth Sowter に話をききました。
[caption id="attachment_3481" align="alignnone" width="500"] ベス・ソーター[/caption]
元々このキャンプはタスマニアでスタートしました。アメリカで行なわれていた、アラスデア・フレイザー Alasdair Fraser 主催のスコティッシュ・フィドル・スクール“Valley of the Moon”から着想を得て、1999年にスコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドル、パイピング・クラス、ホイッスル・クラスの4クラス、50名ほどの参加者でスタートしました。2006年には場所をタスマニアからカイントンに移し、その後も参加者は増え続け、最終年度の2015年は18クラス計150名の規模になりました。
「スコティッシュとアイリッシュを区別せず、一緒に学べる環境をつくる」というベスのポリシーで、スコティッシュ・フィドルとアイリッシュ・フィドルのクラスが同時に用意されているという珍しい環境です。
「基本ビギナーではなくアドバンスを対象にしている」「講師のレベルについても厳しくみている」という基準の元に運営されており、参加者のレベルや意欲はなかなか高いように感じました。また同時に毎年必ずスクールに戻ってくるという人が多く、参加者同士の連帯感も感じることができました。
ベスは「このスクールは、間違いなくオーストラリアのケルト音楽シーンに貢献している」といいます。オーストラリアのケルティック・ミュージック・シーンはまだ若く、誰かがリードしていかなければいけない。このミュージックキャンプはその一つになっていると思う、とベスはいいます。
スコティッシュ・ミュージック事情
ところで、アイリッシュ以外の音楽、例えばスコティッシュ・ミュージックの状況はどうでしょうか? 上記のスクールに参加した際、スコティッシュ・フィドルの生徒数はアイリッシュのそれよりもやや少ないくらいでしたが、同程度には演奏人口があるのかなという印象をもちました。
エイドは、アイリッシュは主にセッションや個人レッスンなどで技術を磨いていくが、スコティッシュには組織された団体があり、セッションの代わりに定期的に集まって演奏したり練習したりするところが大きく違う、と指摘しています。
メルボルンには Melbourne Scottish Fiddle Club という団体があり、スコティッシュ音楽を学んだり練習したりする機会が作られているようです。こうしたスコティッシュ系の団体は、シドニーやブリスベンといった他の大都市にもあるようです。
サマースクールでスコティッシュ・フィドルのアドバンス・クラス講師を務めるクリス・ダンカン Chris Duncan はオーストラリアでスコティッシュ・フィドラーの第一人者です。その演奏は本当に素晴らしく、スクールのセッション時間に共演させてもらいましたが、いつまでも聞き惚れていたくなるような美しい音色でした。スコティッシュ・ダンスの伴奏者として、夫人のキャサリン・ストラト Catherine Strutt と共に来日も何度か経験しており、日々オーストラリア国内での指導・演奏活動に精を出しています。
[caption id="attachment_3482" align="alignnone" width="500"]
ベス・ソーター[/caption]
元々このキャンプはタスマニアでスタートしました。アメリカで行なわれていた、アラスデア・フレイザー Alasdair Fraser 主催のスコティッシュ・フィドル・スクール“Valley of the Moon”から着想を得て、1999年にスコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドル、パイピング・クラス、ホイッスル・クラスの4クラス、50名ほどの参加者でスタートしました。2006年には場所をタスマニアからカイントンに移し、その後も参加者は増え続け、最終年度の2015年は18クラス計150名の規模になりました。
「スコティッシュとアイリッシュを区別せず、一緒に学べる環境をつくる」というベスのポリシーで、スコティッシュ・フィドルとアイリッシュ・フィドルのクラスが同時に用意されているという珍しい環境です。
「基本ビギナーではなくアドバンスを対象にしている」「講師のレベルについても厳しくみている」という基準の元に運営されており、参加者のレベルや意欲はなかなか高いように感じました。また同時に毎年必ずスクールに戻ってくるという人が多く、参加者同士の連帯感も感じることができました。
ベスは「このスクールは、間違いなくオーストラリアのケルト音楽シーンに貢献している」といいます。オーストラリアのケルティック・ミュージック・シーンはまだ若く、誰かがリードしていかなければいけない。このミュージックキャンプはその一つになっていると思う、とベスはいいます。
スコティッシュ・ミュージック事情
ところで、アイリッシュ以外の音楽、例えばスコティッシュ・ミュージックの状況はどうでしょうか? 上記のスクールに参加した際、スコティッシュ・フィドルの生徒数はアイリッシュのそれよりもやや少ないくらいでしたが、同程度には演奏人口があるのかなという印象をもちました。
エイドは、アイリッシュは主にセッションや個人レッスンなどで技術を磨いていくが、スコティッシュには組織された団体があり、セッションの代わりに定期的に集まって演奏したり練習したりするところが大きく違う、と指摘しています。
メルボルンには Melbourne Scottish Fiddle Club という団体があり、スコティッシュ音楽を学んだり練習したりする機会が作られているようです。こうしたスコティッシュ系の団体は、シドニーやブリスベンといった他の大都市にもあるようです。
サマースクールでスコティッシュ・フィドルのアドバンス・クラス講師を務めるクリス・ダンカン Chris Duncan はオーストラリアでスコティッシュ・フィドラーの第一人者です。その演奏は本当に素晴らしく、スクールのセッション時間に共演させてもらいましたが、いつまでも聞き惚れていたくなるような美しい音色でした。スコティッシュ・ダンスの伴奏者として、夫人のキャサリン・ストラト Catherine Strutt と共に来日も何度か経験しており、日々オーストラリア国内での指導・演奏活動に精を出しています。
[caption id="attachment_3482" align="alignnone" width="500"] クリス・ダンカン[/caption]
彼もまたエイドやベンと同様、家族のルーツからではなく、自らの関心・嗜好からスコティッシュ・フィドルを習得するに至ったといいます。彼の話を聞いて面白いなと感じたのは、実はスコットランドには一度しか行ったことがない(しかも旅行で)ということと、スコティッシュ・スタイルのフィドルをオーストラリアで極めている人は非常に少ない、ということでした。
スコティッシュ・スタイルを極めるのが難しいという事情はオーストラリアならではかもしれません。割と似た要素の強いフォーク音楽が混在するオーストラリアでは、様々なスタイルをミックスさせる傾向は強く、違うスタイルのものを並行して習得する人たちがいます。結果ブレンドされたものができあがり、中には非常にユニークで新しいものがある一方で、一つのスタイルを純化させた音と比べるとその特性は希薄にもなりがちです。クリスのように、スコティッシュに特化して演奏を磨くということは、そうしたブレンドへの欲求を捨て去り、一つのものを貫く意志が必要です。「僕はスコティッシュが好きなんだよね、アイリッシュでもなくね」というクリスの言葉にはスコティッシュへの強い愛と一つのものを貫いているという自信に満ちていました。
TOLKAにみる次世代のアイリッシュ・ミュージック
さて、話をアイリッシュ・ミュージックに戻します。200年の移民の歴史をもつオーストラリアで、アイリッシュが盛んになり始めたのは、フォーク・リバイバルの時期1960〜70年代の頃で、90年代に入るとミュージック・スクールなどの環境整備ができつつありました。セッション・シーンが連綿と継承されていく中、世代交代は進み現在は20代のミュージシャンがシーンで活躍しています。
[caption id="attachment_3486" align="alignnone" width="500"]
クリス・ダンカン[/caption]
彼もまたエイドやベンと同様、家族のルーツからではなく、自らの関心・嗜好からスコティッシュ・フィドルを習得するに至ったといいます。彼の話を聞いて面白いなと感じたのは、実はスコットランドには一度しか行ったことがない(しかも旅行で)ということと、スコティッシュ・スタイルのフィドルをオーストラリアで極めている人は非常に少ない、ということでした。
スコティッシュ・スタイルを極めるのが難しいという事情はオーストラリアならではかもしれません。割と似た要素の強いフォーク音楽が混在するオーストラリアでは、様々なスタイルをミックスさせる傾向は強く、違うスタイルのものを並行して習得する人たちがいます。結果ブレンドされたものができあがり、中には非常にユニークで新しいものがある一方で、一つのスタイルを純化させた音と比べるとその特性は希薄にもなりがちです。クリスのように、スコティッシュに特化して演奏を磨くということは、そうしたブレンドへの欲求を捨て去り、一つのものを貫く意志が必要です。「僕はスコティッシュが好きなんだよね、アイリッシュでもなくね」というクリスの言葉にはスコティッシュへの強い愛と一つのものを貫いているという自信に満ちていました。
TOLKAにみる次世代のアイリッシュ・ミュージック
さて、話をアイリッシュ・ミュージックに戻します。200年の移民の歴史をもつオーストラリアで、アイリッシュが盛んになり始めたのは、フォーク・リバイバルの時期1960〜70年代の頃で、90年代に入るとミュージック・スクールなどの環境整備ができつつありました。セッション・シーンが連綿と継承されていく中、世代交代は進み現在は20代のミュージシャンがシーンで活躍しています。
[caption id="attachment_3486" align="alignnone" width="500"] トルカ[/caption]
TOLKA
Cameron Hibbs - Tenor Banjo
Allan Evans - Flute, Whistles & Vo
Robert Hillman - Guitar & Vo
Hilary Glaisher - Fiddle & Vo
トルカ TOLKAは、そんな新世代のアイリッシュ・シーンを象徴する存在です。20代前半の若い4人のメンバーで構成されたこのバンドは、2014年にオーストラリア政府の助成金を得て、4ヶ月間をかけて北アイルランドでレコーディングを行いました。ブライアン・フィネガン Brian Finnegan のプロデュースのもと完成したアルバムは、その新しい感性が瑞々しく吹き込まれています。
TOLKA 「One House」sound cloud
TOLKA Website
実はこのトルカを最初に見たのは3年前の2012年1月でした。当時は主にトラディショナルな曲を演奏していて、若い上手なアイリッシュ・バンドという印象でしたが、今回彼らの音楽は驚くほどガラリと変わっていました。4ヶ月の北アイルランド生活は彼らに大きな変化をもたらしていたようです。
第1回でご紹介したバンド、トラブル・イン・ザ・キッチンが盛んに活動していた1997年〜2007年は、世界的にもアイリッシュ・バンドのツアーが多い時期でした。アルタン Altan、ダーヴィッシュ Dervish、ルナサ Lunasa⋯⋯日本にも来日経験のあるバンドたちは、それぞれ特徴は異なるにせよ、ギターやブズーキ、ベース、バウロンといった伴奏楽器が独自のカラーを強く押し出していました。トラブル・イン・ザ・キッチンにもやはりその傾向は強くあります。しかし、演奏する曲自体は基本的には伝統曲でした。
しかしアイリッシュ・ミュージックのような民族的な伝統音楽の世界でも10年経てばブームも変わります。近年はアレンジも多彩になり、かつオリジナルの楽曲を演奏するバンドも増えてきました。トルカはまさにそうした時代を切り取ったようなバンドです。地元メルボルンの同世代のミュージシャンが「あのバンドはクールなアレンジがいいのよね」と言うように、アレンジは複雑です。主線楽器がフィドル、フルート、バンジョーと3本あっても、従来のユニゾン奏法だけでなく、ハーモニーやバッキング、リフのようなメロディを弾き分けます。まるで何層にも折り重ねたレイヤーのように音楽を展開しているのです。
彼らの音楽を聴いていてふと、これは果たしてアイリッシュ・ミュージックなんだろうか、という素朴な疑問が生まれました。メンバー達に率直に訊いて見たところ、アイリッシュにこだわりはあるけれども、自分たちがバンドでやっている音楽はもはやアイリッシュではないと思う、といいます。そんなトルカにアイリッシュやオーストラリアの環境についてインタビューをしてみました。(つづく)
トルカ[/caption]
TOLKA
Cameron Hibbs - Tenor Banjo
Allan Evans - Flute, Whistles & Vo
Robert Hillman - Guitar & Vo
Hilary Glaisher - Fiddle & Vo
トルカ TOLKAは、そんな新世代のアイリッシュ・シーンを象徴する存在です。20代前半の若い4人のメンバーで構成されたこのバンドは、2014年にオーストラリア政府の助成金を得て、4ヶ月間をかけて北アイルランドでレコーディングを行いました。ブライアン・フィネガン Brian Finnegan のプロデュースのもと完成したアルバムは、その新しい感性が瑞々しく吹き込まれています。
TOLKA 「One House」sound cloud
TOLKA Website
実はこのトルカを最初に見たのは3年前の2012年1月でした。当時は主にトラディショナルな曲を演奏していて、若い上手なアイリッシュ・バンドという印象でしたが、今回彼らの音楽は驚くほどガラリと変わっていました。4ヶ月の北アイルランド生活は彼らに大きな変化をもたらしていたようです。
第1回でご紹介したバンド、トラブル・イン・ザ・キッチンが盛んに活動していた1997年〜2007年は、世界的にもアイリッシュ・バンドのツアーが多い時期でした。アルタン Altan、ダーヴィッシュ Dervish、ルナサ Lunasa⋯⋯日本にも来日経験のあるバンドたちは、それぞれ特徴は異なるにせよ、ギターやブズーキ、ベース、バウロンといった伴奏楽器が独自のカラーを強く押し出していました。トラブル・イン・ザ・キッチンにもやはりその傾向は強くあります。しかし、演奏する曲自体は基本的には伝統曲でした。
しかしアイリッシュ・ミュージックのような民族的な伝統音楽の世界でも10年経てばブームも変わります。近年はアレンジも多彩になり、かつオリジナルの楽曲を演奏するバンドも増えてきました。トルカはまさにそうした時代を切り取ったようなバンドです。地元メルボルンの同世代のミュージシャンが「あのバンドはクールなアレンジがいいのよね」と言うように、アレンジは複雑です。主線楽器がフィドル、フルート、バンジョーと3本あっても、従来のユニゾン奏法だけでなく、ハーモニーやバッキング、リフのようなメロディを弾き分けます。まるで何層にも折り重ねたレイヤーのように音楽を展開しているのです。
彼らの音楽を聴いていてふと、これは果たしてアイリッシュ・ミュージックなんだろうか、という素朴な疑問が生まれました。メンバー達に率直に訊いて見たところ、アイリッシュにこだわりはあるけれども、自分たちがバンドでやっている音楽はもはやアイリッシュではないと思う、といいます。そんなトルカにアイリッシュやオーストラリアの環境についてインタビューをしてみました。(つづく)
 ベス・ソーター[/caption]
元々このキャンプはタスマニアでスタートしました。アメリカで行なわれていた、アラスデア・フレイザー Alasdair Fraser 主催のスコティッシュ・フィドル・スクール“Valley of the Moon”から着想を得て、1999年にスコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドル、パイピング・クラス、ホイッスル・クラスの4クラス、50名ほどの参加者でスタートしました。2006年には場所をタスマニアからカイントンに移し、その後も参加者は増え続け、最終年度の2015年は18クラス計150名の規模になりました。
「スコティッシュとアイリッシュを区別せず、一緒に学べる環境をつくる」というベスのポリシーで、スコティッシュ・フィドルとアイリッシュ・フィドルのクラスが同時に用意されているという珍しい環境です。
「基本ビギナーではなくアドバンスを対象にしている」「講師のレベルについても厳しくみている」という基準の元に運営されており、参加者のレベルや意欲はなかなか高いように感じました。また同時に毎年必ずスクールに戻ってくるという人が多く、参加者同士の連帯感も感じることができました。
ベスは「このスクールは、間違いなくオーストラリアのケルト音楽シーンに貢献している」といいます。オーストラリアのケルティック・ミュージック・シーンはまだ若く、誰かがリードしていかなければいけない。このミュージックキャンプはその一つになっていると思う、とベスはいいます。
スコティッシュ・ミュージック事情
ところで、アイリッシュ以外の音楽、例えばスコティッシュ・ミュージックの状況はどうでしょうか? 上記のスクールに参加した際、スコティッシュ・フィドルの生徒数はアイリッシュのそれよりもやや少ないくらいでしたが、同程度には演奏人口があるのかなという印象をもちました。
エイドは、アイリッシュは主にセッションや個人レッスンなどで技術を磨いていくが、スコティッシュには組織された団体があり、セッションの代わりに定期的に集まって演奏したり練習したりするところが大きく違う、と指摘しています。
メルボルンには Melbourne Scottish Fiddle Club という団体があり、スコティッシュ音楽を学んだり練習したりする機会が作られているようです。こうしたスコティッシュ系の団体は、シドニーやブリスベンといった他の大都市にもあるようです。
サマースクールでスコティッシュ・フィドルのアドバンス・クラス講師を務めるクリス・ダンカン Chris Duncan はオーストラリアでスコティッシュ・フィドラーの第一人者です。その演奏は本当に素晴らしく、スクールのセッション時間に共演させてもらいましたが、いつまでも聞き惚れていたくなるような美しい音色でした。スコティッシュ・ダンスの伴奏者として、夫人のキャサリン・ストラト Catherine Strutt と共に来日も何度か経験しており、日々オーストラリア国内での指導・演奏活動に精を出しています。
[caption id="attachment_3482" align="alignnone" width="500"]
ベス・ソーター[/caption]
元々このキャンプはタスマニアでスタートしました。アメリカで行なわれていた、アラスデア・フレイザー Alasdair Fraser 主催のスコティッシュ・フィドル・スクール“Valley of the Moon”から着想を得て、1999年にスコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドル、パイピング・クラス、ホイッスル・クラスの4クラス、50名ほどの参加者でスタートしました。2006年には場所をタスマニアからカイントンに移し、その後も参加者は増え続け、最終年度の2015年は18クラス計150名の規模になりました。
「スコティッシュとアイリッシュを区別せず、一緒に学べる環境をつくる」というベスのポリシーで、スコティッシュ・フィドルとアイリッシュ・フィドルのクラスが同時に用意されているという珍しい環境です。
「基本ビギナーではなくアドバンスを対象にしている」「講師のレベルについても厳しくみている」という基準の元に運営されており、参加者のレベルや意欲はなかなか高いように感じました。また同時に毎年必ずスクールに戻ってくるという人が多く、参加者同士の連帯感も感じることができました。
ベスは「このスクールは、間違いなくオーストラリアのケルト音楽シーンに貢献している」といいます。オーストラリアのケルティック・ミュージック・シーンはまだ若く、誰かがリードしていかなければいけない。このミュージックキャンプはその一つになっていると思う、とベスはいいます。
スコティッシュ・ミュージック事情
ところで、アイリッシュ以外の音楽、例えばスコティッシュ・ミュージックの状況はどうでしょうか? 上記のスクールに参加した際、スコティッシュ・フィドルの生徒数はアイリッシュのそれよりもやや少ないくらいでしたが、同程度には演奏人口があるのかなという印象をもちました。
エイドは、アイリッシュは主にセッションや個人レッスンなどで技術を磨いていくが、スコティッシュには組織された団体があり、セッションの代わりに定期的に集まって演奏したり練習したりするところが大きく違う、と指摘しています。
メルボルンには Melbourne Scottish Fiddle Club という団体があり、スコティッシュ音楽を学んだり練習したりする機会が作られているようです。こうしたスコティッシュ系の団体は、シドニーやブリスベンといった他の大都市にもあるようです。
サマースクールでスコティッシュ・フィドルのアドバンス・クラス講師を務めるクリス・ダンカン Chris Duncan はオーストラリアでスコティッシュ・フィドラーの第一人者です。その演奏は本当に素晴らしく、スクールのセッション時間に共演させてもらいましたが、いつまでも聞き惚れていたくなるような美しい音色でした。スコティッシュ・ダンスの伴奏者として、夫人のキャサリン・ストラト Catherine Strutt と共に来日も何度か経験しており、日々オーストラリア国内での指導・演奏活動に精を出しています。
[caption id="attachment_3482" align="alignnone" width="500"] クリス・ダンカン[/caption]
彼もまたエイドやベンと同様、家族のルーツからではなく、自らの関心・嗜好からスコティッシュ・フィドルを習得するに至ったといいます。彼の話を聞いて面白いなと感じたのは、実はスコットランドには一度しか行ったことがない(しかも旅行で)ということと、スコティッシュ・スタイルのフィドルをオーストラリアで極めている人は非常に少ない、ということでした。
スコティッシュ・スタイルを極めるのが難しいという事情はオーストラリアならではかもしれません。割と似た要素の強いフォーク音楽が混在するオーストラリアでは、様々なスタイルをミックスさせる傾向は強く、違うスタイルのものを並行して習得する人たちがいます。結果ブレンドされたものができあがり、中には非常にユニークで新しいものがある一方で、一つのスタイルを純化させた音と比べるとその特性は希薄にもなりがちです。クリスのように、スコティッシュに特化して演奏を磨くということは、そうしたブレンドへの欲求を捨て去り、一つのものを貫く意志が必要です。「僕はスコティッシュが好きなんだよね、アイリッシュでもなくね」というクリスの言葉にはスコティッシュへの強い愛と一つのものを貫いているという自信に満ちていました。
TOLKAにみる次世代のアイリッシュ・ミュージック
さて、話をアイリッシュ・ミュージックに戻します。200年の移民の歴史をもつオーストラリアで、アイリッシュが盛んになり始めたのは、フォーク・リバイバルの時期1960〜70年代の頃で、90年代に入るとミュージック・スクールなどの環境整備ができつつありました。セッション・シーンが連綿と継承されていく中、世代交代は進み現在は20代のミュージシャンがシーンで活躍しています。
[caption id="attachment_3486" align="alignnone" width="500"]
クリス・ダンカン[/caption]
彼もまたエイドやベンと同様、家族のルーツからではなく、自らの関心・嗜好からスコティッシュ・フィドルを習得するに至ったといいます。彼の話を聞いて面白いなと感じたのは、実はスコットランドには一度しか行ったことがない(しかも旅行で)ということと、スコティッシュ・スタイルのフィドルをオーストラリアで極めている人は非常に少ない、ということでした。
スコティッシュ・スタイルを極めるのが難しいという事情はオーストラリアならではかもしれません。割と似た要素の強いフォーク音楽が混在するオーストラリアでは、様々なスタイルをミックスさせる傾向は強く、違うスタイルのものを並行して習得する人たちがいます。結果ブレンドされたものができあがり、中には非常にユニークで新しいものがある一方で、一つのスタイルを純化させた音と比べるとその特性は希薄にもなりがちです。クリスのように、スコティッシュに特化して演奏を磨くということは、そうしたブレンドへの欲求を捨て去り、一つのものを貫く意志が必要です。「僕はスコティッシュが好きなんだよね、アイリッシュでもなくね」というクリスの言葉にはスコティッシュへの強い愛と一つのものを貫いているという自信に満ちていました。
TOLKAにみる次世代のアイリッシュ・ミュージック
さて、話をアイリッシュ・ミュージックに戻します。200年の移民の歴史をもつオーストラリアで、アイリッシュが盛んになり始めたのは、フォーク・リバイバルの時期1960〜70年代の頃で、90年代に入るとミュージック・スクールなどの環境整備ができつつありました。セッション・シーンが連綿と継承されていく中、世代交代は進み現在は20代のミュージシャンがシーンで活躍しています。
[caption id="attachment_3486" align="alignnone" width="500"] トルカ[/caption]
TOLKA
Cameron Hibbs - Tenor Banjo
Allan Evans - Flute, Whistles & Vo
Robert Hillman - Guitar & Vo
Hilary Glaisher - Fiddle & Vo
トルカ TOLKAは、そんな新世代のアイリッシュ・シーンを象徴する存在です。20代前半の若い4人のメンバーで構成されたこのバンドは、2014年にオーストラリア政府の助成金を得て、4ヶ月間をかけて北アイルランドでレコーディングを行いました。ブライアン・フィネガン Brian Finnegan のプロデュースのもと完成したアルバムは、その新しい感性が瑞々しく吹き込まれています。
TOLKA 「One House」sound cloud
TOLKA Website
実はこのトルカを最初に見たのは3年前の2012年1月でした。当時は主にトラディショナルな曲を演奏していて、若い上手なアイリッシュ・バンドという印象でしたが、今回彼らの音楽は驚くほどガラリと変わっていました。4ヶ月の北アイルランド生活は彼らに大きな変化をもたらしていたようです。
第1回でご紹介したバンド、トラブル・イン・ザ・キッチンが盛んに活動していた1997年〜2007年は、世界的にもアイリッシュ・バンドのツアーが多い時期でした。アルタン Altan、ダーヴィッシュ Dervish、ルナサ Lunasa⋯⋯日本にも来日経験のあるバンドたちは、それぞれ特徴は異なるにせよ、ギターやブズーキ、ベース、バウロンといった伴奏楽器が独自のカラーを強く押し出していました。トラブル・イン・ザ・キッチンにもやはりその傾向は強くあります。しかし、演奏する曲自体は基本的には伝統曲でした。
しかしアイリッシュ・ミュージックのような民族的な伝統音楽の世界でも10年経てばブームも変わります。近年はアレンジも多彩になり、かつオリジナルの楽曲を演奏するバンドも増えてきました。トルカはまさにそうした時代を切り取ったようなバンドです。地元メルボルンの同世代のミュージシャンが「あのバンドはクールなアレンジがいいのよね」と言うように、アレンジは複雑です。主線楽器がフィドル、フルート、バンジョーと3本あっても、従来のユニゾン奏法だけでなく、ハーモニーやバッキング、リフのようなメロディを弾き分けます。まるで何層にも折り重ねたレイヤーのように音楽を展開しているのです。
彼らの音楽を聴いていてふと、これは果たしてアイリッシュ・ミュージックなんだろうか、という素朴な疑問が生まれました。メンバー達に率直に訊いて見たところ、アイリッシュにこだわりはあるけれども、自分たちがバンドでやっている音楽はもはやアイリッシュではないと思う、といいます。そんなトルカにアイリッシュやオーストラリアの環境についてインタビューをしてみました。(つづく)
トルカ[/caption]
TOLKA
Cameron Hibbs - Tenor Banjo
Allan Evans - Flute, Whistles & Vo
Robert Hillman - Guitar & Vo
Hilary Glaisher - Fiddle & Vo
トルカ TOLKAは、そんな新世代のアイリッシュ・シーンを象徴する存在です。20代前半の若い4人のメンバーで構成されたこのバンドは、2014年にオーストラリア政府の助成金を得て、4ヶ月間をかけて北アイルランドでレコーディングを行いました。ブライアン・フィネガン Brian Finnegan のプロデュースのもと完成したアルバムは、その新しい感性が瑞々しく吹き込まれています。
TOLKA 「One House」sound cloud
TOLKA Website
実はこのトルカを最初に見たのは3年前の2012年1月でした。当時は主にトラディショナルな曲を演奏していて、若い上手なアイリッシュ・バンドという印象でしたが、今回彼らの音楽は驚くほどガラリと変わっていました。4ヶ月の北アイルランド生活は彼らに大きな変化をもたらしていたようです。
第1回でご紹介したバンド、トラブル・イン・ザ・キッチンが盛んに活動していた1997年〜2007年は、世界的にもアイリッシュ・バンドのツアーが多い時期でした。アルタン Altan、ダーヴィッシュ Dervish、ルナサ Lunasa⋯⋯日本にも来日経験のあるバンドたちは、それぞれ特徴は異なるにせよ、ギターやブズーキ、ベース、バウロンといった伴奏楽器が独自のカラーを強く押し出していました。トラブル・イン・ザ・キッチンにもやはりその傾向は強くあります。しかし、演奏する曲自体は基本的には伝統曲でした。
しかしアイリッシュ・ミュージックのような民族的な伝統音楽の世界でも10年経てばブームも変わります。近年はアレンジも多彩になり、かつオリジナルの楽曲を演奏するバンドも増えてきました。トルカはまさにそうした時代を切り取ったようなバンドです。地元メルボルンの同世代のミュージシャンが「あのバンドはクールなアレンジがいいのよね」と言うように、アレンジは複雑です。主線楽器がフィドル、フルート、バンジョーと3本あっても、従来のユニゾン奏法だけでなく、ハーモニーやバッキング、リフのようなメロディを弾き分けます。まるで何層にも折り重ねたレイヤーのように音楽を展開しているのです。
彼らの音楽を聴いていてふと、これは果たしてアイリッシュ・ミュージックなんだろうか、という素朴な疑問が生まれました。メンバー達に率直に訊いて見たところ、アイリッシュにこだわりはあるけれども、自分たちがバンドでやっている音楽はもはやアイリッシュではないと思う、といいます。そんなトルカにアイリッシュやオーストラリアの環境についてインタビューをしてみました。(つづく) 第3回 TOLKAに聞く
さてそのトルカのメンバー達が、北アイルランドで4ヶ月過ごしてきた中で、現地の同世代から受けた影響はどのようなものだったのでしょうか? フィドラーのヒラリー Hiraly は「彼らの育ってきた環境はシック(分厚い)ね」と言います。
「彼らの伝統は厚くて、周囲に音楽をやる環境が揃っている。セッションも多いし、プレーヤーも多いし。それに比べると、自分たちの環境はまだまだだな、って思う」
フルートのアラン Allan も同様の印象だといいます。
「僕らは、例えばナショナル・フォーク・フェスティバル National Folk Festival なんかでは常に同じ顔ぶれに会う感じなんだけど、彼らはもっともっと音楽人口がいる。それに音楽を学べる機会の頻度も違う。僕らには時々しかないけど、彼らには毎週末あるわけなんだよね」
ヒラリーもさらに続けていいます。
「北アイルランドの状況と比べると、この音楽は私たちの文化ではないと感じる。とにかく環境の整備状況が違うしね。そして、オーストラリアではこの手の音楽で食べていくのは、ビッグネームにならないかぎり難しいけど、アイルランドではそれが可能だ、という違いもあるかな」
そんな環境の差を肌で感じながら、彼らはブライアン・フィネガンによるプロデュースのもと、レコーディングを行います。
「ブライアンには『アイリッシュ・ミュージックの伝統に囚われる必要はない』と言われたの。それで気持ちが楽になった。私はずっとアイリッシュ・フィドルの伝統的な奏法ができているのか不安だったけど、それに囚われすぎるのも良くないと思ったわ。だからバンドではアイリッシュ・ミュージックをベースにしつつ、それを広げられるように考えている。全曲オリジナルなのもそういう訳なの」
彼らのアイリッシュ・ミュージックへの憧憬と葛藤の感覚は、日本人にはよく理解できる悩みかもしれません。同時に、オーストラリアと日本の状況が非常に似ていることを彼らの言葉から汲み取ることができるでしょう。
ティム・スカンランに聞く
[caption id="attachment_3493" align="alignnone" width="500"] 吉祥寺の商店街でバスキングをするティム・スカンランと筆者[/caption]
オーストラリアの状況については、別の視点からも話をききました。現在日本に在住しているオーストラリア出身のミュージシャン、ティム スカンラン Tim Scanlan です。メルボルン出身のティムは、放浪中にオリジナルのスタイルを身につけた、非常にユニークなケルティック・ミュージシャンです。
Tim Scanlan & Toshi Bodhran
https://www.youtube.com/watch?v=PXpUYerFINY
ティムがまず語ってくれたのは、自身のスタイルとアイリッシュ・トラッドの距離、そしてシーンとの距離です。
「ギターがメインで、パーカッションをするようにもなり、ハーモニカで曲を弾くようにはなったけど、基本のレパートリーはフォークのダンス曲全般を中心にしている。アイリッシュだけというわけではないね。インプロビゼーションが占める割合も自作曲の中には多い。1/4はトラッドで、残りはインプロ・ミュージックという感じかな。トラッドは愛しているし、ベースにはしているけど、同時にエフェクトを試したり新しい技術を模索してもいる。トラッドに捧げている人はとても尊敬しているけど、いつもセッションに参加して曲を弾くようなのには自分は向いていない。僕はトラベラーだからね。例えばレゲエのリズムをセッションで弾いた日には、みんなから白い目で見られるだろうと思う。トラッドの世界ではそういうのは受け入れられないからね」
彼は自分一人で複数の楽器やエフェクターを操作し、まるでバンド・サウンドのような複合的な音を作り上げています。このワンマン・バンド・スタイルはどこから影響を受けたものなのでしょうか?
「僕のやっているようなスタイルは、オーストラリアのルーツ(ブルース)ミュージック・シーンには多いと思う。ジェフ・ラング Jeff Lang 、アッシュ・グラウンウォルド Ash Grunwald、ザビエル・ラッド Xavier Rudd、ライズ・クリミン Rhys Crimmin のようにね。正直な気持ちとしては、アイリッシュのトラッド・シーンよりも彼らのほうにシンパシーを感じる。トラッドの世界では僕のスタイルで演奏している人はいないしね。余談だけど、ジェフ・ラングと一度一緒にやったときに『トラッドの世界でも、ティムみたいにやる人がもっと増えたらいいのにね』と言われたよ。いまアイリッシュ・ミュージックをやりながら、日本にもオーストラリアのブルース・ルーツ・シーンを持ち込んでいるように思っている。ジェフもイーリアン・パイプのドローンの音づくりを真似ようとしているみたいだね。僕がやっているフリーズ・ペダルの効果を勉強していたよ」
「僕のスタイルは間違いなく、旅をしながら身につけたものだ。ギターで弾き語るうちにアイリッシュ・バラッドを好きでやるようになり、ダンス・チューンも増えていった。このミクスチャーなスタイルは別にオーストラリアだからとかは関係ないし、オーストラリア的なアイデンティティも関係ないよ。僕の血筋が元々アイリッシュだということも関係はない。ただ初めてアイルランドに渡ったときに感動したのは覚えているけどね」
そんな彼が、世界を旅した中で感じるオーストラリアの環境とはどういったものなのでしょうか?
「オーストラリアのアイリッシュ・シーンは、何人かはワールドクラスの腕前だと思う。トラブル・イン・ザ・キッチンのメンバーはそれぞれがそうだよね。あと若い子たちも出てきているのは知っている。その中にはアイルランドに行ったことがない子たちもいると思う。YoutubeやCDなんかで学んでるよね。でも、もちろんすべてのミュージシャンのレベルがそんなに高いわけではないし、ゆったり弾いている年寄りの人たちもいるよね。オーストラリアのアイリッシュ・シーンに望むことは、もっと色んなところでやってほしいってことかな。パブの片隅だけでなく、カフェとかレストランとか。どこでもそういうセッションをやってたらいいなとは思うよね。でもアイリッシュ・ミュージック・シーンだけでなく、音楽シーン全体がオーストラリアではまだまだ未成熟だと思う。そこから受ける刺激も限定的だ。でもオーストラリアは自然がとても素晴らしくて、自然の中に包まれていると色んな刺激を受けられる。それは本当に素晴らしいと思うよ」
【後記】
今回オーストラリアを旅して感じたのは、ここのケルティック・ミュージック・シーンを巡る状況は日本ときわめて近いということです。一方で、英語圏でもあるオーストラリアには、アイルランドやスコットランドなどから多くのミュージシャンが訪れます。またオーストラリアからも現地に出かけるなどの交流があり、そこには日本とのギャップを感じます。少し先を行っている先輩、そんな気持ちを抱きながらオーストラリアのシーンをリサーチしてきました。これから彼の地の隆盛については目が離せません。
今回の取材にあたり、下記の方々、団体にお力添えをいただきました。深く感謝いたします。
Woodford Folk Festival, Chloe Goodyear, Trouble in the kitchen, TOLKA, Celtic Southern Cross Summer School, Beth Sowter, Chris Duncan, Catherine Strutt, James & Jane Thompson, Tim Scanlan.
(了)
吉祥寺の商店街でバスキングをするティム・スカンランと筆者[/caption]
オーストラリアの状況については、別の視点からも話をききました。現在日本に在住しているオーストラリア出身のミュージシャン、ティム スカンラン Tim Scanlan です。メルボルン出身のティムは、放浪中にオリジナルのスタイルを身につけた、非常にユニークなケルティック・ミュージシャンです。
Tim Scanlan & Toshi Bodhran
https://www.youtube.com/watch?v=PXpUYerFINY
ティムがまず語ってくれたのは、自身のスタイルとアイリッシュ・トラッドの距離、そしてシーンとの距離です。
「ギターがメインで、パーカッションをするようにもなり、ハーモニカで曲を弾くようにはなったけど、基本のレパートリーはフォークのダンス曲全般を中心にしている。アイリッシュだけというわけではないね。インプロビゼーションが占める割合も自作曲の中には多い。1/4はトラッドで、残りはインプロ・ミュージックという感じかな。トラッドは愛しているし、ベースにはしているけど、同時にエフェクトを試したり新しい技術を模索してもいる。トラッドに捧げている人はとても尊敬しているけど、いつもセッションに参加して曲を弾くようなのには自分は向いていない。僕はトラベラーだからね。例えばレゲエのリズムをセッションで弾いた日には、みんなから白い目で見られるだろうと思う。トラッドの世界ではそういうのは受け入れられないからね」
彼は自分一人で複数の楽器やエフェクターを操作し、まるでバンド・サウンドのような複合的な音を作り上げています。このワンマン・バンド・スタイルはどこから影響を受けたものなのでしょうか?
「僕のやっているようなスタイルは、オーストラリアのルーツ(ブルース)ミュージック・シーンには多いと思う。ジェフ・ラング Jeff Lang 、アッシュ・グラウンウォルド Ash Grunwald、ザビエル・ラッド Xavier Rudd、ライズ・クリミン Rhys Crimmin のようにね。正直な気持ちとしては、アイリッシュのトラッド・シーンよりも彼らのほうにシンパシーを感じる。トラッドの世界では僕のスタイルで演奏している人はいないしね。余談だけど、ジェフ・ラングと一度一緒にやったときに『トラッドの世界でも、ティムみたいにやる人がもっと増えたらいいのにね』と言われたよ。いまアイリッシュ・ミュージックをやりながら、日本にもオーストラリアのブルース・ルーツ・シーンを持ち込んでいるように思っている。ジェフもイーリアン・パイプのドローンの音づくりを真似ようとしているみたいだね。僕がやっているフリーズ・ペダルの効果を勉強していたよ」
「僕のスタイルは間違いなく、旅をしながら身につけたものだ。ギターで弾き語るうちにアイリッシュ・バラッドを好きでやるようになり、ダンス・チューンも増えていった。このミクスチャーなスタイルは別にオーストラリアだからとかは関係ないし、オーストラリア的なアイデンティティも関係ないよ。僕の血筋が元々アイリッシュだということも関係はない。ただ初めてアイルランドに渡ったときに感動したのは覚えているけどね」
そんな彼が、世界を旅した中で感じるオーストラリアの環境とはどういったものなのでしょうか?
「オーストラリアのアイリッシュ・シーンは、何人かはワールドクラスの腕前だと思う。トラブル・イン・ザ・キッチンのメンバーはそれぞれがそうだよね。あと若い子たちも出てきているのは知っている。その中にはアイルランドに行ったことがない子たちもいると思う。YoutubeやCDなんかで学んでるよね。でも、もちろんすべてのミュージシャンのレベルがそんなに高いわけではないし、ゆったり弾いている年寄りの人たちもいるよね。オーストラリアのアイリッシュ・シーンに望むことは、もっと色んなところでやってほしいってことかな。パブの片隅だけでなく、カフェとかレストランとか。どこでもそういうセッションをやってたらいいなとは思うよね。でもアイリッシュ・ミュージック・シーンだけでなく、音楽シーン全体がオーストラリアではまだまだ未成熟だと思う。そこから受ける刺激も限定的だ。でもオーストラリアは自然がとても素晴らしくて、自然の中に包まれていると色んな刺激を受けられる。それは本当に素晴らしいと思うよ」
【後記】
今回オーストラリアを旅して感じたのは、ここのケルティック・ミュージック・シーンを巡る状況は日本ときわめて近いということです。一方で、英語圏でもあるオーストラリアには、アイルランドやスコットランドなどから多くのミュージシャンが訪れます。またオーストラリアからも現地に出かけるなどの交流があり、そこには日本とのギャップを感じます。少し先を行っている先輩、そんな気持ちを抱きながらオーストラリアのシーンをリサーチしてきました。これから彼の地の隆盛については目が離せません。
今回の取材にあたり、下記の方々、団体にお力添えをいただきました。深く感謝いたします。
Woodford Folk Festival, Chloe Goodyear, Trouble in the kitchen, TOLKA, Celtic Southern Cross Summer School, Beth Sowter, Chris Duncan, Catherine Strutt, James & Jane Thompson, Tim Scanlan.
(了)
 吉祥寺の商店街でバスキングをするティム・スカンランと筆者[/caption]
オーストラリアの状況については、別の視点からも話をききました。現在日本に在住しているオーストラリア出身のミュージシャン、ティム スカンラン Tim Scanlan です。メルボルン出身のティムは、放浪中にオリジナルのスタイルを身につけた、非常にユニークなケルティック・ミュージシャンです。
Tim Scanlan & Toshi Bodhran
https://www.youtube.com/watch?v=PXpUYerFINY
ティムがまず語ってくれたのは、自身のスタイルとアイリッシュ・トラッドの距離、そしてシーンとの距離です。
「ギターがメインで、パーカッションをするようにもなり、ハーモニカで曲を弾くようにはなったけど、基本のレパートリーはフォークのダンス曲全般を中心にしている。アイリッシュだけというわけではないね。インプロビゼーションが占める割合も自作曲の中には多い。1/4はトラッドで、残りはインプロ・ミュージックという感じかな。トラッドは愛しているし、ベースにはしているけど、同時にエフェクトを試したり新しい技術を模索してもいる。トラッドに捧げている人はとても尊敬しているけど、いつもセッションに参加して曲を弾くようなのには自分は向いていない。僕はトラベラーだからね。例えばレゲエのリズムをセッションで弾いた日には、みんなから白い目で見られるだろうと思う。トラッドの世界ではそういうのは受け入れられないからね」
彼は自分一人で複数の楽器やエフェクターを操作し、まるでバンド・サウンドのような複合的な音を作り上げています。このワンマン・バンド・スタイルはどこから影響を受けたものなのでしょうか?
「僕のやっているようなスタイルは、オーストラリアのルーツ(ブルース)ミュージック・シーンには多いと思う。ジェフ・ラング Jeff Lang 、アッシュ・グラウンウォルド Ash Grunwald、ザビエル・ラッド Xavier Rudd、ライズ・クリミン Rhys Crimmin のようにね。正直な気持ちとしては、アイリッシュのトラッド・シーンよりも彼らのほうにシンパシーを感じる。トラッドの世界では僕のスタイルで演奏している人はいないしね。余談だけど、ジェフ・ラングと一度一緒にやったときに『トラッドの世界でも、ティムみたいにやる人がもっと増えたらいいのにね』と言われたよ。いまアイリッシュ・ミュージックをやりながら、日本にもオーストラリアのブルース・ルーツ・シーンを持ち込んでいるように思っている。ジェフもイーリアン・パイプのドローンの音づくりを真似ようとしているみたいだね。僕がやっているフリーズ・ペダルの効果を勉強していたよ」
「僕のスタイルは間違いなく、旅をしながら身につけたものだ。ギターで弾き語るうちにアイリッシュ・バラッドを好きでやるようになり、ダンス・チューンも増えていった。このミクスチャーなスタイルは別にオーストラリアだからとかは関係ないし、オーストラリア的なアイデンティティも関係ないよ。僕の血筋が元々アイリッシュだということも関係はない。ただ初めてアイルランドに渡ったときに感動したのは覚えているけどね」
そんな彼が、世界を旅した中で感じるオーストラリアの環境とはどういったものなのでしょうか?
「オーストラリアのアイリッシュ・シーンは、何人かはワールドクラスの腕前だと思う。トラブル・イン・ザ・キッチンのメンバーはそれぞれがそうだよね。あと若い子たちも出てきているのは知っている。その中にはアイルランドに行ったことがない子たちもいると思う。YoutubeやCDなんかで学んでるよね。でも、もちろんすべてのミュージシャンのレベルがそんなに高いわけではないし、ゆったり弾いている年寄りの人たちもいるよね。オーストラリアのアイリッシュ・シーンに望むことは、もっと色んなところでやってほしいってことかな。パブの片隅だけでなく、カフェとかレストランとか。どこでもそういうセッションをやってたらいいなとは思うよね。でもアイリッシュ・ミュージック・シーンだけでなく、音楽シーン全体がオーストラリアではまだまだ未成熟だと思う。そこから受ける刺激も限定的だ。でもオーストラリアは自然がとても素晴らしくて、自然の中に包まれていると色んな刺激を受けられる。それは本当に素晴らしいと思うよ」
【後記】
今回オーストラリアを旅して感じたのは、ここのケルティック・ミュージック・シーンを巡る状況は日本ときわめて近いということです。一方で、英語圏でもあるオーストラリアには、アイルランドやスコットランドなどから多くのミュージシャンが訪れます。またオーストラリアからも現地に出かけるなどの交流があり、そこには日本とのギャップを感じます。少し先を行っている先輩、そんな気持ちを抱きながらオーストラリアのシーンをリサーチしてきました。これから彼の地の隆盛については目が離せません。
今回の取材にあたり、下記の方々、団体にお力添えをいただきました。深く感謝いたします。
Woodford Folk Festival, Chloe Goodyear, Trouble in the kitchen, TOLKA, Celtic Southern Cross Summer School, Beth Sowter, Chris Duncan, Catherine Strutt, James & Jane Thompson, Tim Scanlan.
(了)
吉祥寺の商店街でバスキングをするティム・スカンランと筆者[/caption]
オーストラリアの状況については、別の視点からも話をききました。現在日本に在住しているオーストラリア出身のミュージシャン、ティム スカンラン Tim Scanlan です。メルボルン出身のティムは、放浪中にオリジナルのスタイルを身につけた、非常にユニークなケルティック・ミュージシャンです。
Tim Scanlan & Toshi Bodhran
https://www.youtube.com/watch?v=PXpUYerFINY
ティムがまず語ってくれたのは、自身のスタイルとアイリッシュ・トラッドの距離、そしてシーンとの距離です。
「ギターがメインで、パーカッションをするようにもなり、ハーモニカで曲を弾くようにはなったけど、基本のレパートリーはフォークのダンス曲全般を中心にしている。アイリッシュだけというわけではないね。インプロビゼーションが占める割合も自作曲の中には多い。1/4はトラッドで、残りはインプロ・ミュージックという感じかな。トラッドは愛しているし、ベースにはしているけど、同時にエフェクトを試したり新しい技術を模索してもいる。トラッドに捧げている人はとても尊敬しているけど、いつもセッションに参加して曲を弾くようなのには自分は向いていない。僕はトラベラーだからね。例えばレゲエのリズムをセッションで弾いた日には、みんなから白い目で見られるだろうと思う。トラッドの世界ではそういうのは受け入れられないからね」
彼は自分一人で複数の楽器やエフェクターを操作し、まるでバンド・サウンドのような複合的な音を作り上げています。このワンマン・バンド・スタイルはどこから影響を受けたものなのでしょうか?
「僕のやっているようなスタイルは、オーストラリアのルーツ(ブルース)ミュージック・シーンには多いと思う。ジェフ・ラング Jeff Lang 、アッシュ・グラウンウォルド Ash Grunwald、ザビエル・ラッド Xavier Rudd、ライズ・クリミン Rhys Crimmin のようにね。正直な気持ちとしては、アイリッシュのトラッド・シーンよりも彼らのほうにシンパシーを感じる。トラッドの世界では僕のスタイルで演奏している人はいないしね。余談だけど、ジェフ・ラングと一度一緒にやったときに『トラッドの世界でも、ティムみたいにやる人がもっと増えたらいいのにね』と言われたよ。いまアイリッシュ・ミュージックをやりながら、日本にもオーストラリアのブルース・ルーツ・シーンを持ち込んでいるように思っている。ジェフもイーリアン・パイプのドローンの音づくりを真似ようとしているみたいだね。僕がやっているフリーズ・ペダルの効果を勉強していたよ」
「僕のスタイルは間違いなく、旅をしながら身につけたものだ。ギターで弾き語るうちにアイリッシュ・バラッドを好きでやるようになり、ダンス・チューンも増えていった。このミクスチャーなスタイルは別にオーストラリアだからとかは関係ないし、オーストラリア的なアイデンティティも関係ないよ。僕の血筋が元々アイリッシュだということも関係はない。ただ初めてアイルランドに渡ったときに感動したのは覚えているけどね」
そんな彼が、世界を旅した中で感じるオーストラリアの環境とはどういったものなのでしょうか?
「オーストラリアのアイリッシュ・シーンは、何人かはワールドクラスの腕前だと思う。トラブル・イン・ザ・キッチンのメンバーはそれぞれがそうだよね。あと若い子たちも出てきているのは知っている。その中にはアイルランドに行ったことがない子たちもいると思う。YoutubeやCDなんかで学んでるよね。でも、もちろんすべてのミュージシャンのレベルがそんなに高いわけではないし、ゆったり弾いている年寄りの人たちもいるよね。オーストラリアのアイリッシュ・シーンに望むことは、もっと色んなところでやってほしいってことかな。パブの片隅だけでなく、カフェとかレストランとか。どこでもそういうセッションをやってたらいいなとは思うよね。でもアイリッシュ・ミュージック・シーンだけでなく、音楽シーン全体がオーストラリアではまだまだ未成熟だと思う。そこから受ける刺激も限定的だ。でもオーストラリアは自然がとても素晴らしくて、自然の中に包まれていると色んな刺激を受けられる。それは本当に素晴らしいと思うよ」
【後記】
今回オーストラリアを旅して感じたのは、ここのケルティック・ミュージック・シーンを巡る状況は日本ときわめて近いということです。一方で、英語圏でもあるオーストラリアには、アイルランドやスコットランドなどから多くのミュージシャンが訪れます。またオーストラリアからも現地に出かけるなどの交流があり、そこには日本とのギャップを感じます。少し先を行っている先輩、そんな気持ちを抱きながらオーストラリアのシーンをリサーチしてきました。これから彼の地の隆盛については目が離せません。
今回の取材にあたり、下記の方々、団体にお力添えをいただきました。深く感謝いたします。
Woodford Folk Festival, Chloe Goodyear, Trouble in the kitchen, TOLKA, Celtic Southern Cross Summer School, Beth Sowter, Chris Duncan, Catherine Strutt, James & Jane Thompson, Tim Scanlan.
(了)