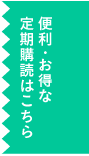アルテス初登場の浅井佑太さんは、新ウィーン楽派を専門とする京都大学の大学院生にして、現在はケルン大学で博士論文を準備中の若き研究者です。ケルンといえば、アルテス読者諸氏であればWDR(西ドイツ放送ケルン局)内の電子音響スタジオを思いおこされる向きも多いことでしょう。本稿は、そのスタジオの名とともに記憶されるシュトックハウゼンにも師事した、電子音響音楽の大家、フランソワ・ベイルに迫ったものです。電子音楽の本場ケルンの空気をたっぷりと吸った文章をご堪能ください。

浅井佑太
音楽学
1988年生まれ。京都大学文学研究科修士課程修了(美学美術史学)。2014年より日本学術振興会特別研究員 DC1。現在ドイツ、ケルン大学に留学中。専門は20世紀以降の音楽、とりわけ新ウィーン楽派。
江戸時代の禅僧、白隠(はくいん)は修行者を前にして、次のように問うたという。
隻手声あり、その声を聞け(大意:両手を打ち合わせると音が鳴るが、片方の手からはどのような音が聞こえるか)。
もちろんこれは答えがないゆえに問いとして成立する禅問答であり、どれだけ耳を澄ましてみても「隻手声」を聴くことはできない。科学的にいえば、私たちが聴いているのはたんなる空気の振動であり、手のひらはその振動を作りだす媒体にすぎない。けれども私たちはふつう、音を作りだす原因との関連のなかで知覚しているから、「隻手声」といわれると戸惑ってしまう。私たちがふだん聴いていると信じているのは、じつのところ「音」ではなく、その「文脈」なのである。 かりに視覚的な情報が完全に遮断されたとしても、そのことはほとんど変わらない。たとえば居間でくつろぎながら交響曲のCDを聴くとき、私たちは心の底でひそかに、スピーカーのなかには小人のオーケストラ団員が隠れていて、自分ひとりのためだけに演奏会を開いているような気になっている。この一種馬鹿馬鹿しく子供じみた幻想は、私たちがなんの疑問もなく、大晦日にテレビで放送されるベートーヴェンの《第九》を聴いているとき、いわば否定しがたい現実として姿を現す。スクリーンのうえに映しだされる演奏者たちは、じつはこの「子供じみた幻想」が実体化した姿にほかならない。そしてテレビの隅のスピーカーは、「スクリーンの上にしか存在しない」演奏者と、「空気の振動としてのみ存在する」音楽という2つの幻想をつなぐ、か細い糸なのである。 私はじつは今、ケルン大学の3階に位置する「音響スタジオ」でこの原稿を書いている。部屋の一室には8台のスピーカーが私自身を取り巻くように円形状に設置され、中央のパソコンとミキシング・コンソールによって同期的に操作することができる。日本人である私には、正面の額に飾られた大阪万博博覧会でのシュトックハウゼンのサイン入りブロマイドがとりわけ目に飛び込んでくる。奥の棚には電子音響音楽の録音テープとCDがぎっしりと収められ、よく見るとそこには、ここケルンでも学んだ日本人の作曲家、Makoto Shinoharaの名前もある。この部屋はまさに「電子音響音楽」のためだけに作られた一室なのである。
[caption id="attachment_3986" align="alignnone" width="500"] ケルン大学内の音響スタジオ[/caption]
ケルン大学内の音響スタジオ[/caption]
電子音響音楽の発展において、このドイツのケルンという地が果たした役割について長々と述べる必要はないだろう。1951年にWDR放送局の一部門として創設されたスタジオはドイツにおける電子音響音楽の技術的発展を主導する役割をにない、とりわけシュトックハウゼンの名とともに記憶されている。あるいは彼が学んだケルン大学には、今日にいたるまで毎年多くの作曲家が招かれるとともに、その講堂は電子音響音楽初演の場としても利用され、近年ではとりわけフランスを代表する作曲家フランソワ・ベイルが毎年のようにここに招かれ、講演を開くとともに自作の上演をおこなっている(ちなみに彼はミュージック・コンクレートの創始者であるピエール・シェフェール、ならびにシュトックハウゼンのもとでも学んだ現代を代表する電子音響音楽の作曲家である)。ここでの彼の講演と自作の解説は定期的に書籍としても刊行されており、ベイルはいわば電子音響音楽を美的・理論的にも牽引する人物のひとりである。 音響技術が発達した今日では、ラジオやCDを思い描くまでもなく、スピーカーによって音がその文脈から切り離されるという経験は、もはや日常的な光景となってしまったように思う。ベイルの言葉を借りるならば「そこで扱われているのは、たんなる情報伝達の利便性」であり、もはや凡庸な経験にすぎないといってもいいだろう。しかしこの事態は本来、作曲史上まったく未知の事態であった。このことをベイルは2000年に開かれた講演のなかで次のように振り返っている。
私はあの「音の革命」について語りたいと思います。これによって音は物体、それどころか自立した素材となったのです。音というものは、本来つかの間の命しかもっていないのですが(音はあらゆる現象のなかでもっともはかないものです)、この革命以来、音はその時間的経緯において精密に記録され、それゆえ容易に探究し操作されうるものとなったのです。(…)突如として音楽家には、画家や彫刻家と同じような経験をする可能性がもたらされました。というのも音楽家は自身の手と体を動かし、直接作品そのものを形づくっていくことができるのです。
楽音という一種の抽象的記号を紙の上に配置してきた以前の作曲家と異なり、いまや作曲家は実際に鳴り響く音そのものを作曲の出発点とする。いわば画家が絵筆でもってキャンバスのうえに画面を構成するのと同じように、作曲家は「音」を録音器具へと直接刻み込むのである。 ためしに棚からテープを取りだして、シュトックハウゼンの《習作Ⅰ》(1953)を聴いてみよう。電子音響音楽黎明期にケルンのスタジオで作られたこの作品は、技術的には倍音をいっさいふくまない純音の合成によって製作され、構成的にはトータル・セリエリズムのもとにある。スピーカーから水面を打つような静的な音が突如として浮かび上がり、流れの奥底でその音は胎動し続ける。そしてその変化は無限のヴァリエーションをもって、わずか9分ほどの楽曲全体を貫く。 もっともこの曲を伝統的な音楽と同じように聴くものは失望するに違いない。たとえばベートーヴェンの《運命》を思い浮かべてみるといい。その有名な冒頭の動機は、かりにベルリン・フィルの壮麗な弦楽器で演奏されようとも、素人のおぼつかない手取りのピアノで鳴らされたものであったとしても、それはけっきょくのところ同一の水平線上に存在する無数のヴァリアントのひとつにすぎない。しかし電子音響音楽の場合、そこで鳴り響く音に代替可能なヴァリアントを見出すことはできない。《習作Ⅰ》をもういちど例にとるならば、そこで鳴り響く音が「歴史上かつてどこにも存在しなかった音」であるという事実を認識して初めて、私たちはその真価を理解することができるのである。 ヘルムホルツ以来の音の科学が明らかにしたのは、音の性質を定めるのは、音高のみならず、私たちが音の二次的な要素として無意識に切り捨ててきた、音色、音強、音の減衰といった諸要素であることであった。そして電子音響音楽が照準を合わせているのは、まさにこれらの伝統的な音楽のなかで二次的・非本質的なものとして切り捨てられてきた側面なのである。それゆえ─多くの革新的な音楽作品の場合と同様―電子音響音楽は新たな音楽の聴き方を聴き手に要求することになる。 スピーカーからのみ聴くことのできる音楽の呼称として1974年にベイルによって提唱された概念「アクスマティーク(acousmatique)」が、まさにこうした音楽聴の特徴を中心的に視野に入れたものであることはけっして偶然ではないだろう(エレキ・ギターのような電子楽器や演奏会におけるエレクトロニクスの使用が一般化した現代の音楽事情の前では、「電子音響音楽」という用語はその妥当性を失いつつある)。そして興味深いことにこの概念は、歴史上最初の音楽理論家のひとりであるピュタゴラスをその規範に据える。伝えられるところによると、授業のさい、ピュタゴラスは自身の弟子たちをカーテンによって2つのクラスに分けたという。エソテリカー(独:Esoteriker)と呼ばれる一部の熟練した生徒のみが、ピュタゴラスの授業を面と向かって受けることができたのにたいし、そのほかのアクスマティカー(独:Akusmatiker、ギリシャ語のἄκουσμα〔聴覚による認識〕に由来する)と呼ばれる生徒はカーテン越しに彼の声を聞くことのみが許された。そしてベイルの解釈によれば、視覚的情報を絶つことによって、ピュタゴラスは「聴く」という行為の集中性を高めたのだという。この歴史的逸話にもとづき、すでに1966年にはシェフェールはこの語を使用し、新たな音楽知覚の意義にかんして述べている。彼によれば「マグネットフォンはピュタゴラスの行為がもつ利点を備えている。マグネットフォンは新たな注目すべき現象を呼び起こし、とりわけ新たな知覚の条件を作りだす。(…)われわれが発見したのは、われわれが聴いていると信じていたことの多くは、実際のところただ見ることができたものであり、その文脈によって説明されていた、ということである」。さらにベイルは「アクスマティーク」を「純粋な聴覚の状況」として定義する。この状況においては音楽を聴くさいの注意は、「視覚可能な因果関係や予期可能な楽器の因果関係によって呼び起こされたり、強められたりすることはありえない」のである。 2014年7月初旬にもベイルはケルン大学を訪れ、1曲の初演をふくむ、初期・後期作品の演奏会を2夜にわたっておこなった。会場には全16台のスピーカーが円形状に設置され、ベイル自身が音響監督(Klangregie)としてスピーカーのコントロールにあたった。彼がミキシング・コンソールの席につくと、会場の照明が消え、暗闇のなかでうっすらとスピーカーが彼を取り囲んでいるのが見える。そして前触れもなく、聴衆であるわれわれを包み込むように、音が空間のなかをうごめき始める。この体験を言葉で描写するのは難しい。たんなる空気の振動として自分を取り巻く音は、いつしか形をもった物体として、(比喩ではなく実際に)空間のなかを縦横無尽に移動する。私たちは音楽を聴く場合、ふつう、その音高(あるいはその連続としての旋律)を何よりも第一に知覚する。しかしこの暗闇のなかで「聴く」のは、音の「速度」や「形態」、「力」であり、私たちがいまだ知ることのない音の姿なのである。
[caption id="attachment_3987" align="alignnone" width="353"] 演奏会プログラム[/caption]
演奏会プログラム[/caption]
すでに述べたように私はさいわいいま音響スタジオにいるから、もういちどそこで上演された曲をひとつ聴いてみよう。1979年の《騒音の終端(La fin du bruit)》では、まず水晶を切り裂くような(としか形容することのできない)電子音が頭上をゆっくりと旋回する。その音響はきわめて洗練されていて、空間のなかで一種の実態をもっているようにすら思える。そしてその裏では低音でゆっくりとノイズのような騒音が保続音のように鳴り響き、しだいにその騒音は前景へと現れる。その騒音は市外の道路や蒸気機関車の音のようにも聞こえるのだが、はっきりとその音の由来をつかむことはできない。そしてふたたびこの騒音は冒頭の電子音と混ざり合う……。ベイル自身は自作について次のように述べている。「私は騒音の境界線を示そうと思います。すなわちそれは、堅固な素材の終端であり、泡でできた周縁なのです」。人工的に彫琢された揺れ動く音の塊は、どこか耳に馴染みのある騒音とのあいだをシームレスに揺れ動き、いま聴いている音がいったい何であるかを容易につかませない。そして音楽が鳴り止み、スピーカーが振動を止めたとき、それは白昼夢のように空間のどこかへと消えていくのである。あるいは2011〜12年に作曲された《転位(Déplacements)》では、パルスのような音の珠がなだれるようにして落ちてくる。その音はいったん鳴り響いたが最後、記憶のなかに確固として捕まえることができないように思える。けれどもその音はうっすらと影のように記憶のなかに貼りつき、新たに紡ぎ出される音と結びつき、そしてふたたび消えていく。 ベイルの作品に共通しているのは、電子音であれ録音された具体音であれ、その音がつねに細部にわたって洗練されていることだろう。シェフェールのミュージック・コンクレートの伝統を多分に引き継ぐ彼の楽曲には、電子音のみならず市街の喧騒や機械的な騒音の録音が同時に使用されるが、それらはすべていちどその文脈から切り離され再創造される。そしてそれは複数のスピーカーへと割り当てられ、独自の空間を作りだす。スピーカーに囲まれた空間のなかで、その音はまったく新たな形態を獲得するのである。私たちはかつて「文脈」をとおして「音」を聴いていた。しかしベイルの場合、むしろ「音」そのものをとおして架空の「文脈」を聴いているような錯覚に陥る。たとえば彼の楽曲にしばしば現れる「扉の閉まる音」や「水の音」は―それがどこに存在するのか、あるいは本当に存在するものなのかを知るよしはないが―、なんらかの言語的な意味をもった実体として、楽曲全体に一種の物語性を与えているように思える。 もっともベイルの音楽を聴く難しさについても、ここで告白しておかなければならないだろう。彼の音楽はその時間の経緯とともに、まさに泡のように消えてしまうのだ。いったん音が過ぎ去るや否や(それがかつて聴くことのなかった音の姿であるだけに)、その音をふたたび脳裏に浮かび上がらせることは難しい。彼の音楽を思いだそうとするとき、私にはその「音」そのものよりも、多くの場合、たとえば頭上できしむ何かがいまにも自身のうえに落ちてきそうな緊張感といった身体的な感覚のほうが先に蘇る。さらにその音は「オーボエのなだらかな上昇する音階」といった客観的な描写を許さない。彼の音楽の音は「~のような」「~を思い起こさせる」といった主観的・個人的な記述によってのみ初めて言語化することができる。私がいままさに音響スタジオのなかで必死に試みているように、音そのものをいったん内面へと取り込み、自身を音楽が作りだす文脈と一体化させることで、初めてその姿をつかむことができるように思える。その「音」そのものへの孤独な問いかけは、たんなる空気の振動の向こう側に「隻手音」を聴こうとする試みと似ていなくもない。 音響技術の発達は、音というつかの間の現象を固定し、あたかも姿形をもつ物体のように扱うことを可能とした。そしてベイルはあらゆる文脈から切り離された音でもって、スピーカー(あるいは空気の振動)の彼岸に新たに文脈を再創造する。彼の音はつねに、まだ聴き知らぬものに照準を合わせており、既存の文脈に収斂することはない。ベイルはその音楽聴について次のように述べている。「まさにこの世界はその幼少期にあるのです。なぜなら私たちはまだ、聴くことがどのように機能するかを学んでいる最中なのですから。アクスマティークは『聴くことの知覚』として現れるのです」。新たな音楽聴の状況を前にして、私たちはまず「聴くこと」を学ばなければならない。そしてスピーカーというカーテンの裏側で鳴り響く彼の音楽を聴くことは、まさに自身が聴いているものは何であるのかをつねに問い続けることのなかにあるのかもしれない。