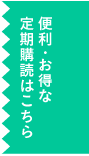誰もが知る大作曲家、ベートーヴェン。その作曲家の魅力を2016年11月に刊行された思想誌『nyx(ニュクス)』第3号が特集しています。なぜ、思想誌でベートーヴェンなのか。音楽にとどまらない魅力、またそこから改めて照射される作品のすばらしさについての論稿が掲載されています。今回は、哲学・倫理学を専門に研究しつつ、音楽評論活動も本格的に行っている若手研究者の多田圭介さんに、その内容を紹介・論評していただきました。

PROFILE
多田圭介
1975年生まれ。北海道大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。専門は、哲学・倫理学、音楽評論。論文は、「田辺元の自由論―弁証法的自由の展開をめぐって」(『哲学の探求』第43号、2016年)他。また、『MPCLand』へのレビュー執筆の他、曲目解説等多数。藤女子大学講師、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員。
 『nyx 第3号』(発行:堀之内出版)
2015年に堀之内出版によって創刊された新思想誌『nyx(ニュクス)』において音楽の特集が組まれた。特集のタイトルは「なぜベートーヴェンか:音と思想が交差する音楽家」である。このタイトルは二重の意味に解しうる。一つは思想誌でなぜ音楽が論じられるのか。二つは数ある音楽のなかでなぜベートーヴェンなのか。個々の論稿をご紹介する前に、この二重の問いについて簡潔に解題してみよう。
リベラル・アーツとしての音楽を、
市民レベルで復権したベートーヴェン
音楽が嫌いという人はいるだろうか。筆者は会ったことがない。音楽は、過酷さに満ちた現実から、あるいは、労働の労苦からの解放と癒しをもたらしてくれるからだろう。この意味での音楽には効用・休息として価値がある。しかし、同時に音楽はギリシャ以来、苦難に満ちていながらも生きるに値する善き生への道しるべとしてリベラルアーツの一役を担ってきた。この意味での音楽には効用を超えた価値が見出される。人格の陶冶、人間性の完成への秩序である。しかし、思想史を紐解くと、この「余暇の楽しみ」と「人格の陶冶」という音楽が持つ両側面は分離していなかった。例えば、アリストテレス。アリストテレスにとって「余暇(閑暇=スコレー)」とは、無為に過ごされる空き時間ではなく、「それ自身のために為される活動」である。余暇とは仕事の空き時間の気晴らしなのではなく、人間にとって最高の活動、真実の時間なのである。人格の完成が目指す「自由」や「幸福」は、むしろ「余暇」に依存する。アリストテレスでは人間の究極目的は閑暇において経験される「時間」にこそある。中世に目を転じてみよう。13世紀の大哲学者、トマス・アクィナスは様々な学問知を、人間がこの地上で到達しうる究極目的への秩序のうちに再編した。そこでは音楽を含むリベラル・アーツ教育は、幸福をよりよく享受しうるための準備学習だったのである。こうして西洋では、快楽や効用としてのみならず、人格を陶冶する教育的役割が音楽に与えられてきた。
思想誌でなぜ音楽かという問いの背景はこのくらいで十分だろう。次になぜベートーヴェンなのかについて。ベートーヴェンが活躍した手前の時代、音楽史で言えばバロックから古典派の時代、上述の二側面は分離していた。芸術音楽は王侯貴族や教会の独占物であってそれを市民が耳にしえる機会はなかったであろう。わずかにバッハがコレギウム・ムジクムを喫茶店で行っていた程度で、サロン音楽もオペラも市民には手が届かなかったはずだ。しかし啓蒙期以降、近代的な「個人」という意識が生じた時期に、市民と貴族の垣根を越えて音楽が親しまれるようになった。そのことと、この時期にベートーヴェンの音楽を特徴づける「ソナタ形式」が成立したことは偶然の一致ではない。「ソナタ形式」とはそもそもベートーヴェンの作品を研究するなかでマルクス(Adolf Bernhard Marx)が提唱した概念である。形式は見取り図であり標識である。自分がいまどこにいるのかを確認するための地図である。特別に教育を受けた貴族や特権階級から市民に音楽が解放された時代にあって、誰もが芸術音楽を享受できるために「地図」が必要だったのである。そして、ベートーヴェンこそは、その「地図」の形式性を表現にまで高めることによって、人間が理想へと向けて自己を陶冶するリベラル・アーツとしての音楽を、市民レベルで復権した音楽家なのだ。思想誌で音楽が扱われること、とりわけベートーヴェンに着目されること、どちらにも十分な理由がある。
なぜベートーヴェンが重要なのか
特集は、本特集の主幹を務めた岡田安樹浩が聞き手となった野平一郎のインタビュー(以下「野平インタビュー」と略)を冒頭に、続けて5本の論文が収録されている。新進気鋭からベテランまでの音楽学者が、ベートーヴェンが見せる多様な外見をそれぞれの視野から表現している。興味深いことに、主幹の岡田が聞き手を務めたこともあってか、野平インタビューは、それぞれの論稿による問題提起を先取りして示す内容となっている。まずそのポイントを紹介し、それに従って個々の論稿を検討する。
野平インタビューでは、野平とベートーヴェンとの出会い、ベートーヴェンに集中的に取り組むようになった経緯が紹介され、なぜベートーヴェンが重要なのかについて簡潔に問題提起されている。筆者が重要と感じた点をいくつかに絞ってみよう。まず1点目。ベートーヴェンが「音響の作曲家」(183頁)であること。どういうことか。ベートーヴェン以前の作曲家にとって、どの楽器を使うか、あるいはどの楽器にどの楽器を重ねるか、という問題は最重要なことではなかった。野平が述べるように「オルガンでやっていたものをチェンバロでやろうと、オーボエでやろうと」(185頁)そんなことで音楽は壊れないという感覚が強かった。しかしベートーヴェンにおいては、楽器の固有の「響き」が音楽を構成する要素のなかで中核を占めるようになったのである。これは、「個人」という意識の成立とともに作品も個人の「所有」であるという自覚を強めた。オリジナルを重視する現代人の一般的感覚に近づくきっかけとなったであろう。この意味については越懸澤論文を紹介する際に立ち返ろう。2点目。その固有の響き、言い換えれば「音色」(186頁)。それによって、何が表現されたか。「不可逆な時間」(同)である。ベートーヴェンこそは不可逆な時間へ舵を切ったのである。例えば、ハイドンの音楽は第一楽章において主題が再現しても、それは調性の面から言っても円環をなしている。つまりスタート地点へ帰ってきて閉じる。後続する楽章はオマケである(例外はあるが)。それに対してベートーヴェンでは、第五交響曲に見られるように終楽章へ向けて音楽は螺旋を描いて上昇する。結論は終楽章にあり、モチーフはそこに収斂する。第二楽章のあのファンファーレが終楽章のハ長調を刻印していることを思い起こされたい。さらに、緩徐楽章ながら輝きだすようなTp.が使用されていることに1点目の論点、「響き」の固有性がいかに作品を構成しているかが見て取れよう。そして3点目「多様性」(192頁)の解放。上述のような要素が強いゆえにベートーヴェンの音楽は、理解することを要求する。聴いて心地よいというに終わらない。彼が残した楽譜が後世どう解釈されたか、その多様性を持った記憶が演奏し作曲する現代の我々に無意識に忍び込んでくる。現代の音楽家にとってその意味で「影の存在」(同)となっている。以上、野平の言葉から、「音響の作曲家」、「不可逆の時間」、「多様性の解放」、という3つの論点を取りだすことができる。
リベラル・アーツが軽んじられる現代において、
人間の本質に意識を向ける意義深い論考群
次に沼口隆による論文「ベートーヴェン研究の現状」をご紹介しよう。野平はベートーヴェンが音楽学の中核に据えられることの必然性を説いた。それに対して沼口は現代の音楽学におけるベートーヴェン研究の状況に広範に目を配りつつ、ベートーヴェン中心からの脱却こそ必要とする。沼口は音楽学という分野の方法論の弱さ、学問分野の自己理解が未成立であることを述べる。しかし「なぜベートーヴェンなのか」(199頁)という問いかけを通してますますベートーヴェンが焦点とならざるをえない研究の現状を正視し、この事態に批判的に取り組むことを要請する。また、英米圏においてスケッチ研究が有効に機能している現状が紹介されている。しかし沼口は「解釈」とは演奏行為をも意味することを考慮するとき解釈の解釈という重層的な状況が生じるゆえにスケッチ研究の一面性に注意喚起している。まさに音楽学の方法論に関わる。筆者としては、野平の「音響の作曲家」という指摘にあったようにベートーヴェンが響きの作曲家であったゆえに、スケッチ研究は同時にいかなる楽器に指定されたか、それはいかなる響きを要求しているのか、これらを総合的に考察するソルフェージュ的な聴取力も研究の方法として重視したいところだ。「複数の解釈を許容」しつつも「あるべき解釈を真摯に追求する」(207頁)ことこそが肝要であると結論されていることは「多様性の解放」の本質としてまことに正論であろう。
岡田安樹浩による「逡巡するベートーヴェン:第五交響曲の創作過程における楽章間接続の試み」では、沼口によって示唆されたスケッチ研究の成果が披露されている。近年のスケッチ研究によれば、第五交響曲は第三と第四楽章の間だけでなく、第二と第三楽章の間の接続をも試みられていたという。ベートーヴェンは晩年に楽章間を切れ目なく接続しそれによって規模を圧縮する傾向が強くなったが、第五交響曲にこそその発端が見られるというのが最大の論点だ。野平の述べる「不可逆性の時間」である。第五交響曲では四つの楽章を通してハ短調からハ長調へ移行したが、最後のピアノソナタ、op.111では二つの楽章に圧縮され夾雑物を排除した純粋な形でそれが達成されている。そこからもこの論点は首肯できる。筆者としては、そこからop.127以降の後期弦楽四重奏曲への展開をどう解しているか、著者に質問をしてみたい。
次に越懸澤麻衣による論文「ベートーヴェンのピアノ協奏曲再考:19世紀出版譜からみる当時の響き」。越懸澤論文では2015年に完結したブライトコプフ版のピアノ協奏曲全集の校訂を通して、作曲された当時いかなる形態で演奏されていたのかが考察されている。ブライトコプフ新版には、トゥッティ部分のピアノ譜に通奏低音(バス音と数字)が記された。これについて越懸澤は校訂に使用された資料を詳細に検討し、ベートーヴェンのピアノ協奏曲は、当時、弦楽合奏をはじめ様々な編成によって演奏されていたこと、必要に応じて通奏低音も演奏されていたことが結論される。この論点は、通俗的音楽史における、「古典派=通奏低音からの脱却」という一般的図式に疑問を投げかけるという点で大きな意味がある。他方で筆者の関心からは、野平インタビューの「音響の作曲家」、「不可逆の時間」、つまり響きのオリジナリティーについての見解を伺いたい。交響曲第三番「英雄」の最終和音は変ホ長調の主和音であるが、最高音は2nd.FlのB♭である。にもかかわらず、鳴った音はEsに聴こえる。FlのB♭はEsの倍音列上の音でEsを豊かに響かせるために書かれているのだ。和声上の配置ではない。野平が述べるようにベートーヴェンは「ぶつかり具合もすべて検証しながら」(189頁)音を配置しているのだ。同じように、ピアノ協奏曲でも、この重ね方でなければ、という確固たる信念もあったはずである。この点はどう考えられるか。著者に尋ねてみたい。
池上純一による論文は「思索する音楽:ベートーヴェンとドイツ思想」と題された。「音楽とは精神の具現化である」とはベートーヴェン自身の言葉である。ドイツ思想において音楽は、カントやゲーテが「感覚の戯れ」として諸芸術の最下位に位置付けたことを除けば、概して精神を陶冶し、やがては「名状しがたいものを開示する」(248頁)右肩上がりの時間経験において思考された。ブロッホが述べるように「既知の全体性へと「円く仕上がった歌」ではなく未知の地平へと「開かれた歌」」(257頁)なのだ。池上論文で興味深いのは、こうした理想と現実、真と善のような二元対立世界把握にニーチェが異を唱えたこと、また、ベートーヴェンにその抑圧を見出していたことが論じられていることだ。池上によれば、「善悪の彼岸」に開ける反ベートーヴェン的な音楽はイメージを結ぶことなく狂気へ至ったという。しかし、他方でアドルノはベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲に、二元対立的な和解を拒絶する「疎外の表現」(261頁)を見出しているとも述べる。この二つの視野はたんにベートーヴェンの音楽のどこに焦点を合わせるかによる違いなのか。それとも音楽とはいかなる営みであるかについての洞察の違いがあるのか。ツヴァイクは、芸術には「前進する闘士たちを民謡や呪文によって死の感激に燃え上がらせる義務があると信じた」。このような根底にある芸術観の差異から解釈の是非を論じることは可能であろうか。
最後は三重野清顕による「アルノルト・シェーリングのベートーヴェン解釈-「古楽」運動の一源泉をめぐる考察」。ベートーヴェンは19世紀のハンスリック以来、絶対音楽の嚆矢と看做された。その一方で、シェーリングはそれを徹底して「文学の象徴」と解した。音楽は音楽の外の「何か」を象徴しているというわけだ。三重野論文の結論は、シェーリングのこの考えがナイーブにすぎることを認めた上で、シェーリングの意図を掬いあげようとする。「解釈は、創造を後追いするような二次的な営みにとどまらず、それ自身創造的な営みでなければならない」(280頁)。すなわち、解釈とは創造へと積極的に参与すること、すなわち象徴を生みだすことに意味がある。野平と沼口の論稿を振りかえり述べるなら、閉じない螺旋の上昇へと自ら参与することに解釈の本質は存すると言えるかもしれない。シェーリングの解釈は、唯一の解釈ではありえないが、しかし、解釈という行為の本質をある面で正当に射抜いているのではないかというのが三重野の主張だ。象徴を生みだすことに創造の本質はあるとすると、その象徴は新たな象徴が創造される際の基準となろう。20世紀前半の音楽評論家P.ベッカーは、音楽のなかに社会(音楽の外)を見るのみならず、音楽が社会を批判し相互に刷新しあう力を認めていた。アドルノが引き継いだ論点である。芸術は批評であり、批評は芸術なのだ。筆者の関心からは、こうした論点とシェーリングの象徴論との対決を期待したくなる。それゆえに三重野論文は、なぜ思想誌でベートーヴェンなのか、という問いを多様に展開させる萌芽を宿している。音楽とはいかなる営みなのか、また音楽を営む人間とはいかなる存在なのか、これらの問いが再燃せざるをえない。まさに特集を締めくくるに相応しい論稿といえよう。芸術を問うことは、社会と社会を構成する人間を問うことである。リベラル・アーツが軽んじられる現代において、その問題意識はますます焦点を結びにくくなりつつある。そんななか音楽と時間、そして人間の本質に意識を向けさせてくれる本特集には啓発されるものがあった。
時間とは何かと問われて「音楽なのよ!」と答えたのはミヒャエル・エンデの『モモ』である。それは、信じること、知解すること、愛すること、これらの働きそのものである「心」の活動を示唆する。ベートーヴェンにおいてはそれが、理想をめがけて螺旋を描いて上昇する「意志」として現れた。しかし、現代の私たちはベートーヴェンのあずかり知らない世界を生きている。市民殲滅戦となった戦争、移民が移住してくる国家、その国家も利害を代表する一人の売り手であるかのような経済。いまわれわれはベートーヴェンに何を聴き取るか。かつてユートピアを信じることができた時代があったことに、あたかも歴史小説を読むかのように接するのか。あるいは、かつてとは同じ文脈では語りえないというまさにそこになお意味を見出すか。つまり、螺旋を描いて上昇するかは未知ではあれ、やはり理想を描くというあり方に人間の本質を認めるかどうか。筆者は後者であるが、ショスタコーヴィチの情緒が欠乏した音楽やマーラーの救いを求めて逡巡する音楽に多くの聴衆がリアリティを感じている現在の状況では、いささか楽観的にすぎるであろうか。
『nyx 第3号』(発行:堀之内出版)
2015年に堀之内出版によって創刊された新思想誌『nyx(ニュクス)』において音楽の特集が組まれた。特集のタイトルは「なぜベートーヴェンか:音と思想が交差する音楽家」である。このタイトルは二重の意味に解しうる。一つは思想誌でなぜ音楽が論じられるのか。二つは数ある音楽のなかでなぜベートーヴェンなのか。個々の論稿をご紹介する前に、この二重の問いについて簡潔に解題してみよう。
リベラル・アーツとしての音楽を、
市民レベルで復権したベートーヴェン
音楽が嫌いという人はいるだろうか。筆者は会ったことがない。音楽は、過酷さに満ちた現実から、あるいは、労働の労苦からの解放と癒しをもたらしてくれるからだろう。この意味での音楽には効用・休息として価値がある。しかし、同時に音楽はギリシャ以来、苦難に満ちていながらも生きるに値する善き生への道しるべとしてリベラルアーツの一役を担ってきた。この意味での音楽には効用を超えた価値が見出される。人格の陶冶、人間性の完成への秩序である。しかし、思想史を紐解くと、この「余暇の楽しみ」と「人格の陶冶」という音楽が持つ両側面は分離していなかった。例えば、アリストテレス。アリストテレスにとって「余暇(閑暇=スコレー)」とは、無為に過ごされる空き時間ではなく、「それ自身のために為される活動」である。余暇とは仕事の空き時間の気晴らしなのではなく、人間にとって最高の活動、真実の時間なのである。人格の完成が目指す「自由」や「幸福」は、むしろ「余暇」に依存する。アリストテレスでは人間の究極目的は閑暇において経験される「時間」にこそある。中世に目を転じてみよう。13世紀の大哲学者、トマス・アクィナスは様々な学問知を、人間がこの地上で到達しうる究極目的への秩序のうちに再編した。そこでは音楽を含むリベラル・アーツ教育は、幸福をよりよく享受しうるための準備学習だったのである。こうして西洋では、快楽や効用としてのみならず、人格を陶冶する教育的役割が音楽に与えられてきた。
思想誌でなぜ音楽かという問いの背景はこのくらいで十分だろう。次になぜベートーヴェンなのかについて。ベートーヴェンが活躍した手前の時代、音楽史で言えばバロックから古典派の時代、上述の二側面は分離していた。芸術音楽は王侯貴族や教会の独占物であってそれを市民が耳にしえる機会はなかったであろう。わずかにバッハがコレギウム・ムジクムを喫茶店で行っていた程度で、サロン音楽もオペラも市民には手が届かなかったはずだ。しかし啓蒙期以降、近代的な「個人」という意識が生じた時期に、市民と貴族の垣根を越えて音楽が親しまれるようになった。そのことと、この時期にベートーヴェンの音楽を特徴づける「ソナタ形式」が成立したことは偶然の一致ではない。「ソナタ形式」とはそもそもベートーヴェンの作品を研究するなかでマルクス(Adolf Bernhard Marx)が提唱した概念である。形式は見取り図であり標識である。自分がいまどこにいるのかを確認するための地図である。特別に教育を受けた貴族や特権階級から市民に音楽が解放された時代にあって、誰もが芸術音楽を享受できるために「地図」が必要だったのである。そして、ベートーヴェンこそは、その「地図」の形式性を表現にまで高めることによって、人間が理想へと向けて自己を陶冶するリベラル・アーツとしての音楽を、市民レベルで復権した音楽家なのだ。思想誌で音楽が扱われること、とりわけベートーヴェンに着目されること、どちらにも十分な理由がある。
なぜベートーヴェンが重要なのか
特集は、本特集の主幹を務めた岡田安樹浩が聞き手となった野平一郎のインタビュー(以下「野平インタビュー」と略)を冒頭に、続けて5本の論文が収録されている。新進気鋭からベテランまでの音楽学者が、ベートーヴェンが見せる多様な外見をそれぞれの視野から表現している。興味深いことに、主幹の岡田が聞き手を務めたこともあってか、野平インタビューは、それぞれの論稿による問題提起を先取りして示す内容となっている。まずそのポイントを紹介し、それに従って個々の論稿を検討する。
野平インタビューでは、野平とベートーヴェンとの出会い、ベートーヴェンに集中的に取り組むようになった経緯が紹介され、なぜベートーヴェンが重要なのかについて簡潔に問題提起されている。筆者が重要と感じた点をいくつかに絞ってみよう。まず1点目。ベートーヴェンが「音響の作曲家」(183頁)であること。どういうことか。ベートーヴェン以前の作曲家にとって、どの楽器を使うか、あるいはどの楽器にどの楽器を重ねるか、という問題は最重要なことではなかった。野平が述べるように「オルガンでやっていたものをチェンバロでやろうと、オーボエでやろうと」(185頁)そんなことで音楽は壊れないという感覚が強かった。しかしベートーヴェンにおいては、楽器の固有の「響き」が音楽を構成する要素のなかで中核を占めるようになったのである。これは、「個人」という意識の成立とともに作品も個人の「所有」であるという自覚を強めた。オリジナルを重視する現代人の一般的感覚に近づくきっかけとなったであろう。この意味については越懸澤論文を紹介する際に立ち返ろう。2点目。その固有の響き、言い換えれば「音色」(186頁)。それによって、何が表現されたか。「不可逆な時間」(同)である。ベートーヴェンこそは不可逆な時間へ舵を切ったのである。例えば、ハイドンの音楽は第一楽章において主題が再現しても、それは調性の面から言っても円環をなしている。つまりスタート地点へ帰ってきて閉じる。後続する楽章はオマケである(例外はあるが)。それに対してベートーヴェンでは、第五交響曲に見られるように終楽章へ向けて音楽は螺旋を描いて上昇する。結論は終楽章にあり、モチーフはそこに収斂する。第二楽章のあのファンファーレが終楽章のハ長調を刻印していることを思い起こされたい。さらに、緩徐楽章ながら輝きだすようなTp.が使用されていることに1点目の論点、「響き」の固有性がいかに作品を構成しているかが見て取れよう。そして3点目「多様性」(192頁)の解放。上述のような要素が強いゆえにベートーヴェンの音楽は、理解することを要求する。聴いて心地よいというに終わらない。彼が残した楽譜が後世どう解釈されたか、その多様性を持った記憶が演奏し作曲する現代の我々に無意識に忍び込んでくる。現代の音楽家にとってその意味で「影の存在」(同)となっている。以上、野平の言葉から、「音響の作曲家」、「不可逆の時間」、「多様性の解放」、という3つの論点を取りだすことができる。
リベラル・アーツが軽んじられる現代において、
人間の本質に意識を向ける意義深い論考群
次に沼口隆による論文「ベートーヴェン研究の現状」をご紹介しよう。野平はベートーヴェンが音楽学の中核に据えられることの必然性を説いた。それに対して沼口は現代の音楽学におけるベートーヴェン研究の状況に広範に目を配りつつ、ベートーヴェン中心からの脱却こそ必要とする。沼口は音楽学という分野の方法論の弱さ、学問分野の自己理解が未成立であることを述べる。しかし「なぜベートーヴェンなのか」(199頁)という問いかけを通してますますベートーヴェンが焦点とならざるをえない研究の現状を正視し、この事態に批判的に取り組むことを要請する。また、英米圏においてスケッチ研究が有効に機能している現状が紹介されている。しかし沼口は「解釈」とは演奏行為をも意味することを考慮するとき解釈の解釈という重層的な状況が生じるゆえにスケッチ研究の一面性に注意喚起している。まさに音楽学の方法論に関わる。筆者としては、野平の「音響の作曲家」という指摘にあったようにベートーヴェンが響きの作曲家であったゆえに、スケッチ研究は同時にいかなる楽器に指定されたか、それはいかなる響きを要求しているのか、これらを総合的に考察するソルフェージュ的な聴取力も研究の方法として重視したいところだ。「複数の解釈を許容」しつつも「あるべき解釈を真摯に追求する」(207頁)ことこそが肝要であると結論されていることは「多様性の解放」の本質としてまことに正論であろう。
岡田安樹浩による「逡巡するベートーヴェン:第五交響曲の創作過程における楽章間接続の試み」では、沼口によって示唆されたスケッチ研究の成果が披露されている。近年のスケッチ研究によれば、第五交響曲は第三と第四楽章の間だけでなく、第二と第三楽章の間の接続をも試みられていたという。ベートーヴェンは晩年に楽章間を切れ目なく接続しそれによって規模を圧縮する傾向が強くなったが、第五交響曲にこそその発端が見られるというのが最大の論点だ。野平の述べる「不可逆性の時間」である。第五交響曲では四つの楽章を通してハ短調からハ長調へ移行したが、最後のピアノソナタ、op.111では二つの楽章に圧縮され夾雑物を排除した純粋な形でそれが達成されている。そこからもこの論点は首肯できる。筆者としては、そこからop.127以降の後期弦楽四重奏曲への展開をどう解しているか、著者に質問をしてみたい。
次に越懸澤麻衣による論文「ベートーヴェンのピアノ協奏曲再考:19世紀出版譜からみる当時の響き」。越懸澤論文では2015年に完結したブライトコプフ版のピアノ協奏曲全集の校訂を通して、作曲された当時いかなる形態で演奏されていたのかが考察されている。ブライトコプフ新版には、トゥッティ部分のピアノ譜に通奏低音(バス音と数字)が記された。これについて越懸澤は校訂に使用された資料を詳細に検討し、ベートーヴェンのピアノ協奏曲は、当時、弦楽合奏をはじめ様々な編成によって演奏されていたこと、必要に応じて通奏低音も演奏されていたことが結論される。この論点は、通俗的音楽史における、「古典派=通奏低音からの脱却」という一般的図式に疑問を投げかけるという点で大きな意味がある。他方で筆者の関心からは、野平インタビューの「音響の作曲家」、「不可逆の時間」、つまり響きのオリジナリティーについての見解を伺いたい。交響曲第三番「英雄」の最終和音は変ホ長調の主和音であるが、最高音は2nd.FlのB♭である。にもかかわらず、鳴った音はEsに聴こえる。FlのB♭はEsの倍音列上の音でEsを豊かに響かせるために書かれているのだ。和声上の配置ではない。野平が述べるようにベートーヴェンは「ぶつかり具合もすべて検証しながら」(189頁)音を配置しているのだ。同じように、ピアノ協奏曲でも、この重ね方でなければ、という確固たる信念もあったはずである。この点はどう考えられるか。著者に尋ねてみたい。
池上純一による論文は「思索する音楽:ベートーヴェンとドイツ思想」と題された。「音楽とは精神の具現化である」とはベートーヴェン自身の言葉である。ドイツ思想において音楽は、カントやゲーテが「感覚の戯れ」として諸芸術の最下位に位置付けたことを除けば、概して精神を陶冶し、やがては「名状しがたいものを開示する」(248頁)右肩上がりの時間経験において思考された。ブロッホが述べるように「既知の全体性へと「円く仕上がった歌」ではなく未知の地平へと「開かれた歌」」(257頁)なのだ。池上論文で興味深いのは、こうした理想と現実、真と善のような二元対立世界把握にニーチェが異を唱えたこと、また、ベートーヴェンにその抑圧を見出していたことが論じられていることだ。池上によれば、「善悪の彼岸」に開ける反ベートーヴェン的な音楽はイメージを結ぶことなく狂気へ至ったという。しかし、他方でアドルノはベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲に、二元対立的な和解を拒絶する「疎外の表現」(261頁)を見出しているとも述べる。この二つの視野はたんにベートーヴェンの音楽のどこに焦点を合わせるかによる違いなのか。それとも音楽とはいかなる営みであるかについての洞察の違いがあるのか。ツヴァイクは、芸術には「前進する闘士たちを民謡や呪文によって死の感激に燃え上がらせる義務があると信じた」。このような根底にある芸術観の差異から解釈の是非を論じることは可能であろうか。
最後は三重野清顕による「アルノルト・シェーリングのベートーヴェン解釈-「古楽」運動の一源泉をめぐる考察」。ベートーヴェンは19世紀のハンスリック以来、絶対音楽の嚆矢と看做された。その一方で、シェーリングはそれを徹底して「文学の象徴」と解した。音楽は音楽の外の「何か」を象徴しているというわけだ。三重野論文の結論は、シェーリングのこの考えがナイーブにすぎることを認めた上で、シェーリングの意図を掬いあげようとする。「解釈は、創造を後追いするような二次的な営みにとどまらず、それ自身創造的な営みでなければならない」(280頁)。すなわち、解釈とは創造へと積極的に参与すること、すなわち象徴を生みだすことに意味がある。野平と沼口の論稿を振りかえり述べるなら、閉じない螺旋の上昇へと自ら参与することに解釈の本質は存すると言えるかもしれない。シェーリングの解釈は、唯一の解釈ではありえないが、しかし、解釈という行為の本質をある面で正当に射抜いているのではないかというのが三重野の主張だ。象徴を生みだすことに創造の本質はあるとすると、その象徴は新たな象徴が創造される際の基準となろう。20世紀前半の音楽評論家P.ベッカーは、音楽のなかに社会(音楽の外)を見るのみならず、音楽が社会を批判し相互に刷新しあう力を認めていた。アドルノが引き継いだ論点である。芸術は批評であり、批評は芸術なのだ。筆者の関心からは、こうした論点とシェーリングの象徴論との対決を期待したくなる。それゆえに三重野論文は、なぜ思想誌でベートーヴェンなのか、という問いを多様に展開させる萌芽を宿している。音楽とはいかなる営みなのか、また音楽を営む人間とはいかなる存在なのか、これらの問いが再燃せざるをえない。まさに特集を締めくくるに相応しい論稿といえよう。芸術を問うことは、社会と社会を構成する人間を問うことである。リベラル・アーツが軽んじられる現代において、その問題意識はますます焦点を結びにくくなりつつある。そんななか音楽と時間、そして人間の本質に意識を向けさせてくれる本特集には啓発されるものがあった。
時間とは何かと問われて「音楽なのよ!」と答えたのはミヒャエル・エンデの『モモ』である。それは、信じること、知解すること、愛すること、これらの働きそのものである「心」の活動を示唆する。ベートーヴェンにおいてはそれが、理想をめがけて螺旋を描いて上昇する「意志」として現れた。しかし、現代の私たちはベートーヴェンのあずかり知らない世界を生きている。市民殲滅戦となった戦争、移民が移住してくる国家、その国家も利害を代表する一人の売り手であるかのような経済。いまわれわれはベートーヴェンに何を聴き取るか。かつてユートピアを信じることができた時代があったことに、あたかも歴史小説を読むかのように接するのか。あるいは、かつてとは同じ文脈では語りえないというまさにそこになお意味を見出すか。つまり、螺旋を描いて上昇するかは未知ではあれ、やはり理想を描くというあり方に人間の本質を認めるかどうか。筆者は後者であるが、ショスタコーヴィチの情緒が欠乏した音楽やマーラーの救いを求めて逡巡する音楽に多くの聴衆がリアリティを感じている現在の状況では、いささか楽観的にすぎるであろうか。