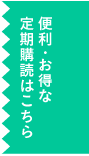プロフィールには「ワールド・ミュージックと実験音楽系の仕事が中心」とありますが、アイドルから現代音楽まで、文字通り古今東西ありとあらゆる音楽を長年にわたって聴きまくり続けている音楽評論家の松山晋也さんによる新しいコーナーがスタートします。題して「INTERVIEWS」。内外のミュージシャンたちへのインタビュー取材の中から、音楽専門誌など他のメディアで紹介しきれない素材をこの「アルテス」で披露していきます。

PROFILE
松山晋也
音楽評論家
1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。『ミュージック・マガジン』他の音楽専門誌や朝日新聞などでレギュラー執筆。時々、ラジオやイヴェント等での解説、選曲なども。ワールド・ミュージックと実験音楽系の仕事が中心。著書『めかくしプレイ~Blind Jukebox』、編著書『プログレのパースペクティヴ』のほか数多くの音楽関係のガイドブックやムック類に寄稿している。
「ギャラをちゃんと計算し、キープしながら生活できるんだ(笑)」──ファンファーレ・チョカリーア・インタビュー
90年代以降のワールド・ミュージック・シーンで最も注目を集めた分野の一つはジプシー音楽だった。その象徴がルーマニアのタラフ・ドゥ・ハイドゥークスとファンファーレ・チォカリーアであることに異論を唱える者は、まずいないだろう。前者はヴァイオリンやツィンバロムを中心とする弦楽グループ、後者はブラスバンドとスタイルは異なるが、共に、観光地のレストラン等で演奏されるいわゆる“土産ジプシー音楽”ではない、ノイズまみれ垢まみれの本物のジプシー音楽を演奏し、欧米のリスナーたちにショックを与えた。
[caption id="attachment_2352" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニ村への標識[/caption]
[caption id="attachment_2353" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニ村への標識[/caption]
[caption id="attachment_2353" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニの風景[/caption]
[caption id="attachment_2354" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニの風景[/caption]
[caption id="attachment_2354" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニのメインストリート[/caption]
[caption id="attachment_2355" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニのメインストリート[/caption]
[caption id="attachment_2355" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニの人々[/caption]
[caption id="attachment_2356" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニの人々[/caption]
[caption id="attachment_2356" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニのこどもたち[/caption]
私は2000年にタラフの暮らすクレジャニ村に、そして2005年にチォカリーアの住むゼチェ・プラジーニ村に取材に行ったのだが、何よりも印象深かったのは、両者の雰囲気の違いである。前者は、道も空き地もゴミだらけで荒れ果て、一体どうやって生活しているのか心配になるほど住民のほとんどが日中からブラブラしていた。まあ、イメージ通りといえばそうなのだが。対して、チォカリーアの村は、とても明るかった。貧しさはクレジャニと大差ないのだろうが、とにかく人々の表情が朗らかなのだ。
小さな村にはたった1本のメイン・ストリート(もちろん舗装などされていない)があるだけで、その道をあと1時間ほど東へ車で走ればそこは旧ロシアのモルドヴァ共和国という、まさにルーマニア北東部のはずれの寒村。だが、チォカリーアのメンバーをはじめ、村の誰もが畑を耕したり工場で働いたりと、まっとうな生業についており、クレジャニのように至るところにゴミが散乱してたりもしない。村には、完成間近の小さな教会もあった。チォカリーアのメンバーが音楽活動で稼いだ金を出し合って建てたものだという。公衆電話のある売店兼集会所のような場所が1軒あるだけで他には何もない静かな村だが、けっして寂れてはいない。つまり、この村の人々は、行き当たりばったりのその日暮らしではなく、目標を持ってきちんと生きているのだ。それが、彼らの表情の明るさの理由だと私には感じられた。ファンファーレ・チォカリーアというグループ名の「Ciocǎrlia(現地の発音だとチョクルリーア)」とはルーマニア語で「ひばり」のことだというが、彼らのブラスの音色の輝かしさは、まさに、大空を飛び交うひばりのさえずりと呼ぶにふさわしい。
ゼチェ・プラジーニで、祖父から代々受け継いだ楽器を手に、冠婚葬祭などで演奏していた人々の中からファンファーレ・チォカリーアというグループが生まれたのは1996年のこと。旧東ドイツのライプツィヒで生まれ育ち、映画関係の仕事をしていたヘンリー・エルンストという青年が、たまたま訪れたゼチェ・プラジーニで村のブラスバンドに出会ったのがきっかけだった。彼らの演奏に仰天したヘンリーは、西側の人々にこの感動を伝えたいと思い、選抜メンバーによるグループの結成を提案。西ヨーロッパでの初めてのコンサートでいきなり大成功を収めた彼らは、98年には『Radio Paşcani』でアルバム・デビュー。以後リリースされた9枚のアルバムはすべて商業的にも成功し、2003年には、長編ドキュメンタリー映画『IagBari - Brass on Fire』(邦題「炎のジプシーブラス 〜地図にない村から」。監督はラルフ・マルシャレック)も製作・公開された。
正式なグループ結成から既に18年。その間ずっとチォカリーアは、ジプシー音楽シーンのトップを走り続けてきたわけだが、特筆すべきは、彼らが常に、新しいアイデアを取り入れながら音楽的マンネリを上手に回避してきたことだ。それは、ジプシー音楽界において、かなり珍しいことである。
この夏、フジロックへの参加で来日した彼らに久しぶりにインタヴューした際も、そのあたりを中心に、キャリアを振り返ってもらった。答えてくれたのは、グループ結成以来ずっとプロデューサー/マネジャーを務めてきたヘンリー・エルンストと、トランペット/ヴォーカル担当のチマイ(Costicǎ “Cimai” Trifan)である。
ゼチェ・プラジーニのこどもたち[/caption]
私は2000年にタラフの暮らすクレジャニ村に、そして2005年にチォカリーアの住むゼチェ・プラジーニ村に取材に行ったのだが、何よりも印象深かったのは、両者の雰囲気の違いである。前者は、道も空き地もゴミだらけで荒れ果て、一体どうやって生活しているのか心配になるほど住民のほとんどが日中からブラブラしていた。まあ、イメージ通りといえばそうなのだが。対して、チォカリーアの村は、とても明るかった。貧しさはクレジャニと大差ないのだろうが、とにかく人々の表情が朗らかなのだ。
小さな村にはたった1本のメイン・ストリート(もちろん舗装などされていない)があるだけで、その道をあと1時間ほど東へ車で走ればそこは旧ロシアのモルドヴァ共和国という、まさにルーマニア北東部のはずれの寒村。だが、チォカリーアのメンバーをはじめ、村の誰もが畑を耕したり工場で働いたりと、まっとうな生業についており、クレジャニのように至るところにゴミが散乱してたりもしない。村には、完成間近の小さな教会もあった。チォカリーアのメンバーが音楽活動で稼いだ金を出し合って建てたものだという。公衆電話のある売店兼集会所のような場所が1軒あるだけで他には何もない静かな村だが、けっして寂れてはいない。つまり、この村の人々は、行き当たりばったりのその日暮らしではなく、目標を持ってきちんと生きているのだ。それが、彼らの表情の明るさの理由だと私には感じられた。ファンファーレ・チォカリーアというグループ名の「Ciocǎrlia(現地の発音だとチョクルリーア)」とはルーマニア語で「ひばり」のことだというが、彼らのブラスの音色の輝かしさは、まさに、大空を飛び交うひばりのさえずりと呼ぶにふさわしい。
ゼチェ・プラジーニで、祖父から代々受け継いだ楽器を手に、冠婚葬祭などで演奏していた人々の中からファンファーレ・チォカリーアというグループが生まれたのは1996年のこと。旧東ドイツのライプツィヒで生まれ育ち、映画関係の仕事をしていたヘンリー・エルンストという青年が、たまたま訪れたゼチェ・プラジーニで村のブラスバンドに出会ったのがきっかけだった。彼らの演奏に仰天したヘンリーは、西側の人々にこの感動を伝えたいと思い、選抜メンバーによるグループの結成を提案。西ヨーロッパでの初めてのコンサートでいきなり大成功を収めた彼らは、98年には『Radio Paşcani』でアルバム・デビュー。以後リリースされた9枚のアルバムはすべて商業的にも成功し、2003年には、長編ドキュメンタリー映画『IagBari - Brass on Fire』(邦題「炎のジプシーブラス 〜地図にない村から」。監督はラルフ・マルシャレック)も製作・公開された。
正式なグループ結成から既に18年。その間ずっとチォカリーアは、ジプシー音楽シーンのトップを走り続けてきたわけだが、特筆すべきは、彼らが常に、新しいアイデアを取り入れながら音楽的マンネリを上手に回避してきたことだ。それは、ジプシー音楽界において、かなり珍しいことである。
この夏、フジロックへの参加で来日した彼らに久しぶりにインタヴューした際も、そのあたりを中心に、キャリアを振り返ってもらった。答えてくれたのは、グループ結成以来ずっとプロデューサー/マネジャーを務めてきたヘンリー・エルンストと、トランペット/ヴォーカル担当のチマイ(Costicǎ “Cimai” Trifan)である。
 インタビューに応えてくれた、ヘンリー・エルンスト(左)とチマイ(右)[/caption]
彼らの生活水準は、あれ以来、非常に高くなった。子供たちを高校や大学にまでやれるようになったし、それまでの自分たちの世代とは違う未来を子供たちを通して見ることができるようになったんだ。実際、このチマイだって、あの村で生まれ、一生そこから出ることもなく死んでゆく運命だったと思う。出口のない世界なんだ。だが、この音楽を通じて、彼の人生は大きく変わったし、子供たちの世代に至っては、見える世界もまったく変わってしまった。レヴェルアップしたんだ。こういったことは、音楽そのものとは直接関係ないけど、実際、彼らの頑張りの大きな要因だったと思う。
次に、彼らは本当に頑張る、ハードワーキングなバンドであるということ。ジプシー・ブラスバンドで、彼らほど頑張る連中は他にいないと思う。ツアーがなく地元にいる時も、常に演奏してアンサンブルを磨いているし。そういうのは、他のジプシー・バンドでは、実はなかなか見られないことなんだ。ジプシー・バンドの多くは、誰かに見出され、人気者になり、東京だのニューヨークだのに連れて行かれ、神だのなんだのとほめられることにより、逆に、キャリアの終わりが意外に早く訪れる。しかしこのバンドの連中は、本当に謙虚で、浮かれることなく、素朴な生き方、考え方を変えようとしない。日本にこれてうれしい、とはしゃぐ一方で、とても慎重だ。お金がたくさん入ってくるわけだが、その代償として、しっかり働くことが大切なんだということをちゃんと認識している。ワールド・ミュージックの世界で、2〜3年で消えていってしまう連中がいかに多いかをこの目で見てきた僕からしても、彼らは明らかに違うと思う。
そしてもちろん、彼らの伝統音楽、伝統文化そのものの素晴らしさということ。伝統をきちんと守って生きることの大事さを彼らはよくわかっている。アーティストとして周りから崇め奉られても、自分たちはたまたまブラスをやっており、好きなことをやっていたら周りの人たちもそれを気に入ってくれたんだという流れを彼らはきちんと理解している。去年だけでも、素晴らしいアーティストだと海外で何百回も言われたはずだが、そういう中にあって、うぬぼれるということではなく、自分たちはもっと違うこともやっていいんじゃないか、それが許される高度な音楽性を持っているんじゃないかということに、自分たちでもだんだん気づいてきていると思う。
インタビューに応えてくれた、ヘンリー・エルンスト(左)とチマイ(右)[/caption]
彼らの生活水準は、あれ以来、非常に高くなった。子供たちを高校や大学にまでやれるようになったし、それまでの自分たちの世代とは違う未来を子供たちを通して見ることができるようになったんだ。実際、このチマイだって、あの村で生まれ、一生そこから出ることもなく死んでゆく運命だったと思う。出口のない世界なんだ。だが、この音楽を通じて、彼の人生は大きく変わったし、子供たちの世代に至っては、見える世界もまったく変わってしまった。レヴェルアップしたんだ。こういったことは、音楽そのものとは直接関係ないけど、実際、彼らの頑張りの大きな要因だったと思う。
次に、彼らは本当に頑張る、ハードワーキングなバンドであるということ。ジプシー・ブラスバンドで、彼らほど頑張る連中は他にいないと思う。ツアーがなく地元にいる時も、常に演奏してアンサンブルを磨いているし。そういうのは、他のジプシー・バンドでは、実はなかなか見られないことなんだ。ジプシー・バンドの多くは、誰かに見出され、人気者になり、東京だのニューヨークだのに連れて行かれ、神だのなんだのとほめられることにより、逆に、キャリアの終わりが意外に早く訪れる。しかしこのバンドの連中は、本当に謙虚で、浮かれることなく、素朴な生き方、考え方を変えようとしない。日本にこれてうれしい、とはしゃぐ一方で、とても慎重だ。お金がたくさん入ってくるわけだが、その代償として、しっかり働くことが大切なんだということをちゃんと認識している。ワールド・ミュージックの世界で、2〜3年で消えていってしまう連中がいかに多いかをこの目で見てきた僕からしても、彼らは明らかに違うと思う。
そしてもちろん、彼らの伝統音楽、伝統文化そのものの素晴らしさということ。伝統をきちんと守って生きることの大事さを彼らはよくわかっている。アーティストとして周りから崇め奉られても、自分たちはたまたまブラスをやっており、好きなことをやっていたら周りの人たちもそれを気に入ってくれたんだという流れを彼らはきちんと理解している。去年だけでも、素晴らしいアーティストだと海外で何百回も言われたはずだが、そういう中にあって、うぬぼれるということではなく、自分たちはもっと違うこともやっていいんじゃないか、それが許される高度な音楽性を持っているんじゃないかということに、自分たちでもだんだん気づいてきていると思う。
 モルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがある[/caption]
[caption id="attachment_2358" align="alignleft" width="500"]
モルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがある[/caption]
[caption id="attachment_2358" align="alignleft" width="500"] 楽器は代々受け継がれる[/caption]
[ヘンリー]そのとおりだと思うよ。彼らの場合は、習慣としての労働があるからね。それは、社会主義時代のボルト1本作るのに10人かがりでやるような奇妙な労働であろうとも、昔からずっと続いてきた習慣なんだ。だから今も、朝はちゃんと起きて、工場とか畑とかに行って10時間働き、夕方家に戻ってくる。それとは別に、彼らには、音楽での収入源もあった。チマイは今も工場で働いているんだが、面白いことに、ゼチェ・プラジーニのあるモルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがいる。それは、自分たちの楽しみのためのバンドであり、時々、副次的にお金もついてくる。そこには、自分たちの伝統文化を残してゆこうという意識ももちろんある。一種、義務としてのブラスバンド、みたいな感じかな。子供には自分の楽器を受け継がせるし。多くのジプシー・バンドは、仕事がきたら演奏し、たくさんお金を稼ぎ、2日で使い切ってしまう。将来を考えたお金の使い方などまったくしないんだ。チョカリーアの連中は、ギャラをもらったらちゃんと計算し、キープしながら生活することができるんだ(笑)。
18年間やってきて、たくさん苦労があったはずです。もうダメだ、彼らとは一緒にやれないと思ったことは?
[ヘンリー]もちろんあった。もう語ってもいい頃だろうね。何度も自問したよ。こういうことを続けてていいのか⋯⋯自分の一生をかけていいのか⋯⋯と。これだけ個性豊かな連中と四六時中一緒にいれば、それは当然だろう。メンバー間のつまらない諍いもあるし。たまには僕が大きな声を一声上げて、全員にとくとくと説き、なだめて、問題を収めるという場面もある。結局、大事なのは忍耐だよ。お互いが納得できる妥協点を見つけ、話しあうことだ。あと、音楽ビジネスのダークな部分に直面したりとか。好きだ、楽しい、という情熱だけでやっている頃はいいけど、メンバーの家族も含め、たくさんの人間の生活を担う義務が生じてくると、楽しいだけじゃすまなくなってくる。そういう経済的な面でのプレッシャーから、もうこれ以上前に進めないと思ったことは何度もあった。
結局、ここまでこれたのは、彼らの音楽の素晴らしさ、それにつきると思う。いくら長く続けていても、今でもやるたびに僕には新しい発見があり、楽しめる。昨日もフジロックで、PAをやりながら、こんなこともできるのかという発見があり、そこから新しいアイデアも生まれてきた。そんなことをメンバーたちと話し合うことも楽しい。そういったことが、続けるモティヴェションになっているんだと思う。やっぱり、もう1年やってみよう⋯⋯そんな繰り返しだったよ。
楽器は代々受け継がれる[/caption]
[ヘンリー]そのとおりだと思うよ。彼らの場合は、習慣としての労働があるからね。それは、社会主義時代のボルト1本作るのに10人かがりでやるような奇妙な労働であろうとも、昔からずっと続いてきた習慣なんだ。だから今も、朝はちゃんと起きて、工場とか畑とかに行って10時間働き、夕方家に戻ってくる。それとは別に、彼らには、音楽での収入源もあった。チマイは今も工場で働いているんだが、面白いことに、ゼチェ・プラジーニのあるモルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがいる。それは、自分たちの楽しみのためのバンドであり、時々、副次的にお金もついてくる。そこには、自分たちの伝統文化を残してゆこうという意識ももちろんある。一種、義務としてのブラスバンド、みたいな感じかな。子供には自分の楽器を受け継がせるし。多くのジプシー・バンドは、仕事がきたら演奏し、たくさんお金を稼ぎ、2日で使い切ってしまう。将来を考えたお金の使い方などまったくしないんだ。チョカリーアの連中は、ギャラをもらったらちゃんと計算し、キープしながら生活することができるんだ(笑)。
18年間やってきて、たくさん苦労があったはずです。もうダメだ、彼らとは一緒にやれないと思ったことは?
[ヘンリー]もちろんあった。もう語ってもいい頃だろうね。何度も自問したよ。こういうことを続けてていいのか⋯⋯自分の一生をかけていいのか⋯⋯と。これだけ個性豊かな連中と四六時中一緒にいれば、それは当然だろう。メンバー間のつまらない諍いもあるし。たまには僕が大きな声を一声上げて、全員にとくとくと説き、なだめて、問題を収めるという場面もある。結局、大事なのは忍耐だよ。お互いが納得できる妥協点を見つけ、話しあうことだ。あと、音楽ビジネスのダークな部分に直面したりとか。好きだ、楽しい、という情熱だけでやっている頃はいいけど、メンバーの家族も含め、たくさんの人間の生活を担う義務が生じてくると、楽しいだけじゃすまなくなってくる。そういう経済的な面でのプレッシャーから、もうこれ以上前に進めないと思ったことは何度もあった。
結局、ここまでこれたのは、彼らの音楽の素晴らしさ、それにつきると思う。いくら長く続けていても、今でもやるたびに僕には新しい発見があり、楽しめる。昨日もフジロックで、PAをやりながら、こんなこともできるのかという発見があり、そこから新しいアイデアも生まれてきた。そんなことをメンバーたちと話し合うことも楽しい。そういったことが、続けるモティヴェションになっているんだと思う。やっぱり、もう1年やってみよう⋯⋯そんな繰り返しだったよ。
 地元に戻っても演奏はやめない[/caption]
ギャラは、昔よりもだいぶ高くなったんじゃないの?
[チマイ]お金の価値観が、僕らの中でもだいぶ変わったしね。でも地元でやる場合は、それはやっぱり関係ないかな。友達だったらタダでやったりもするし。金持ち相手だったら高めに請求するし。君だったら友達だから結婚式でもタダで演奏してあげるよ(笑)。
地元に戻っても演奏はやめない[/caption]
ギャラは、昔よりもだいぶ高くなったんじゃないの?
[チマイ]お金の価値観が、僕らの中でもだいぶ変わったしね。でも地元でやる場合は、それはやっぱり関係ないかな。友達だったらタダでやったりもするし。金持ち相手だったら高めに請求するし。君だったら友達だから結婚式でもタダで演奏してあげるよ(笑)。
 ゼチェ・プラジーニ村への標識[/caption]
[caption id="attachment_2353" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニ村への標識[/caption]
[caption id="attachment_2353" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニの風景[/caption]
[caption id="attachment_2354" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニの風景[/caption]
[caption id="attachment_2354" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニのメインストリート[/caption]
[caption id="attachment_2355" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニのメインストリート[/caption]
[caption id="attachment_2355" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニの人々[/caption]
[caption id="attachment_2356" align="alignleft" width="500"]
ゼチェ・プラジーニの人々[/caption]
[caption id="attachment_2356" align="alignleft" width="500"] ゼチェ・プラジーニのこどもたち[/caption]
私は2000年にタラフの暮らすクレジャニ村に、そして2005年にチォカリーアの住むゼチェ・プラジーニ村に取材に行ったのだが、何よりも印象深かったのは、両者の雰囲気の違いである。前者は、道も空き地もゴミだらけで荒れ果て、一体どうやって生活しているのか心配になるほど住民のほとんどが日中からブラブラしていた。まあ、イメージ通りといえばそうなのだが。対して、チォカリーアの村は、とても明るかった。貧しさはクレジャニと大差ないのだろうが、とにかく人々の表情が朗らかなのだ。
小さな村にはたった1本のメイン・ストリート(もちろん舗装などされていない)があるだけで、その道をあと1時間ほど東へ車で走ればそこは旧ロシアのモルドヴァ共和国という、まさにルーマニア北東部のはずれの寒村。だが、チォカリーアのメンバーをはじめ、村の誰もが畑を耕したり工場で働いたりと、まっとうな生業についており、クレジャニのように至るところにゴミが散乱してたりもしない。村には、完成間近の小さな教会もあった。チォカリーアのメンバーが音楽活動で稼いだ金を出し合って建てたものだという。公衆電話のある売店兼集会所のような場所が1軒あるだけで他には何もない静かな村だが、けっして寂れてはいない。つまり、この村の人々は、行き当たりばったりのその日暮らしではなく、目標を持ってきちんと生きているのだ。それが、彼らの表情の明るさの理由だと私には感じられた。ファンファーレ・チォカリーアというグループ名の「Ciocǎrlia(現地の発音だとチョクルリーア)」とはルーマニア語で「ひばり」のことだというが、彼らのブラスの音色の輝かしさは、まさに、大空を飛び交うひばりのさえずりと呼ぶにふさわしい。
ゼチェ・プラジーニで、祖父から代々受け継いだ楽器を手に、冠婚葬祭などで演奏していた人々の中からファンファーレ・チォカリーアというグループが生まれたのは1996年のこと。旧東ドイツのライプツィヒで生まれ育ち、映画関係の仕事をしていたヘンリー・エルンストという青年が、たまたま訪れたゼチェ・プラジーニで村のブラスバンドに出会ったのがきっかけだった。彼らの演奏に仰天したヘンリーは、西側の人々にこの感動を伝えたいと思い、選抜メンバーによるグループの結成を提案。西ヨーロッパでの初めてのコンサートでいきなり大成功を収めた彼らは、98年には『Radio Paşcani』でアルバム・デビュー。以後リリースされた9枚のアルバムはすべて商業的にも成功し、2003年には、長編ドキュメンタリー映画『IagBari - Brass on Fire』(邦題「炎のジプシーブラス 〜地図にない村から」。監督はラルフ・マルシャレック)も製作・公開された。
正式なグループ結成から既に18年。その間ずっとチォカリーアは、ジプシー音楽シーンのトップを走り続けてきたわけだが、特筆すべきは、彼らが常に、新しいアイデアを取り入れながら音楽的マンネリを上手に回避してきたことだ。それは、ジプシー音楽界において、かなり珍しいことである。
この夏、フジロックへの参加で来日した彼らに久しぶりにインタヴューした際も、そのあたりを中心に、キャリアを振り返ってもらった。答えてくれたのは、グループ結成以来ずっとプロデューサー/マネジャーを務めてきたヘンリー・エルンストと、トランペット/ヴォーカル担当のチマイ(Costicǎ “Cimai” Trifan)である。
ゼチェ・プラジーニのこどもたち[/caption]
私は2000年にタラフの暮らすクレジャニ村に、そして2005年にチォカリーアの住むゼチェ・プラジーニ村に取材に行ったのだが、何よりも印象深かったのは、両者の雰囲気の違いである。前者は、道も空き地もゴミだらけで荒れ果て、一体どうやって生活しているのか心配になるほど住民のほとんどが日中からブラブラしていた。まあ、イメージ通りといえばそうなのだが。対して、チォカリーアの村は、とても明るかった。貧しさはクレジャニと大差ないのだろうが、とにかく人々の表情が朗らかなのだ。
小さな村にはたった1本のメイン・ストリート(もちろん舗装などされていない)があるだけで、その道をあと1時間ほど東へ車で走ればそこは旧ロシアのモルドヴァ共和国という、まさにルーマニア北東部のはずれの寒村。だが、チォカリーアのメンバーをはじめ、村の誰もが畑を耕したり工場で働いたりと、まっとうな生業についており、クレジャニのように至るところにゴミが散乱してたりもしない。村には、完成間近の小さな教会もあった。チォカリーアのメンバーが音楽活動で稼いだ金を出し合って建てたものだという。公衆電話のある売店兼集会所のような場所が1軒あるだけで他には何もない静かな村だが、けっして寂れてはいない。つまり、この村の人々は、行き当たりばったりのその日暮らしではなく、目標を持ってきちんと生きているのだ。それが、彼らの表情の明るさの理由だと私には感じられた。ファンファーレ・チォカリーアというグループ名の「Ciocǎrlia(現地の発音だとチョクルリーア)」とはルーマニア語で「ひばり」のことだというが、彼らのブラスの音色の輝かしさは、まさに、大空を飛び交うひばりのさえずりと呼ぶにふさわしい。
ゼチェ・プラジーニで、祖父から代々受け継いだ楽器を手に、冠婚葬祭などで演奏していた人々の中からファンファーレ・チォカリーアというグループが生まれたのは1996年のこと。旧東ドイツのライプツィヒで生まれ育ち、映画関係の仕事をしていたヘンリー・エルンストという青年が、たまたま訪れたゼチェ・プラジーニで村のブラスバンドに出会ったのがきっかけだった。彼らの演奏に仰天したヘンリーは、西側の人々にこの感動を伝えたいと思い、選抜メンバーによるグループの結成を提案。西ヨーロッパでの初めてのコンサートでいきなり大成功を収めた彼らは、98年には『Radio Paşcani』でアルバム・デビュー。以後リリースされた9枚のアルバムはすべて商業的にも成功し、2003年には、長編ドキュメンタリー映画『IagBari - Brass on Fire』(邦題「炎のジプシーブラス 〜地図にない村から」。監督はラルフ・マルシャレック)も製作・公開された。
正式なグループ結成から既に18年。その間ずっとチォカリーアは、ジプシー音楽シーンのトップを走り続けてきたわけだが、特筆すべきは、彼らが常に、新しいアイデアを取り入れながら音楽的マンネリを上手に回避してきたことだ。それは、ジプシー音楽界において、かなり珍しいことである。
この夏、フジロックへの参加で来日した彼らに久しぶりにインタヴューした際も、そのあたりを中心に、キャリアを振り返ってもらった。答えてくれたのは、グループ結成以来ずっとプロデューサー/マネジャーを務めてきたヘンリー・エルンストと、トランペット/ヴォーカル担当のチマイ(Costicǎ “Cimai” Trifan)である。
「自分たちがあたりまえのように思っていた音楽に 大きな価値があったことに気づいたんだ」
結成以来18年間ずっとトップのポジションを維持できた理由について、どう考えていますか。 [ヘンリー]要因はいくつかあると思う。まず、メンバー全員が、音楽で自分たちの生活がいかに変わるのかということをしっかり自覚したことがある。元々彼らは、地元でずっと昔から音楽をやってきたわけだが、ゼチェ・プラジーニ村は外界と遠く隔てられた場所にあり、そこで暮らす人々は、現金収入の手段も非常に限られている。そんな中、一人のドイツ人(つまりヘンリー)が村を訪れたことによって、自分たちがあたりまえのように思っていた音楽に大きな価値があったんだということに気づいた。それを大事にしたいという思いを強く持つようになったことは大きな要因だろう。つまり、自信を得たということだね。そして、そのドイツ人、私の決断は正しかったんだと思う。彼らの持っている音楽は、神様から与えられた本当に大きな贈り物、財産であるということを、彼ら自身が知らなかったんだ。その素晴らしさは、僕がこのバンドを結成して世界に紹介したことで、実証されたと思っている。 [caption id="attachment_2351" align="alignleft" width="500"] インタビューに応えてくれた、ヘンリー・エルンスト(左)とチマイ(右)[/caption]
彼らの生活水準は、あれ以来、非常に高くなった。子供たちを高校や大学にまでやれるようになったし、それまでの自分たちの世代とは違う未来を子供たちを通して見ることができるようになったんだ。実際、このチマイだって、あの村で生まれ、一生そこから出ることもなく死んでゆく運命だったと思う。出口のない世界なんだ。だが、この音楽を通じて、彼の人生は大きく変わったし、子供たちの世代に至っては、見える世界もまったく変わってしまった。レヴェルアップしたんだ。こういったことは、音楽そのものとは直接関係ないけど、実際、彼らの頑張りの大きな要因だったと思う。
次に、彼らは本当に頑張る、ハードワーキングなバンドであるということ。ジプシー・ブラスバンドで、彼らほど頑張る連中は他にいないと思う。ツアーがなく地元にいる時も、常に演奏してアンサンブルを磨いているし。そういうのは、他のジプシー・バンドでは、実はなかなか見られないことなんだ。ジプシー・バンドの多くは、誰かに見出され、人気者になり、東京だのニューヨークだのに連れて行かれ、神だのなんだのとほめられることにより、逆に、キャリアの終わりが意外に早く訪れる。しかしこのバンドの連中は、本当に謙虚で、浮かれることなく、素朴な生き方、考え方を変えようとしない。日本にこれてうれしい、とはしゃぐ一方で、とても慎重だ。お金がたくさん入ってくるわけだが、その代償として、しっかり働くことが大切なんだということをちゃんと認識している。ワールド・ミュージックの世界で、2〜3年で消えていってしまう連中がいかに多いかをこの目で見てきた僕からしても、彼らは明らかに違うと思う。
そしてもちろん、彼らの伝統音楽、伝統文化そのものの素晴らしさということ。伝統をきちんと守って生きることの大事さを彼らはよくわかっている。アーティストとして周りから崇め奉られても、自分たちはたまたまブラスをやっており、好きなことをやっていたら周りの人たちもそれを気に入ってくれたんだという流れを彼らはきちんと理解している。去年だけでも、素晴らしいアーティストだと海外で何百回も言われたはずだが、そういう中にあって、うぬぼれるということではなく、自分たちはもっと違うこともやっていいんじゃないか、それが許される高度な音楽性を持っているんじゃないかということに、自分たちでもだんだん気づいてきていると思う。
インタビューに応えてくれた、ヘンリー・エルンスト(左)とチマイ(右)[/caption]
彼らの生活水準は、あれ以来、非常に高くなった。子供たちを高校や大学にまでやれるようになったし、それまでの自分たちの世代とは違う未来を子供たちを通して見ることができるようになったんだ。実際、このチマイだって、あの村で生まれ、一生そこから出ることもなく死んでゆく運命だったと思う。出口のない世界なんだ。だが、この音楽を通じて、彼の人生は大きく変わったし、子供たちの世代に至っては、見える世界もまったく変わってしまった。レヴェルアップしたんだ。こういったことは、音楽そのものとは直接関係ないけど、実際、彼らの頑張りの大きな要因だったと思う。
次に、彼らは本当に頑張る、ハードワーキングなバンドであるということ。ジプシー・ブラスバンドで、彼らほど頑張る連中は他にいないと思う。ツアーがなく地元にいる時も、常に演奏してアンサンブルを磨いているし。そういうのは、他のジプシー・バンドでは、実はなかなか見られないことなんだ。ジプシー・バンドの多くは、誰かに見出され、人気者になり、東京だのニューヨークだのに連れて行かれ、神だのなんだのとほめられることにより、逆に、キャリアの終わりが意外に早く訪れる。しかしこのバンドの連中は、本当に謙虚で、浮かれることなく、素朴な生き方、考え方を変えようとしない。日本にこれてうれしい、とはしゃぐ一方で、とても慎重だ。お金がたくさん入ってくるわけだが、その代償として、しっかり働くことが大切なんだということをちゃんと認識している。ワールド・ミュージックの世界で、2〜3年で消えていってしまう連中がいかに多いかをこの目で見てきた僕からしても、彼らは明らかに違うと思う。
そしてもちろん、彼らの伝統音楽、伝統文化そのものの素晴らしさということ。伝統をきちんと守って生きることの大事さを彼らはよくわかっている。アーティストとして周りから崇め奉られても、自分たちはたまたまブラスをやっており、好きなことをやっていたら周りの人たちもそれを気に入ってくれたんだという流れを彼らはきちんと理解している。去年だけでも、素晴らしいアーティストだと海外で何百回も言われたはずだが、そういう中にあって、うぬぼれるということではなく、自分たちはもっと違うこともやっていいんじゃないか、それが許される高度な音楽性を持っているんじゃないかということに、自分たちでもだんだん気づいてきていると思う。
「最初のフランス〜ドイツ・ツアーのことは、今も鮮明に憶えている。 国境を越えてゆく、そのことだけに興奮していた」
そういったバンドの資質も当然ですが、あなたとヘルムート・ノイマン(ヘンリーと共同でずっとチォカリーアをプロデュースしてきたドイツ人)が、サウンドがマンネリに陥らないように、毎回いろいろと新しいアイデアを出してきたことも大きいのではないですか。マネジメントとプロデュースが、とてもクレヴァーだと思います。 [ヘンリー]国際的認知という点においては、確かに、僕らのサポートがなければ無理だったとは思う。マネジメントや様々な問題解決、メンバーとのコミュニケイション等々だけでなく、重要な仕事だと考えてきたのが、彼らのレパートリーの豊かさを彼ら自身に気づかせることなんだ。どんな曲をやるのが、このバンドを世界で認知させてゆく上で得策なのか、ということを僕らは常に考えてきた。彼ら自身が重要だと思うレパートリーは、もちろんあった。これをやれば外国人が喜ぶという曲だね。でも、うまく演奏できる素晴らしい曲なのに、それを敢えて人前ではやらない、そんな曲もたくさんあった。それをやれば、彼らの能力の多彩さがよりうまく伝わるのにといった曲。そういうものもうまく組み込み、彼らの魅力を効果的に伝えるコンサート・プログラムにすることを常に心がけてきたんだ。本当に彼らのレパートリーは膨大だ。そういった点で僕らの果たしてきた役割は、実際大きかったとは思っているよ。最初の頃は、演奏の速さばかりがとりざたされてきたしね。 96年にヘンリーの提案で結成され、海外で初めてコンサートをやった時、バンドがここまで成功し、長続きすることをチマイは予想してましたか。 [チマイ]最初に行ったフランス〜ドイツ・ツアーのことは、今も鮮明に憶えている。国境を越えてゆく、そのことだけに皆は興奮し、大喜びしていた。なにしろ国外に出るのは初めての経験だっし。地元ではずっと冠婚葬祭で演奏してきたけど、いわゆるコンサートの観客の前での演奏というのは、それが初めてであり、勝手が違った。自分たちの音楽が受け入れてもらえるのか、わかってもらえるのか、不安だった。それが好評を博し、予想をはるかに超える展開をその後していったわけで⋯⋯いつも不安を抱えながら、今回もうまくいったな、ということの連続だった。まさかそれが18年も続くとはね⋯⋯。 海外でコンサートをやり始める前は、地元の人々のリクエストに従った支離滅裂なレパートリーだったけど、ツアーをやるようになり、演奏のタイトさも考えつつ、人にちゃんと聴いてもらえるようなパフォーマンスになっていった。面白ければ何でもいい、という演奏からアーティストとしての演奏に変わったというか。「今も朝はちゃんと起きて、工場や畑やに行って10時間働き、 夕方には家に戻ってくるんだ」
ゼチェ・プラジーニに行った時、一番印象的だったのは、メンバーも含めて村人だれもが朝から働いていることでした。その数年前に行った、タラフ・ドゥ・ハイドゥークスのクレジャニの状況とはまったく違っていた。きちんと働き、穏やかで平和な日常生活を送る、そうした真面目な姿勢こそが、18年間のあなたたちの成功を支えてきたのかもしれないと思ったわけです。 [caption id="attachment_2357" align="alignleft" width="500"] モルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがある[/caption]
[caption id="attachment_2358" align="alignleft" width="500"]
モルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがある[/caption]
[caption id="attachment_2358" align="alignleft" width="500"] 楽器は代々受け継がれる[/caption]
[ヘンリー]そのとおりだと思うよ。彼らの場合は、習慣としての労働があるからね。それは、社会主義時代のボルト1本作るのに10人かがりでやるような奇妙な労働であろうとも、昔からずっと続いてきた習慣なんだ。だから今も、朝はちゃんと起きて、工場とか畑とかに行って10時間働き、夕方家に戻ってくる。それとは別に、彼らには、音楽での収入源もあった。チマイは今も工場で働いているんだが、面白いことに、ゼチェ・プラジーニのあるモルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがいる。それは、自分たちの楽しみのためのバンドであり、時々、副次的にお金もついてくる。そこには、自分たちの伝統文化を残してゆこうという意識ももちろんある。一種、義務としてのブラスバンド、みたいな感じかな。子供には自分の楽器を受け継がせるし。多くのジプシー・バンドは、仕事がきたら演奏し、たくさんお金を稼ぎ、2日で使い切ってしまう。将来を考えたお金の使い方などまったくしないんだ。チョカリーアの連中は、ギャラをもらったらちゃんと計算し、キープしながら生活することができるんだ(笑)。
18年間やってきて、たくさん苦労があったはずです。もうダメだ、彼らとは一緒にやれないと思ったことは?
[ヘンリー]もちろんあった。もう語ってもいい頃だろうね。何度も自問したよ。こういうことを続けてていいのか⋯⋯自分の一生をかけていいのか⋯⋯と。これだけ個性豊かな連中と四六時中一緒にいれば、それは当然だろう。メンバー間のつまらない諍いもあるし。たまには僕が大きな声を一声上げて、全員にとくとくと説き、なだめて、問題を収めるという場面もある。結局、大事なのは忍耐だよ。お互いが納得できる妥協点を見つけ、話しあうことだ。あと、音楽ビジネスのダークな部分に直面したりとか。好きだ、楽しい、という情熱だけでやっている頃はいいけど、メンバーの家族も含め、たくさんの人間の生活を担う義務が生じてくると、楽しいだけじゃすまなくなってくる。そういう経済的な面でのプレッシャーから、もうこれ以上前に進めないと思ったことは何度もあった。
結局、ここまでこれたのは、彼らの音楽の素晴らしさ、それにつきると思う。いくら長く続けていても、今でもやるたびに僕には新しい発見があり、楽しめる。昨日もフジロックで、PAをやりながら、こんなこともできるのかという発見があり、そこから新しいアイデアも生まれてきた。そんなことをメンバーたちと話し合うことも楽しい。そういったことが、続けるモティヴェションになっているんだと思う。やっぱり、もう1年やってみよう⋯⋯そんな繰り返しだったよ。
楽器は代々受け継がれる[/caption]
[ヘンリー]そのとおりだと思うよ。彼らの場合は、習慣としての労働があるからね。それは、社会主義時代のボルト1本作るのに10人かがりでやるような奇妙な労働であろうとも、昔からずっと続いてきた習慣なんだ。だから今も、朝はちゃんと起きて、工場とか畑とかに行って10時間働き、夕方家に戻ってくる。それとは別に、彼らには、音楽での収入源もあった。チマイは今も工場で働いているんだが、面白いことに、ゼチェ・プラジーニのあるモルダヴィア地方では工場ごとにブラスバンドがいる。それは、自分たちの楽しみのためのバンドであり、時々、副次的にお金もついてくる。そこには、自分たちの伝統文化を残してゆこうという意識ももちろんある。一種、義務としてのブラスバンド、みたいな感じかな。子供には自分の楽器を受け継がせるし。多くのジプシー・バンドは、仕事がきたら演奏し、たくさんお金を稼ぎ、2日で使い切ってしまう。将来を考えたお金の使い方などまったくしないんだ。チョカリーアの連中は、ギャラをもらったらちゃんと計算し、キープしながら生活することができるんだ(笑)。
18年間やってきて、たくさん苦労があったはずです。もうダメだ、彼らとは一緒にやれないと思ったことは?
[ヘンリー]もちろんあった。もう語ってもいい頃だろうね。何度も自問したよ。こういうことを続けてていいのか⋯⋯自分の一生をかけていいのか⋯⋯と。これだけ個性豊かな連中と四六時中一緒にいれば、それは当然だろう。メンバー間のつまらない諍いもあるし。たまには僕が大きな声を一声上げて、全員にとくとくと説き、なだめて、問題を収めるという場面もある。結局、大事なのは忍耐だよ。お互いが納得できる妥協点を見つけ、話しあうことだ。あと、音楽ビジネスのダークな部分に直面したりとか。好きだ、楽しい、という情熱だけでやっている頃はいいけど、メンバーの家族も含め、たくさんの人間の生活を担う義務が生じてくると、楽しいだけじゃすまなくなってくる。そういう経済的な面でのプレッシャーから、もうこれ以上前に進めないと思ったことは何度もあった。
結局、ここまでこれたのは、彼らの音楽の素晴らしさ、それにつきると思う。いくら長く続けていても、今でもやるたびに僕には新しい発見があり、楽しめる。昨日もフジロックで、PAをやりながら、こんなこともできるのかという発見があり、そこから新しいアイデアも生まれてきた。そんなことをメンバーたちと話し合うことも楽しい。そういったことが、続けるモティヴェションになっているんだと思う。やっぱり、もう1年やってみよう⋯⋯そんな繰り返しだったよ。
「音楽的バリアを彼らは一切感じない。 音楽のジャンル、ボーダーを知らず、何でも素直に受け入れてしまうんだ」
あなたたちは、他のジプシー音楽家たちとのコラボレイションなどもたくさんやってきましたが、他の連中と比べた時、チォカリーアの際立った魅力、特徴はどこにあると思いますか。 [ヘンリー]音楽的な面だと、非常に憶えが早いということ。日本のメロディでも何でも、全員5分で憶え、吹けるようになる。そして、音楽的バリアを彼らは一切感じない。音楽のジャンル、ボーダーを知らず、何でも素直に受け入れてしまう。あと、人間的に、とても敬意に満ちた人たちだということ。外国のどの音楽家たちと会っても、しっかりと敬意を持って接することができる。実はこれが、他の有名ジプシー・ミュージシャンたちにはなかなか見られない資質なんだ。多くのジプシー・ミュージシャンたちは、自分たちはスターであり、他は何者でもない、みたいな態度をとることが少なくないんだが、チォカリーアの連中は誰に対しても心を閉ざすことなく平等につきあえる。これは、彼らの大きな魅力、能力だと思う。 [チマイ]自分たちは、常に一歩先を見据え、新しいことを学びたいと思っている。その姿勢が自分たちの魅力だと思っている。新しい音楽と出会うと、その人から何かを学び、自分たちの音楽にフィードバックし、さらなる成功に結びつけてゆきたいと思っているんだ。野心という言葉に言い換えることもできるだろう。どんな音楽家と出会っても、こちらが心を開いていれば、相手も必ず心を開いてくれる。常に、自分たちに対して興味を持ってもらう、そういう説得力を僕らの姿勢から感じ取ってもらうように努力している。僕らはずっと出会いに恵まれてきた。そして、出会った人たちに、こいつら面白い連中だと思ってもらえるようなハッピー・ピープルでもあったと思う。 現在は、地元にいる時に冠婚葬祭で演奏することはないんですか。 [チマイ]いや、機会があればやっているよ。このメンバーでやることもあるし、それはそのまま、バンドの練習にもなっている。全員集まれなくても、少人数でやったりする。とにかく、常に演奏している。やっぱり、音楽こそが自分たちの最大の情熱だしね。 [caption id="attachment_2369" align="alignleft" width="500"] 地元に戻っても演奏はやめない[/caption]
ギャラは、昔よりもだいぶ高くなったんじゃないの?
[チマイ]お金の価値観が、僕らの中でもだいぶ変わったしね。でも地元でやる場合は、それはやっぱり関係ないかな。友達だったらタダでやったりもするし。金持ち相手だったら高めに請求するし。君だったら友達だから結婚式でもタダで演奏してあげるよ(笑)。
地元に戻っても演奏はやめない[/caption]
ギャラは、昔よりもだいぶ高くなったんじゃないの?
[チマイ]お金の価値観が、僕らの中でもだいぶ変わったしね。でも地元でやる場合は、それはやっぱり関係ないかな。友達だったらタダでやったりもするし。金持ち相手だったら高めに請求するし。君だったら友達だから結婚式でもタダで演奏してあげるよ(笑)。 マイケル・マクグリン(アヌーナ)
[caption id="attachment_2645" align="alignnone" width="550"] 2014/11/21 兵庫県立芸術文化センター公演の様子[/caption]
この原稿がアップされる頃(2014年11月下旬)、大規模な日本公演ツアーをスタートさせるアイルランドのアヌーナ。1987年ダブリンにて、リーダー(作・編曲家、シンガー、プロデューサー)のマイケル・マクグリンによって結成されたこの混声合唱団は、“神秘的なケルティック・コーラス・グループ”というありがちなイメージに包まれつつも、実は、ケルト音楽を巧妙かつ大胆に逸脱し、その可能性を広げてきた極めてユニークな集団である。中世アイルランド音楽の発掘・再生を目的に出発したというだけあり、ラテン語、英語、ゲール語が交錯する歌は、なるほど一見グレゴリア聖歌風であり、またメロディなどいろんな点にケルティック・モードが認められるわけだが、しかし同時に、現代音楽(20世紀音楽)的な不協和音や音色が頻繁に顔をのぞかせたりして、常時、過去と未来の両極を瞬間移動しているような気分にさせられる。そこにあるのは、trans(越境)とtrance(恍惚)である。
今年五十路を迎えたマイケルは、非常に知的かつウィットに富み、正直というか辛辣な言葉を次から次へと吐き出すクセ者であり、我々が知る朴訥でのん兵衛なアイリッシュ・ミュージシャンのプロトタイプとはかけ離れた人物だ。私は過去、数え切れないほど多くの音楽家たちにインタヴューしてきたが、こういう人はなかなかいない。私の中でイメージがダブるのは、キップ・ハンラハンぐらいだろうか。
この記事では、そういった彼の人柄(もちろんそれは、グループの在り方を決定づけている重要なファクターである)も含め、アヌーナの背景と変化について紹介したいと思い、新旧二つのインタヴューから抜粋構成してみた。前半は2009年暮れ、後半は2014年秋におこなったもので、前半は部分的に雑誌(『ラティーナ』誌)に掲載したものと重なることをお断りしておく。
2014/11/21 兵庫県立芸術文化センター公演の様子[/caption]
この原稿がアップされる頃(2014年11月下旬)、大規模な日本公演ツアーをスタートさせるアイルランドのアヌーナ。1987年ダブリンにて、リーダー(作・編曲家、シンガー、プロデューサー)のマイケル・マクグリンによって結成されたこの混声合唱団は、“神秘的なケルティック・コーラス・グループ”というありがちなイメージに包まれつつも、実は、ケルト音楽を巧妙かつ大胆に逸脱し、その可能性を広げてきた極めてユニークな集団である。中世アイルランド音楽の発掘・再生を目的に出発したというだけあり、ラテン語、英語、ゲール語が交錯する歌は、なるほど一見グレゴリア聖歌風であり、またメロディなどいろんな点にケルティック・モードが認められるわけだが、しかし同時に、現代音楽(20世紀音楽)的な不協和音や音色が頻繁に顔をのぞかせたりして、常時、過去と未来の両極を瞬間移動しているような気分にさせられる。そこにあるのは、trans(越境)とtrance(恍惚)である。
今年五十路を迎えたマイケルは、非常に知的かつウィットに富み、正直というか辛辣な言葉を次から次へと吐き出すクセ者であり、我々が知る朴訥でのん兵衛なアイリッシュ・ミュージシャンのプロトタイプとはかけ離れた人物だ。私は過去、数え切れないほど多くの音楽家たちにインタヴューしてきたが、こういう人はなかなかいない。私の中でイメージがダブるのは、キップ・ハンラハンぐらいだろうか。
この記事では、そういった彼の人柄(もちろんそれは、グループの在り方を決定づけている重要なファクターである)も含め、アヌーナの背景と変化について紹介したいと思い、新旧二つのインタヴューから抜粋構成してみた。前半は2009年暮れ、後半は2014年秋におこなったもので、前半は部分的に雑誌(『ラティーナ』誌)に掲載したものと重なることをお断りしておく。

 2014/11/21 兵庫県立芸術文化センター公演の様子[/caption]
この原稿がアップされる頃(2014年11月下旬)、大規模な日本公演ツアーをスタートさせるアイルランドのアヌーナ。1987年ダブリンにて、リーダー(作・編曲家、シンガー、プロデューサー)のマイケル・マクグリンによって結成されたこの混声合唱団は、“神秘的なケルティック・コーラス・グループ”というありがちなイメージに包まれつつも、実は、ケルト音楽を巧妙かつ大胆に逸脱し、その可能性を広げてきた極めてユニークな集団である。中世アイルランド音楽の発掘・再生を目的に出発したというだけあり、ラテン語、英語、ゲール語が交錯する歌は、なるほど一見グレゴリア聖歌風であり、またメロディなどいろんな点にケルティック・モードが認められるわけだが、しかし同時に、現代音楽(20世紀音楽)的な不協和音や音色が頻繁に顔をのぞかせたりして、常時、過去と未来の両極を瞬間移動しているような気分にさせられる。そこにあるのは、trans(越境)とtrance(恍惚)である。
今年五十路を迎えたマイケルは、非常に知的かつウィットに富み、正直というか辛辣な言葉を次から次へと吐き出すクセ者であり、我々が知る朴訥でのん兵衛なアイリッシュ・ミュージシャンのプロトタイプとはかけ離れた人物だ。私は過去、数え切れないほど多くの音楽家たちにインタヴューしてきたが、こういう人はなかなかいない。私の中でイメージがダブるのは、キップ・ハンラハンぐらいだろうか。
この記事では、そういった彼の人柄(もちろんそれは、グループの在り方を決定づけている重要なファクターである)も含め、アヌーナの背景と変化について紹介したいと思い、新旧二つのインタヴューから抜粋構成してみた。前半は2009年暮れ、後半は2014年秋におこなったもので、前半は部分的に雑誌(『ラティーナ』誌)に掲載したものと重なることをお断りしておく。
2014/11/21 兵庫県立芸術文化センター公演の様子[/caption]
この原稿がアップされる頃(2014年11月下旬)、大規模な日本公演ツアーをスタートさせるアイルランドのアヌーナ。1987年ダブリンにて、リーダー(作・編曲家、シンガー、プロデューサー)のマイケル・マクグリンによって結成されたこの混声合唱団は、“神秘的なケルティック・コーラス・グループ”というありがちなイメージに包まれつつも、実は、ケルト音楽を巧妙かつ大胆に逸脱し、その可能性を広げてきた極めてユニークな集団である。中世アイルランド音楽の発掘・再生を目的に出発したというだけあり、ラテン語、英語、ゲール語が交錯する歌は、なるほど一見グレゴリア聖歌風であり、またメロディなどいろんな点にケルティック・モードが認められるわけだが、しかし同時に、現代音楽(20世紀音楽)的な不協和音や音色が頻繁に顔をのぞかせたりして、常時、過去と未来の両極を瞬間移動しているような気分にさせられる。そこにあるのは、trans(越境)とtrance(恍惚)である。
今年五十路を迎えたマイケルは、非常に知的かつウィットに富み、正直というか辛辣な言葉を次から次へと吐き出すクセ者であり、我々が知る朴訥でのん兵衛なアイリッシュ・ミュージシャンのプロトタイプとはかけ離れた人物だ。私は過去、数え切れないほど多くの音楽家たちにインタヴューしてきたが、こういう人はなかなかいない。私の中でイメージがダブるのは、キップ・ハンラハンぐらいだろうか。
この記事では、そういった彼の人柄(もちろんそれは、グループの在り方を決定づけている重要なファクターである)も含め、アヌーナの背景と変化について紹介したいと思い、新旧二つのインタヴューから抜粋構成してみた。前半は2009年暮れ、後半は2014年秋におこなったもので、前半は部分的に雑誌(『ラティーナ』誌)に掲載したものと重なることをお断りしておく。
実際、アイルランド人のほとんどは伝統音楽などには興味ないんだ。
これまで、たくさんのアイリッシュ・ミュージシャンにインタヴューしてきたけど、会ったことのないタイプの人ですね(笑)。 僕はアイルランドでは、決して仕事がしやすい人間と思われていないんだ。なぜって、他の音楽家たちとは似ていないから。僕はただの作曲家/歌手ではなく、会社を経営していて、レコードを出し、契約書を作り、映像を作り、その映像をリリースし、シンガーやコーラス隊を訓練し、コンサート・プログラムを考え、ツアーの移動手段や宿泊施設を手配し、電話の応対をし、メールの返事を出し、楽譜を販売し、アヌーナのHPに世界中から注文が来たCDを自分で箱詰めして発送したりしているし……だから僕の視点は、他のミュージシャンたちとは違っているんだ。 アイルランドは国が狭いこともあって、多くのミュージシャンが、自分たちが思っていることをあまりはっきりとは口に出さない。自分が仕事仲間からどう見られているかということは、彼らにとって非常に重要なことなんだ。でも僕は、彼らの誰とも仕事をしていないから、彼らがどう思っているかなんて気にしないで、真実だと思うことを何でも言ってしまう傾向がある。だから、ある意味、よく思われないということになってしまうし、大きな仕事にもあまり誘われないというわけだ(勝手に爆笑)。 でも僕は、いつも自分に正直でありたいんだ。アーティストとしてのたった一つの目的、人生の目的の──つまり、この音楽をプロデュースするために。アヌーナは非常に難しいグループさ。まったく他に類をみない独自の活動をしている。全部自前でシンガーたちを探し出し、訓練するところからやらないといけない。だから僕は、さっき言ったようなすべての仕事をこなさないといけない。でもそれが、パーフェクトじゃないけど、どこか人間味のある、壊れやすいサウンドというものを作り出しているとも思うんだ。 あなたは現代音楽も勉強し、メシアンやクセナキス、リゲティなどからの影響も公言してますが、アイルランドの伝統音楽には子供の頃から親しんでましたか。 日本に来ると不思議な気分になる。アイリッシュ・ミュージックに対する日本人の認識は、とても変わったものに思えるから。実際、アイルランド人のほとんどは伝統音楽などには興味ないんだ。私の両親も、非常に嫌ってたよ。パブとかでその手の音楽が聴こえてくると、チッ、また始まったよ、なんて言っていたぐらいさ。つまりそれが、僕のバック・グラウンドだ。 だが、ゲール語の学校に通っていた10歳の時、僕が共感できて歌えるような伝統的な歌、物語や歴史のある歌というものに出会い、理解できないながらも興味を抱いた。そして大学(ダブリンのトリニティ・カレッジ)で音楽と英語を勉強していた時、歴史や文学への強い興味から、いったいアイルランドの古楽はどこにあるのだろうと疑問を抱くようになった。イギリスやドイツの古楽は歌うけど、アイルランドの古楽は歌ってないじゃないか、と。そこで、古い楽譜を集めだしたんだ。それらは千年も前の音楽で、あまりにも博物館的であり、いわゆる伝統音楽すら通り過ぎていったものだ。自分の人生にもアイルランドの人々にもまったく無関係だ。でも逆に、これを現代の人々にも理解できるようにアレンジしたら、人々の心を打つものができるのではないか、と思ったんだよ。 でも、いわゆる伝統音楽はアイルランドではたくさんのリスナーに支持されているし、ミュージシャンも多いですよね。 伝統音楽家が生きている世界は、実際のアイルランド人が生きている世界とは違う。彼らが生きているのは“伝統音楽の世界”であり、一般のアイルランド人の文化とは結びついていない。アイルランド人はそれらを理解していると思い込むことが好きなんだよ。でも、それはセント・パトリックス・デイに、何か緑色のものを身につけて『アイルランド音楽が好きだ~!』と言っているだけのことさ。実際には、ほとんどの人は、ポップ・ソングしか知らないし、ゲール語の歌など理解しない。アイリッシュ・ダンスを踊れる人も少ない。それが現状だ。もちろん伝統音楽家は、本当に素晴らしい人々だよ。誤解しないでほしい。でもそれは、僕らが実際アイルランドで見ている世界とは違うんだ。人々は何千年後の未来でもこんな音楽を聴くに違いないと思う。
アヌーナでは、いわゆる指揮者っていないですよね。どうしてあなたは前で指揮をせず、メンバーの一員として歌うんですか。 指揮をするとお客さんには、僕の尻しか見えないじゃないか(笑)。実は、指揮者をなくせば、皆、お互いの声を本当によく聴くようになるということに気づいたんだ。アヌーナの芸術は単純だ。つまりそれは“聴取の芸術”(Art of listening)なんだ。ほとんどの合唱団が、そのことを完全に忘れていると思う。そして指揮者をなくすと、歌手とお客さんの壁をなくすことにもなる。その結果として、シンガー全員が平等に重要なものとなり、お互いに対して責任を持つようになる。そして、お客に向けて自分を表わしていくことになる。その時、僕ら歌手も客も、等しくショウの一部になるんだ。最高のステージというものは、観客からエネルギーをもらい、それを観客に戻すものだ。アヌーナもそうさ。観客に立ち向かう時、僕らは素っ裸だ。 そういうメンバー同士の関係性、歌手と客との関係性は、あなたの考える「ケルト的世界」とも関係あるんでしょうか。 イエス。一人一人への祝福、個性への祝福……僕らは有史前、すごくユニークなものを持っていた。社会性も重んじるけど、その中における個々の存在というものも同時にまたとても重んじられているんだ。 アヌーナの音楽で僕自身が最もスリリングに感じるのは、すごく古い過去と未来が瞬時に入れ替わる、トランスする瞬間なんです。それはたぶん不協和音の使い方に関係あるんだと思う。カルロ・ジェズアルド(16世紀イタリアの作曲家)を思い出させたりもします。 オー! 日本では僕が訊いてほしいと思う質問がちゃんと出るね(笑)。最高の質問だ。うれしいよ。過去のインタヴューでジェズアルドについて訊かれたのは初めてだ。彼は非常に興味深い作曲家だ。彼の作品は、木の上で収穫されることなく腐っていく果物だった。でも、彼のやったことは論理的で、すべては腑に落ちるものだった。彼は、音楽への情熱を形にした。君の意見はまったく真実で、正しいよ。アヌーナとは、古代でありながら同時に現代でもあるという“能力”なんだ。 2つの世界に同時に生きるという概念は、西欧では考えられないものだが、どうやら東洋では存在するらしい。〈今〉と〈あの時〉という概念、そして〈未来〉も、すべてが一つの思考の流れなのだ、と。それこそがスピリチュアルな人生へのアプローチだと思うよ。 つまり⋯⋯アヌーナはスピリチュアルへの賞賛なんだ。アヌーナは、今を生きる人々のための音楽を賞賛する。人々は何千年後の未来でもこんな音楽を聴くに違いないと思う。500年前にある人がある場所でやったことと、今私がやろうとしていることに、何の違いもないという事実は、人々にとって非常に理解しがたいコンセプトなのかもしれないけどね。 1万年前に音楽を作っていた人がいたとしよう。作曲の語法は違っているのかもしれないけど、アーティストとしての彼がやろうとしていることは現在とまったく同じことなんだと思う。つまりそれは、自分の周りに起こっていることの解釈(interpretation)に他ならない。我々の人生にいったいどんなことが起きるかということ。そしてそれこそが、アヌーナのやっていることでもあるんだ。
アヌーナは、伝統的合唱のあり方に“なぜ”という疑問を初めて持ち、 実践したグループなんだ
日本でも最近出た新作『イルミネーション』は、まずクレジットを見て驚きました。ステイシー・リー・ロッソウという米人女性の指揮者が加わっていますね。以前あなたは、アヌーナの重要なコンセプトとして、指揮者がいないということを挙げていた。アヌーナの合唱は「アート・オブ・リスニング」であり、歌手一人一人が指揮者を見るのではなく他の歌手たちの歌を慎重に聴ききながら歌うことが最も重要なポイントであると。 そのことについて質問してくれて、うれしいよ。指揮者は、全曲ではなく、曲によって使ったんだけど、今回はちょっと違うことにトライしたくなったんだ。 指揮者という存在には、常にある種の神秘性がつきまとっている。ありもしないその神秘性により、リスペクトを得ている指揮者が確かにいる。指揮者には2種類のタイプがあると思う。一つは、情熱を持って合唱団と一体化し、音楽を作り上げてゆく人。もう一つは、これは俺の作品だと言わんばかりに自分の好みを押し通す人。当然僕は、後者は好きじゃないし、興味もない。指揮者の仕事は、合唱団が出す音をアートの領域まで引き上げることにあると思うが、それが可能なのは、あくまでも合唱団が優秀であるという前提あってのことだ。合唱団が本当の力量を発揮するためには、リラックスしてありのままの姿を見せられるようでなくてはならないし、何かを強制されたり押しつけられたりするようではいけない。だから、そういう指揮者は不要なんだ。個性的なアートを作り上げるためには、どの合唱団でも求めるような画一的なクオリティを求めてはだめだ。どんな合唱団でも、いい演奏、歌を披露しようとするわけだが、しかしその結果、同じような音楽になってしまう。実はそれが、合唱の世界にはつきものだ。そんな中にあって、僕らは自分たちだけのサウンド、世界を追求してきた。だから、たとえばコラール(讃美歌)を聴きたい人にとって、こんなのコラールじゃないと思うかもしれない。でも、僕らはそれをやりたいので、指揮者には何も言わせないわけだ。今回は、統一感を図るために、ステイシー・リー・ロッソウという指揮者を入れてみた。でも、何かを強要するわけでもなく、形を整え、コントロールしてもらうために入れただけなんだ。だから、通常の指揮者と合唱団という関係とは違う。 アヌーナ自体が何らかの変化を求めているという見方もできるのかな? そうだね。僕ら自身、この2年ほどでずいぶん変わったんだよ。お互いの息遣いを感じながら、阿吽の呼吸で歌に入ること、そして、合唱の一体感というのは今も変わらず最重要だし、誰か一人の声が際立ってしまったり支配的だったりしてはならない。一人が全員であり、全員が一人である。それは今も同じだが、許容力とか柔軟性のようなものが大きくなったと思う。アヌーナは、雲のような存在であり、集合体だと僕は考えている。歌手だけでなく、周囲で関わる全ての人を含んだ集合体だ。その点も、この2年ほどでかなり変わった部分だと思う。根本にあるものは同じだけど、表現手法のヴァリエイションが増えた。 今の僕らのスタイル、在り方が一番近いのは、米サンフランシスコの男声合唱団チャンティクリア(Chanticleer)かな。彼らも基本的に指揮者なしでやっている。ただ、彼らはテクニックを前面に押し出した合唱だ。技術的に上手い人たちの歌は、もちろん聴き応えがあるわけだが、僕らの場合は、技術がサウンドに影響してはならないという考え方でやっている。たまに、ものすごくテクニックのあるシンガーがアヌーナにも入ってくることがあり、こういう風に習ったとか、伝統的にはこういう風に歌うのが正しいとか主張したりするんだけど、僕は無視して、そういうものはアヌーナには必要ないんだということから説明するんだ。おそらくアヌーナは、そういった伝統的合唱のあり方に“なぜ”という疑問を初めて持ち、実践したグループなんだと思う。伝統的スタイルにこだわらず、トレーニングした結果を披露するのではなく、私/君はどういう歌を歌う人なのかという問いかけをし続けるグループだ。 実は、今横にいるこのローラ(一昨年アヌーナに新加入した米人シンガー)も、参加した当初は、ちょっと前かがみになって歌っていた。それは、彼女がずっと受けてきたクラシックのトレーニングがそうだったからだ。でも、それだとアヌーナの歌は実は歌えない。もっと胸を開いてゆったりと歌うようにさせたら、やっとアヌーナの歌になってきた。だから、変な話、クラシックのトレーニングを受けたことのない子供の素直な歌い方の方が、アヌーナの合唱には合っているんだ。こういうアヌーナ独自の歌唱法を僕らは“アヌーナ・メソッド”と呼んでおり、ワークショップもおこなっている。外国人歌手の加入は、僕らの音楽が本来持っていた 普遍性や柔軟性といったものを思い出させてくれた。
ローラにがきらず、近年はアイルランド以外の外国人シンガーの加入が多いそうですね。 そうなんだ。彼らは、アイルランド人とはまた違った音楽的経験や文化的背景を持ち込んでくれるので、楽しい。たとえば、今年(2014年)の日本公演にも来るサラという新加入の歌手は、シチリア島出身だ。元々はオペラ歌手だが、6年ほど前にアヌーナを聴いてほれ込み、僕らのサマー・スクールに参加したいと手紙を書いてきた。会って話してみると、僕も気づかなかったようなアヌーナの本質を彼女はわかっているなと思った。たとえば、海の色がシリチアとアイルランドでは違うけど、アヌーナで歌ってみて、海というものの本質が理解できたと彼女が言うのを聞き、僕らの音楽が本来持っていたはずなのに僕自身が忘れかけていた普遍性や柔軟性といったものを彼女は思い出させてくれた。外国人歌手の加入は、そういった様々な刺激を与えてくれる。今回の日本公演に連れてくる予定のメンバーも、大半は外国人歌手だ。 自分の考えるアイルランドのヴィジョンを具現化するためにこのグループを作ったと、以前語っていましたが、つまり、部外者の視点も取り入れながら、そのヴィジョンを今一度、明確にしてゆこうということですね。 アーティストというものは、そもそも、何かを伝えたくて作品を作っているはずなんだが、その部分を忘れてしまうことがままある。一般リスナー相手だけでなく、アーティスト同士の場合でも、何を言いたかったのか自分でもわからなくなってしまうこともある。さっきのサラは、僕が最近聴かなくなっていたアヌーナの大昔の曲を、これが一番好きなんだと言ってきた。そう言われて、自分も昔大好きだったこの曲の魅力、価値について改めて発見したんだ。アイルランドでは、アヌーナはたいして興味を持たれていない。せっかく僕らがこうやって種をまいても、そこに水をやって育ててくれる人がいない。そういう中で、外部から栄養や刺激をもらうことは、とても大事なことなんだ。 今年(2014年)暮れの日本公演では、リアム・オ・メンリィやサム・リーなどととのコラボレイションも予定されていますね。伝統音楽の世界とはあまりソリが合わないと以前から言ってたけど、大丈夫ですか? まず、リアムは伝統音楽シンガーではない。ただのシンガーであり、音楽家だ。たとえ、シャン・ノース(民謡の古い歌唱スタイル)を歌ってもね。サムも、元々はダンスなど音楽以外のアートからキャリアを始めた人間だ。音楽家が伝えようとしていることは、ジャンルに関係なく、結局同じことなんだ。使っている言葉、語法が違うだけで。特にリアムとは、そのあたりのことはツーカーで通じ合える。彼は常に身体で語っている人だしね。サムは、新しい世代ということもあって、表現の姿勢がとてもオープンだ。音楽という世界が彼自身にとって日々探訪の世界であり、彼もどんどん変化、成長している。音楽を始めたのが遅かったことは、彼にとって幸いだったとも思うよ。僕らは、これまでにもたくさんのコラボレイションをおこなってきたけど、サムやリアムのように言葉や説明なしで通じ合える音楽家はそうそういないと思っている。楽しみだよ。 (写真提供:株式会社プランクトン) 【アヌーナ来日公演】 ※詳細とチケット購入は招聘元プランクトンのウェブサイトをご覧ください。 http://www.plankton.co.jp/anuna/index.html ■11/28(金)ハーモニーホールふくい 大ホール 18:15開場/19:00開演 指定5,000円/ペア券8,000円/学生半額 問:0776-38-8282 ■11/30(日)いわき芸術文化交流館アリオス 中劇場 17:00開演 指定3,500円/学生・車いす席1,500円 ※14:00~映画「ブレンダンとケルズの秘密」上映あり。コンサートチケット購入者無料。 問:0246-22-5800 ■12/3(水)岩手県民会館 大ホール 会員制公演につき一般発売はございません ■12/5(金)つくばノバホール 大ホール 18:30開場/19:00開演 指定3,500円 問:029-856-7007 ■ケルティック・クリスマス2014~アメイジング・ヴォイス~ 出演:アヌーナ/サム・リー&フレンズ/リアム・オ・メンリィ 12/6(土)錦糸町・すみだトリフォニーホール 16:30開場/17:30開演 前売:S席6,500円/A席5,000円/B席4,000円(税込) ※当日券は500円増し お問い合わせ:トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212 ■12/7(日)まつもと市民芸術館 主ホール 14:30開場/15:00開演 一般4,000円/学生2,500円 問:0263-33-3800 ■ 12/9(火)名古屋・三井住友海上しらかわホール 18:45開演 S席5,000円/A席4,000円 問:CBCテレビ事業 052-241-8118ポップかつ柔軟なアート感覚で貫かれた英国フォーク・シーンの革新的な存在──サム・リー
2012年のデビュー・アルバム『Ground Of Its Own』で英国フォーク・シーンを震撼させ、新時代を切り開く異能として注目を集めてきた新進シンガー、サム・リー。2014年12月の日本公演にタイミングを合わせるように、2年ぶりの新作『The Fade In Time』を完成させた。今回は、ペンギン・カフェのアーサー・ジェフスを共同プロデューサーに迎えていることも話題のひとつだ。
 photo by FREDERI ARANDA
サム・リーはなぜここまで英国フォーク・シーンを驚かせたのか。それは彼がいろんな点で、それまでにはなかったユニークかつ革新的な存在だったからである。彼のレパートリーは基本的にブリテン諸島各地で継承されてきたトラディショナル・フォークなのだが、彼自身は元々は伝統音楽とは何の縁もない、ダンスやアート好きの若者である。数年前、突然、伝統音楽に魅せられたサムは、ブリテン諸島に昔から住んでいるトラヴェラーズ(漂泊民)のシンガーに直接教えを乞うなどして伝承曲を習得し、今や、大学などでもトラディショナル・フォークについて講義するまでになっている。
そして、その表現は、歌い方にしろアレンジにしろ、伝統音楽家のスタイルをそのまま真似たものではなく、自分なりのやり方を貫いている。音作りでは、トランペットやチェロ、更にはジューズ・ハープ(口琴)やインドのドローン専用楽器であるシュルティ・ボックス(ハルモニウム)、タンク・ドラム(プロパンガスのタンクの湾曲部分を切り取ったものを素手で叩くメタル・パーカッション)、日本の琴といった、英国フォークとはなじみのない珍しい楽器が随所で効果的に用いられている。ヴォーカルも独特だ。歌い回しは伝統音楽のように素朴ではあるけど、田舎の農夫のごとき土臭さやゴツゴツした感触はなく、時にジャズのクルーナーのようにソフトで洗練されてもいる。つまり、表現全体が、ポップかつ柔軟なアート感覚で貫かれているのだ。一種のモダン・アートと言っていい。新作『The Fade In Time』も、そういった特質が更に追求された力作に仕上がっている。
サム・リーには、2012年から最近まで、過去数回のインタヴューをおこなってきたが、ここでは今述べた彼の特長、異能に焦点をあてつつ、発言を抜粋・編集してみた。ちなみにサムは、1980年ロンドン生まれ。ルーツは東欧系ジューイッシュである。
photo by FREDERI ARANDA
サム・リーはなぜここまで英国フォーク・シーンを驚かせたのか。それは彼がいろんな点で、それまでにはなかったユニークかつ革新的な存在だったからである。彼のレパートリーは基本的にブリテン諸島各地で継承されてきたトラディショナル・フォークなのだが、彼自身は元々は伝統音楽とは何の縁もない、ダンスやアート好きの若者である。数年前、突然、伝統音楽に魅せられたサムは、ブリテン諸島に昔から住んでいるトラヴェラーズ(漂泊民)のシンガーに直接教えを乞うなどして伝承曲を習得し、今や、大学などでもトラディショナル・フォークについて講義するまでになっている。
そして、その表現は、歌い方にしろアレンジにしろ、伝統音楽家のスタイルをそのまま真似たものではなく、自分なりのやり方を貫いている。音作りでは、トランペットやチェロ、更にはジューズ・ハープ(口琴)やインドのドローン専用楽器であるシュルティ・ボックス(ハルモニウム)、タンク・ドラム(プロパンガスのタンクの湾曲部分を切り取ったものを素手で叩くメタル・パーカッション)、日本の琴といった、英国フォークとはなじみのない珍しい楽器が随所で効果的に用いられている。ヴォーカルも独特だ。歌い回しは伝統音楽のように素朴ではあるけど、田舎の農夫のごとき土臭さやゴツゴツした感触はなく、時にジャズのクルーナーのようにソフトで洗練されてもいる。つまり、表現全体が、ポップかつ柔軟なアート感覚で貫かれているのだ。一種のモダン・アートと言っていい。新作『The Fade In Time』も、そういった特質が更に追求された力作に仕上がっている。
サム・リーには、2012年から最近まで、過去数回のインタヴューをおこなってきたが、ここでは今述べた彼の特長、異能に焦点をあてつつ、発言を抜粋・編集してみた。ちなみにサムは、1980年ロンドン生まれ。ルーツは東欧系ジューイッシュである。
 photo by FREDERI ARANDA
サム・リーはなぜここまで英国フォーク・シーンを驚かせたのか。それは彼がいろんな点で、それまでにはなかったユニークかつ革新的な存在だったからである。彼のレパートリーは基本的にブリテン諸島各地で継承されてきたトラディショナル・フォークなのだが、彼自身は元々は伝統音楽とは何の縁もない、ダンスやアート好きの若者である。数年前、突然、伝統音楽に魅せられたサムは、ブリテン諸島に昔から住んでいるトラヴェラーズ(漂泊民)のシンガーに直接教えを乞うなどして伝承曲を習得し、今や、大学などでもトラディショナル・フォークについて講義するまでになっている。
そして、その表現は、歌い方にしろアレンジにしろ、伝統音楽家のスタイルをそのまま真似たものではなく、自分なりのやり方を貫いている。音作りでは、トランペットやチェロ、更にはジューズ・ハープ(口琴)やインドのドローン専用楽器であるシュルティ・ボックス(ハルモニウム)、タンク・ドラム(プロパンガスのタンクの湾曲部分を切り取ったものを素手で叩くメタル・パーカッション)、日本の琴といった、英国フォークとはなじみのない珍しい楽器が随所で効果的に用いられている。ヴォーカルも独特だ。歌い回しは伝統音楽のように素朴ではあるけど、田舎の農夫のごとき土臭さやゴツゴツした感触はなく、時にジャズのクルーナーのようにソフトで洗練されてもいる。つまり、表現全体が、ポップかつ柔軟なアート感覚で貫かれているのだ。一種のモダン・アートと言っていい。新作『The Fade In Time』も、そういった特質が更に追求された力作に仕上がっている。
サム・リーには、2012年から最近まで、過去数回のインタヴューをおこなってきたが、ここでは今述べた彼の特長、異能に焦点をあてつつ、発言を抜粋・編集してみた。ちなみにサムは、1980年ロンドン生まれ。ルーツは東欧系ジューイッシュである。
photo by FREDERI ARANDA
サム・リーはなぜここまで英国フォーク・シーンを驚かせたのか。それは彼がいろんな点で、それまでにはなかったユニークかつ革新的な存在だったからである。彼のレパートリーは基本的にブリテン諸島各地で継承されてきたトラディショナル・フォークなのだが、彼自身は元々は伝統音楽とは何の縁もない、ダンスやアート好きの若者である。数年前、突然、伝統音楽に魅せられたサムは、ブリテン諸島に昔から住んでいるトラヴェラーズ(漂泊民)のシンガーに直接教えを乞うなどして伝承曲を習得し、今や、大学などでもトラディショナル・フォークについて講義するまでになっている。
そして、その表現は、歌い方にしろアレンジにしろ、伝統音楽家のスタイルをそのまま真似たものではなく、自分なりのやり方を貫いている。音作りでは、トランペットやチェロ、更にはジューズ・ハープ(口琴)やインドのドローン専用楽器であるシュルティ・ボックス(ハルモニウム)、タンク・ドラム(プロパンガスのタンクの湾曲部分を切り取ったものを素手で叩くメタル・パーカッション)、日本の琴といった、英国フォークとはなじみのない珍しい楽器が随所で効果的に用いられている。ヴォーカルも独特だ。歌い回しは伝統音楽のように素朴ではあるけど、田舎の農夫のごとき土臭さやゴツゴツした感触はなく、時にジャズのクルーナーのようにソフトで洗練されてもいる。つまり、表現全体が、ポップかつ柔軟なアート感覚で貫かれているのだ。一種のモダン・アートと言っていい。新作『The Fade In Time』も、そういった特質が更に追求された力作に仕上がっている。
サム・リーには、2012年から最近まで、過去数回のインタヴューをおこなってきたが、ここでは今述べた彼の特長、異能に焦点をあてつつ、発言を抜粋・編集してみた。ちなみにサムは、1980年ロンドン生まれ。ルーツは東欧系ジューイッシュである。
民謡研究家ピーター・ケネディに、 手紙を書いて、会いにいったんだ。
伝統音楽とは無縁の家庭で育ったそうですね。 うん、でも僕の家族は音楽一家だったんだ。父(イアン・リー)は、若い頃はシンガー・ソングライターを目指していたことがあり、その後アートの世界に転じた。タイポグラフィやシンボルなどに関する記号論の著書(『The Third Word War:Apostrophe Theory』)もある作家なんだ。今も達者なギターを弾くよ。僕も若い頃に少し教わった。母は根っからのオペラ・ファンだ。なんでも若い頃、パヴァロッティと付き合っていたらしい(笑)。母からは、彼女がオペラにおいてしていたような、歌やシンガーについて研究する尋常でない探究心や百科事典的な知識欲を受け継いだと思う。 ギター以外の音楽教育は? 小さい時にピアノのレッスンを受けていたけど、あまり熱心ではなかった。25歳の時に伝統音楽に出会うまでの長い間、自分が音楽家になるなんて考えてもみなかった。とにかく僕はダンスに夢中だったから。ずっと、ソウルやファンク、R&Bといった黒人音楽やジャズばかり聴いていた。とりわけマイケル・ジャクソンに関しては熱狂的ファンで、その流れでダンスにものめりこんでいったんだ。マイケルを真似て踊っているうちに、今度は自分独自のダンスをしたくなった。即興のね。週に3〜4回は踊りに行っていたよ。まさに、踊るために生きていた。一時期はバーレスク・ショウでダンサーとしても働いていたことがあったんだよ。そして、ダンスに関してもっと理解を深めたくなり、1年ほど正式に習った。クラシック・バレエもジャズ・ダンスもコンテンポラリー・ダンスも。今でもダンスは大好きで、踊っている時が一番表現的で、自由な気がするんだ。 で、25歳の時、本格的に伝統音楽の世界にのめりこんでいった。その時の状況は? きっかけは、3枚のアルバムだった。当時87歳のシンガー、ハリー・コックス(Harry Cox)の70曲入り2枚組CD。それから、コッパー・ファミリー(Copper Family)の『The Classic Ballads of Great Britain And Ireland』。もうひとつは、トピック・レーベルから出ていた2枚組アルバム『I'm A Romany Rai』。そういったフィールド・レコーディングの作品はそれまで聴いたことがなかった。ウォーターソンズとかジューン・テイバーなど、60〜70年代のいわゆるリヴァイヴァル・ソングは聴いていたし、けっこう好きだったんだけど、でもなんか違う、人工的だ……みたいな違和感も感じていた。そこで自分でいろいろ調べて、ハリー・コックスなどの歌に出会ったんだ。やっと大本にたどり着いた感じだった。 そして、トラヴェラーズなどのコミュニティに入り、直接、伝承歌を学び始めたわけですね。 民謡研究家ピーター・ケネディが50〜60年代に英国南部のジプシー系シンガーたちの歌を録音し、それをシャーリー・コリンズ(後述)が編集した『I'm A Romany Rai』は、特に重要だった。僕は、まだ存命中だったピーターにすぐに手紙を書き、自宅に会いに行った。こういう世界にすごく興味があるので、助手として手伝わせてもらえないかと。当時彼は83歳で癌を患っていたが、フィールド・レコーディングのやり方をいろいろ教えてくれ、昔録音した膨大な音源を全部コピーさせてくれた。自分の遺産を全部僕に譲ってくれたに等しい。05〜06年のことだ。 『I'm A Romany Rai』の中で歌っていたシーラ・スミス(Sheila Smith)は録音当時10歳だったので、こういう歌を歌っているジプシー系シンガーはきっとまだいるはずだとピーターに言われた。僕は、このアルバムの収録曲を全部歌えるまでじっくり聴きこんだ。そして、こういう人にはどこで会えるのか、調べ始めた。それ以前にも、世界中の様々な民族音楽についていろいろ調べていた僕は、この人たちは英国におけるネイティヴ・アメリカンのような存在なのかもしれないと思った。当時僕は、フォーク・クラブのオーガナイズの仕事もやっていたんだが、当時のロンドンではフォーク関係で面白いことは何も起こってなかったし、オーガナイズの内容も全然充実してなかった。自分で何か面白いことを始めようと、ワークショップを企画したり、古いフォークの記録映像をDVDにして各地の音楽フェスで巡回上映をやったりもした。英国アート・カウンシル(芸術協会)から資金を提供してもらいながら、古いフォークに対する一般の関心を高めたいと活動していたんだ。しかし、いくらやってもライブラリー、資料の域を超えないわけで。自分としては、生きているフォーク・シンガーたちを探し出して、紹介したかった。そこで、トラヴェラーズと呼ばれる人たちの居留区を探し出して、直接自分で乗り込んでいった。その人たちが歌うのかどうかもわからないままに、あなたたちの音楽に興味があります、と言って。そうやって、徐々にコミュニティに入り込んでいった。でも、そういう場所に住んでいる人たち自身には、自分たちの伝承歌が価値あるものだとか特殊なものだなんていう意識は全然なかった。だからまず、そこに気づいてもらうところから話を始めていったんだ。リー(Lee)という姓はジプシー由来のものなんだ。 ルックスもジプシー系だと彼らからは言われる(笑)。
ジプシーやトラヴェラーズなど、英国内の移動民には、いくつかの種類がありますね。 主に3つのグループがある。ひとつめは、イングリッシュ・ジプシー。ふたつめはアイリッシュ・トラヴェラーズ。みっつめはスコティッシュ・トラヴェラーズ。アイリッシュ・トラヴェラーズとスコティッシュ・トラヴェラーズは、ケルト民族が渡来する以前の古代から住んでいたブリテン諸島の土着民で、基本的には遊牧民だ。様々なグループがどのように離合集散してトラヴェラーズとよばれる集団になったかに関しては諸説あるが、それら2つは、生活様式がかなり似ている。今は定住してモダンな生活をしている人が多いけど、元々はテントでのキャラヴァン生活だった。そして、各々が古い独自の言葉を持っている。アイリッシュの言葉はギャモン(gammon)あるいはシェルタ(shelta)、スコティッシュの言葉はカント(cant)と呼ばれる。どちらもアイリッシュ・ゲーリックやスコティッシュ・ガーリック以前からブリテン諸島に存在していた言語だ。もちろん、単純に古い、新しいと断定することはできないわけで、ギャモンなどの言葉もたぶんゲーリックやガーリックと混ざり合っているだろうし、いろんな方言もあったりと、ことは複雑だ。スコットランドのカントは、現在はほぼ絶滅しているが、ギャモンやシェルタは多少は単語が残っている。元々、特定のコミュニティだけで使われる秘密の言葉のようなものであり、長い歴史の中で抑圧されたりもしてきたから、他には広まらなかったんだ。 一方、イングリッシュ・ジプシーのルーツは、12世紀頃に大陸から渡ってきた人々であり、生活様式もヨーロッパのロマに近いし、音楽的にも、ロマ音楽との共通点があったりする。彼らは今はほとんどが定住している。大陸から持ち込まれたものと、元々ブリテンにあった土着なものがいろいろと混ざり合ってしまっているので、他の2グループよりも民族的アイデンティティが希薄になっている。 それら3つの集団は、顔つきなどでも判別できるものですか。 わかる。僕の住んでいるエリア(ホックニー)は、ロンドンの中でも特にアイリッシュ・トラヴェラーズが多い場所だ。僕は、見た目でわかるし、彼らも、お互い、世界中どこにいてもわかるらしい。僕はジプシーじゃないけど、リー(Lee)という姓は元々ジプシー由来のものなんだ。そして、ルックスもジプシー系だと彼らからは言われる(笑)。 そういうコミュニティにあなたは入っていったわけですが、そこでは、音楽の在り方、伝え方、楽しみ方が一般の英国人とは違うんですか。 彼らは特に歌がうまいわけじゃないし、専門的に音楽を勉強した人たちでもない。ただ、家族の中で綿々と受け継がれてきた伝統を守っているだけだ。なんだけど、たとえば僕が訪ねたキャシディという一家では、5歳から85歳まで、全員、素晴らしい声を持っていた。5歳でもポップ・スターなみに歌える。真似事で歌うことに長けているんだ。もちろん、歌が苦手なファミリーもあるけどね。あと、基本的に、伝承歌の価値を自覚していない人たちなので、古い歌と混じってボニー・タイラーなどのポップスも普通に歌う。たくさん聴かされる中に、数曲だけ古いフォーク・ソングがあったりするわけだ。だから、レコーディング作業も、けっこう忍耐を要する。信頼関係を築き、受け入れてもらうまでには長い時間がかかるわけで。いきなりテレコを突き出しても、自分を有名にしてくれると思われるか、文化を盗みに来た奴だと思われるかの、どっちかだ。だから、とにかく先方の文化に対するリスペクトの念を示し、その貴重な文化を保全したいんだという基本的姿勢を理解してもらうということから始めなくてはならない。なにしろ、ずっと搾取され、抑圧されてきた人々なので、そういうことに関しては、とても敏感なんだ。伝統がほとんど死に絶えてしまったイングランドでは、 僕みたいな者がルール無用で実験できる自由がある気がする。
あなたのデビュー・アルバムは、スコティッシュ・トラヴェラーズの民謡歌手スタンリー・ロバートソン(1940〜2009)に捧げられていますが、彼からは特にたくさんの歌を習ったんですね。 スタンリー・ロバートソンはとても面白い人だった。僕の出会ったたくさんのトラヴェラーズの歌手たちは、ほとんど、膨大にあったはずの伝承曲の中の最後の一滴程度しか持っておらず、しかもその重要性については無自覚だった。でもスタンリーは、特にスコットランドの伝統音楽がたくさん残っている地域のファミリーの、しかも最後の生き残りといっていい歌手だった。歌だけでなく、そのコミュニティで継承されてきた様々な伝統文化の知識も持っていた。スコティッシュ・トラヴェラーズの伝承歌を記録したヘミッシュ・ヘンダーソンという研究家が1950年にロバートソン・ファミリーに出会い、歌の録音を開始したんだが、その時にヘミッシュはこう言ったという。「遂に、スコットランドの古い聖杯に出会った。そして、その聖杯に注ぎきれない、ナイアガラの滝の水量ほどの伝統音楽がここにはある」と。昔から受け継がれてきた伝統音楽の最後の継承者とも言うべきスタンリーから、僕は直接教わることができて幸運だった。トラヴェラーズの多くは、近代化の中で過去を封印せざるを得なかった。だから、文化が死に絶えていった。でもスタンリーは2009年に亡くなるまで、自分の祖先としっかりとつながっていた人だったと言える。 トラヴェラーズやジプシーのコミュニティがなかったら、ブリテン諸島の伝統音楽は継承されなかったと言っていいんでしょうか。 そうだね。特にスコティッシュ・トラヴェラーズは、ブリテン諸島の伝統(音楽)の最後の保管者だと思う。僕ら英国人は、彼らには大きな借りがある。イングランドにおいては、古い文化の再評価が始まっている気がする。スコットランド、アイルランドでは、イングランドよりは古いものが大事にされてきた。でも、アイルランドでもスコットランドでも、古いものは、ルールに従って保存すべき、みたいなきらいがある。もしかしたら、もっといろんな可能性があるかもしれないのに、その可能性と、こうあるべきとする姿の間のせめぎあいの中で、大事にされすぎた局面もあると思う。リヴァーダンスのように。僕は、ああいうものは、ちょっと窮屈に感じる。対して、イングランドでは、伝統がほとんど死に絶えてしまったのが逆に功を奏して、僕みたいな者がルール無用で実験できる自由がある気がする。もちろん、その伝統を現代に生き返らせるところまではできてないけど。アイルランドなどでは、伝統が残っていたが故に、ヘタにいじりづらいというか。 そういう長年の調査・研究の成果は、現在、〈Song Collectors Collective〉というサイトで公表されてますね。そこでは、ブリテン諸島の伝統音楽の音源や映像などがアーカイヴ化され、誰でも自由に閲覧できるようになっている。素晴らしい仕事だと思います。 2013年1月に正式に立ち上げたんだが、反響がすごいんだ。英国はもちろん、アメリカやその他の国々からもたくさんアクセスがあり、いろんな反応のメールが届いている。自分としては、当然のことと思ってやっているんだけどね。もっとこうやったらいいとか、サポートのための資金を出そうとか、いろんな声が届いている。 実際、どこかから金銭的サポートはあるの? うん、英国アート・カウンシルからサポートしてもらっている。ちゃんとしたファウンデイション(基金)というシステムになっているので、ヴォランティアだけど正式な担当者もついている。このサイトを実際に現地で見せると、音楽家たちもよく理解でき、前向きに協力してくれるんだ。以前は、なんのために協力しなくちゃいけないんだ……みたいなこともあったけど。僕自身も、今も調査・採集を続けている。この(2014年)7月にも10日間ほどアイルランドに行き、たくさんの歌手たちの撮影をしてきた。まさに黄金のような旅だった。次々と新しい歌手たちが集まって、録音させてくれた。いわゆる、アイリッシュ・トラヴェラーズたちの歌だ。 〈Song Collectors Collective〉での活動は、最終的にどういうふうに持ってゆきたいと考えてますか。 まずはコントリビューターを増やし、音や映像のアーカイヴを着実に増やしてやきたい。あと、自分たちの活動のプロセスが見える形でみんなに情報を公開してゆきたい。でないと、後続者が途絶えてしまうと思うから。そして、カヴァする範囲をもっと広げてゆきたいね。現在、ブリテン諸島のものに関してはかなり充実しているとは思うけど、ジプシーはブリテン以外にもたくさんいるわけで。大陸などのジプシーまで射程に入れてゆくと、リサーチャーや収集者も現在の状況では不可能だ。言葉の問題もあるし。だから、そういった人材も増やしてゆきたい。ひとくちにジプシー・コミュニティといっても、楽曲や知識の消失具合、変化の具合も、地域の歴史によってだいぶ異なる。そういう点まできちんと把握した状態で、このサイトにはアップしてゆきたい。ブリテン諸島以外の地域まで〈ジプシー〉ということで範囲を広げてゆくことが、当面の目標かな。僕らが集めた情報をサイトにアップすることによって、実際のジプシー・コミュニティの人たちも、自分たちの過去の文化に触れ、再発見することができる。つまり、部外者だけでなく、当該者にも広く情報を知らしめる、そんなサイトにしたいんだ。伝統の本来の姿と、リヴァイヴァリストたちの表現、 そのどちらにも入り込めない距離感が、僕の批評性かもしれない。
そういえば、あなたの表現の特異さを支える最も重要なポイントは、「部外者」としての視点だと僕は考えてきました。あなたの表現には常に、対象との絶妙な距離感と批評性を感じます。 なるほど(笑)。コミュニティにはトラヴェラーズやジプシーだけでなく、フォーク・ミュージックのコミュニティというのもある。2005〜6年、伝統継承が危機的状況にあったあの時期、僕がトラヴェラーズのコミュニティに入ってゆき、教えてくれと言ったとき、こいつが引き継いでくれるかもしれないという希望を見出した人もいたかのもしれない。だからこそ、積極的に僕を支えてくれる人もいたんだと思う。その一人がシャーリー・コリンズ(註:英国伝統音楽界の伝説的歌手。現在はシンガーとしての活動は引退し、EFDSS[English Folk Dance And Song Society/英国トラディショナル・フォークの由緒ある振興団体]の会長を務めている)で、彼女はいろいろと面倒を見てくれた。でも、そういう支えがあっても、自分の中には、彼らの伝統音楽との距離感が常にあった。それは、自分はジプシー/トラヴェラーズの一員ではないという距離感であると同時に、シャーリーたち英国フォーク・コミュニティの一員でもないという距離感だ。シャーリーたち、英国フォーク音楽コミュニティは、つまりフォーク・リヴァイヴァリストたちのコミュニティだ。マーティン・カーシーとかニック・ジョーンズとか。もちろん彼らは素晴らしい音楽家だ。でも、それは僕の聴きたい音楽じゃなかった。同じ素材を使ってはいても。当時(60〜70年代のフォーク・リヴァイヴァル期)はそれでよかったかもしれないけど、今は通じないんじゃないか、という印象だった。今は更に、ローラ・マニングとかマムフォード・アンド・サンズのような新しいリヴァイヴァリストたちが注目されているけど、それがフォークだと言われると、これまた違うと僕は感じる。古いものをただなぞっているだけというか。マーティン・カーシーが60年代のフォーク・リヴァイヴァル期に「フォーク・ミュージックにとって最悪なことは、それを誰も歌ってくれないことだ」と言った。現在の僕に言わせれば、「フォーク・ミュージックにとって最悪なことは、それを変えようと誰もチャレンジしないことだ」となる。伝統は常に変化、進化してきたものだと思う。でも今のフォーク・ミュージックは、最も変化していない、ある意味固定化された音楽ではないか。そういう中にあって、伝統の本来の姿と、リヴァイヴァリストたちの表現、その2つの狭間の中で自分はどちらにも入り込めないという距離感が、一種の批評性につながっているのかもしれないね。チャレンジしない姿勢に対しては、絶対に批評性を持つべきだと思っている。エレクトロニクスなどを入れることも僕の自由だと思っているし。でも、伝統的コミュニティに入り込んでしまったがゆえに、ちゃんとしたリスペクトも持たなくてはならない。非常に微妙なポジションにあり、どこにも属さない感じがするわけで、それが批評性につながっているのかもしれないね。 (写真提供:株式会社プランクトン) 【サム・リー来日公演】 ※詳細とチケット購入は招聘元プランクトンのウェブサイトをご覧ください。 ■ケルティック・クリスマス2014~アメイジング・ヴォイス~ 出演:アヌーナ/サム・リー&フレンズ/リアム・オ・メンリィ 12/6(土)錦糸町・すみだトリフォニーホール 16:30開場/17:30開演 前売:S席6,500円/A席5,000円/B席4,000円(税込) ※当日券は500円増し お問い合わせ:トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212 ■サム・リー&フレンズ 12月8日(月)京都 磔磔 18:00開場/19:00開演 前売:3,800円(税込・ドリンク別) 発売中:プランクトン 03-3498-2881 ■ヴォイス・オブ・グラウンド 出演:サム・リー&フレンズ(イングランド/トラヴェラーズ) リアム・オ・メンリィ(アイルランド) ゲスト:OKI(アイヌ/トンコリ)/上間綾乃(沖縄/シンガー) 12月10日(水)渋谷クラブクアトロ 18:00開場/19:00開演 前売5,800円(税込/ドリンク別/自由/整理番号付・当日券500円増し) 問・予約:プランクトン 03-3498-2881(平日11~19時) ■サム・リー&フレンズ with 雅楽~イングランド伝承歌と和楽器の出会い~ 出演:サム・リー&フレンズ(イングランド/トラヴェラーズ)、東野珠実(笙)、稲葉明徳(篳篥)、〈トーク・ナビゲーター〉 小沼純一 12月11日(木)マウントレーニアホール渋谷 プレジャープレジャー 18:00開場/19:00開演 全指定席 3,000円(税込) プランクトン:03-3498-2881(平日11~19時) ※東京文化発信プロジェクト事業の一環として実施 ※未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。 ■サム・リー&フレンズ with 上間綾乃 出演:サム・リー、上間綾乃 12月13日(土)所沢市民文化センター ミューズ キューブホール 14:30開場/15:00開演 全席指定:3,800円(税込) 発売中:ミューズチケットカウンター 04-2998-7777「日本て何だろうという思いを改めて深めることができました」──松田美緒(『クレオール・ニッポン』)
松田美緒の新作『クレオール・ニッポン──うたの記憶を旅する』(アルテスパブリッシング)は画期的な作品だ。日本の音楽シーンにとっても、彼女自身のキャリアにとっても。
このアルバムは、日本の民謡や童謡などを日本語で歌った作品である。というと、すこぶる単純でありきたりなもののように聞こえるが、歌われている計14曲は、一般的にはあまり知られていない珍しいものが少なくなく、ここでの松田の歌唱によって初めて白日の下に晒されたと言っていいようなものまである。それらの楽曲は、松田自身が長い時間をかけて調べあげ、継承されてきた現地に赴き、歌の背景まできちんと調査、理解した上で録音されたものである。そして、そういった歌を巡るひとつひとつの旅を自ら文章や映像でドキュメントし、CDブックという形で世に送り出した。全身全霊を傾けた、足かけ3年のプロジェクトなのだ。
長年、ヨーロッパから南米までを旅し、様々な文化に触れ、たくさんの歌に出会ってきた松田美緒というシンガーが、いかにして今回のプロジェクトに至り、どのように考え、何を得たのか。『クレオール・ニッポン』なるアルバム・タイトルに込められた思いとは、いかなるものなのか。
 そもそも、最初に秋田の資料館に行った理由は?
私が秋田生まれだったから。幼少期の数年間、秋田の山の中で育ったんです。生まれ故郷に戻ったのは25年ぶりで。秋田は、世界のどこよりも遠い場所だったんです。
秋田の資料館以外には、どこに調査に行ったんですか。
秋田の資料館で見つけた歌に導かれる形であちこち。片っ端から聴いて、この場所は面白そうだということで、徳島の祖谷(いや)や長崎の伊王島、福岡の行橋(ゆくはし)、福島の相馬、それからブラジルのサンパウロの日伯文化協会や小笠原島にも。この作品に入っているところは全部。小笠原は一度しか行けなかったけど、祖谷には4回も行ったし。でも、その現場に行ってみても、必ずしも実際にお目当ての民謡を聴けるわけじゃない。資料館にあった録音の歌い手のほとんどは既に亡くなっているし、現地で民謡についてインタヴューできた人たちも百歳とかだった。今回行かなかったら、もう会えなかった人たちだと思います。
小笠原や祖谷などの取材映像が今ネットに上げられていますね。ということは、調査している段階から、このプロジェクトは、ただ歌うだけじゃなく、解説なども含めたメディアミックスの作品にしようと考えていたわけですか。
そうです。最初からそう思っていました。CDだけじゃなく、その歌がどういう風に歌われていたのかちゃんと自分で理解し、その全体像をそのままリスナーに届けたいという気持ちがあった。
そういったメディアミックス・プロジェクトとしてアルテスからリリースするということは、最初から決まっていたんですか。
いや、全然決まってなかった。実際、CDブックという形に決めたのは、2013年の秋ですね。「地中海の歌」をテーマにしたコンサートをリュート奏者つのだたかしさんと一緒にやった時、アルテスの方たちが聴きにきてくださり、その時に一気に話が決まったんです。で、レコーディングにもその頃から本格的に着手した。共同プロデュースを宮田茂樹さんにお願いしたのも私です。2011年の年末に宮田さんとご飯を食べた時、伊王島の「アンゼラスの歌」のことを話したのが最初のきっかけ。その後、レコーディングの段階で、宮田さんにアナログ録音のスタジオのことなどで相談し、そのまま共同プロデューサーとして参加していただきました。
そもそも、最初に秋田の資料館に行った理由は?
私が秋田生まれだったから。幼少期の数年間、秋田の山の中で育ったんです。生まれ故郷に戻ったのは25年ぶりで。秋田は、世界のどこよりも遠い場所だったんです。
秋田の資料館以外には、どこに調査に行ったんですか。
秋田の資料館で見つけた歌に導かれる形であちこち。片っ端から聴いて、この場所は面白そうだということで、徳島の祖谷(いや)や長崎の伊王島、福岡の行橋(ゆくはし)、福島の相馬、それからブラジルのサンパウロの日伯文化協会や小笠原島にも。この作品に入っているところは全部。小笠原は一度しか行けなかったけど、祖谷には4回も行ったし。でも、その現場に行ってみても、必ずしも実際にお目当ての民謡を聴けるわけじゃない。資料館にあった録音の歌い手のほとんどは既に亡くなっているし、現地で民謡についてインタヴューできた人たちも百歳とかだった。今回行かなかったら、もう会えなかった人たちだと思います。
小笠原や祖谷などの取材映像が今ネットに上げられていますね。ということは、調査している段階から、このプロジェクトは、ただ歌うだけじゃなく、解説なども含めたメディアミックスの作品にしようと考えていたわけですか。
そうです。最初からそう思っていました。CDだけじゃなく、その歌がどういう風に歌われていたのかちゃんと自分で理解し、その全体像をそのままリスナーに届けたいという気持ちがあった。
そういったメディアミックス・プロジェクトとしてアルテスからリリースするということは、最初から決まっていたんですか。
いや、全然決まってなかった。実際、CDブックという形に決めたのは、2013年の秋ですね。「地中海の歌」をテーマにしたコンサートをリュート奏者つのだたかしさんと一緒にやった時、アルテスの方たちが聴きにきてくださり、その時に一気に話が決まったんです。で、レコーディングにもその頃から本格的に着手した。共同プロデュースを宮田茂樹さんにお願いしたのも私です。2011年の年末に宮田さんとご飯を食べた時、伊王島の「アンゼラスの歌」のことを話したのが最初のきっかけ。その後、レコーディングの段階で、宮田さんにアナログ録音のスタジオのことなどで相談し、そのまま共同プロデューサーとして参加していただきました。
 鶴来正基(ピアノ)、沢田穣治(ウッドベース)、渡辺亮(パーカッション)[/caption]
今回収録された14曲を選ぶ際、最も重視したのはどういった点でしたか。
歌詞の世界観というか……世界に開かれており、根源的であるということ。局地的な歌だけど、世界のどこででも通じるような歌を選びました。
(アルテス鈴木)たとえばアルゼンチンのフォルクローレでも何でもいいんだけど、そういうのを聴いて「いい歌だな」と思うのとまったく同じ感覚で、日本語による日本の民謡を歌った人は、これまであまりいなかったと思うんですよ。民謡を民謡らしく歌う、あるいは民謡らしくなく歌う人はいたけど。そういう作為を入れず、普通に誰が聴いてもいい歌を、そのままいい歌として歌った、そんな作品だと思っています。外国の歌と同じように日本語の歌も歌えるのは松田美緒ならではの美点だし、そこは、日本より海外にいるほうがホッとするっていう彼女の独特の感覚やポジションも関係あると思う。
松田さんは、この作品を聴いたリスナーから、日本民謡に聴こえないと言われても問題ない?
もちろん。私はこれらの歌を、世界中の山や海で歌いたいし。既にカーボヴェルデの切り立った岸壁で山の歌を歌ってきたし、韓国ではキリシタンの歌がすごく受けた。似たような歴史があるからかも。小笠原の「レモングラス」などは、是非カーボヴェルデでも歌いたいですね。日本の歌というよりは、たまたま日本のある場所に暮らしていた人たちの歌、という感じで。
鶴来正基(ピアノ)、沢田穣治(ウッドベース)、渡辺亮(パーカッション)[/caption]
今回収録された14曲を選ぶ際、最も重視したのはどういった点でしたか。
歌詞の世界観というか……世界に開かれており、根源的であるということ。局地的な歌だけど、世界のどこででも通じるような歌を選びました。
(アルテス鈴木)たとえばアルゼンチンのフォルクローレでも何でもいいんだけど、そういうのを聴いて「いい歌だな」と思うのとまったく同じ感覚で、日本語による日本の民謡を歌った人は、これまであまりいなかったと思うんですよ。民謡を民謡らしく歌う、あるいは民謡らしくなく歌う人はいたけど。そういう作為を入れず、普通に誰が聴いてもいい歌を、そのままいい歌として歌った、そんな作品だと思っています。外国の歌と同じように日本語の歌も歌えるのは松田美緒ならではの美点だし、そこは、日本より海外にいるほうがホッとするっていう彼女の独特の感覚やポジションも関係あると思う。
松田さんは、この作品を聴いたリスナーから、日本民謡に聴こえないと言われても問題ない?
もちろん。私はこれらの歌を、世界中の山や海で歌いたいし。既にカーボヴェルデの切り立った岸壁で山の歌を歌ってきたし、韓国ではキリシタンの歌がすごく受けた。似たような歴史があるからかも。小笠原の「レモングラス」などは、是非カーボヴェルデでも歌いたいですね。日本の歌というよりは、たまたま日本のある場所に暮らしていた人たちの歌、という感じで。
(撮影:石田昌隆、2014年12月4日 sonoriumにて)
海外で日本の歌を歌っていても、 どこか借り物の感覚があった
松田さんに関しては、海外の伝統的な歌ばかりに取り組んできたという印象が強いのですが、2012年から、日本語で日本の歌を歌う「にほんのうた」なるプロジェクトを開始しました。きっかけはどういうことだったんでしょうか。 ヨーロッパなど海外をあちこち回り、2009年ぐらいからは毎年のように南米各地に行って歌うようになったんですが、その際、日本の歌を披露する機会がよくあったんです。でも、歌っていても、いつもどこか借り物のような感覚があった。自分の中では新しすぎる、みたいな。で、もっと古い、土着の物を歌いたいなと感じていた。それが、直接のきっかけになったと思います。 南米で、具体的にはどういった作品を歌っていたんですか。 たとえば武満徹の作品とか、中山晋平の抒情歌とか。あと、よく知られたポピュラーな民謡とか。でも、さっき言った違和感があり、当時からずっと日本の土着の歌を探していたんです。しかも、土着であるだけじゃなく、海外ともつながっている歌を。 そんな頃、2011年の終わりに、自分が幼少期を過ごした秋田県のある民俗資料館を訪れました。そこで、全国の各市町村で録音された民謡などを教育委員会が集成したアーカイヴを聴かせてもらった。で、なんとなく最初に長崎のものを探したら、伊王島(いおうじま)の民謡に出会ったんです。とても感銘を受け、これだと思った。結局、伊王島のその3曲(「アンゼラスの歌」他)を歌いたいがために「にほんのうた」プロジェクトを始めたようなものですね。で、2012年からライヴで歌い始めました。でも、最初の頃は、伊王島の歌の他、抒情歌や武満徹作品といった感じで、統一感もなくバラバラだった。これではいけないと思い、どんどん熱心に、他の地域の民謡も調べていったんです。 そもそも、最初に秋田の資料館に行った理由は?
私が秋田生まれだったから。幼少期の数年間、秋田の山の中で育ったんです。生まれ故郷に戻ったのは25年ぶりで。秋田は、世界のどこよりも遠い場所だったんです。
秋田の資料館以外には、どこに調査に行ったんですか。
秋田の資料館で見つけた歌に導かれる形であちこち。片っ端から聴いて、この場所は面白そうだということで、徳島の祖谷(いや)や長崎の伊王島、福岡の行橋(ゆくはし)、福島の相馬、それからブラジルのサンパウロの日伯文化協会や小笠原島にも。この作品に入っているところは全部。小笠原は一度しか行けなかったけど、祖谷には4回も行ったし。でも、その現場に行ってみても、必ずしも実際にお目当ての民謡を聴けるわけじゃない。資料館にあった録音の歌い手のほとんどは既に亡くなっているし、現地で民謡についてインタヴューできた人たちも百歳とかだった。今回行かなかったら、もう会えなかった人たちだと思います。
小笠原や祖谷などの取材映像が今ネットに上げられていますね。ということは、調査している段階から、このプロジェクトは、ただ歌うだけじゃなく、解説なども含めたメディアミックスの作品にしようと考えていたわけですか。
そうです。最初からそう思っていました。CDだけじゃなく、その歌がどういう風に歌われていたのかちゃんと自分で理解し、その全体像をそのままリスナーに届けたいという気持ちがあった。
そういったメディアミックス・プロジェクトとしてアルテスからリリースするということは、最初から決まっていたんですか。
いや、全然決まってなかった。実際、CDブックという形に決めたのは、2013年の秋ですね。「地中海の歌」をテーマにしたコンサートをリュート奏者つのだたかしさんと一緒にやった時、アルテスの方たちが聴きにきてくださり、その時に一気に話が決まったんです。で、レコーディングにもその頃から本格的に着手した。共同プロデュースを宮田茂樹さんにお願いしたのも私です。2011年の年末に宮田さんとご飯を食べた時、伊王島の「アンゼラスの歌」のことを話したのが最初のきっかけ。その後、レコーディングの段階で、宮田さんにアナログ録音のスタジオのことなどで相談し、そのまま共同プロデューサーとして参加していただきました。
そもそも、最初に秋田の資料館に行った理由は?
私が秋田生まれだったから。幼少期の数年間、秋田の山の中で育ったんです。生まれ故郷に戻ったのは25年ぶりで。秋田は、世界のどこよりも遠い場所だったんです。
秋田の資料館以外には、どこに調査に行ったんですか。
秋田の資料館で見つけた歌に導かれる形であちこち。片っ端から聴いて、この場所は面白そうだということで、徳島の祖谷(いや)や長崎の伊王島、福岡の行橋(ゆくはし)、福島の相馬、それからブラジルのサンパウロの日伯文化協会や小笠原島にも。この作品に入っているところは全部。小笠原は一度しか行けなかったけど、祖谷には4回も行ったし。でも、その現場に行ってみても、必ずしも実際にお目当ての民謡を聴けるわけじゃない。資料館にあった録音の歌い手のほとんどは既に亡くなっているし、現地で民謡についてインタヴューできた人たちも百歳とかだった。今回行かなかったら、もう会えなかった人たちだと思います。
小笠原や祖谷などの取材映像が今ネットに上げられていますね。ということは、調査している段階から、このプロジェクトは、ただ歌うだけじゃなく、解説なども含めたメディアミックスの作品にしようと考えていたわけですか。
そうです。最初からそう思っていました。CDだけじゃなく、その歌がどういう風に歌われていたのかちゃんと自分で理解し、その全体像をそのままリスナーに届けたいという気持ちがあった。
そういったメディアミックス・プロジェクトとしてアルテスからリリースするということは、最初から決まっていたんですか。
いや、全然決まってなかった。実際、CDブックという形に決めたのは、2013年の秋ですね。「地中海の歌」をテーマにしたコンサートをリュート奏者つのだたかしさんと一緒にやった時、アルテスの方たちが聴きにきてくださり、その時に一気に話が決まったんです。で、レコーディングにもその頃から本格的に着手した。共同プロデュースを宮田茂樹さんにお願いしたのも私です。2011年の年末に宮田さんとご飯を食べた時、伊王島の「アンゼラスの歌」のことを話したのが最初のきっかけ。その後、レコーディングの段階で、宮田さんにアナログ録音のスタジオのことなどで相談し、そのまま共同プロデューサーとして参加していただきました。
やっと自分も日本とつながった気がした
秋田の山中で生活していた幼少時、日本民謡などを習っていたと以前の取材で語られていました。ということは、日本民謡とのつきあいは、実際はとても長いわけですよね。 そういうことになるけど、あれは、習わされていたわけで、自分の歌だという実感はまったくありませんでした。ところが、今回歌った秋田民謡「山子歌」は、実は子供の頃にも歌っていたもので、最初に資料館で聴いた時、とても懐かしかったし、どこか体の中に残っているという感じがありましたね。 自分と日本の歌とのつながりを初めて実感したと。 そうです。今回のプロジェクトは、有名な日本民謡や童謡などを歌うというものではありません。異文化との交流の中で生まれた伝承歌、あるいは多様なものが混ざり合ってできた知られざる歌を見つけたので、なんとかそれを形にしたいというプロジェクト。そういう歌に出会って、やっと自分も日本とつながった気がしたんです。 逆に言えば、それ以前、ほんの3年ほど前までは、自分と日本のつながりを感じてなかったということですか。 ブラジル移民の人とか、カーボヴェルデで会ったマグロ漁船の人とかとは、つながりを感じたことがあったんだけど……(笑)。あと、日本の本当にローカルな人たち、たとえば私の親戚のお百姓さんたちが楽しく歌っている姿とか見ると、自分もその仲間だと感じるし、更に、世界のどことでも通じているなという思いはあった。日本でも、地域の人々が集まり、酔っ払いながら一緒に歌っていた時代、姿がすごく好きなんです。日本でも、そういう時代のそういう人たちに出会いたいという気持ちがずっとあった。形がきちんと整えられた民謡とは違う、コミュニティで伝えられてきた本来の伝承歌を私は探していたんだと思います。 それはもちろん、あなたが長年、世界中を旅し、様々な文化に触れ、歌に出会ってきた結果ですよね。だからこそ、そういうもの、民謡におけるひとつの普遍性を求めたと。 そうです。喜びを分かち合うため、悲しみを紛らわすために、仲間たちと歌うということ、それは世界のどこにあっても同じであり、歌の普遍的な姿だと思う。そういう歌をひとつひとつ追いかけてゆく中で、何か見えてくるんじゃないかなと思うんです。一番大事にしたのは、リズムです。歌本来のリズム
レコーディングは、鶴来正基(p)さんと渡辺亮(per)さんとのトリオを核に、沢田穣治(b)さん、早坂紗知(sax)さんも加わった5人でおこなわれています。サウンド・プロダクション、アレンジに関しては、あなたが中心になったんですか。 鶴来さん、渡辺亮さんと私の3人で一緒に。もちろん最初のイメージは私が伝えるんだけど……ここで海が大西洋になってとか、ブラジル移民の一生を描く感じで、とか、かなり抽象的な説明でしかない。一番大事にしたのは、リズムです。歌本来のリズム。その歌がずっと持っていたリズムは変えない方がいいと思って。特に仕事歌は、体の動きと一体化したものだし。 特に苦労した点は? ほとんどの曲は、2年間ライヴをやる中で作り上げてきたので、録音はわりとスムーズでした。録音自体は、14曲を2日間で終えたし。準備をしっかりやって、ほぼ一発録りのつもりで臨んだ。ただ、「トコハイ節」はかなり苦労しました。4時間ぐらいかかったかな。メンバー間のとらえ方が違ってて。私はあれはファンクだと思ったので、黒人のお兄ちゃんも踊れる感じ、アフロな感じでやりたいと思ったんです。元々、村上水軍の拠点だった簑島の歌だし。 [caption id="attachment_2901" align="alignnone" width="400"] 鶴来正基(ピアノ)、沢田穣治(ウッドベース)、渡辺亮(パーカッション)[/caption]
今回収録された14曲を選ぶ際、最も重視したのはどういった点でしたか。
歌詞の世界観というか……世界に開かれており、根源的であるということ。局地的な歌だけど、世界のどこででも通じるような歌を選びました。
(アルテス鈴木)たとえばアルゼンチンのフォルクローレでも何でもいいんだけど、そういうのを聴いて「いい歌だな」と思うのとまったく同じ感覚で、日本語による日本の民謡を歌った人は、これまであまりいなかったと思うんですよ。民謡を民謡らしく歌う、あるいは民謡らしくなく歌う人はいたけど。そういう作為を入れず、普通に誰が聴いてもいい歌を、そのままいい歌として歌った、そんな作品だと思っています。外国の歌と同じように日本語の歌も歌えるのは松田美緒ならではの美点だし、そこは、日本より海外にいるほうがホッとするっていう彼女の独特の感覚やポジションも関係あると思う。
松田さんは、この作品を聴いたリスナーから、日本民謡に聴こえないと言われても問題ない?
もちろん。私はこれらの歌を、世界中の山や海で歌いたいし。既にカーボヴェルデの切り立った岸壁で山の歌を歌ってきたし、韓国ではキリシタンの歌がすごく受けた。似たような歴史があるからかも。小笠原の「レモングラス」などは、是非カーボヴェルデでも歌いたいですね。日本の歌というよりは、たまたま日本のある場所に暮らしていた人たちの歌、という感じで。
鶴来正基(ピアノ)、沢田穣治(ウッドベース)、渡辺亮(パーカッション)[/caption]
今回収録された14曲を選ぶ際、最も重視したのはどういった点でしたか。
歌詞の世界観というか……世界に開かれており、根源的であるということ。局地的な歌だけど、世界のどこででも通じるような歌を選びました。
(アルテス鈴木)たとえばアルゼンチンのフォルクローレでも何でもいいんだけど、そういうのを聴いて「いい歌だな」と思うのとまったく同じ感覚で、日本語による日本の民謡を歌った人は、これまであまりいなかったと思うんですよ。民謡を民謡らしく歌う、あるいは民謡らしくなく歌う人はいたけど。そういう作為を入れず、普通に誰が聴いてもいい歌を、そのままいい歌として歌った、そんな作品だと思っています。外国の歌と同じように日本語の歌も歌えるのは松田美緒ならではの美点だし、そこは、日本より海外にいるほうがホッとするっていう彼女の独特の感覚やポジションも関係あると思う。
松田さんは、この作品を聴いたリスナーから、日本民謡に聴こえないと言われても問題ない?
もちろん。私はこれらの歌を、世界中の山や海で歌いたいし。既にカーボヴェルデの切り立った岸壁で山の歌を歌ってきたし、韓国ではキリシタンの歌がすごく受けた。似たような歴史があるからかも。小笠原の「レモングラス」などは、是非カーボヴェルデでも歌いたいですね。日本の歌というよりは、たまたま日本のある場所に暮らしていた人たちの歌、という感じで。
日本語で歌うことがちょっと上手になった
この作品、プロジェクトを通して、一番伝えたかったのは、どういうことでしょうか。 リスナーに伝えたかったことというよりも、自分の中で一番強く感じたことになるけど……日本も捨てたもんじゃない、ということかな。日本にもこんなに素晴らしい歌がたくさんあると。日本とか世界とか区別することなく、こんなにも根源的な歌があり、それを継承してきた素晴らしい一般の人たちが身近にいる。その人たちに出会えたことが、自分にとって最も幸運なことだったと思います。今回ここに入れることのできなかった素晴らしい歌は、まだまだたくさんあります。他にも素晴らしい歌や人が、日本にはまだまだ無数にいるんだということを今回は実感させられました。決して閉じていない日本が、確かにある。歌と海で世界とつながっている日本が、確かにある。 閉じていない日本、歌と海で世界とつながっている日本というあなたの思いは、『クレオール・ニッポン』というタイトルからも伝わってきますね。 タイトルは『クレオール・ニッポン』にしたけど、もはや、日本ということを強調しなくてもいいとも、実は思っています。まあ、日本語で歌っているので、そうしたんだけど。結果、日本て何だろうという思いを改めて深めることができました。沖縄やアイヌを今回入れなかったのは、日本というエリアや概念を勝手に決めつけたくなかったというのもあります。とりあえず、今現在の自分が理解できる日本語の歌ということで。 足かけ3年のこのプロジェクトを通して、何か新しい自分を見つけることはできましたか。 私、日本人だったんだ、ということ。より正確に言えば、クレオール日本人。これまでは、在日日本人という意識でした。この3年、ずっと通っていた南米にまったく行かなかったので、また戻れるのか、ちょっと心配でもある。ちょっと日本人になりすぎたというか(笑)。 日本人になりすぎたら、だめなんですか。 ちょっと窮屈かも(笑)……でも、日本語が理解できて良かったと、今しみじみ思っています。日本中のいろんな地域に行って、そこの人たちと密なコミュニケイションをとれる。今更ながら、そんなことの幸運を感じています。この作品のおかげで、日本語で歌うことがちょっと上手になったとも思っています。 これまでのあなたの活動を振り返ってみると、自分は何者なのかを問い続ける旅だったようにも見えますが。 うーん……いや、自分を探しているわけじゃない。世界の大きさの前で、「自分」なんてちっちゃなものは考えてられないというか。私はとにかく、世界中の素晴らしい歌、その背景にある物語や歴史に出会い、自分の中に取り込んでゆくことが楽しくて仕方ない。だから続けてこられたわけで。自分ではなく、歌を探す旅ですね。(12月19日 淡路島と鎌倉をスカイプで結んで)