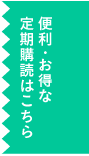4月に刊行した林達也著『新しい和声──理論と聴感覚の統合』は、東京藝術大学と同大学附属音楽高校の和声教本に採用され、「東京芸大、和声教本を半世紀ぶり刷新」(日経新聞2015年5月9日付朝刊)と新聞でも取り上げられるなど、大きな反響を呼んでいます。同書の企画にかかわった作曲家で東京藝術大学音楽学部作曲科教授・小鍛冶邦隆さんが、本誌連載「Carte blanche」において、同書といわゆる「島岡和声」の考え方の違いについて論じた原稿を、特別に公開します。

PROFILE
小鍛冶邦隆
東京藝術大学作曲科教授
こかじ・くにたか:東京藝術大学作曲科教授、慶應義塾大学講師。東京藝術大学、パリ国立高等音楽院、ウィーン国立音楽大学で学ぶ。クセナキス作曲コンクール(パリ)第1位、国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」に入選ほか。CDに《ドゥブル−レゾナンス》、銀色夏生の詩による《マドリガルⅠ〜Ⅵ》(以上ALM Records)他、著書に『作曲の思想 音楽・知のメモリア』(アルテスパブリッシング)、『作曲の技法 バッハからウェーベルンまで』(音楽之友社)、監修書にベルリオーズ/R.シュトラウス『管弦楽法』(音楽之友社)、訳書に『ケルビーニ 対位法とフーガ講座』(アルテスパブリッシング)などがある。
 林達也『新しい和声─理論と聴感覚の統合』(小社刊)
林達也著『新しい和声』の刊行は、和声教育の現場に多大な関心を引き起こしているようだ。
関係者からは、島岡譲氏が『和声 理論と実習』(音楽之友社)ほかで創案し普及させた記号から伝統的な数字付き表記への変更や、課題の質の高さについてはおおむね賛同を得ていると聞くが、一部からは、教科書としての構成や、用語や説明の一貫性について、いささかわかりづらい箇所があるという指摘がある。
そうした点については、今後の改訂で改善することができるが、一部の批判において「島岡和声」との比較があり、それらの観点こそまさに、企画にかかわった私が著者とともに『新しい和声』をつうじて議論を喚起したいと考えた点である。批判についての批判という無利益な繰り返しは避けたいが、それらの批判にみられる「島岡和声」への盲信とまた誤解こそ、日本の音楽教育の過去と現在を反映するものである以上、この連載でも取り上げる価値があると考える。
カデンツとはなにか?──和音進行、声部進行よりシンタックスへ
いくつかの批判[註1]に特徴的に見られる指摘は、『新しい和声』では、カデンツ進行の説明が不十分、あるいは重視されていないため、学習者に対して和音進行の説明が困難であるということであろう。当然ながらこれらは、「島岡和声」においては整然と記号化され、和音進行の可能性がわかりやすく整理されているという(批判者の)観点にもとづくものである。
ところで上記の批判は、記号か数字かという問題とかかわる。
歴史的にみて、和音進行は数字化された各声部の進行の結果であり、かならずしも和音進行を前提としたカデンツとして記号化できるものではない。また「カデンツ」という用語自体、cadence(カダンス)/Kadenz(カデンツ)における「Cad/Kad」の語義として「落ちる」を意味すると考えられる。「カデンツ」とは、シンタックス(構文法)における同義の用法にもあるように、一定のフレーズ構成(つまり「落ち」)を生み出す「終止形」を意味すると考えてよいであろう。
ここでの構成は、あきらかに旋律的フレーズ=テクスト的韻律を前提としたものであり、多声音楽の歴史は、「声部進行」としてこれらの旋律の音響化(構造化)をおこなってきたのである。
結果としてそこに生ずる和音は、ソノリテ(心地よい響き)として認知されるとしても、構成法としての声部進行を表記する「数字」を前提とする。同時にテクスト的=韻律的構成そのものから、音楽的シンタックス(文法)としてのカデンツ(段落)が生じる。
音楽的テクスト性を前提とした韻律的区切りとしてのカデンツは、どちらにしても「島岡和声」にある機能としてのカデンツ(あるいは和音進行の原理)でなく、さらにはかならずしも数字化されるものでもないのである。それがテクスト性をもたない器楽作品や理論的な和声法に移行されたとしても、音楽的進行がカデンツ(和声機能)として独立的に扱われることはまずないといえる[註2]。
こうした歴史的変遷における諸問題が、近代的カデンツ機能の検討に特化した理論─たとえばシェンカー理論[註3]へと展開する場面があったとしても、その前提として旋律と韻律構成の認識があることは否定できないし、残念ながら「島岡和声」においては理解されなかった(あるいは扱われなかった)問題点でもあろう。
カデンツでなく響き=聴覚で理解すべきこと
『新しい和声』のサブタイトル「聴覚と理論の統合」は、(不確かな)聴覚よりも音楽的判断にさいして記号化された思考法(「理論と実習」)を優先する「島岡和声」の姿勢に対して、前述した歴史的課題への認識も反映している(もっともこの問題は同書の範囲を超えているので、とうぜん扱う対象ではない)。
サブタイトルにある「聴覚」とは、とうぜんながらソルフェージュ教育における、音程・リズムからなる旋律的・和声的韻律(イントネーション)の訓練を意味している。つまり、『新しい和声』はたんに和声教育の方法を扱ったものというよりは、「和声」にいたる音楽的訓練のあり方をも視野に入れているのであるが、こうした問題を本文の記述と一字一句関連させて記述するのは不可能である。また批判者が厳密な定義を求めている、特定の和声進行や転調法についても、クリシェといえるこうした慣用的手法は、歴史的用法としては分類する必要があるとしても、ほんらい音楽的コンテクストにおいて選択的にもちいられる方法にすぎないため、厳密に理論的定義をおこなうことはむずかしい(同書では、こうした和声進行を作曲様式においてのみ分類している)。歴史的な「和声理論」[註4]はあくまでも聴覚上の指針と、実施における手引きなのであり、今日の和声教育においてもそれは同様なのである。
メソードとしての音楽教育
戦後日本の専門音楽教育は一連のメソードによっておこなわれてきた。『和声 理論と実習』の刊行以降、半世紀にわたっておこなわれてきた「島岡和声」の学習効果を優先したメソードは、そのひとつでもある。
「島岡和声」に先行する、「ヤマハ音楽教室」「鈴木メソード」「桐朋学園子供のための音楽教室」から今日「ピティナ」にいたるまで、歴史的・文化的背景を共有しないヨーロッパ音楽をいかに日本の文化的・経済的背景に取り込むかという問題が、大衆的レヴェルにおいて企業的・教育的に検討され、その結果として諸メソードがあるのである。
細目にわたって巧妙に設定されたメソードにより、ほんらい理解困難な技術が、平等に教育者と学習者相互の所有となるのである。
ここで所有されたものとは、とうぜんながら音楽ほんらいのあいまいなコンテクストから切り離されることにより、対象として具体性を帯び、扱い方次第で他の教育者(教育機関、団体)と学習者相互の「差別化」をたやすく生み出すことが可能となり、「教育法」として商品化できるという特権がある[註5]。
「島岡和声」もそうした一連の方式の延長線上にある。
大学や個人の「和声学習」において効率化をはかるには、とうぜんながらヨーロッパの歴史的音楽における複雑な修辞的(レトリック)問題を一時的に切り離し、音響体(和音配置)の推移としての構成(カデンツ)から、音楽を再構成することになる。それに反して、がんらい「和声」にかぎらず、「音楽」を対象とする諸言説や説明が意図せずしばしば不明瞭になるのは、前述したような根本的問題がある以上、不可避のものなのである。
「音楽教育」とはまさに「段取り」としての対処法を複数提示するのみを目的とするものであり(説明や用法が場合により多義化するのはとうぜんであろう)、たとえ集団授業であっても、それらを適切に扱うすべを教えるのは、教本でなく教育者の役目である。
『新しい和声』は「島岡和声」の歴史的意味を確認し腑観する地点に成立したものなのである[註6]。
註
[1]──Amazonの読者レビューはしばしば恣意的な判断が目立つが、批判内容については、ある意味想定される範囲でもあるので、あえて取り上げることにしたい。「筆者は長年音楽教育現場でエクリチュールを講じて来た」(木下板風)あるいは「私自身は音大出身でも専門家でもないが」(Amazonカスタマー)という違いがあるにもかかわらず、同様の批判を繰り返すところが、「島岡和声」を基点にする和声理論の興味深いところであろうか。
[2]──これらの課題(カデンツ機能)は、器楽作品における主題法・動機法、あるいは形式問題に移行する。
[3]──本連載第2回[2013年11月号]「和声理論と分析の問題」、および[註6]を参照。
[4]──「和声」とは実践なのである。歴史的な和声書ではGide(手引き)、Pratique(実用)、Traité(原義は概論というより「扱い方」)というタイトルが一般的である。著名なラモー『和声概論』(1722)は、どちらかというと理論的考察として異例(例外的)なものではあるが、それでもそこでの「カデンツ」は和声機能としてではなく終止形として考察されている。
[5]──本連載第1回[2013年9月号]「〈消費〉としての音楽教育」、第2回[2013年11月号]「音楽・社会・階級」を参照。教科書は音楽出版社がその利益をささやかながら享受することになる。
[6]──Amazonレビューにあるように、筆者が述べた「島岡和声」の世界基準としての評価は批判者の読み違いであろう。[註3]でも触れたが、水準は異なるとはいえ、同様にドグマ的理論としての「シェンカー理論とシェンカー主義者」との比較を前提として、「島岡理論」を批判的に述べた箇所が、拙著『作曲の思想─音楽 ・知のメモリア』(アルテスパブリッシング)にある(152-153ページ)。さらに日本における音楽学論文が、しばしば「島岡和声」記号による分析をおこなっている問題についてはあらためて検討する。
関連イベント
『新しい和声』の学び方・使い方
本稿で取り上げられた林達也著『新しい和声──理論と聴感覚の統合』(小社刊)は、東京藝術大学と同大学附属音楽高校の和声教本として採用され、日経新聞で取り上げられるほどの大きな反響を呼びましたが、「従来の教本とどう違うのか」「どのように教えればよいのか」「藝大はなぜいま教科書の刷新に踏み切ったのか」などのお問い合わせもいただいています。
そこで、著者の林達也(東京藝大作曲科准教授)、解説を執筆した小鍛冶邦隆(同作曲科教授)の両氏による説明会を、下記のとおり開催します。
本書の特長、他の教本との違い、学習や指導における留意点などを、鍵盤をもちいて具体的に解説し、参加者からのご質問にもお応えします(質問は事前にメールかFAXでお送りください)。
入場は無料です。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。
◎日時
第1回:6月27日(土)/第2回:7月11日(土)/第3回:8月22日(土)
時間はいずれも15:00-17:00 ※各回は基本的には同様の内容です。
◎場所
東京都千代田区西神田2-4-1 東方学会 新館2階「学び舎 遊人」
(営団地下鉄・都営地下鉄「神保町」駅「A2」出口から徒歩3分)
https://goo.gl/asavdz
◎入場料 無料
◎お申し込み
メールまたはFAXでお申し込みください。
件名を「和声説明会申し込み」とし、
◎お名前 ◎ご所属 ◎ご連絡先(メールアドレス、お電話、FAX)
◎人数 ◎日程(以上必須)
○質問事項(任意。できるだけ簡潔に)をお知らせください。
各回定員30名に達し次第、締め切らせていただきます。
お問い合わせもこちらで受け付けます。
メール:info@artespublishing.com
FAX:03-3411-7927
林達也『新しい和声─理論と聴感覚の統合』(小社刊)
林達也著『新しい和声』の刊行は、和声教育の現場に多大な関心を引き起こしているようだ。
関係者からは、島岡譲氏が『和声 理論と実習』(音楽之友社)ほかで創案し普及させた記号から伝統的な数字付き表記への変更や、課題の質の高さについてはおおむね賛同を得ていると聞くが、一部からは、教科書としての構成や、用語や説明の一貫性について、いささかわかりづらい箇所があるという指摘がある。
そうした点については、今後の改訂で改善することができるが、一部の批判において「島岡和声」との比較があり、それらの観点こそまさに、企画にかかわった私が著者とともに『新しい和声』をつうじて議論を喚起したいと考えた点である。批判についての批判という無利益な繰り返しは避けたいが、それらの批判にみられる「島岡和声」への盲信とまた誤解こそ、日本の音楽教育の過去と現在を反映するものである以上、この連載でも取り上げる価値があると考える。
カデンツとはなにか?──和音進行、声部進行よりシンタックスへ
いくつかの批判[註1]に特徴的に見られる指摘は、『新しい和声』では、カデンツ進行の説明が不十分、あるいは重視されていないため、学習者に対して和音進行の説明が困難であるということであろう。当然ながらこれらは、「島岡和声」においては整然と記号化され、和音進行の可能性がわかりやすく整理されているという(批判者の)観点にもとづくものである。
ところで上記の批判は、記号か数字かという問題とかかわる。
歴史的にみて、和音進行は数字化された各声部の進行の結果であり、かならずしも和音進行を前提としたカデンツとして記号化できるものではない。また「カデンツ」という用語自体、cadence(カダンス)/Kadenz(カデンツ)における「Cad/Kad」の語義として「落ちる」を意味すると考えられる。「カデンツ」とは、シンタックス(構文法)における同義の用法にもあるように、一定のフレーズ構成(つまり「落ち」)を生み出す「終止形」を意味すると考えてよいであろう。
ここでの構成は、あきらかに旋律的フレーズ=テクスト的韻律を前提としたものであり、多声音楽の歴史は、「声部進行」としてこれらの旋律の音響化(構造化)をおこなってきたのである。
結果としてそこに生ずる和音は、ソノリテ(心地よい響き)として認知されるとしても、構成法としての声部進行を表記する「数字」を前提とする。同時にテクスト的=韻律的構成そのものから、音楽的シンタックス(文法)としてのカデンツ(段落)が生じる。
音楽的テクスト性を前提とした韻律的区切りとしてのカデンツは、どちらにしても「島岡和声」にある機能としてのカデンツ(あるいは和音進行の原理)でなく、さらにはかならずしも数字化されるものでもないのである。それがテクスト性をもたない器楽作品や理論的な和声法に移行されたとしても、音楽的進行がカデンツ(和声機能)として独立的に扱われることはまずないといえる[註2]。
こうした歴史的変遷における諸問題が、近代的カデンツ機能の検討に特化した理論─たとえばシェンカー理論[註3]へと展開する場面があったとしても、その前提として旋律と韻律構成の認識があることは否定できないし、残念ながら「島岡和声」においては理解されなかった(あるいは扱われなかった)問題点でもあろう。
カデンツでなく響き=聴覚で理解すべきこと
『新しい和声』のサブタイトル「聴覚と理論の統合」は、(不確かな)聴覚よりも音楽的判断にさいして記号化された思考法(「理論と実習」)を優先する「島岡和声」の姿勢に対して、前述した歴史的課題への認識も反映している(もっともこの問題は同書の範囲を超えているので、とうぜん扱う対象ではない)。
サブタイトルにある「聴覚」とは、とうぜんながらソルフェージュ教育における、音程・リズムからなる旋律的・和声的韻律(イントネーション)の訓練を意味している。つまり、『新しい和声』はたんに和声教育の方法を扱ったものというよりは、「和声」にいたる音楽的訓練のあり方をも視野に入れているのであるが、こうした問題を本文の記述と一字一句関連させて記述するのは不可能である。また批判者が厳密な定義を求めている、特定の和声進行や転調法についても、クリシェといえるこうした慣用的手法は、歴史的用法としては分類する必要があるとしても、ほんらい音楽的コンテクストにおいて選択的にもちいられる方法にすぎないため、厳密に理論的定義をおこなうことはむずかしい(同書では、こうした和声進行を作曲様式においてのみ分類している)。歴史的な「和声理論」[註4]はあくまでも聴覚上の指針と、実施における手引きなのであり、今日の和声教育においてもそれは同様なのである。
メソードとしての音楽教育
戦後日本の専門音楽教育は一連のメソードによっておこなわれてきた。『和声 理論と実習』の刊行以降、半世紀にわたっておこなわれてきた「島岡和声」の学習効果を優先したメソードは、そのひとつでもある。
「島岡和声」に先行する、「ヤマハ音楽教室」「鈴木メソード」「桐朋学園子供のための音楽教室」から今日「ピティナ」にいたるまで、歴史的・文化的背景を共有しないヨーロッパ音楽をいかに日本の文化的・経済的背景に取り込むかという問題が、大衆的レヴェルにおいて企業的・教育的に検討され、その結果として諸メソードがあるのである。
細目にわたって巧妙に設定されたメソードにより、ほんらい理解困難な技術が、平等に教育者と学習者相互の所有となるのである。
ここで所有されたものとは、とうぜんながら音楽ほんらいのあいまいなコンテクストから切り離されることにより、対象として具体性を帯び、扱い方次第で他の教育者(教育機関、団体)と学習者相互の「差別化」をたやすく生み出すことが可能となり、「教育法」として商品化できるという特権がある[註5]。
「島岡和声」もそうした一連の方式の延長線上にある。
大学や個人の「和声学習」において効率化をはかるには、とうぜんながらヨーロッパの歴史的音楽における複雑な修辞的(レトリック)問題を一時的に切り離し、音響体(和音配置)の推移としての構成(カデンツ)から、音楽を再構成することになる。それに反して、がんらい「和声」にかぎらず、「音楽」を対象とする諸言説や説明が意図せずしばしば不明瞭になるのは、前述したような根本的問題がある以上、不可避のものなのである。
「音楽教育」とはまさに「段取り」としての対処法を複数提示するのみを目的とするものであり(説明や用法が場合により多義化するのはとうぜんであろう)、たとえ集団授業であっても、それらを適切に扱うすべを教えるのは、教本でなく教育者の役目である。
『新しい和声』は「島岡和声」の歴史的意味を確認し腑観する地点に成立したものなのである[註6]。
註
[1]──Amazonの読者レビューはしばしば恣意的な判断が目立つが、批判内容については、ある意味想定される範囲でもあるので、あえて取り上げることにしたい。「筆者は長年音楽教育現場でエクリチュールを講じて来た」(木下板風)あるいは「私自身は音大出身でも専門家でもないが」(Amazonカスタマー)という違いがあるにもかかわらず、同様の批判を繰り返すところが、「島岡和声」を基点にする和声理論の興味深いところであろうか。
[2]──これらの課題(カデンツ機能)は、器楽作品における主題法・動機法、あるいは形式問題に移行する。
[3]──本連載第2回[2013年11月号]「和声理論と分析の問題」、および[註6]を参照。
[4]──「和声」とは実践なのである。歴史的な和声書ではGide(手引き)、Pratique(実用)、Traité(原義は概論というより「扱い方」)というタイトルが一般的である。著名なラモー『和声概論』(1722)は、どちらかというと理論的考察として異例(例外的)なものではあるが、それでもそこでの「カデンツ」は和声機能としてではなく終止形として考察されている。
[5]──本連載第1回[2013年9月号]「〈消費〉としての音楽教育」、第2回[2013年11月号]「音楽・社会・階級」を参照。教科書は音楽出版社がその利益をささやかながら享受することになる。
[6]──Amazonレビューにあるように、筆者が述べた「島岡和声」の世界基準としての評価は批判者の読み違いであろう。[註3]でも触れたが、水準は異なるとはいえ、同様にドグマ的理論としての「シェンカー理論とシェンカー主義者」との比較を前提として、「島岡理論」を批判的に述べた箇所が、拙著『作曲の思想─音楽 ・知のメモリア』(アルテスパブリッシング)にある(152-153ページ)。さらに日本における音楽学論文が、しばしば「島岡和声」記号による分析をおこなっている問題についてはあらためて検討する。
関連イベント
『新しい和声』の学び方・使い方
本稿で取り上げられた林達也著『新しい和声──理論と聴感覚の統合』(小社刊)は、東京藝術大学と同大学附属音楽高校の和声教本として採用され、日経新聞で取り上げられるほどの大きな反響を呼びましたが、「従来の教本とどう違うのか」「どのように教えればよいのか」「藝大はなぜいま教科書の刷新に踏み切ったのか」などのお問い合わせもいただいています。
そこで、著者の林達也(東京藝大作曲科准教授)、解説を執筆した小鍛冶邦隆(同作曲科教授)の両氏による説明会を、下記のとおり開催します。
本書の特長、他の教本との違い、学習や指導における留意点などを、鍵盤をもちいて具体的に解説し、参加者からのご質問にもお応えします(質問は事前にメールかFAXでお送りください)。
入場は無料です。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。
◎日時
第1回:6月27日(土)/第2回:7月11日(土)/第3回:8月22日(土)
時間はいずれも15:00-17:00 ※各回は基本的には同様の内容です。
◎場所
東京都千代田区西神田2-4-1 東方学会 新館2階「学び舎 遊人」
(営団地下鉄・都営地下鉄「神保町」駅「A2」出口から徒歩3分)
https://goo.gl/asavdz
◎入場料 無料
◎お申し込み
メールまたはFAXでお申し込みください。
件名を「和声説明会申し込み」とし、
◎お名前 ◎ご所属 ◎ご連絡先(メールアドレス、お電話、FAX)
◎人数 ◎日程(以上必須)
○質問事項(任意。できるだけ簡潔に)をお知らせください。
各回定員30名に達し次第、締め切らせていただきます。
お問い合わせもこちらで受け付けます。
メール:info@artespublishing.com
FAX:03-3411-7927