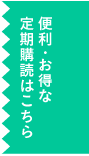去る8月13日、世界的なリコーダー奏者、指揮者のフランス・ブリュッヘンさんが逝去されました。日本を代表するチェリストで指揮者の鈴木秀美さんが、本サイトにブリュッヘンさんの思い出を寄せてくれました。

PROFILE
鈴木秀美
チェリスト、指揮者
神戸生まれ。チェロを井上頼豊、アンナー・ビルスマに師事。18世紀オーケストラに在籍。ラ・プティット・バンド、バッハ・コレギウム・ジャパンの首席チェロ奏者を務める。2001年にオーケストラ・リベラ・クラシカを結成。ハイドンをはじめ古典派を中心とする演奏活動を展開している。第37回サントリー音楽賞、第10回斎藤秀雄メモリアル基金賞受賞。山形交響楽団首席客演指揮者。著書に『「古楽器」よ、さらば!』(音楽之友社)、『ガット・カフェ』『無伴奏チェロ組曲』(以上東京書籍)。www.hidemisuzuki.com (photo by K. Miura)
2014年8月13日、あと2ヶ月半で80歳になるところだったフランス・ブリュッヘン氏が逝った。もう随分前から、その時がいつ来るかと世界が見守っていたようなものだから、突然の驚きではない。しかし、また一人、私達の生きている時代の最も優れた芸術家の一人がいなくなってしまった。その寂しさ、喪失感が日を追うごとに胸の奥にじんわりと広がっていく。
彼について語りたい想い出を持っている人は世の中に多く、いわゆる古楽という分野のみならず、およそ音楽と名の付く全てのジャンルにおいて、彼から影響を受けた人は数え切れない。彼の周りにいられた全ての音楽家は、何らかの驚くべきこと、忘れがたいことを経験したはずであり、私もまたそのような一人である。
*
リコーダー奏者としてのフランス、彼の音を実際に知っているということは今や宝物のようなものだ。彼の若かりし頃、その演奏を見たり聴いたりして一体どれだけ多くのリコーダー奏者が世界中に生まれたことだろう。日本にも訪れていたが、長身痩軀、長い脚を組んでやや俯き加減に座る独特のポーズ、大きな手と長い指で楽器を妖しげに揺らしながら吹くさま、驚きの音色と技術、言葉に尽くせない音楽性は、多くのファンを魅惑したに違いない。とはいうものの、彼がリコーダー奏者として日本に来た頃のことを私はあまり知らず、記憶や想い出の殆どはヨーロッパに住むようになってからのことである。イタリアの片田舎の教会であった一晩のソロでは、ダブダブのニットのセーターとジーンズを穿き、夏の休暇の真っ只中にこんなコンサートをさせられるのは迷惑とでも言いたげな風で現れたのだが、CDで聞き知っている曲が次々と演奏されるにつれ、独特の世界が創られていった。終演後に主催者の家でパーティがあって同席したが、彼のすぐ近くにいたのにあまり話せず、キッチンでパスタを茹でるお湯が十分沸騰していなくて不味そうだったことがなぜか蘇ってくる。*
その彼が40代後半の時に始めたのが、世界中から年に2〜3度奏者が集まる大所帯《18世紀オーケストラ》である。大所帯といっても45人前後だっただろうか。そのモデルは18世紀後半パリとマンハイムにあった大きなオーケストラであった。どちらも20〜24人のヴァイオリンに始まる大きなもので、モーツァルトが大いに喜んで第31番交響曲《パリ》を書いたこと、またハイドンがパリからの委嘱によって6曲の交響曲を書いたことはよく知られている。それを世界中の古楽のスペシャリストで構成するというフランスの夢は壮大であった。 《18世紀オーケストラ》は旅をするオーケストラである。私が参加したのは出来てまだ5年ほどの頃だ。アムステルダムの古い教会で約1週間のリハーサル、その後10〜20回近いコンサートのツァーに出かける。その間ずっと同じプログラム。同じ曲を何度も演奏するということに慣れていなかったので、最初はその事にまず驚いた。オペラや芝居、日本でも歌舞伎などでは同じ場所で何度も公演するのが当たり前なのに、音楽ではなぜか一度きり、一回に賭けるのが美しいことのように思われているが、そんな勿体ないことはないのである。 そうはいっても、移動してはコンサートを続ける日程は疲れるものだが、指揮するフランス・ブリュッヘンの音楽的エネルギーによって、私達は活かされていた。まず何と言っても、世界各国から集まる専門的な音楽家達を前に、交響曲2曲か3曲、それだけリハーサルをするだけ言うことがあるのが信じられない。その上毎回コンサートの前にもどこか必ず細かい注文がある。そしてそのリハーサルはいつも何か発見がある、かけがえのない時間であった。 18世紀の音楽に必要な様々な約束事、フレージングやアーティキュレーションを指揮でうまく表すのはなかなか難しい。ブリュッヘンはその大きな手と長い指で、文章の句点に当たるコンマを指揮する不思議な方法を見つけ出したが、それは時に実に奇妙な動きであった。背は高いが丸めた背中に長い手足、衣紋掛けが歩いているようでもあるし、ぎこちない仕草、ホッチキスを留めているような仕草をすることもあり、批判的な意見を言う聴衆も少なからずいたのだが、奏者側、少なくとも私には常に、まさしくinspiringなものであった。そしてその頃は、毎回出会う度に指揮が急速に上手くなっていったのも驚くべき事であった。 私の知るところでは一度だけ、そのオーケストラのツァーで彼がリコーダーを吹いたことがあった。大編成をバックに、彼自身が編曲したバッハのコンチェルトを演奏したのだが、特にその緩徐楽章では皆、彼を後ろから見守り聴き入って、胸一杯の静かな感動がステージの上を満たしていた。 その時はフィンランドにも行ったのだが、ツァー中の僅かな空き時間に「急流下り」を楽しみに行く時があった。どこの川だったのか、ロシアとの国境に近い辺りである。フランスをはじめ、名だたる音楽家達が皆オレンジ色の救命胴衣を付けて船に乗り込むのはとんでもなく滑稽な風景であり、そのうえフランスの怖がり方が人一倍で、みんなで笑ったものだった。そういえば彼は飛行機も怖くて嫌い、ヨーロッパ内など電車で行けるところはできるだけそうしていたそうだ。そんな彼が旅するオーケストラを作ったとは……。*
楽団を去ってから15年ほども経ったある時、ベートーヴェンの全交響曲を行う1週間程の香港公演があり、来られなくなったメンバーの代わりに参加することになった。午前中のみのリハーサルでは、未だにスラーを訂正したりアーティキュレーションを要求したりしていて、その細かさには驚いたが、ブリュッヘンはもうずっと猫背で座ったまま、やや退屈な雰囲気の時もあった。それをふと察知したのか、彼はやおら立ち上がり、フーっと両腕を拡げたかと思うと“Come on”と大きな仕草をした。突如風が吹いたか魔法にかかったか、オーケストラは白黒写真がカラーになったかのように音が変わり、私は何かヴィジョンを見ているような気さえした。まことに指揮者の仕事とは図形を描くことでも拍子を表すことでもなく、楽譜の奥や裏に秘められている何かを引き出して、言葉に出来ない稀有な時間を創り出すことなのだ。 今年の5月、フランスはデン・ハーグの音楽院を訪れ、学生達は18世紀オーケストラのメンバーと共に彼の指揮で演奏した。幸いにも、その時の様子の一部がネット上で見られるようになっている。若い学生達にとって、これほど貴重で夢のような時間はなかっただろう。己の持つエネルギーを何よりも先ず音楽のために使うのが真の芸術家、とはよく言われるところだが、それを如実に目の当たりにすることはそう多くない。*
あの魔法のような時間をもう味わうことは出来ない。しかしそのスピリットは、彼を知る世界中の音楽家の胸の裡に生き続けているはずである。私達一人ひとりが新たな魔法を創るべく努めていかなければなるまい。素晴らしい時を与えてくれた彼の魂が今は安らかにいることを心から祈りたい。