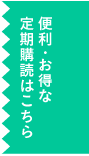アイルランドの打楽器バウロンのプレイヤー、トシバウロンさんによる世界のケルト音楽探訪記。
〈アトランティック・カナダ編〉〈オーストラリア編〉に続く第3弾は、本場スコットランドへと旅立ちます。ヨーロッパ伝統音楽のファンにはアイルランドに並んでなじみの深い地域ですが、新しい動きが目立つ近年のシーンの隆盛ぶりには、いったいどんな背景があるのか? 現地のキーパースンたちへの取材の成果をお届けします。
このあとは、さらに〈ウェールズ編〉〈マン島編〉と世界を駆けめぐっていきますので、どうぞご期待ください。
[連載記事一覧]
世界のケルト音楽を訪ねて〈アトランティック・カナダ編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈オーストラリア編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈スコットランド編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈ウェールズ編〉
世界のケルト音楽を訪ねて〈マン島編〉
世界のケルト音楽を訪ねてボーナストラック〈オーストラリア・バスキング事情 メルボルン編〉

トシバウロン
1978年、東京生まれ。日本では数少ないバウロン専門のプレーヤー。他の楽器と波長を合わせグルーヴを作り出すことに長けているが、首が曲がりメガネが弾け飛ぶほどダイナミックな動きには賛否両論がある。2000年冬アイルランド留学中にアイリッシュ音楽を始めパブセッションで研鑽を積む。現在東京にてJohn John Festivalを軸に多様な活動を展開中。2012年スペイン国際ケルト音楽フェスでHarmonica Creamsとして日本人初の優勝を果たす。葉加瀬太郎、鬼束ちひろのレコーディングにも参加。アイリッシュ・ミュージック専門イベント企画やCD販売レーベル「TOKYO IRISH COMPANY」を主宰している。http://www.t-bodhran.com/
第1回 ケルト音楽シーンの牽引役として躍進中
 ▲グラスゴーの街並み
2015年7月8日。七夕が終わった翌日、昼の12時を回ったころ、スコットランドのグラスゴーに到着した。気温は17度だったが、もっと肌寒く感じる。地元の人たちが言うには、例年もよりも寒い夏だという。日本は、というか世界的に猛暑だというのに。半袖に半ズボンの格好は間違っていたな、と内心後悔しながら、もってきたジャケットを着込んだ。予約していた宿に着くと、通りの向こうからハイランドパイプの音が聴こえてくる。いきおいスコットランドにやってきた実感が湧く。
今回の旅の目的は、昨年の東カナダ、今年のオーストラリアに引き続き、伝統音楽の調査である。スコットランドといえば去年世界的に注目を集めた場所だ。イギリスからの独立投票が実施され、わずかに反対票が上回り独立は見送られたが、開票まで結果が予想できなかったので世界中が期待と不安で見守っていた。スコットランドをイギリスの一部としてしか見ていなかった日本人には、そこまで強い民族意識があったのかと驚いたことだろう。
スコットランドといえば、日本人にはスコッチ・ウィスキーが一番馴染みがあるかもしれない。NHKの連続テレビ小説『マッサン』でも一躍脚光を浴びた。〈蛍の光〉がスコットランド民謡であることを改めて知ったり、勇壮なハイランドパイプ(スコットランドのバグパイプ)の音色に、彼の地への想いを馳せた人も多いだろう。
▲グラスゴーの街並み
2015年7月8日。七夕が終わった翌日、昼の12時を回ったころ、スコットランドのグラスゴーに到着した。気温は17度だったが、もっと肌寒く感じる。地元の人たちが言うには、例年もよりも寒い夏だという。日本は、というか世界的に猛暑だというのに。半袖に半ズボンの格好は間違っていたな、と内心後悔しながら、もってきたジャケットを着込んだ。予約していた宿に着くと、通りの向こうからハイランドパイプの音が聴こえてくる。いきおいスコットランドにやってきた実感が湧く。
今回の旅の目的は、昨年の東カナダ、今年のオーストラリアに引き続き、伝統音楽の調査である。スコットランドといえば去年世界的に注目を集めた場所だ。イギリスからの独立投票が実施され、わずかに反対票が上回り独立は見送られたが、開票まで結果が予想できなかったので世界中が期待と不安で見守っていた。スコットランドをイギリスの一部としてしか見ていなかった日本人には、そこまで強い民族意識があったのかと驚いたことだろう。
スコットランドといえば、日本人にはスコッチ・ウィスキーが一番馴染みがあるかもしれない。NHKの連続テレビ小説『マッサン』でも一躍脚光を浴びた。〈蛍の光〉がスコットランド民謡であることを改めて知ったり、勇壮なハイランドパイプ(スコットランドのバグパイプ)の音色に、彼の地への想いを馳せた人も多いだろう。
 ▲グラスゴーでハイランドパイプを吹く子供達
スコットランドはケルティック・ミュージック・シーンの中ではアイルランドに次ぐ独自の存在感を発揮している。ここ10〜20年の間には新しい試みに挑むモダンなバンドが一気に増えてきた。
日本にも数度来日しているラウー LAU、トリチェラス・オーケストラ Treacherous Orchestra、サルサ・ケルティカ Salsa Celtica、アンユージュアル・サスペクツ The unusual suspects、タナヒル・ウィーヴァーズ Tannahill Weavers、セッションA9 Session A9、そして今でも精力的に活動しているシューグルニフティ Shooglenifty、バウシュ Baucheやカパケリー Capercaillie など、伝統の枠を飛び越えたバンドは枚挙にいとまがない。60〜70年代にアイルランドが牽引したシーンの革新役を、今ではスコットランドが担っている、そんな印象すら感じる。
その躍進の原動力はどんなところにあるのだろうか? どうして新しい試みを躊躇わないのだろうか? そんな問いを持ちながら現地にやってきた。
ミュージシャンや振興組織の方々と話して知ったのは、いまや伝統音楽はスコットランドのアイデンティティーのひとつにまで復興しつつあるということ。政府からの援助金を元に伝統音楽・ダンスを復興させるべく組織化された動きが功を奏しつつあるということ。若い世代の育成が20年のスパンを経て現在の勢いにつながっていること。つまりは長期的かつ戦略的な動きが近年になっていよいよ具現化しつつあるのだ。だが、音楽を巡る状況は必ずしも伝統的に良かったわけではない。関係者の尽力の賜物なのだ。
こうした実際の事情は外側からはわかりにくいものだ。まずは飛び込んでみなければ。そんな思いで、今最も熱いシーンと言われているグラスゴーにやってきたのだった。
▲グラスゴーでハイランドパイプを吹く子供達
スコットランドはケルティック・ミュージック・シーンの中ではアイルランドに次ぐ独自の存在感を発揮している。ここ10〜20年の間には新しい試みに挑むモダンなバンドが一気に増えてきた。
日本にも数度来日しているラウー LAU、トリチェラス・オーケストラ Treacherous Orchestra、サルサ・ケルティカ Salsa Celtica、アンユージュアル・サスペクツ The unusual suspects、タナヒル・ウィーヴァーズ Tannahill Weavers、セッションA9 Session A9、そして今でも精力的に活動しているシューグルニフティ Shooglenifty、バウシュ Baucheやカパケリー Capercaillie など、伝統の枠を飛び越えたバンドは枚挙にいとまがない。60〜70年代にアイルランドが牽引したシーンの革新役を、今ではスコットランドが担っている、そんな印象すら感じる。
その躍進の原動力はどんなところにあるのだろうか? どうして新しい試みを躊躇わないのだろうか? そんな問いを持ちながら現地にやってきた。
ミュージシャンや振興組織の方々と話して知ったのは、いまや伝統音楽はスコットランドのアイデンティティーのひとつにまで復興しつつあるということ。政府からの援助金を元に伝統音楽・ダンスを復興させるべく組織化された動きが功を奏しつつあるということ。若い世代の育成が20年のスパンを経て現在の勢いにつながっていること。つまりは長期的かつ戦略的な動きが近年になっていよいよ具現化しつつあるのだ。だが、音楽を巡る状況は必ずしも伝統的に良かったわけではない。関係者の尽力の賜物なのだ。
こうした実際の事情は外側からはわかりにくいものだ。まずは飛び込んでみなければ。そんな思いで、今最も熱いシーンと言われているグラスゴーにやってきたのだった。
第2回 スコットランド伝統音楽の基礎
第3回 グラスゴー・シーンの現在
 ▲The Ivory Hotelでのセッション
グラスゴーに集まっているミュージシャンも、イギリス全土から来ているのかと思うほど多彩だ。ハイランドから出てきた若者もいれば、北部の諸島、オークニー Orkney やシェトランド Shetland 出身のミュージシャンもいる。彼らは伝統的にフィドルが強く、レパートリーもまた独特のため、グラスゴーのセッションでお目にかかる曲や演奏スタイルに彩りを添えている。今回の取材で出会ったなかでは、ロス・クーパー Ross Couper というシェトランド出身の20代後半のフィドラーに惹かれた。数多の腕利き達が霞んで見えるくらい、剛腕かつ超速で曲を弾く姿がシェトランドの荒波を感じさせた。
▲The Ivory Hotelでのセッション
グラスゴーに集まっているミュージシャンも、イギリス全土から来ているのかと思うほど多彩だ。ハイランドから出てきた若者もいれば、北部の諸島、オークニー Orkney やシェトランド Shetland 出身のミュージシャンもいる。彼らは伝統的にフィドルが強く、レパートリーもまた独特のため、グラスゴーのセッションでお目にかかる曲や演奏スタイルに彩りを添えている。今回の取材で出会ったなかでは、ロス・クーパー Ross Couper というシェトランド出身の20代後半のフィドラーに惹かれた。数多の腕利き達が霞んで見えるくらい、剛腕かつ超速で曲を弾く姿がシェトランドの荒波を感じさせた。
 ▲グラスゴーのパブ Ben Nevisでのセッション
グラスゴーでの初日に私が参加させてもらったセッションは、Solansという市内中心地にあるパブでのものだった。人数こそ少なかったが(グラスゴーのセッションはたいてい人で溢れている)、グラスゴーの質と混交を見事に反映させている、そんなセッションだった。参加していたミュージシャンは、地元出身のハープ奏者レイチェル・ヘア Rachel Hair と、マン島出身のブズーキ奏者アダム・ルーデス Adam Rhodes、アイルランドはコーク出身のイーリアン・パイプス奏者ライアン・マーフィー Ryan Murphy とグラスゴー出身だがアイリッシュ家系のボタン・アコーディオン奏者パディー・カラハン Paddy Callaghan。
歳は20代後半から30代前半というところだろうか。皆、技量がものすごく高く、場慣れしている。後から知ったのだが、それぞれバンドに参加しながら国内外を頻繁にツアーしている、まさに旬のミュージシャン達だった。これはなかなか刺激的な場所に来たな、と気合いを入れ直した。
▲グラスゴーのパブ Ben Nevisでのセッション
グラスゴーでの初日に私が参加させてもらったセッションは、Solansという市内中心地にあるパブでのものだった。人数こそ少なかったが(グラスゴーのセッションはたいてい人で溢れている)、グラスゴーの質と混交を見事に反映させている、そんなセッションだった。参加していたミュージシャンは、地元出身のハープ奏者レイチェル・ヘア Rachel Hair と、マン島出身のブズーキ奏者アダム・ルーデス Adam Rhodes、アイルランドはコーク出身のイーリアン・パイプス奏者ライアン・マーフィー Ryan Murphy とグラスゴー出身だがアイリッシュ家系のボタン・アコーディオン奏者パディー・カラハン Paddy Callaghan。
歳は20代後半から30代前半というところだろうか。皆、技量がものすごく高く、場慣れしている。後から知ったのだが、それぞれバンドに参加しながら国内外を頻繁にツアーしている、まさに旬のミュージシャン達だった。これはなかなか刺激的な場所に来たな、と気合いを入れ直した。
 ▲Solansでのセッション
その後グラスゴーには足掛け1週間ほど滞在することになったが、どのセッションもハイ・レベルだった。グラスゴーのミュージシャンたちが口を揃えて言うのは「いつでも演奏する機会はあって、レベルが高く刺激的だ」ということだ。地域コミュニティー内での満足度は音楽の練度につながっていくのだろう。
▲Solansでのセッション
その後グラスゴーには足掛け1週間ほど滞在することになったが、どのセッションもハイ・レベルだった。グラスゴーのミュージシャンたちが口を揃えて言うのは「いつでも演奏する機会はあって、レベルが高く刺激的だ」ということだ。地域コミュニティー内での満足度は音楽の練度につながっていくのだろう。
第4回 ルア・マクミランとパディー・カラハンに聞く
第5回 サイモン・トゥミアの戦略
 ▲サイモン・トゥミア
サイモンのオフィシャルサイト
サイモンは様々な肩書きを持つ人物だ。まずミュージシャンであること。楽器はコンサーティーナを演奏する。その腕前は確かで、BBC Radio2主催のコンテストでも1989年に優勝している。またFoot somping recordingというレーベルを家族で経営していた。いまはAmazonやitunesなど配信の力に押されて2年前にこの事業は畳んだという。正直ほっとしているよ、とサイモンは言った。「実は白状するけど、僕はいま一切CDを買ってないんだ。CDプレーヤーもないしね。整理が面倒だからすべて音源をダウンロードしているよ」
彼がレーベルと並行して始めた事業が、いま生活の中核をなしているようだ。それは「Hands up for trad」というスコットランド伝統音楽振興組織だ。「情報、教育、および提言を通して伝統音楽をもっと広く伝える」ことを使命とし活動している。BBC Radio Scotland Young Traditional Musican Awardもサイモンの提案で始まった。
「私がこのコンペティションを始めたのは、スコットランド音楽が本質的にコンペが好きだとかは関係なく(まったくコンペと関係なく運営されている組織もあるしね)キャリア形成のためには本当に素晴らしい機会だということと、それが人々の記憶にも残りやすく、メディアを巻き込めるからだ。反対する人がいるのもわかるけど、勝者が紙面を飾ることの意義は大きいよね。たしかに出場者がメーリングリストなどで多くのサポーターを事前に獲得していれば受賞しやすいといった不公平な点があり、それはネガティブな要素かもしれない。でも、私はそんな瑣末なことよりももっと大きな青写真に興味があり、多くの人を取り込みたいと思っている。実際かなりの人がコンペをきっかけに伝統音楽を聞くようになったと思うよ」
こうした企画を成立させたのも、Creative Scotland(旧スコティッシュアーツ・カウンシル)から予算がおりるようになったのが大きいという。「例えば去年、2014年はCreative Scotlandから3年分の予算をもらうことができたから、これまでのプロジェクトを促進させることができる。80年代はこうした援助を政府からもらうことができなかったから、皆手弁当でアマチュア的な対応をしていたものだ。当時クラシック音楽に組まれていた予算が伝統音楽にまわるように、スコティッシュ・アーツ・カウンシルが方針を変えたのは大きな決断だった。財源はとても大事だ。例えばイングランドはこの財源がカットされたため、伝統音楽が衰退している」
サイモンはHands up for tradの他に、財源を割り当てられ伝統音楽の復興と発展に寄与している組織として以下の3つを挙げてくれた。
Feisean nan gaidheal(フェイスアンナグエル)
──ガーリック文化振興のための機関、伝統音楽やダンスも含む。
Feis Rois(フェイスロス)
──フェイスアングエル傘下の機関で、伝統音楽を学校に普及させることに特化している。
TRACS(Traditional Arts and Culture Scotland)
──口承文学、音楽、ダンスという3つの伝統芸術の振興を目的として、2012年に創設された。
こうした組織が20年間かけて培ってきた成果が今になって現れている、とサイモンは言う。
サイモンにはずばり、スコティッシュ・ミュージックがどうしてクリエイティヴなことに意欲的なのか、と尋ねてみた。彼はアイリッシュ・ミュージックを引き合いに、こんな風に答えている。
「アイルランドにはプランクシティやボシー・バンドのようにすべてを変えたようなバンドがいて、全てのスコティッシュバンドも影響を受けた。しかしアイルランドは未だに彼らの影響下で戦っているようにみえる。一方で、スコットランドは80年代から実験的な表現に取り組み始めた。ジャズやファンクなどとの融合がその例だ。アイリッシュは本当に好きだが、時々ファンシーじゃないと感じるときがある。
なぜスコットランドはそういう気質になったのか、正直なところはわからない。ただ、我々はクロスオーバーしていくことに自信をもっていて、色んな音楽に興味がある。でも伝統音楽を愛しているのは間違いなくて、それが中心にある。トリチェラス・オーケストラやクロフト・ナンバー5 Croft No.5 などは最近のクロスオーバーのいい例だと思う」
https://www.youtube.com/watch?v=AUSV56QsHIg
♪Treacherous Orchestra〈Superfly〉
では、と矛先をかえて少し意地悪な質問をしてみた。世界的な影響力ではアイルランドに勝るものはなく、一人勝ちしているようにもみえるが、これはどうして起きた現象なのか? サイモンはあえて否定もせず、その話はしばしば私の仲間内でも議題に上るよ、と言いながら答えてくれた。
「アイルランド音楽がこんなに世界的に普及しているのはギネス(・ビール)の影響が大きい。伝統音楽を普及戦略の一部として取り込んだ結果(ハープの紋章がそれを象徴している)、世界中のどこでもギネスを飲み、アイリッシュ音楽を楽しむことができるようになった。スコットランドにはギネスのように強いブランドがなく、それが普及の点で、アイリッシュ音楽に遅れをとっている原因だと思う。
アイリッシュ音楽にはメインのキーがDやGの曲が多いというのも広く普及した理由の一つかもしれない。プレーヤーにとっては弾きやすいだろう。対してスコティッシュはAやEやフラットやシャープが多い。曲調は明るいが、弾きにくさは増す。セッションなどでアイリッシュ・チューンが多く演奏されているのには、そうした側面もあると思う」
しかし、サイモンはアイルランド国内の状況について、以下のように釘を刺している。
「ただ、アイルランドにも問題はあると思う。それは国内では音楽にお金を払わない、という点だ。アイルランドでは多くのライヴが無料で聴けてしまう。だから、バンドであってもアイルランドでツアーするのはとても難しい。スコットランドの状況はそれとは違う」
▲サイモン・トゥミア
サイモンのオフィシャルサイト
サイモンは様々な肩書きを持つ人物だ。まずミュージシャンであること。楽器はコンサーティーナを演奏する。その腕前は確かで、BBC Radio2主催のコンテストでも1989年に優勝している。またFoot somping recordingというレーベルを家族で経営していた。いまはAmazonやitunesなど配信の力に押されて2年前にこの事業は畳んだという。正直ほっとしているよ、とサイモンは言った。「実は白状するけど、僕はいま一切CDを買ってないんだ。CDプレーヤーもないしね。整理が面倒だからすべて音源をダウンロードしているよ」
彼がレーベルと並行して始めた事業が、いま生活の中核をなしているようだ。それは「Hands up for trad」というスコットランド伝統音楽振興組織だ。「情報、教育、および提言を通して伝統音楽をもっと広く伝える」ことを使命とし活動している。BBC Radio Scotland Young Traditional Musican Awardもサイモンの提案で始まった。
「私がこのコンペティションを始めたのは、スコットランド音楽が本質的にコンペが好きだとかは関係なく(まったくコンペと関係なく運営されている組織もあるしね)キャリア形成のためには本当に素晴らしい機会だということと、それが人々の記憶にも残りやすく、メディアを巻き込めるからだ。反対する人がいるのもわかるけど、勝者が紙面を飾ることの意義は大きいよね。たしかに出場者がメーリングリストなどで多くのサポーターを事前に獲得していれば受賞しやすいといった不公平な点があり、それはネガティブな要素かもしれない。でも、私はそんな瑣末なことよりももっと大きな青写真に興味があり、多くの人を取り込みたいと思っている。実際かなりの人がコンペをきっかけに伝統音楽を聞くようになったと思うよ」
こうした企画を成立させたのも、Creative Scotland(旧スコティッシュアーツ・カウンシル)から予算がおりるようになったのが大きいという。「例えば去年、2014年はCreative Scotlandから3年分の予算をもらうことができたから、これまでのプロジェクトを促進させることができる。80年代はこうした援助を政府からもらうことができなかったから、皆手弁当でアマチュア的な対応をしていたものだ。当時クラシック音楽に組まれていた予算が伝統音楽にまわるように、スコティッシュ・アーツ・カウンシルが方針を変えたのは大きな決断だった。財源はとても大事だ。例えばイングランドはこの財源がカットされたため、伝統音楽が衰退している」
サイモンはHands up for tradの他に、財源を割り当てられ伝統音楽の復興と発展に寄与している組織として以下の3つを挙げてくれた。
Feisean nan gaidheal(フェイスアンナグエル)
──ガーリック文化振興のための機関、伝統音楽やダンスも含む。
Feis Rois(フェイスロス)
──フェイスアングエル傘下の機関で、伝統音楽を学校に普及させることに特化している。
TRACS(Traditional Arts and Culture Scotland)
──口承文学、音楽、ダンスという3つの伝統芸術の振興を目的として、2012年に創設された。
こうした組織が20年間かけて培ってきた成果が今になって現れている、とサイモンは言う。
サイモンにはずばり、スコティッシュ・ミュージックがどうしてクリエイティヴなことに意欲的なのか、と尋ねてみた。彼はアイリッシュ・ミュージックを引き合いに、こんな風に答えている。
「アイルランドにはプランクシティやボシー・バンドのようにすべてを変えたようなバンドがいて、全てのスコティッシュバンドも影響を受けた。しかしアイルランドは未だに彼らの影響下で戦っているようにみえる。一方で、スコットランドは80年代から実験的な表現に取り組み始めた。ジャズやファンクなどとの融合がその例だ。アイリッシュは本当に好きだが、時々ファンシーじゃないと感じるときがある。
なぜスコットランドはそういう気質になったのか、正直なところはわからない。ただ、我々はクロスオーバーしていくことに自信をもっていて、色んな音楽に興味がある。でも伝統音楽を愛しているのは間違いなくて、それが中心にある。トリチェラス・オーケストラやクロフト・ナンバー5 Croft No.5 などは最近のクロスオーバーのいい例だと思う」
https://www.youtube.com/watch?v=AUSV56QsHIg
♪Treacherous Orchestra〈Superfly〉
では、と矛先をかえて少し意地悪な質問をしてみた。世界的な影響力ではアイルランドに勝るものはなく、一人勝ちしているようにもみえるが、これはどうして起きた現象なのか? サイモンはあえて否定もせず、その話はしばしば私の仲間内でも議題に上るよ、と言いながら答えてくれた。
「アイルランド音楽がこんなに世界的に普及しているのはギネス(・ビール)の影響が大きい。伝統音楽を普及戦略の一部として取り込んだ結果(ハープの紋章がそれを象徴している)、世界中のどこでもギネスを飲み、アイリッシュ音楽を楽しむことができるようになった。スコットランドにはギネスのように強いブランドがなく、それが普及の点で、アイリッシュ音楽に遅れをとっている原因だと思う。
アイリッシュ音楽にはメインのキーがDやGの曲が多いというのも広く普及した理由の一つかもしれない。プレーヤーにとっては弾きやすいだろう。対してスコティッシュはAやEやフラットやシャープが多い。曲調は明るいが、弾きにくさは増す。セッションなどでアイリッシュ・チューンが多く演奏されているのには、そうした側面もあると思う」
しかし、サイモンはアイルランド国内の状況について、以下のように釘を刺している。
「ただ、アイルランドにも問題はあると思う。それは国内では音楽にお金を払わない、という点だ。アイルランドでは多くのライヴが無料で聴けてしまう。だから、バンドであってもアイルランドでツアーするのはとても難しい。スコットランドの状況はそれとは違う」
第6回 民族意識の象徴としての音楽



 ▲スカイ島の写真、タリスカー蒸留所数点
スカイ島は風光明媚な場所として知られ、夏は観光客で溢れかえっている。ウィスキー・メーカー、タリスカー Talisker の蒸留所がある島としても有名だ。ポートリー Portree が島で一番大きな街になる。アーサーと待ち合わせをしたのは朝の10時頃だった。1軒だけ開いているカフェに連れて行ってもらった。組織の長を務めており、長年伝統音楽シーンに関わっているアーサーの話は示唆に富んでいた。以下要約する。
「フェイスアンナグエル Feisean nan gaidheal(以下フェイスアン)はガーリック文化芸術振興を目的として1991年に設立された組織だ。設立の5年前からCreative Scotlandをはじめとした財団からの資金援助を募り始め、現在の形ができあがった。いまでは46あるスコットランド各地のフェイスアン Feisean(Festival)を統括し、ボランティアを募って運営している。そこでは主に伝統音楽、芸能を子供達に教えている。
フェイスアンは元々コンペティションから脱却するために始められた。伝統音楽の世界では、必ずしもコンペティションに参加するのを好まない人たちもいるからだ。競い合わず、伸び伸びと演奏の仕方を学ぶことができる場として機能している。そして今はコンペとフェイスアンの両輪が若者たちを支えている。
RCSが90年代に伝統音楽コースを設立したことで、様々な機関が同時に伝統音楽を盛り上げるために設立されていった。
財源の母体となるCreative Scotland。ジョン・マーフィー John Murphy という男がいて、彼は伝統音楽やコミュニティーのあり方に強い関心を持っていた。それ以前はクラシック音楽に資金を援助していたが、優先順位が変わり、伝統音楽に資金が割り当てられるようになると、急速に若い人たちをガーリック伝統音楽の世界に取り込むことができるようになった。その数は毎年400〜500人にも及ぶ。彼の前にはなかった現象だ。こうしたムーヴメントの中で成長した若者たちには、RSCなどで教鞭をとったり、フルタイムで音楽をやったりしている人が多い。
同時期、コンサートホールinグラスゴーは、閑散期だった1月になにかケルト音楽のフェスをできないかと企画した。これがケルティック・コネクションだ。当初はごく小さな規模だったのが、今では巨大なフェスに成長した」
ケルティック・コネクションのウェブサイト
アーサーは、こうした動きが同時に起きた最大の理由は政治的なものだ、と言う。スコットランドが民族としてのアイデンティティーを獲得するために伝統芸能、音楽を必要としたのだ。実際、昨年実施されたイギリスからの独立の是非を問う投票でも、伝統音楽はスコットランドのアイデンティティーを象徴するものとして注目された。
こうした機運の中でスコティッシュ・アーツ・カウンシルが伝統音楽を支援し始めたことで、それ以前にはありえなかったことが起きるようになった。「重要なことはこれがいまでも続いているということだ」とアーサーは言う。伝統音楽への需要の高まりは常に意識されていて、援助は切れることがないというのだ。
「若者を地域レベルで伝統音楽の世界に取り込む試みが功を奏しつつあるが、それは何年もかけて音楽の仕事を増やしてきたからだ。例えばフェイスアンで育った若者たちが、30代、40代になって教える側に回っているのは良い例だ。給料がとくに高いわけでもないが、彼らにとっていい経験になるのだろう。そしてそれは過去10年の間に公的な教育機関にまで浸透しつつある。クラシックの音楽教育が伝統音楽へと徐々に転換しつつあるのだ。といっても未だにクラシックの教育を受けた先生のほうが多数派だが、40〜50年後に伝統音楽がそれに取って代わっていたら素晴らしいと思う。それは私たちの教育のあり方の正しさを示しているからだ」とアーサーはインタビューを締めくくってくれた。
▲スカイ島の写真、タリスカー蒸留所数点
スカイ島は風光明媚な場所として知られ、夏は観光客で溢れかえっている。ウィスキー・メーカー、タリスカー Talisker の蒸留所がある島としても有名だ。ポートリー Portree が島で一番大きな街になる。アーサーと待ち合わせをしたのは朝の10時頃だった。1軒だけ開いているカフェに連れて行ってもらった。組織の長を務めており、長年伝統音楽シーンに関わっているアーサーの話は示唆に富んでいた。以下要約する。
「フェイスアンナグエル Feisean nan gaidheal(以下フェイスアン)はガーリック文化芸術振興を目的として1991年に設立された組織だ。設立の5年前からCreative Scotlandをはじめとした財団からの資金援助を募り始め、現在の形ができあがった。いまでは46あるスコットランド各地のフェイスアン Feisean(Festival)を統括し、ボランティアを募って運営している。そこでは主に伝統音楽、芸能を子供達に教えている。
フェイスアンは元々コンペティションから脱却するために始められた。伝統音楽の世界では、必ずしもコンペティションに参加するのを好まない人たちもいるからだ。競い合わず、伸び伸びと演奏の仕方を学ぶことができる場として機能している。そして今はコンペとフェイスアンの両輪が若者たちを支えている。
RCSが90年代に伝統音楽コースを設立したことで、様々な機関が同時に伝統音楽を盛り上げるために設立されていった。
財源の母体となるCreative Scotland。ジョン・マーフィー John Murphy という男がいて、彼は伝統音楽やコミュニティーのあり方に強い関心を持っていた。それ以前はクラシック音楽に資金を援助していたが、優先順位が変わり、伝統音楽に資金が割り当てられるようになると、急速に若い人たちをガーリック伝統音楽の世界に取り込むことができるようになった。その数は毎年400〜500人にも及ぶ。彼の前にはなかった現象だ。こうしたムーヴメントの中で成長した若者たちには、RSCなどで教鞭をとったり、フルタイムで音楽をやったりしている人が多い。
同時期、コンサートホールinグラスゴーは、閑散期だった1月になにかケルト音楽のフェスをできないかと企画した。これがケルティック・コネクションだ。当初はごく小さな規模だったのが、今では巨大なフェスに成長した」
ケルティック・コネクションのウェブサイト
アーサーは、こうした動きが同時に起きた最大の理由は政治的なものだ、と言う。スコットランドが民族としてのアイデンティティーを獲得するために伝統芸能、音楽を必要としたのだ。実際、昨年実施されたイギリスからの独立の是非を問う投票でも、伝統音楽はスコットランドのアイデンティティーを象徴するものとして注目された。
こうした機運の中でスコティッシュ・アーツ・カウンシルが伝統音楽を支援し始めたことで、それ以前にはありえなかったことが起きるようになった。「重要なことはこれがいまでも続いているということだ」とアーサーは言う。伝統音楽への需要の高まりは常に意識されていて、援助は切れることがないというのだ。
「若者を地域レベルで伝統音楽の世界に取り込む試みが功を奏しつつあるが、それは何年もかけて音楽の仕事を増やしてきたからだ。例えばフェイスアンで育った若者たちが、30代、40代になって教える側に回っているのは良い例だ。給料がとくに高いわけでもないが、彼らにとっていい経験になるのだろう。そしてそれは過去10年の間に公的な教育機関にまで浸透しつつある。クラシックの音楽教育が伝統音楽へと徐々に転換しつつあるのだ。といっても未だにクラシックの教育を受けた先生のほうが多数派だが、40〜50年後に伝統音楽がそれに取って代わっていたら素晴らしいと思う。それは私たちの教育のあり方の正しさを示しているからだ」とアーサーはインタビューを締めくくってくれた。