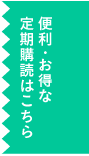本サイトの「特別公開」、「『新しい和声』──長き迷妄の時刻(とき)の後に」に引き続き、『新しい和声』の企画にかかわった作曲家で東京藝術大学音楽学部作曲科教授・小鍛冶邦隆による、同書に寄せられた批判へのコメントです。この原稿は、本誌連載「Carte blanche」に掲載されたものです。

PROFILE
小鍛冶邦隆
東京藝術大学作曲科教授
こかじ・くにたか:東京藝術大学作曲科教授、慶應義塾大学講師。東京藝術大学、パリ国立高等音楽院、ウィーン国立音楽大学で学ぶ。クセナキス作曲コンクール(パリ)第1位、国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」に入選ほか。CDに《ドゥブル−レゾナンス》、銀色夏生の詩による《マドリガルⅠ〜Ⅵ》(以上ALM Records)他、著書に『作曲の思想 音楽・知のメモリア』(アルテスパブリッシング)、『作曲の技法 バッハからウェーベルンまで』(音楽之友社)、監修書にベルリオーズ/R.シュトラウス『管弦楽法』(音楽之友社)、訳書に『ケルビーニ 対位法とフーガ講座』(アルテスパブリッシング)などがある。
 林達也『新しい和声──理論と聴感覚の統合』(小社刊)
電子版アルテスでの本連載、Carte blancheは最終回となるが、このところその評価をめぐり、とりわけ一部の読者による批判が絶えない、林達也『新しい和声』についての私の考えを、前回[第11回、2015年6月号]に引き続き再度書いておこう。
反好事家(アンティ・ディレッタント)のために
『ムッシュ・クロッシュ・アンティ・ディレッタント(反好事家八分音符氏)』として知られるドビュッシーの辛辣な評論集は、作曲家の音楽観、他人の作品評などで構成され、ドビュシー生前に出版が企画されたが、けっきょく死後、1921年に刊行された。
音楽に関する教訓・教育(Didactique)というものが、いかに狭量でしばしば独裁的(Dictature)な影響力をともなうか、また、それらにかかわる人たちを好事家(ディレッタント Dilettante)[註1]として、音楽に敵対するものとしている。
私が批判の対象として取り上げるのは、アマゾン評者[註2]のごとく好事家にして独学者(Auto-didacteur)である。ドビュッシーの著作の登場人物、八分音符(クロッシュ)氏ならぬ二分音符(ブランシュ)氏による好事家への勘定書(キャルト Carte)として、反好事家(アンティ・ディレッタント)のCarte blancheというわけである。
独学者(Auto-didacteur)のために
「独学者」とは魅力的な言葉だ。
ただし、アマゾン評で誤解されているが、和声の「初歩の学習」と「独習」は異なり、「独習=独学」とはある程度の音楽的素養(たとえば演奏技術を習得していること)、また、なによりも歴史的に音楽文化水準の保証された社会環境を前提としたものであるのは明らかだ。ヨーロッパ社会において「独学」とは、究極的にはじゅうぶんな音楽的環境が保証されながらも「意思による独学者」(ブーレーズ)たらんことをいうこととなろう。
いっぽう、日本の戦後の音楽専門教育は、さまざまな学習「メソード」の開発により、消費者(学習者)主体の選択的な音楽教育として今日に至っている[註3]。
学習者は内容あるいは効率性という基準から、諸メソードを標榜する音楽教育を自ら選択し、それらの指導者のもと、「相性と結果」を考慮しつつ音楽を学ぶのである。
「独学=独習」もこうしたメソードの一形態であろうが、ただし一般的に指導者なしにおこなう学習は、前述したように「初歩」というよりはむしろじゅうぶんな音楽的能力を条件とする。
また、アマゾン評者が常用する「教本」という用語も、理論書で一般的にもちいられる「理論(Théorie)」「概論(Traité)」や「摘要(Présis)」と異なり、あきらかに「メソード(教則本 Méthode)」を指していると思われる[註4]。
「島岡和声」は、「理論と実習」の両側面を兼ね備えた、戦後のもっとも優れた和声学習の「メソード」なのである。そこ(「島岡和声」)では、「響き」も理論的演繹から生じる。論理の組み立ては正確で、それこそがアマゾン評者をして、完璧な「響き」と錯覚させるのであろう。しかしながら「響き」とは、訓練によって獲得された聴覚のことなのである。「和声的」感覚は、音楽基礎訓練=ソルフェージュと器楽演奏訓練における身体性の自覚から生まれるのである(当然ながら「島岡和声」は、それらを反映したものではない)。
和声的感覚とは、指導者(教師)の助言のもとでの実践的な学習・教育から、帰納的にいくつかの「選択的」判断による、(演奏技術修得同様の)「音楽的行為」として修得されるのものである。『新しい和声』における「美しい音響を聴きとる」とは、それらのプロセスをいうにすぎない。
専門音楽教育においては教師が必要であり、「教育」とは教師と学習者の相互的水準の平均値で構成されるものである。『新しい和声』が東京藝術大学音楽学部の和声教科書として採用されたのは、こうした基準の設定であり、藝大教育だけを意図したものでないのは自明のことである。
さらに和声理論を中心にした、「音楽分析」あるいは音楽学研究における「作品分析」とのかかわりについて書いておきたい。
分析=理解と記述──「作品」をいかに対象化するのか
音楽学論文中で必要とされる音楽分析において、日本では執筆者の大半は「島岡和声」にもとづく方法をもちいているものと思われる。問題は「島岡式」理論や記号にあるというより、「音楽作品」と、その理解・記述の背反にあると考えなければならない。
歴史的な音楽作品を対象とするとき、「作品」は、その作品が生み出された時代様式と、その前提となる「音楽理論」から分析されなければならないのは当然のことであろう。
「島岡和声」のように優れて理論化された方法においては、当然ながら歴史性や時代的特質は抽象化される。ある意味使いやすいその手法により、歴史的作品が理解され、また(「島岡和声」)独自の理論・記号体系から記述されるのである。表層的な「様式」理解をうんぬんしても、そもそも分析の前提となるべき理論的背景がかならずしも「様式的」ではないのである[註5]。
「作品」とは、その時代におけるあり方よりも、「現在」において語られ理解(評価)されるものであるという考え方は、誤解を生みやすい。とりわけヨーロッパ音楽のような歴史性をもつ創作においては、現在との距離の取り方そのものが「歴史性」であるのは当然として、諸対象(諸作品、諸時代)のあいだの複雑な関係(ネットワーク)を反映するところの、音楽理論や作曲技法の重層的な関連性をひもとく分析についての考え方が要求されることになる。
『新しい和声』は、当然ながら和声理論史ではないが、「数字付き低音」をもちいる和声的発想のシミュレーションと、その歴史的変遷[註6]を、理論的文脈の中心に据えている。「数字付き低音」は、「鍵盤上で弾く」という一点において(指、手のポジションほかの近代的教育法を基準とした)身体的制約から限定されるため、和声進行の原型とその変化形の範囲が比較的変動してこなかったと思われ、今日でも理解しやすいといえる。
『新しい和声』で記述されるところの、和音構成、声部進行、非和声音の扱いといった技法は、あくまでも音楽にかかわる歴史的な身体的記憶から生み出されるものである。場合によっては、これらが理論的な整合性をかならずしも必須のものとしていないのは、欠陥でなく多様性、多義性の所以(ゆえん)であるからこそ、(平均的水準の)教師による指導が最低限の前提となるのである。
『新しい和声』刊行へのさまざまな反応は、まさに戦後日本の音楽教育の問題点であるのみならず、読み落とされつづけてきた、明治以降のヨーロッパ音楽受容の「歴史的意味」を再検討する契機となろう。。
註
[1]──一般的に「専門家」でない人のことであるが、場合によっては「専門家」と思われている人、また自身を「専門家」と考える人のことをいう場合もある。
[2]──「Amazonカスタマー」名義によるレビュー(2015年4月20日投稿)のこと。
[3]──Carte blancheの第1回『「消費」としての音楽教育』を参照。
[4]──興味深いことに、ピアノやほかの楽器の演奏技術習得のための「教本・教則本」の効用は、学習者の側の問題(水準)もふくめて評価されるのがふつうだ。また音楽理論でもっとも厳格な「対位法」、たとえば邦訳文献の代表的な理論書でありながら、ほとんど学習のための「覚書(Note)」ともいえるJ.ギャロン/M.ビッチュの『対位法』(矢代秋雄訳、音楽之友社)は、著述のあまりに簡潔な在り方からして、「独習」はほぼ不可能であろう。
こうした教則本や著作については、『新しい和声』批判にあるような具体的な批判を聞いたことはない。
[5]──『ワーグナーシュンポシオン2015』(日本ワーグナー協会編)の「特集《トリスタンとイゾルデ》初演150年」所載の川島素晴「トリスタン和音クロニクル」は、研究論文というより、作曲家の視点からの分析論であるが、ここでも「島岡和声」にもとづく「トリスタン和音」の機能(カデンツ)分析から始まり、非機能的和音分析にいたる過程で、ジャズ理論のコードネームまで援用しながら、「トリスタン和音」というコンテクストをめぐるクロニクル(歴史物語)が延々と続く。
「トリスタン和音」の分析だけでなく、バッハからモーツァルト、ショパン、ワーグナーへといたる和声書法を理解するには、「機能」でも「響き」でもなく、声部進行を記述する伝統的な「和音数字(数字付き低音)」から理解しないかぎり不可能であろう。なぜならこれらの作曲家たちの作曲技法の学習は、対位法を前提とする「数字付き低音」の修得からおこなわれたものだからである。この論考は、「トリスタン和音」を理解するにあたり、島岡理論、ジャズ理論から歴史的音楽を読み解こうとしながらも、逆説的に分析、記述が困難になるという今日的な音楽理論(分析法)の不毛性を明らかにしている。
[6]──これらはパリ国立高等音楽院の教育課程にあっての「伝承的」なものにすぎないとしても、ラモー以降の(和声)理論にかんする「歴史的」諸テクストを前提としたものであるのは事実といえる。
林達也『新しい和声──理論と聴感覚の統合』(小社刊)
電子版アルテスでの本連載、Carte blancheは最終回となるが、このところその評価をめぐり、とりわけ一部の読者による批判が絶えない、林達也『新しい和声』についての私の考えを、前回[第11回、2015年6月号]に引き続き再度書いておこう。
反好事家(アンティ・ディレッタント)のために
『ムッシュ・クロッシュ・アンティ・ディレッタント(反好事家八分音符氏)』として知られるドビュッシーの辛辣な評論集は、作曲家の音楽観、他人の作品評などで構成され、ドビュシー生前に出版が企画されたが、けっきょく死後、1921年に刊行された。
音楽に関する教訓・教育(Didactique)というものが、いかに狭量でしばしば独裁的(Dictature)な影響力をともなうか、また、それらにかかわる人たちを好事家(ディレッタント Dilettante)[註1]として、音楽に敵対するものとしている。
私が批判の対象として取り上げるのは、アマゾン評者[註2]のごとく好事家にして独学者(Auto-didacteur)である。ドビュッシーの著作の登場人物、八分音符(クロッシュ)氏ならぬ二分音符(ブランシュ)氏による好事家への勘定書(キャルト Carte)として、反好事家(アンティ・ディレッタント)のCarte blancheというわけである。
独学者(Auto-didacteur)のために
「独学者」とは魅力的な言葉だ。
ただし、アマゾン評で誤解されているが、和声の「初歩の学習」と「独習」は異なり、「独習=独学」とはある程度の音楽的素養(たとえば演奏技術を習得していること)、また、なによりも歴史的に音楽文化水準の保証された社会環境を前提としたものであるのは明らかだ。ヨーロッパ社会において「独学」とは、究極的にはじゅうぶんな音楽的環境が保証されながらも「意思による独学者」(ブーレーズ)たらんことをいうこととなろう。
いっぽう、日本の戦後の音楽専門教育は、さまざまな学習「メソード」の開発により、消費者(学習者)主体の選択的な音楽教育として今日に至っている[註3]。
学習者は内容あるいは効率性という基準から、諸メソードを標榜する音楽教育を自ら選択し、それらの指導者のもと、「相性と結果」を考慮しつつ音楽を学ぶのである。
「独学=独習」もこうしたメソードの一形態であろうが、ただし一般的に指導者なしにおこなう学習は、前述したように「初歩」というよりはむしろじゅうぶんな音楽的能力を条件とする。
また、アマゾン評者が常用する「教本」という用語も、理論書で一般的にもちいられる「理論(Théorie)」「概論(Traité)」や「摘要(Présis)」と異なり、あきらかに「メソード(教則本 Méthode)」を指していると思われる[註4]。
「島岡和声」は、「理論と実習」の両側面を兼ね備えた、戦後のもっとも優れた和声学習の「メソード」なのである。そこ(「島岡和声」)では、「響き」も理論的演繹から生じる。論理の組み立ては正確で、それこそがアマゾン評者をして、完璧な「響き」と錯覚させるのであろう。しかしながら「響き」とは、訓練によって獲得された聴覚のことなのである。「和声的」感覚は、音楽基礎訓練=ソルフェージュと器楽演奏訓練における身体性の自覚から生まれるのである(当然ながら「島岡和声」は、それらを反映したものではない)。
和声的感覚とは、指導者(教師)の助言のもとでの実践的な学習・教育から、帰納的にいくつかの「選択的」判断による、(演奏技術修得同様の)「音楽的行為」として修得されるのものである。『新しい和声』における「美しい音響を聴きとる」とは、それらのプロセスをいうにすぎない。
専門音楽教育においては教師が必要であり、「教育」とは教師と学習者の相互的水準の平均値で構成されるものである。『新しい和声』が東京藝術大学音楽学部の和声教科書として採用されたのは、こうした基準の設定であり、藝大教育だけを意図したものでないのは自明のことである。
さらに和声理論を中心にした、「音楽分析」あるいは音楽学研究における「作品分析」とのかかわりについて書いておきたい。
分析=理解と記述──「作品」をいかに対象化するのか
音楽学論文中で必要とされる音楽分析において、日本では執筆者の大半は「島岡和声」にもとづく方法をもちいているものと思われる。問題は「島岡式」理論や記号にあるというより、「音楽作品」と、その理解・記述の背反にあると考えなければならない。
歴史的な音楽作品を対象とするとき、「作品」は、その作品が生み出された時代様式と、その前提となる「音楽理論」から分析されなければならないのは当然のことであろう。
「島岡和声」のように優れて理論化された方法においては、当然ながら歴史性や時代的特質は抽象化される。ある意味使いやすいその手法により、歴史的作品が理解され、また(「島岡和声」)独自の理論・記号体系から記述されるのである。表層的な「様式」理解をうんぬんしても、そもそも分析の前提となるべき理論的背景がかならずしも「様式的」ではないのである[註5]。
「作品」とは、その時代におけるあり方よりも、「現在」において語られ理解(評価)されるものであるという考え方は、誤解を生みやすい。とりわけヨーロッパ音楽のような歴史性をもつ創作においては、現在との距離の取り方そのものが「歴史性」であるのは当然として、諸対象(諸作品、諸時代)のあいだの複雑な関係(ネットワーク)を反映するところの、音楽理論や作曲技法の重層的な関連性をひもとく分析についての考え方が要求されることになる。
『新しい和声』は、当然ながら和声理論史ではないが、「数字付き低音」をもちいる和声的発想のシミュレーションと、その歴史的変遷[註6]を、理論的文脈の中心に据えている。「数字付き低音」は、「鍵盤上で弾く」という一点において(指、手のポジションほかの近代的教育法を基準とした)身体的制約から限定されるため、和声進行の原型とその変化形の範囲が比較的変動してこなかったと思われ、今日でも理解しやすいといえる。
『新しい和声』で記述されるところの、和音構成、声部進行、非和声音の扱いといった技法は、あくまでも音楽にかかわる歴史的な身体的記憶から生み出されるものである。場合によっては、これらが理論的な整合性をかならずしも必須のものとしていないのは、欠陥でなく多様性、多義性の所以(ゆえん)であるからこそ、(平均的水準の)教師による指導が最低限の前提となるのである。
『新しい和声』刊行へのさまざまな反応は、まさに戦後日本の音楽教育の問題点であるのみならず、読み落とされつづけてきた、明治以降のヨーロッパ音楽受容の「歴史的意味」を再検討する契機となろう。。
註
[1]──一般的に「専門家」でない人のことであるが、場合によっては「専門家」と思われている人、また自身を「専門家」と考える人のことをいう場合もある。
[2]──「Amazonカスタマー」名義によるレビュー(2015年4月20日投稿)のこと。
[3]──Carte blancheの第1回『「消費」としての音楽教育』を参照。
[4]──興味深いことに、ピアノやほかの楽器の演奏技術習得のための「教本・教則本」の効用は、学習者の側の問題(水準)もふくめて評価されるのがふつうだ。また音楽理論でもっとも厳格な「対位法」、たとえば邦訳文献の代表的な理論書でありながら、ほとんど学習のための「覚書(Note)」ともいえるJ.ギャロン/M.ビッチュの『対位法』(矢代秋雄訳、音楽之友社)は、著述のあまりに簡潔な在り方からして、「独習」はほぼ不可能であろう。
こうした教則本や著作については、『新しい和声』批判にあるような具体的な批判を聞いたことはない。
[5]──『ワーグナーシュンポシオン2015』(日本ワーグナー協会編)の「特集《トリスタンとイゾルデ》初演150年」所載の川島素晴「トリスタン和音クロニクル」は、研究論文というより、作曲家の視点からの分析論であるが、ここでも「島岡和声」にもとづく「トリスタン和音」の機能(カデンツ)分析から始まり、非機能的和音分析にいたる過程で、ジャズ理論のコードネームまで援用しながら、「トリスタン和音」というコンテクストをめぐるクロニクル(歴史物語)が延々と続く。
「トリスタン和音」の分析だけでなく、バッハからモーツァルト、ショパン、ワーグナーへといたる和声書法を理解するには、「機能」でも「響き」でもなく、声部進行を記述する伝統的な「和音数字(数字付き低音)」から理解しないかぎり不可能であろう。なぜならこれらの作曲家たちの作曲技法の学習は、対位法を前提とする「数字付き低音」の修得からおこなわれたものだからである。この論考は、「トリスタン和音」を理解するにあたり、島岡理論、ジャズ理論から歴史的音楽を読み解こうとしながらも、逆説的に分析、記述が困難になるという今日的な音楽理論(分析法)の不毛性を明らかにしている。
[6]──これらはパリ国立高等音楽院の教育課程にあっての「伝承的」なものにすぎないとしても、ラモー以降の(和声)理論にかんする「歴史的」諸テクストを前提としたものであるのは事実といえる。