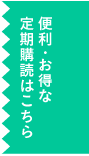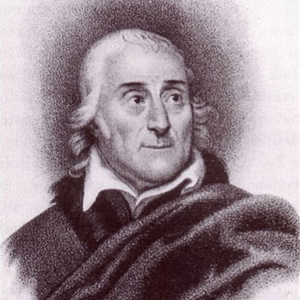
──モーツァルトの最高傑作との誉れ高い3つのオペラ《フィガロの結婚》《ドン・ジョヴァンニ》《コジ・ファン・トゥッテ》の台本作家として、音楽史に名を残すロレンツォ・ダ・ポンテ(1749-1838)。彼は1791年、モーツァルトが亡くなる直前にウィーンを去り、まずロンドン、そしてアメリカへ渡り、ニューヨークにイタリア語学校を開いて成功。またアメリカ初のオペラ劇場を設立しようとして失敗するなど、波瀾万丈の生涯を送りました。
ダ・ポンテの残した『回想録(Memorie)』(初版:1823-27/改訂版:1829-30)は、18世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパの芸術文化や興業の実態を知ることができる第一級の史料というにとどまらず、ときには美しい詩句で紅涙を絞り、ときには嘘八百のはったりで権力者を向こうにまわし、ヨーロッパとアメリカを股にかけて生き抜いたひとりの傑物の破天荒な生き様を写すドキュメントでもあります。
笑いあり、冒険あり、お色気あり──ときには眉唾の記述も散見される『回想録』のイタリア語原典からの本邦初訳に、フランス文学、イタリア文学の第一人者・西本晃二さんが取り組みます。落語にも通暁する西本さんならではの名調子もお楽しみください。

西本晃二
にしもと・こうじ■1934年奈良生まれ。専攻:ルネッサンス研究、1952年東大文学部卒(仏文)、61年Ph.D(カナダ、Laval大学)、フランス政府給費留学生、ローマ大学研究生。東大教養学部講師、同文学部助教授・教授(仏文→伊文)、文学部長。在ローマ日本文化会館長(1994-97)、政策研究大学院教授・副学長(-2006)。 著書:『イタリア文学史』(東京大学出版会)、『落語「死神」の世界』(青蛙房)、『モーツァルトはオペラ』(音楽之友社)など。 訳書:ジャン・ルノワ-ル『わが父ルノワ-ル』(みすず書房)、ランペドゥーザ他『南欧怪談三題』(未来社)など。
(1)
お送りくだされ、どうかなにとぞ、オオ父上、 ホレ十五文、もしなることならば二十文、 すれば、さやけきこの竪琴(チェトラ)、わが手に執りて、 高らかに歌いまつらん、お宝の功徳。この最後の行を書き終えた途端、たちまち背後(うしろ)にはじける爆笑の響き。振り返ってみれば、そこにはなんと友達のコロンボ! 私の詩作をシッカリ拝見というわけだった。しかも上記最終行をば、何処に行ってもイタリアの街角、盲目のお貰いが歌う節まわしに乗せ声高(こわだか)に、ただし笑いこけつつ唱えたものだ! それも伴奏の竪琴をば、[哀れっぽく]掻き鳴らす仕草をも真似つつ! まったく怒りと恥ずかしさとで、私は涙が出るほどだった。その後三日あまりというもの、コロンボと口を利くこともなければ、面と向かって顔を見ることさえしなかった。奴はその間もずっと、意地悪に輪をかけ、盲目のお貰いよろしく例の最終行を歌い、下手に竪琴を掻き鳴らす仕草をしてみせるのだった。とはいえ、こんなふうに私をひとしきりからかった後で、最初に仲直りし、そのうえいろいろ詩を作ってみるよう私を励ましたのも彼で、私もそうすることを彼に約束した。いったんそうと話が決まれば、こんどはコロンボはたいへんな熱意で、わがイタリア作家たちのうちのすぐれた者を私に読ませ、学ばせたのだ。したがって私は以後、若者たちにとってはあれほどお気に入り、そのためあたら才能が浪費されかねぬ安逸、あるいはお遊びなどはいうにおよばず、寝食さえをもすっかり忘れて、イタリア作家たちに打ち込むこととなった。ダンテ、ペトラルカ、アリオストそしてタッソが、私の最初の師匠であった。半年も経たぬうちに私は、第一のダンテについてはその『地獄篇』のほぼすべてを、第二のペトラルカについては、その最良のソネットを残らずと、カンツォーネのうちの少なからずを、他の二人についても、聞きどころの抜粋は余すことなく、いずれも宙(そら)んじて朗唱することができるほどとなったのである。 こうして修練を重ね、二千行にも余る詩句を密かに作り、しかも(いずれも気に入らなくて)火に燻べたうえで、やっと私は同級の仲間たちと(作詩の)腕を競い合い、例の竪琴に乗せて歌うばかりだけではない詩句を作れる自信を得るにいたった。ちょうどこのとき、われわれの学校の校長先生が他の、より名誉ある職務に推挽されるということが起こり、校長のポストを去らねばならぬ次第となった。多くの生徒が校長先生の徳を称えて詠んだ、少なからざる詩作にまじって、私も一首のソネットをものしたので、この『回想録』の中に印刷して、皆様のお目にかけることにする。かかる挙におよぶというのも、けっして同作が、広く公表さるに足る値打ちを有していると私が思ったからではない。そうではなくて、ひとえにわずか六カ月のあいだに私がなし遂げた進歩のほどをご判断いただき、それが他の方々にとって、たとえやや遅まきなりとも、生まれ持ったる素質の援けを得て、詩作に挑戦する励みとならんことを希ってのことである。
かの神の聖霊、至高の愛より発する、 浄き、燃え立つ[導きの]火箭(ひや)もて、 知覚を閉ざす迷蒙の闇を払い、 あらゆる誤謬の過ちより、魂を解き放つ聖霊、 その聖霊こそ、聡明なるお方よ、偉大なる 栄光の玉座(みくら)より、汝(なれ)を栄誉の座に招きたまい、 もって、御民(みたみ)をば、正しき途(みち)に 歩(あゆ)まする道標(しるべ)となさせたもう。 されば、今は行かれよ、して新たなる民草をば導きたまえ、 新らしき役職(つとめ)の座に昇りたまえ、 より高き印授を帯びて、より称えられかし。 いざ行きたまえ、彼地(かのち)にて、御業により サタンの汚辱に塗れさせ、キリストの掟の、いや栄えんことを! なれど、アア! 君よ、吾等をば忘れざられんことを![原註][原注]──この同じときに、わが友人コロンボによって作られたソネットは、以下のようなものであった。彼も喜んでくれると思って、それをここに掲げる。これによって、六十五年の歳月も私の記憶から、かくも親しい友の思い出を消し去るを得なかったことの、証しとしたい。
愛情(あい)の如何に強きことよ! 吾等、慈父に恵まれいたり、 優しく、愛に満ちたる慈父にこそ! 実(げ)に、アダムの 生を受けし日よりこの方、かかる父をば 持ちたる者、かってあらずと覚ゆる慈父をば。 吾等、かくも愛(いと)しき慈父をば、いま失いつ。 そも、いと高く、永遠(とは)に世を治しめす神の御意にて、 父上には好けれど、吾等にとりては破滅に異らぬ思召しの、 慈父をば他処(よそ)に率い行きて、吾等、いま孤児(みなしご)となれば。 その痛手の、いかに辛く、また重きか、身に沁みて思い知らる。 なれど恨まじ、慈父の好き運勢を思えば[別れの]辛さも 和らぐ。いな、辛ささえ消ゆる心地す。 して(慈父を思う)愛よ、吾等が優しき暴君となりて、 吾等が不幸に涙に暮るるではなく、さなくて、ただひたすら 勇んで、慈父の意志(こころ)を援けに、率[い]て行け。このソネットより以前に、例の(父宛の)「竪琴の四行詩」は別として、私は自分のイタリア語での詩作を誰にも見せたことがなかった。したがってこの十四行(=ソネット)を私の作と信じようとする者は誰もいなかった。ひとりコロンボのみがその真実なることを信じ、(こんな男が競争相手では)以後自分はイタリア語の詩作の筆を折ると、おごそかに宣言した。ただ同宣言は、美しくも艶(あで)やかな一少女の出現によって、脆くも打ち破られてしまった。というのもわれわれは、二人ともに彼女に恋し、競って(彼女を讃える)詩句を捧げたからである。 この、最初のソネットが私の作だと皆が信じようとしなかったよいう事実は、言うなれば(私にとって)新たな種類の賛辞であり、それによって私の自尊心が度外れに掻き立てられたというわけではないけれども、それでもいっそうの努力を傾けるよう私を励まし、以後イタリア詩の分野で身を立てることを決心させるよすがとなった。二カ年も経ぬうちに、私はすべてのわが国の古典作家たちを一再ならず読破し、夜を日に継いで、彼等ばかりか、真に価値ありとして多くの人々の手に取られた著者たちをみな読んだ。ただし十七世紀の作家[訳註10]となると話は別で、私は自分に、良質のものから悪質のものを、見かけの美しさから真の美しさを見分けるに足るじゅうぶんな判断力が身についたと信じることができるまでは、あえてこれらの作家を読むのを差し控えたのである。かつまた、ただ(受け身で)読むばかりではなく、わが国の作家たちの最もすぐれた箇所と思われる部分を、ラテン語に翻訳してみるというようなこともしてみた。彼等[の作品]を何度となく書き写し、これを批判し、注釈を加え、すっかり暗記してみたし、しばしば[短歌や長歌など]あらゆる詩形や韻の踏み方において真似し、その最も魅力的な詩想に倣い、最も洒落た言いまわしを取り込み、いうなれば吾等の先駆者たちにより用いられた中で、最良の詩風を自家薬籠中のものとしようとも試みた。そのさいにも常に、わが崇拝するペトラルカを他の誰にも増して高く評価することを忘れなかった。しっさい彼の詩句を読み返すたびに、一行ごとに新たなる珠玉の美を見出す心地がするのだった。 こういった具合で、かつ絶えざる、また疲れを知らぬ研鑽によって私は、学業も三年目の始まる頃には最優秀の者たちと腕を競ってヒケをとらぬほどとなり、わが詩句が最高位を獲得して栄冠を授けられ、学内で持て囃されることも一再ではない次第とはなった。あるコンク-ルで、多くの学識あるチェーネダの若者たちと競って私が作ったカンツォ-ネは、おおかたの喝采を浴びたほどである。しかしこうした称賛も私自身に、わがカンツォ-ネが本当の傑作であると信じさせるにはにほど遠かった。私は幸運にも、自己の文人としての修行時代の、そもそもの初めの頃から、自己が獲得した称賛たる、じつは弱輩の努力を評価してやり、もって将来において真に値打ちのある詩人として成長することを希って下さる、人々のありがたい心から生まれた励ましの言葉にほかならないと考える習慣を身につけていた。こうした考えが私を、愚にもつかぬ自惚れやら、根も葉もない思い上がりから遠ざけるのに役立ったのである。じっさいのところ、かかる妄想こそ、学習者たちがそれにぶつかって難破しやすい暗礁であって、よく起こることだが、彼等は自分がもうなにもかも心得ていると勝手に思い込んで、まさにそこから詩人としての途を歩み始めなければならぬその地点で、歩みを止めてしまうのである[訳註11]。 自然が私に与えてくれたいくばくかの詩才、そしてこの詩作に対する限りない愛情、もしもこれらが、いま述べたような正しい原則とともに私を導いてくれたのであったらば、私もひとかどの詩人という評判を獲得するにいたったことでもあろう。だがそれは、もしも[気まぐれな]運命の女神[フォルトゥーナ]がそれこそひっきりなしに、こうした私のまことにもっともな決意の邪魔をせず、その抗がい難い腕(かいな)をもって、人生のこのうえなく危険かつ容赦ない渦巻きの中に、私を力ずくで引き摺り込みさえしなかったならの話である。だが女神は、そうした高尚な立場に到達しようと志す者にとっては欠くべからざる心の平安、物質的な手段、そして心地好き閑暇、それらなくしては人の心がそうした高尚な地位を求めたとて、いかなる甲斐もありはせぬ諸条件を、私から奪ってしまったのである。 だが私は当時、詩人にとって必須とされるあらゆる知識と英知でもって、わが才能をみごと飾りたててみせんという、いとも気高い意気に燃え立っていたので諸事倹約に勤め、さらには若者にとってごく当然の出費さえも切り詰めて、ラテン語書籍の数少ない蔵書に加うるに、イタリア作家のうち最良の者たちの作品をも足して、これをより豊かなものにしようと努めていたところだった。われわれのチェーネダにはひとりの書籍商がいて、これが知識も才能もないというのに、偶然の気まぐれから極上の品揃えを有していた。私は数リラなりと金が溜まると、直ちにこの男のところに出かけて幾冊かの書物を選ぶことにしていた。大部分は廉価版のエルゼヴィル叢書のものであったが、それでもその値段は貧弱なわが財布の中身をはるかに越えていた。この本屋には、息子がひとりいて靴屋をやっていた。そこで老人のほうから、私と自分の両方の役に立つ、けっこうな解決策を見つけてくれた。彼が言うには、「あんたの親父さんの仕事場から、ロバでも犢(こうし)でもいい、(鞣〔なめ〕した)革を持って来なされ。そしたら、なんとか折り合いをつけることにしてあげよう」というわけだった[訳註12]。 この取引は、しごく私にも気に入った。そこでさっそく家に飛んで帰り、ソッと倉庫に忍び込むと、犢革の鞣したやつを三枚選びシッカリと丸めて筒状にすると、これを神学生の長裾の制服の背中に差し込んで、戸口を指して出て行こうとした。ところが間の悪いことに、ちょうどこの戸口に継母(ままはは)が、近所の女たちとお喋りしているところにぶつかったものだ。やらかした盗みに気づかれてはまずいと思ったので、私はくるりと向きを変えて、別の出口から出て行くことにした。いったんは道路に出るところまで行ったのだが、それでも女連中の集まりの前を通り過ぎないわけには行かなかった。で、ホンの何歩か行き過ぎたところで、連中のうちのひとりが声高に「あの若い者(もん)が、背中があんなに曲がっているなんて、なんて運が悪いこと!」と言うのが聞こえた。背中に隠した荷物が、私をそんな格好にみせることになってしまったのだ。しかも道の反対側に、はすかいにひとっ飛びと躍り上がったとたんに、荷物は地面に転がり落ち、女たちは腹を抱えて大笑い。継母は駆け寄ってそれを拾い上げ、私はといえば振り返るはおろか、ひとことも口を利く勇気さえなく、ひたすら前を向いてしょんぼり、ひっそり本屋の親父の店に駆け込んだ次第である。親父には大失敗の顛末を話して聞かせ、何リラかを手付金として渡して、選んだ書物を取っておいてくれるように頼み、じっさい親父は、そうしてくれたというわけだった。
訳註
[1]──ダ・ポンテはここで、イタリアに限らず当時のヨーロッパにおける人種差別の情況を反映して、自分の出自がユダヤ系であることにまったく触れていない。この不当な差別が、ダ・ポンテの性格形成に、彼がその才能によってそれを乗り切りはしたものの、なんらかの歪みを与えたことは否めない。 [2]──十三世紀末に始まるルネッサンス以来、イタリア半島に割拠していた都市共和国は、その大部分が十五世紀末に始まる外国勢力の侵入により姿を消してしまう。ひとりヴェネツィアのみは十八世紀の終りまで好くその独立を保ったが、ナポレオンの侵入により一七九七年十月のカンポフォルミオ条約で、イストリア地域とともにオ-ストリアに割譲され、その独立共和国としての地位を失ってしまう。ダ・ポンテは、ちょうどこの時期に生きていたわけである。 [3]──十八世紀末のこの時代は、漢文を重んじた江戸期におけるわが国と同様、教育といえばラテン語の修得と決まっていた。 [4]──ギリシャ神話では、シチリア島のエトナ火山の下には、鍛冶屋の神ヘファエストス(ロ-マではヴルカヌス)の仕事場があって、神が巨人族の助手を使って仕事に取り掛かると噴火や地震が起こるとされた。 [5]──最初の六作品は、中世フランスや北イタリアで大いにもて囃された武勲詩あるいは騎士道物語。いっぽうピエトロ・メタスタジオ(一六九八~一七八二)はローマ生まれの劇詩人。有名なソプラノ、マリアンナ・ブルガレルリに愛されて、彼女のために『捨てられた女王ディドオ』(一七二四)の台本を書いて一躍名声を博した。一七三〇年以降はヴィーンのハプスブルグ王朝の宮廷詩人としてヨ-ロッパ的な名声を獲得、ダ・ポンテの先達であった。 [6]──本来はユダヤ人としてエマヌエ-レ・コネリアーノという名前だったダ・ポンテは、この大司教のロレンツォ・ダ・ポンテによって一家(父親と三人の息子)がキリスト教に改宗し、洗礼を受けた際に、洗礼親の姓ダ・ポンテを名告ることになり、かつ名前としては大司教と同じロレンツォを与えられた。ダ・ポンテが十四歳の時である。 一家の改宗は、父(ユダヤ名ジェレミア・コネリアーノ、当時四十一歳)が、キリスト教徒の娘で、僅か十七歳のクリスティ-ナ・オルソラ・パスクワ・パイエッタとの結婚に踏み切った結果、行われた(ユダヤ教徒とキリスト教との結婚は認められなかった)。 [7]──註1で触れたように、ユダヤ系だったダ・ポンテにとり、被差別的情況を脱出してキリスト教社会で受け入れられるには、先祖伝来のユダヤ教の信仰を捨ててキリスト教に改宗するしかなかったし、また教育に金を出す気のなかった父親を説得するには、ユダヤ人を転向させて一人でも異教徒の数を減らそうと狙っていたカトリック教会経営の神学校に給費寄宿生として入学するのが手っ取り早い方法だった。 だが神学校に、それも給費生として入るということは、まずキリスト教に改宗して、かつ宗教的使命感の有無にかかわらず、将来は神父として教会に仕えることを意味した(ここらあたりから、ダ・ポンテのみならずユダヤ人たちが、ヨーロッパ=キリスト教社会で背負わされていた歪みが顕在化してくる)。じじつ才気はあり余るほどだったが、18世紀の啓蒙思潮に触れた一般イタリア人と同じく、かつ貿易立国を国の基本方針として、伝統的に東地中海のギリシャ正教やイスラム圏との接触を保つヴェネツィア共和国に生まれた者として、必ずしも宗教的な性格の持ち主ではなかったダ・ポンテは、教会人としての資格を取りながら、後に教会から離れていく。つまり結果として神学校入学が、自己の社会的地位向上のための手段と見られる可能性無しとしない。これは御都合主義といえば御都合主義だが、当時のイタリアではやむを得ない面もなきにしもあらずだったのである。 [8]──イタリア半島では十九世紀後半まで国家統一が実現しなかった事情もあって、共通語の成立が遅れた。その中でフィレンツェでダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョという、俗語つまりラテン語でない民衆の言葉で傑作を書いた三大作家を生んだトスカーナ地方の方言が、他に勝る権威を獲得しイタリア語になっていく。 [9]──ソネットは別名「十四行詩」といわれるように、一篇が十四行からなる短詩型の抒情詩で、その構成は4-4-3-3行(英国のシェイクスピア風のソネットは4-4-4-2行)をとる。イタリアで十三世紀末に栄えた「新優美体」と呼ばれる詩派によって用いられた詩型で、この詩派にダンテが属しており、ついで十四世紀に入ってペトラルカによって大成された。以後ソネットは西欧抒情詩の典型的な詩型となり、ハイネやボオドレ-ルによって傑作が書かれた。 [10]──ダ・ポンテにとっては、まだその評価が確定しているとはいえない、身近な作家たち。 [11]──後年、語学校を経営することになるダ・ポンテの文章には。教師にありがちな、こうした説教癖がよく顔を出す。 [12]──皮鞣(なめ)しという職業は、洋の東西を問わず卑しまれ、被差別民族が携わる生業ということになっていた。(2)
されど天が、この御方(=聖ルイージ)を、かく呼び返されては、 黄金(こがね)に輝く明星も光を失い、 その栄光もいささか減じ、陰(かげ)るかと見ゆ。この演唱に際して、さる高貴・博学のお方の口をついて出た「ブラヴォ!」という賛辞が、コンコルディア[訳註5]の司教、博学・高貴のお生まれと、教義こ関する該博な知識をもって知られるガブリエリ猊下をして、即日(自己の教区における)修辞学講座担当のポストを私に提供するという申し出をなさしめる結果をもたらすこととあいなった。だが私は当時、すでに若年の頃よりかなり勉強したヘブライ語をまずマスターし、同時にギリシャ作家たちの研究にもいそしもうと考えていた。それというのもギリシャの大家たちの作品を読まずしては、何人(なんぴと)も立派な詩人たるを得ないと固く信じて止まなかったからである。これらの理由で、私は何日か猊下の御提案をお受けしたものかどうか躊躇(ためら)ったのだが、結局は私をとても愛してくれた校長先生の説得に任せて、とはすなわち同職から得ることの見込まれる収入で経済状況を改善できるという見込みよりも、むしろ諸種の状況に押されて、心を決めた次第である。そこでともかくも、私は猊下のお申し出を承諾した。ということは、いまだ自分自身がそれこそ山ほども学ばなければならぬことがある歳なのに、他の者たちに文学を教授しなければならぬ立場に身を置く羽目となったのである。とはいえ、こうした種類のいわば中断が、私の文学修行における進歩の妨げになったわけではない。[原註:私は、他の何者にも増して、自分の生徒たちから多くを学んだ。]このポストに任命されたとき、私はまだ満二十二歳にもなっていなかった。私の指導には三十余名の若者たち、いずれも熱意と才能に溢れ、やる気満々、しかもこのときまではわが同級生だった者たちが委ねられた。司教猊下は私の心の中に、このうえなく強くまた激しい自尊心の刺激を掻き立てられたのである。町中の人々の目が私に注がれていた。どうか読者の方々よ、私が内心どんなにおそれ震(おのの)いていたか、思ってもみていただきたい。私は自分に与えられた責務に恥じざる成果を挙げるべく、普段に倍する勤勉と思索と努力を傾けてことに当たった。そして、それまでにわが師たちが教えてくれる暇がなかった事どもは、ある賢きユダヤ教の教師(ラビ)の言にあるように、これを己れの生徒たちから学んだのである。 私の賞賛に価する努力がもたらした好もしい成果は、何人かの人々の心に憎(おぞ)ましい嫉妬(やっかみ)の衝動を掻き立てた。神学校の教師の二・三人が、私にとって不倶戴天の仇(かたき)となった。私が物理学と数学を十分に学んでいないと主張して、彼等はこの方面から攻撃してきた。言い分は、私が単なる喋り屋で、真の学問を身につけていないヘボ詩人にすぎないというのだった。そこで私は物理学のいくつかの論点に関してラテン語で、またイタリア語でも、何篇かの詩作をものした。そしてこれらは、わがクラスの学生たちによって学年末の発表会で公(おおやけ)に披露され、大方(おおかた)の賛同を得たが、その中でも「匂い」についてのバッカス讃歌(デティランボス)などには、(フランチェスコ・)レーディ[訳註6]ばりの才能の閃きが認められると言われた詩句、
「そもいかなる幸いによりて……」などなどが含まれていた。 しかし私が(コンコルディアの)町の知識人たち、学生連中、そして司教猊下御自身により賞讃され喝采さればされるほど、わが仇(かたき)どもの怒りはいや増し、競争相手たちの憎しみは無限に燃え熾(さか)るばかりであった。 二年間にわたる隠忍の後、とうとう私は辞職を申し出ることにした。しかもまずいことに、ヴェネツィアに移ることにしたのである。なにしろ血気盛んな年頃で、性格的にも活発、加えて世間の噂によれば「男前」だったので、私はついつい(ヴェネツィアの享楽的な)風習(しきたり)、気安さと、周囲にいくらでも見あたる例に引き摺られて、自分が享楽と遊蕩に溺れるに任せ、文学と学業をすっかり忘れてしまった。この大都会で屈指の美女だが、また同時に極め付きの移り気と評判の女性[訳註7]にぞっこん惚れてしまったのである。この女(ひと)は、お祭りと大宴会や飲み会で、お定まりの恋の気紛れと馬鹿騒ぎ、それに嫉妬(やきもち)でもって、私の心を朝から晩まで二六時中占領してしまったので、なにか書物を読むにしても、わずかに習慣で夜中に数時間かしか残されていない有様となってしまった。こうした乱痴気騒ぎが続いた三年間[訳註8]というもの、私はそれまでに知っていたこと以外に、新しいことは何ひとつ学ばなかったし、また知るべき価値のある事柄を学ぶこともなかった。 だが天の御加護が、囚われていたこの恐るべき危険から私を解放してやろうと思し召されたとみえて、この女性の、あらゆる凄まじい嫉妬と、とんでもない気紛れとにも拘らず、私は夕方にはさるコーヒー店、そこはヴェネツィア切っての知識人や文化人たちが集(つど)う場所で、それゆえ「文人カフェ」と呼ばれていたのだが、そのカフェに顔を出すという好き習慣を守り続けていた。その店である晩、私が仮面で半ば顔を隠して座っていると、ひとりのゴンドラ漕ぎ(バルカイウォーロ)が入って来て辺りを見廻し、私に目を留めると、店を出るように合図をしたのである。私が表に出ると、自分について来るように身振りをし、カフェの近くだが店とは反対側にある、運河の岸まで私を引っ張っていった。そして一艘のゴンドラに乗り込ませたものだ。キットそこには私の彼女がいるものと決め込んで、というのは彼女も時折り私を店まで迎えに来ることがあったからだが、特に詮索もせずに私は乗り込み、女性の傍らに席を占めた。それは漆黒(しっこく)の夜だった。やや離れたところに灯(とも)っていた街燈が、それまでは私に道を照らしてくれていた。しかしいったんゴンドラに乗り込むと、ゴンドラ漕ぎは船室の入り口にある帷(とばり)を下ろしたので、暗闇はもう完全になってしまった。女性と私が互いに、かつ同時に挨拶を交わし、その途端に、両人ともに声が別なのに気付いて、漕手が人違いをやらかしたと知った。私は腰を降ろすと、習慣(しきたり)に従ってその女(ひと)の手を取って唇(くち)づけしようとした。その手は私の彼女のより、はるかにふくよかな手だった。その女(ひと)は、むろん直ぐ手を引っ込めようとした。しかし私は優しくその手を引き止めて、「なにも心配なさることはありません」と真剣な声音(こわね)で申し上げた。その女(ひと)の応対は慇懃なものだったが、しかししきりに私に立ち去ってくれと求め続けた。彼女がヴェネツィア人でないことを知って、というのはその話し振りが生粋のトスカーナ弁だったからだが、いったいどんな人か知りたいと興味を掻き立てられ、私は言葉の限りを尽くして、どうかお住まいまでお供させていただきたいと申し出た。その方はいろいろ難を挙げられたが、ともかくも一口飲み物を召し上がることに同意された。だがそれはもうこれ以上詮索することなしに、ゴンドラから出て行くという条件でだった。ゴンドラ漕ぎが近くのカフェに飲み物を注文に行き、カンテラを持って戻ってきた。光に照らされて私の目に映ったのは、素晴らしい美貌と気高さを兼ね備えた若い女性の姿だった。まだ十七歳か、それほどにも達していないかと思われた。着付けはたいへん好い趣味で、身のこなしも気高く優雅、話される言葉の端々には才気と慎みとが輝いていた。我々は二人ともに、一瞬口を噤(つぐ)んだ。だが彼女のほうも、私が彼女を見詰めたときに覚えたのと似たり寄ったりの感情を、私に対しても抱かれたように思えたので、勇気を奮い起こして、かような情況において美しい女性に対して語り掛けるのがお定まりの、思い付くかぎりの科白(せりふ)を申し上げた。さらに重ねて「どうかお住まいまで、お供をさせていただきたい。または少なくとも、いったい誰方(どなた)とお言葉を交わす喜びを得たのかお教えいただきたい」とお願いしてみた。彼女に対するに、私が彼女のような女性の立場にふさわしい、あらゆる礼節と尊敬の念とをもって接しているのを見て、これは十分に教養のある、きちんとした性格の者に違いないと看て取ると、彼女のほうも打ち解けた様子で、次のように応(こた)えた。「思いもよらず奇妙な情況が重なって、このような有様となりましたのですから、残念ながらお望みには従いかねます。でも事情が変わることもあり得ますでしょうし、そうなった暁には、またお会いすることもございますでしょう。そうお約束いたしてもよろしいかと存じますし、「もっとハッキリ」と仰言ゃいますなら、そうなることを私も望んでおりますし、またそうなるようできるだけのことをいたす所存であるとも、ここで申し上げておきます」。そこで私も、自分が何者であるかを明かした。そしてこの当のコーヒー店、および事の起こったその同じ時間を、将来の出会いの場所と時刻と取り決めたうえで、時をおかずに彼女は去って行ってしまわれた。 この事件についての好奇心か、それともまたこの事件が、あの我々の関係、つまりそもそもの付き合いの初めから、自分の幸福のためには激しすぎるという気がしていた、私と私の彼女との関係から、ヒョットすれば自分を解放してくれるのではないかという期待があってか、私は毎晩きまって約束のカフェに足を運んだものだ。だがしばらく時が経つと、そんな希望は水の泡と消えてしまった。それに反比例して、もう一方の女性に対する私の情熱は昂ずるばかり、同時に彼女の私に対する気紛れな圧制と支配も高まるばかりだった。彼女には兄がひとりいて、この男が私にとっては憎しみの種だった。そして妹の私に対する支配力をよいことに、私を自分の奴隷・腹心・金蔓(かねづる)と化してしまったのだ。そこで私もいったんは断然ヴェネツィアを出て行こうと決心した。町から遠ざかることで、この病(やまい)から癒されるのではないかと期待したのだ。ところが別離は、かえって私の弱みと、彼女に対する欲望を掻き立てることにしかならなかった。とても耐え切れずに、激烈な心中の苦悩を経て、一週間後にはヴェネツィアに舞い戻らざるを得ず、さらに情けないことに彼女の家に一緒に住むという屈辱的な申し出を受け入れねばならぬ羽目になってしまった。とはいっても、夕方にはいつものカフェに出掛けて行ったのだが、そこでガックリきたことには、数日前にゴンドラ漕者が私を探しに現れたのに、「何処かに旅立ってしまった」と告げられて帰って行ってしまったというのだ! という次第で、もうあの見知らぬ美女の報せを耳にすることがあろうなどとは、私は夢にも思っていなかった。ところがその数日後サン・マルコ広場を散歩していると、服の裾が引っぱられ自分の名前が呼ばれるのが聞こえた。例の女性のゴンドラ漕者の、喜色満面の姿がそこにあった。「町に戻らしゃんしたか。好がった、好がっだ! 御主人さま慰めに行ってくべえ。今晩、また会いますべえが」[訳註9]と言うなり、こちらの返答も聞かずにトットと行ってしまった。夕方になると、麗わしの美女を連れてカフェにやって来た。ゴンドラに私が乗り込むと、「ホラ、参りましてよ!」と彼女、「お約束したとおり」。お定まりの挨拶を交わすと、ゴンドラ漕者に自宅に連れて行くように命じた。到着すると、洒落た部屋に私を通して、自分は隣室にひとりで入って行ったが、数分後に出て来たときにはたいへんな、とはいっても簡素な、優雅さで身を装っていた。そして私の近くに座を占めると、次のように話し出した。 「なによりもまず私自身について、また私をヴェネツィアに来させることになった奇妙な原因について、貴方にお話ししなければなりません。私はナポリの出身で、名前はマチルダと申します[訳註10]。マ・・・ザ公爵の娘です。父は、私の母が亡くなりましたとき、子供は二人しかおりませんでしたが、十年間の鰥夫(やもめ)暮しの後、薬剤師の娘を後妻にもらいました。この女は、もともと弱い性格だった父を色仕掛けでますます意気地無しにして、彼の私と私の兄に対する父親としての愛情をまったく消してしまったとまでは言わぬにしても、すっかり冷え切ったものにするのに成功したのでございます。兄のほうは、父の命令でヴィーンの兵学校に送られたうえ、半年も経たぬうちに亡くなってしまいました。そして私は、当時まだ十一歳にもなっていなかったのですが、嫌だというのにピーザの、とある修道院に入れられて六年間もそこにおりました。しかもその間、父の顔を見ることも、またその消息を聞くことも絶えてなかったのでございます。その修道院の尼さんたちは、彼女らと同じ(修道女の)身となるように、あらゆる手段を用いて私を説得しようと試みました。しかし私はそれを絶対に拒否したのです。とある日、まったく突然に継母(ままはは)がピーザにやって来ました。父もこの女と一緒だったのです。けれどもこの残忍な女は父に、私の顔を見に来ることを許しませんでした。彼女はひとりでやって来て、私に対してありとあらゆる母親としての愛情の表現を装(よそお)いながら、「娘や、」と言いました。「あんたはどうしても、神様の花嫁になる気にはなれないとのことだね。それなら俗世間で生きることにするんだね。で、あんたの将来の世話に関しては、お父さんがすっかり私に任せてくれたのよ。私が自分の実の娘に劣らぬほどのことをあんたのためにする、それくらいあんたを愛していると知ってね。そこで、すでに私があんたのために選んで、あんたの生涯の本当の幸福を保証してくれるような夫と結婚したらどうかと言われるのよ。もしもあんたが私の言うことを聞く、私の言うこととは他ならぬあんたのお父さんの望みでもあるんだけれどもね、もしそうすることを約束するなら、あんたは明日にでも、このお気に召さない(僧院の)囲いから出る用意をするんだね。さもなくば……」 修道院、尼さんたち、またその生活がどうしても気に入らず、六年間の牢獄生活の後、自由の空気を熱烈に求めていた私、さらには私に命を与えてくれた父の顔を見、父を抱き締めたいという気持に駆られていた私は、この「……さもなくば……」を耳にすると、座っていた席から喜びに溢れて立ち上がり、まだどんな人柄なのかも好くわかっていなかったこの女の首に飛び付くなり、「何でも、愛(いと)しいお母様、貴女のお気に召すことなら何でもいたしますわ!」と言ったのです。すると女のほうも私に何度も優しくキスを返して、それならば明日をも待たず、直ぐにも修道院を出ようという話になり、私どもは父上が泊っていた宿屋にまいりました。「オオ、これがわが娘か?」と、父は私の顔を見るなり大きな驚きの叫び声を上げました。「貴方の娘御、それもお申し付けに従順な、素直な娘ですわ」と、悪女の返答。そこで自然が、すべての本来の感情を自由に発揮させることとなり、父がどれだけキスしてくれたか、優しい愛撫の数々、喜びの興奮、私の歓喜のほども申し上げるには及びますまい。 私たちは直ちにナポリに向けて出発し、到着してからは、もう私の婚礼の準備で持ち切りでした。継母(ままはは)は私に、彼女の部屋に隣接した二部屋をあてがい、厳しく私を見張って、誰とでも私が相対(あいたい)で話をするのを許そうとはしませんでした。この奇妙な箱入りの扱いをいったいどう考えたら好いのか、最初は私にも判りませんでした。と、ある日、私がこうした物思いに耽っているところへ、とつぜん継母(ままはは)が部屋に入って来て自分の部屋に連れて行き、私と二人だけで閉じ籠ったのです。そして抽出しから真珠やら宝石がいっぱい詰まった手箱を取り出すと、言いました。「これが、貴女の御主人からの最初の贈り物ですよ。あの方の御身分にふさわしい引き出物の残りは、あちらのお宅に嫁(い)かれたら、どんなものか判りますよ。私の好意と、貴女にどれだけ尽くしてあげたか、私の愛情のことは忘れないでね」。そう言い終わると、ドアをさっと開け放ちました。すると目に映ったのはなんと、見るところ六十歳にもなろうかという、ひどく醜い顔立ちの老人の姿。続くのが、召使いや下僕と小姓たち、それに(結婚)式を執り行うための僧侶が二人という仰々しい行列ではありませんか! その後には父親が黙念と、目を伏せて付き従っている姿。「サアこれが、マチルダ、貴女の旦那様よ!」と、女のヌケヌケとした言い振り。「こちらが、公爵様」と今度は男に向かって、「私の手から、そしてお坊様のお手ずから、奥様としてお受け取りになる娘さんよ」。初めはあまりのことに、私は口を利くどころか、身動きさえもできませんでした。その飛んでもない男のほうは、何かモソモソ口に出して言ったようでしたが、私の耳には何も入りませんでした。けれどもついには気を取り直して、というか苦しみと怒りと絶望の衝動に駆られて高い叫び声を上げ、頭に被せ掛けられた何枚かのヴェールと、それと一緒に髪の毛をも引き毟(むし)るなり、私は居並ぶ人々の間を掻き分けて父の足許に身を投げ、嗚咽に咽(むせ)び、涙ながらに、「父上、お助けください!」と訴えたのです。 この振る舞いは、かの蛇女を怒り狂わせるのに十分でした。どんなに猛(たけ)り立ち我鳴り立てたか、とても口では申せません。アッと言う間に一同、ひとり残らず消えてなくなり、私は女と父と三人で取り残されたのですが、父ときたら私を庇ってくれる勇気も力もありませんでした。女はとうとう二人の召使いを呼び、半死半生の私を馬車に積み込ませました。私はまた気を失ってしまったのです。どれだけ時が経ったか判りませんが、気が付いてみると、どこからみても牢獄の様相を呈している部屋の中に私はいました。ベッドがひとつと椅子が二脚、それに机がひとつあるだけでした。窓には太い鉄棒が嵌め込んであるうえに、壁のずっと高いところにあるので、私がどうやってもそこに届くことなぞできない相談でした。数限り無い怖れに苛(さいな)まれて、私はその日の午後を悲嘆と涙に暮れて過ごしたのです。夕暮れ近くになって、外側から鍵で戸をガチャガチャ開ける音が聞こえ、扉が開くと、部屋に小さなバスケットを抱えた、見るも恐ろしい格好の女が入って来ました。そのバスケットを机の上に置くと、私をジッと穴の開くほど見詰めた後、一言もいわずに出て行ってしまいました。そこでバスケットの中を覗いてみると、あるのは水が一瓶と卵が二つ、それにパンが少々だけ。でも私は自分の涙以外のものを糧(かて)にする気になぞ到底なれぬまま泣き暮らして、この監禁状態が続いた半月間というものを過ごしました。もしもあの死人も同然の骸骨親父(がいこつおやじ)と結婚するくらいなら、どんな牢獄暮しだとてまだ増しと思わなかったらば、私は絶望の余りとっくに死んでいたところでした。なにしろ私の亭主にと持ち出されたあの男ときては、まったくこの名にふさわしい老いぼれだったのですから。 私が、この牢獄がもうそのまま自分の墓場になってしまうのではないかと思い始めた頃、ちょうど十五日目の夜もかなり更け、ベッドに横になっていたところ、ソロリソロリと扉が開く音がして、火を灯(とも)したカンテラを提げた女の人がひとり、入って来るのが見えたのです。なんとその女(ひと)は直ぐに小声で、「怖がらなくて好いのよ、お嬢ちゃん、あんたの乳母ですよ」と言ったのです! むろん私はその首に飛び付きました。彼女は私の頬を涙で濡らした後、直ぐに着物を着て、後について来るようにと命じました。私はこの女(ひと)が、自分の命も同様に私を可愛がってくれているのを知っていたので、一瞬も迷わず言い付けに従いました。かいがいしく着物を着るのを手伝ってくれると、彼女は私を連れて階段を降り、家の門口に出ると、そこには四頭立ての二輪馬車(カレッシュ)が馭者(ぎょしゃ)と、旅行の身なりを整え、男物のマントと帽子とを手にした若者と一緒に待ち構えていました。乳母はいま一度私を抱き締めると、「サアわが娘で御主人様、これが」と言いました、「貴女に残されたただひとつの助かる途(みち)、自由への扉ですよ。これは私の息子です。安全な場所に貴女をお連れし、私自身と同じように、貴女の忠実な召使いとなるでしょう。今はもうこれ以上お話ししている時間(ひま)がありません。時が大切です。残りは息子からお聞きください」。こう言うと、私に例のマントを着せ掛け、帽子を被らせ、馬車に乗り込ませました。 我々は全速力で駆けたので、数時間で、はやガリリアーノに着いてしまいました。翌日にはローマに、三日目にはフィレンツェに到着です。でも何処にも、夜であろうと昼であろうと、止まることはしませんでした、ともかくパドヴァに着くまではね。パドヴァに着いて、やっと少し休ませてくれと頼んだのです。でも私の連れはパドヴァにも、一晩以上は留まろうとしませんでした。彼から、乳母がどんなにして、あの悪女が私に付けた監視の目を誤魔化すことができたか教えてもらいました。彼女は私が、あのお化け男と結婚するのを承知しないかぎりは、わが家の所有する、ナポリから三マイル離れたところにある古城の牢獄で飢え死にさせるつもりだったのです。彼女は、私に母方からの相続権がある領地と引き換えに、あの男が払うと約束した莫大な金額に釣られて、そうする気になったというわけです。そのうえ、あの身の毛もよだつようなお化け男について、こういう話も聞きました。身分といい財産といい、たんまり持っているというのに、結婚を申し込んでも断らないような女性を誰ひとりとして見付けることができなかった、それも体が畸形のためだけでなく心もまた歪んでいたゆえに、ということだったのです。という次第で私は、まさに神助によって天変なり地異から逃れられたと感じました。 とはいったものの、私にしてもまた私の連れにしたところで、わが自由と安心立命を得るために、いったいこれからどうしたものかいっこうに見当がつきませんでした。連れは私に、金貨の詰まった財布と、私の母の物だった宝石で一杯の小筥を私に渡してくれていました。これはどうやってか判りませんが、憐れな父上が(継母の目をかすめて)取りのけておくことができたもので、私のために乳母に与えたというか、むしろ父のほうから進んで、私を救い出すために用立ててほしいと手渡したものだったのです。だがこうした金品は、かえって私が何者か露見させてしまう役に立ちこそすれ、私の微行(おしのび)を守ってくれることにはなりませんでした。
訳註
[1]──ここでダ・ポンテは、生活のために(!)立てた僧籍に入るという誓いのために、法律上認められぬ妻となってしまった結婚相手のナンシー・グラールに気を遣って、事態をボカしている。 [2]──ダ・ポンテが、ポルトグルヮーロの神学校に入ったのは一七六九年で、その二十八年後の一七九七年にはナポレオンの率いるフランス軍の侵入の前になす術もなく、独立を失ってしまう。 [3]──ポルトグルヮーロ、ヴェネツィアの北東、約一一〇キロにある町。 [4]──『アミンタ』(一五七三)はトルクワート・タッソオ(一五四四−一五九五)作、『忠実な牧人』(一五九五)はジャンバッティスタ・グヮリーニ(一五三八−一六一二)作、ともに牧人劇の傑作として知られる。 [5]──コンコルディア・サジッタリアは、ポルトグルヮーロの南二キロの小さな町。 [6]──フランチェスコ・レーディ(一六二六−一六九八)、アレッツォ出身の医師で本草学者。詩人でもあった。酒を歌った「トスカーナのバッカス」は有名。 [7]──アンジェラ・ティエポロ、一七五〇年生まれでダ・ポンテより一歳年下。一七七〇年に三十一歳年上の共和国貴族と結婚、二人の子供を儲けている。 [8]──このダ・ポンテの第一回ヴェネツィア滞在の期間については、一七七三年秋から翌年末まで一年余りであったという指摘もあり、ハッキリしない。 [9]──ゴンドラ漕ぎの喋る言葉は、ヴェネツィア方言で書かれているので、仮にこう訳してみた。 [10]──このマチルダという女性が語る波瀾万丈の脱出物語、さらにはその後のヴェネツィアでのダ・ポンテと彼女の関係は研究者の関心を集め、彼女の正体を突き止めようとさまざまな試みがなされた。ドイツ人研究者で、一七六〇−七〇年代にヴェネツィアに滞在したナポリ出身の外国人リスト、さらにはマチルダがいうヴィーンの士官学校に送られた兄の存在まで確かめようとして、一七六〇年から七五年にかけて入学したナポリ出身の生徒のリストまで、洗いざらい当たったグスタフ・グーギッツは、その『ダ・ポンテ回想録』の独訳版(ドレスデン、一九二四)で、ダ・ポンテの創作という結論に達している。この見解は第二次世界大戦後の学会にも受け継がれ、定説となっている。(3)
訳註
[1]──セバスティアン・フォスカリーニ。ヴェネツィア共和国の名家で総督(ドージェ)や外交官を輩出した家柄の出で、1781年からヴィーンの宮廷でヴェネツィア大使をつとめた。ダ・ポンテが会ったとしたら1782年初めか。またあのジャコモ・カーザノーヴァも、彼の秘書だったことがある。 [2]──これが本当の話かどうかは疑問で、前回の註[10]で指摘したように、ダ・ポンテ研究家グスターフ・グーギッツの浩翰な研究(1924)によれば、どうもダ・ポンテの創作である可能性が高い。(4)
訳註
[1]──聖バルナバはキリスト教の聖人だが、ここではその身体的特徴をさしているわけではない。ヴェネツィアには「サン(聖)・マルコ広場」のように、聖人の名を冠した地名が多く、この(現在ではなくなってしまったが)聖バルナバ地区もそのひとつ。ここには当時、博奕や放縦など、なんらかの理由で財産をなくしてしまった没落貴族が住んでいた。その連中の傲慢な強欲性に、「鷲のような爪」という表現で言及している。(5)
訳註
[1]──このエピソードは、前出ナポリ出身の女性マティルダの物語と同様、ダ・ポンテの創作──いくばくか根拠となる事実があったとしても──と考えられている。 [2]──ダ・ポンテ(元の名エマヌエーレ・コネリアーノ)が、ユダヤ人としての被差別身分から抜け出すために、父親のジェレミアおよび他の2人の兄弟と一緒に1763年8月29日、カトリックに改宗したのは、すでに見たとおりである。そのときに、一家の改宗をつかさどったチェーネダ司教の名前を貰って、キリスト教徒ロレンツォ・ダ・ポンテとなり、神学校に入学して僧籍を獲得(1773年初)している。したがって教会人として結婚することができないというのはそのとおりなのだが、そのことは後に彼がトリエステで出会う(1792年)ことになるナンシー・グラールと結婚することを、いっこうに妨げていない。 [3]──旧約聖書「土師記」に出てくる、サン=サーンスがそのオペラ《サムソンとダリラ》の題材に採り上げた物語。ユダヤ人の戦士サムソンは、ペリシテ人の美女ダリラの色香に惑わされて、その力の源泉が自分の後ろ髪にあることを洩らしてしまう。これを知ったペリシテ人がサムソンの力を奪い、ユダヤ人たちを敗戦に追い込む。同胞の苦しみを目のあたりにしたサムソンが、悔いあらためてエホバに祈ると、ペリシテ人の神ダゴンの神殿が崩れて、サムソンはペリシテ人たちとともに下敷きになって死ぬ。 [4]──18世紀は、ヨーロッパではまだ魔女狩りなどがおこなわれていた時代で、下等な金属を黄金に変える術、つまり「錬金術」を使う者は妖術師として社会から追放され、火あぶりにされた。(6)
ジローラモ、もうカジノも、女も、そしてヴェネツィアもおさらばだ。金さえあれば、即刻発ちたいところだ。けれども三日以内には必ず出立(しゅったつ)と誓いを立てたぞ。神に感謝と、あの哀れな泥棒にお恵みあれ。明日の朝、会うとしよう。手紙を下男に持たせてやった。ところが弟は明日をも待たず、すぐさま私の顔を見にやって来た。そしてシッカリ私を抱き締めたうえで、財布を取り出すなり有り金すべてをくれたのだ。それだけで、もう当座の用にはじゅうぶん、私がこの町から出ていくに足る額だった。しかもこれはなにも、あの神の御使いにも比すべき若者が私にしてくれた唯一で一回きりの兄弟愛の徴(しるし)というわけでは毛頭なかった。わずか三十歳の若さで彼を私から奪ってしまった死は、好き仲間、助言者にして友人という、通常ひとりの人間、わけても兄弟(はらから)の裡(うち)に兼ね備わるのが真に珍らしい美徳を併せ持っていた。そればかりではない、彼は崇高な才能、博大な学識、イタリア文芸のあらゆる分野に通ずるすぐれた趣味を有していた。これらの長所だけでもたいへんなものなのに、さらに円熟せる判断、驚くべき謙譲、まれに見る挙止の上品さが加わって、彼の周りの者たちの感嘆と愛情を呼び起こして止まなかったのだ。かかる弟を失うというかけがえのない損失を悲しんで、流す涙の涸れる日は決して来ることがないであろう[訳註1]。 親愛な読者よ、どうかこの短かい寄り道をお許しいただき、貴方の奇特なお心もて、かくも愛しき弟の尊い想い出に捧げるわが感謝の涙を、憐れみたまわらんことを! サテ、例の神父に話を戻そう。翌日の朝まだき、曙の光も未だ差さぬというのに、私の許には次のような文言の手紙が届いた、
友よ、私は昨晩、じつに怪しからぬ振る舞いにおよんでしまった。君のマントを失敬して、八十リラの抵当(かた)に入れてしまったのだ。さらに悪いことに、その金を持って賭場に行き、みなスッてしまった。もうどうしたら好いか、絶望的だ。マントは君に僕のを送るが、なにしろ古びたので、丈(たけ)は短いし、今の季節には向いていないやつだ(じっさい擦り切れたラクダの布でできたので、追剥ぎやコソ泥よけには持ってこいのやつだ)。でも君だってマントなしというわけにはいかぬだろう。いったいどうしたものだろう? 君の好いようにしてくれたまえ。君の親愛なる、 F...riこの手紙を読んで、私は失笑してしまった。すぐさま家を出て、彼のところに行った。彼の部屋に入っていくと、私が自分のマントを着ているのを看て取ると呆然自失のありさま、ひとことも口を利かずに、異様な目つきをしたかと思うと、まるで気でも狂ったかのように道に飛び出すと逃げ始めた。私が追いかけると、小さな路地に入り込んだが、その路地は行き止まりで、運河に面していた。岸のところまで行き着くと、水中に身を躍らせる構えをみせた。おそらく本気でそうする気はなかっただろうと思う。いずれにしても、私は彼に追いつき、引き止めるのに間に合ったものだ。彼にお説教を垂れる代わりに、静かに弟が私に言った言葉を繰り返すに止どめた。──「「御覧、(賭博)狂いが人をどんな目にあわすものか!」──じじつ彼は「狂い」といったら、じつにいろんなものに狂っていたのだ。私の落ち着いて穏やかな対応は、彼の心を深く打った。涙を堪えることができず、私のほうももらい泣きをせずにはおられず、二人は抱き合うこととなった。気を取り直すように言ってやり、また、もしも彼がヴェネツィアを立ち去ると約束するなら、以後マントの話は決してしないからと約束してやった。そうすると誓ったので、いくらか金をやり、彼は立ち去ったのである。がんらい才能に欠けるところもなく、機知にもあふれた人物だったので、彼は以後は本気で勉学に励み、何年か後にはC...aの神学校で文学教授の講座を与えられ、さらには司祭として小さくはあるが一教区の導化を任せられるほどになった。聞くところによると同教区で彼は毎年敬虔に、かの仕合わせの(因となった)マントの思い出に、「自弁で」何人かの着のみ着のままの貧乏人に衣類を恵んでやっているとのことであった。この不幸な青年の例は、危険きわまりない(ヴェネツィアの)町を後にするという私の健全な決断をいっそう確固たるものにするのに役立った。もしも私がこのときと同じく、心が激しい情熱によって動かされた他のあらゆる情況においても、同様の決断を下すことができていたらば、どんなにか好かったであろうか! あたかも、いまだ「心ハ乱レ狂イハテザリシカバ[訳註2]」とあるごとく、彼の雄々しくも徳高き決断のもたらした善き果実(みのり)をつねに目に浮かべて、私自身も己(おのれ)のなすべきことをばなしていたなら(どんなにか好かったであろう)! とはいえこのときばかりは、私を(ヴェネツィアに)引き留めようとする、あの彼女の願いも、涙も、脅しさえもが、いかなる効果(ききめ)をも発揮することはなかった。 私はチェーネダに戻った。そしてわずか旬日を経ぬうちにハヤ天佑が降って、わが(誘惑に対する)勝利を、いわば嘉(よみ)してくだされた。すなわちヴェネツィア共和国において、文芸の栄える高貴な都市と評判の高い町トレヴィーゾで、神学校に文学の講座に二つの空席が生ずるということが起こり、それらに私と弟二人が招かれるという事態となったのである。われわれは、両名とも大喜びでこの申し出を受けた。とくに弟は、私と同じ町にいられるというその喜びのためだけに、ヴェネツィアでも高名な大家の執事という立派な地位を捨てたのである。 かの恥ずべき(愛欲の)絆から解き放された自分を見出したときの喜びは、まことに筆舌に尽くし難い。それは真実、そのようなものだったのである。あの女(ひと)、三年の長きにわたって片時も離さず私をガンジ搦(がら)めに縛りつけていた彼女、離れた後も私の想いがその後を追い激しく愛し続けていた彼女は、なんと私の出発後数日を経ぬうちに、新たな愛人の腕にその身を委ねてしまったのだ。そればかりか彼女は、もはや私を愛していないという証(あかし)を見せるため、この新しくできたわが憎むべき恋敵の手に私の命を委ね、危険に曝(さら)そうとさえしたのである。 彼女は一日も欠かさず、ヴェネツィアから私に手紙を書き送ってきた。その中には、まことしやかな嘘と、私に対する愛と貞節にあふれていると信じさせるに打ってつけと思った科白(せりふ)が書き連ねてあった。正月の元旦によこした便りには、こう書かれていた。
ロレンツォ、もし私の名誉と命を大切に思うなら、すぐにヴェネツィアに来てちょうだい。晩の十時頃、従妹のところにいるわ。貴方のつねに渝(か)わらぬ恋人。この手紙を読んでは一刻の猶予もなく、私は駅馬車の立場(たてば)に駆けつけると、二頭立の輕輪(カレッシーノ)を傭(やと)いメトレス[訳註3]に向けて駆けさせた。この年の極端な寒さは(本土とヴェネツィア島とを隔てる)潟(ラグーナ、海水が来ているので通常は凍らない)を結氷させていたので、四人の頑丈なゴンドラ漕ぎに、それも多額の賃金をはずんででなければ、メストレからヴェネツィアまで水路を開いて行かせることはできなかった。わがオリジルレ[訳註4]の住む館のある河岸に(ゴンドラから)上がったとき、もう時刻は真夜中に近かった。むろん館の扉は閉ざされていた。撞木(しゅもく)を取ろうとして腕を伸ばしたとたん、別の腕が私をグイと摑むのを私はおぼえた。腕はそれこそたいへんな力で、わが身をシッカリとくるんでいたマントを曳(ひ)っ張るなり、私を何歩か無理やり傍(わき)に引き摺(ず)っていった。それと同時に押し殺したような低い声が耳に入った、「若旦那、中ニ入(ヘ)ェッチャイケネエ。トンデモネエ、コッタ!」 それは私の年老いた下男で、ヴェネツィアを去るときにあの悪女の許(もと)に留めておいた男だった。彼は街灯の明かりというか、むしろ(ゴンドラ漕ぎと交わした)話し声で、私をそれと知ったわけだ。自分に返答する暇(いとま)を与えず、私をさらに引き摺って橋の反対側まで曳っ張っていった。じつはこの橋の袂(たもと)に、彼女の手紙に指定された館があったわけだ。もう安全な距離に来たと思えたところで、「好イカネ、旦那」と嗚咽(おえつ)に喉を詰まらせ、総身をわななかせながら言った。「貴方(アンタ)ノ女ハ、モウ新シイ男ヲ作ッタンデスゼ。ソノ男ハネ、どんどろろーぎトカイウ男デネ、コレモべねちぃゃノ貴族ダガ、町デモイチバンノ図太クテ、危ナイ男ダッテ評判ノ奴ダ。御主人ガ貴方ニ惚レテルッテ知ッテテ、焼キ餅ヲ焼イテネ、モウ旦那ノコトナンカ好キジャナイッテイクラ言ッテモ承知セズ、旦那ニ、夜遅クニべねちぃゃニ来サセテ、着イテ、家ニ入ッタトコロデ、言ウニハ『棍棒デモッテ、骨ヲ粉々ニシテヤルマデハ納得セン!』ッテ言ッテルンデスゼ」。 この話を聞いて私がどんなに仰天したか、もう申し上げるまでもないと思う。この善良な召使としばらく言い争ったあげく、またもっともきわまる用心への配慮もさることながら、けっきょくは嫉妬と怒りと、踏みつけにされた悔しさに負けて、瞋(いか)りに猛り狂って彼女の家に立ち戻った。絶対に仕返ししてやる、「シカラズンバ、死ストモ止マジ!」 あの気の毒な老いた召使も、イザとなったら手助けしてくれようという心意気で後に続いた。とはいえ私とて、ひとりでもこの人殺しからチャンと身を守るだけの勇気にも欠けず、またじゅうぶんな得物をも手にしていなかったわけではないのであるけれども。扉を叩くと、二階から閂(かんぬき)に結びつけてあった綱を引いて開けてくれた。用心オサオサ怠りなく、古びた灯(ともしび)にボンヤリ照らし出された階段を昇った。入口の間に入ると、かの悪女が従姉の部屋から出てくる姿が見えた。ひとりでいたのだ。後で私の召使から聞いたところによると、真夜中近くになって新規の愛人は、もともと「癇癖(かんぺき)性ノ」男だったうえに、他のさまざまな悪癖の他に、賭博の悪習にも染まっていたので、さんざん待ちくたびれたあげくが、手慰みに出かけてしまったというわけだった。けしからぬ彼女のほうは、私の姿を目にするやいなや、取って付けたいかさまの歓びの叫びをあげて、抱き締めようと駆け寄ってきた。その自堕落にしどけない格好と、それにもまして新たな臆面もない厚かましさとは、私の怒りに火を注いだ。近づいた彼女を突きのけると、私は「神の御手の、かかる汚辱に塗れた者どもをば、打ち砕きたまわんことを!」と、予言者風の言葉を吐き捨てるやいなや、転がるように階段を駆け降りると、あたかも重大な危機を逃れる者のごとくに、直近の船着き場に走っていくなりゴンドラに飛び乗ると、メストレに向かい、メストレからまたトレヴィーゾへと戻ったのである。いらい、私はこの女については、もはや話を聞くことさえお断りと固く心を定めた。まさにこのときにおいて天上から、わが理性を照らし、すっかり迷いを覚ますために、導きの光が射したと見えた次第である[訳註5]。 というわけで、自由になったわが魂は、ふたたび詩の女神(ミューズ)たちの司りたもう、快くも甘き(文芸の)園に遊ぶこととなった。しかもそこに見出したのは、じつにあらゆる便宜と、いとも高尚な励ましとであった。すなわち立派な図書室、しかもそれを私の裁量によってあったほうが好もしいと考えられる書物はどれでも発注して、さらに豊かなものにする権限。博学の士および慧眼の人物に満ちあふれた土地[原註2]。活気と才能、栄光を獲得せんという意気に燃え立つ、選ばれた若者たち。自己の教区を深く愛する、気宇壮大かつ学識豊かな司教猊下(げいか)。文芸と文人とを重んじ、高く評価する華やかな社交界。そして清澄で晴れやかな美しさと清々しさをもって、まさに幻想を掻き立て、詩人の心に創作の灯を点すにふさわしい気候と自然。これらがわが生涯における至福の二年余を形作ったのである。この時期、私は自分の生活を、愛する弟とジュリオ・トレント[訳註6]の二人のあいだに等しく分かって過ごした。このジュリオ・トレントは広大無辺の教養と最高の知識、および繊細・高尚な趣味に恵まれた人物であって、トレヴィーゾで私の文学的試作が獲得した評価と賞讃は、ほとんど彼の洗練された批評眼と鑑識眼、またそれに劣らず彼との親しい付き合い、さらには彼の知識人たちのあいだにおける正当かつ高い評判に負うものであるといっても過言ではない。脚韻を踏んだ八行節を連ねて語られた物語詩『イル・チェキーノ』[訳註7]は、じつにこの時期にトレヴィーゾ文芸学会(アカデミア)の会合において、私自身の朗読により発表されたものにほかならぬが、当地の人々ならびに司教猊下もお持ちであられた、私の詩人としての評価を高め、名声を拡めるにあずかって大いに力あった。本回想録の読者も、この小品が収録されているのを御覧になって、お気を悪くなさることはないと思う[訳註8]。 この学年の開始にあたって、私自身もまた弟も、より重要な講座担当に昇進させられる運びとなった。ところがこの思いもかけぬ抜擢が、勝手にわれわれよりも先に昇進するだけの権利があると思い込んでいた土地の教師方の自尊心を傷つける結果となってしまった。むろん彼らのほうが間違っていたのにである。彼らは理論にも学識にも欠けていたわけではないが、文芸の魂そのものであるところのかの才気、およびあの好(よ)き趣味を持ち合わせていなかったのだから。これらの才能は、生まれ持って自然に備わる資質であり、後で獲得しようと思っても、まず身に付くのが難しい類のものなのである。あえてハッキリ申し上げるが、この文芸に対する「好き趣味」は、私とわが弟とによって(トレヴィーゾ)神学校のカリキュラムに初めて導入された科目なのである。いらい四十年にわたって、われわれの教育方式が守られている。われわれが決めた規則が採用され、われわれがトレヴィーゾにやって来たときには、同校の教師方にはその名さえまったく知られていなかった作家たちの作品が、規範として学ばれているのである。 この時点に端を発して、わが生涯の大事件、驚くべき事態が次々と起こり始める。これらにより私は以後、一般的な習慣や情況、あるいはそれまで自分がなしてきた勉学の結果として、自分がこの途(みち)に進むものと思い込んでいた人生から、まったく異なった進路に押し流されていくことになってしまったのだ。イタリア文学およびラテン文学担当教授として、学年の最後の日に、なんらかの学術的テーマについて私が書いた論考を、自分が教育にあたった学生たちに発表させるというのが職務となっていた。その年に私が選んだ論題というのがまずいことに、よりにもよって以下のごときものだったのである。「もし人にして、幸福を追求するに際して、それを社会の(既存)諸制度の枠組の内においておこなったほうが好いか、それとも自然の簡素なままの状態においてなしたるほうが勝ると思うかどうか?[訳註9]」 このテーマ、いやそれにもまして私によりテーマが扱われたそのやり方が、私の審査員たちの(現代哲学の諸命題にかんする)まったくの無智・無関心、および私の競争相手たちの悪意に満ちた曲解によって、あたかも一個のスキャンダル、社会の秩序と平和に反する不用意な挑戦と判断され、ないしは判断することができるとデッチ上げられてしまったのである。わけてもパドヴァ学派[訳註10]の「矯風会」の連中の怒りは凄まじかった。だが連中ときたら、世の中の道徳や世論を矯正するより先に、まず自分たちが矯正されてしかるべき者たちなのにである。ところが彼らは、この件を共和国元老院に提訴し、その結果ヴェネツィア共和国始まっていらい初めて、元老院は行政的な裁定を下す資格と権限を付与されることとなったのである[訳註11]。それもなんと、ごく他愛もない詩的遊戯──じっさいこの件は、それ以外の何物でもなかったのだ──に、公共的利害にかかわるきわめて重大な事件の様相を帯びさせてのことであった[訳註12]。そして仰々しい鳴り物入りで、公聴会の日が告示される運びとなった。わが近親ならびに友人一同、わけてもジュスティニアーニ家の方々、この名家のメンバーにはトレヴィーゾ司教[訳註13]その人もおられたのだが、いずれも私自身がヴェネツィアに出かけて弁護のための論陣を張るのが好かろうと助言してくださった。 そこでヴェネツィアに赴いたわけだが、町に着いてホンの数日経ったところで、同共和国市民のうちでも最も学識豊か、かつ著名な人士のひとりであられるベルナルド・メンモ氏とお近づきになるという幸運に恵まれた。私の話をお聞きになられて、助けてやろうと仰せくださり、ガスパロ・ゴッツィ氏[訳註14]の庇護を獲得していただいた。このゴッツィ氏こそ、じつに当代随一の文人であられ、当年の「矯風会」の連中も尊敬する人物、かつ彼らの相談役でもあられたのである。私はメンモ氏の意見に従い、例の間の悪かった論考をゴッツィ氏に送り、それに好く知られた「ゴッツィよ、もし気高き心の……」で始まる韻文の手紙を付けた。 私の詩作は、この偉大な文人の高貴な心に素晴らしい印象を与え、彼は暖かい言葉で私の詩を評価してくれた。けれども彼の賞讃も私の弁護の役に立つどころか、かえって私の打倒をめざす連中にさらなる根拠を与えることにしかならなかった。というのは彼らに書き送った書簡で、「この若者は有望な才能に恵まれており、支援し力づけてやるにふさわしい」とゴッツィは書いてくれたのだが、これを読んで矯風会の連中は「とんでもないこと!」と反応したからだ。「だからこそ、奴から危険人物になる方途(みち)を徹底的に、奪っておかねばならん」というのがその論拠だった。連中はこうした理屈でもって、ジュスティツィアーニ家に対する憎しみを覆い隠していたのだ。というのはトレヴィーゾの司教は、前にも言ったとおり同家の一員であり、私を貶(おとし)め踏みつけにすることによって、(保護者であられた)司教猊下にも恥をかかせることができると踏んでいたからである。この数年前、司教猊下の弟がやはり元老院で、パドヴァ大学の教授のひとりに対して、その人物が執筆・刊行した文書にみられる反教皇的傾向を取り上げて有効な論陣を張り、教授職を失わせたことがあったのだが、その腹癒(い)せに、こんどは私にトレヴィーゾの神学校における文学教授のポストを失わせることで、連中の子分の仕返しをしてやろうともくろんだというわけである。かくのごとくにして、あの余命幾許(いくばく)もない(ヴェネツィア)共和国[訳註15]の痛ましき末年においては、有為の才能と無実の者が、あるいは復讐のため、またあるいはたんなる気紛れから弾圧を受け、また少数の者の、調子は好くとも嘘で塗り固めた美辞麗句を連ねた雄弁が、多数の者を曳っぱって判断の過ちに陥らせ、また専制君主にとり有効な支配・統治の手段と化してしまうのである。 というわけで、元老院での討論会に定められた夕べがやって来た。メンモ氏、ザグーリ氏またその他の、正義と公平だけのためにも私を弁護してしかるべき少数の友人たちも、相手方の大言壮語や信用に怖じ気づいたか、あるいはまた私に対する論難の他愛のない性質自体が無罪を立証するにじゅうぶんと踏んだのか、何か発言するのは賢明でない、または必要ないと判断したのであった。長広舌をもって鳴るモロジーニ検察官殿は、私とそれに二名の文書監察官とに対して、後者はその「職責上」私の提題の公表を禁止ないしは許可する権限を有する者として、有罪の論告をおこなった。宗門の監察官のほうは修道士で、この者をば、フランチェスコ修道会の不撓の擁護者であったバルバリゴ[訳註16]が「祭壇マデ、否ソレヲモ超エテ」贔屓(ひいき)にしていた。そこでバルバリゴがこの者の弁護に立ち、同時にモロジーニと歩調を合わせて私の論難に大声を張り上げたのである。そして人々の心が彼を応援していると看て取ったか、あるいは勝手にそう思い込んで、割れ鐘のような声でラテン語の悲歌(エレゲイア)を読み上げた。居合わせたお人好しのパンタローネども[訳註17]にそれが理解できたはずもないのだが、ともかくも大袈裟な口調で、恨みつらみおよび皮肉を搗(つ)き混ぜて述べ立てられてみれば、あの鬘(かつら)をつけた癇癪(かんしゃく)持ちの連中を、私に向かってけしかけるには、じつに驚くほどの効果を発揮してのけた。その悲歌のタイトルたるや、「エウローパにおけるアメリカ人」というのであった。
ヨッテ吾(ワレ)、密カニ故郷ヲ、愛(イト)ホシク偲ブ……等々こうしたラテン語の詩句の朗読は終わったのだが、それをば「晴朗ナル」(セレニッジマ)ヴェネツィア共和国元老院の面々は
多くを聞けども、理解はわずか、知り得たるは無、という次第であった。次いでこの抜け目ない「背曲がり」(=バルバリゴ)は一場の説教を垂れたのだが、こちらはイタリア語で書かれていたので、元老院の面々にもよほど分かりやすく思えたはずである。説教の主題は、以下のごとくであった。「人は、性来自由な存在として生まれついているのだが、法によって奴隷とされてしまった」である。この文学的な冗談が読み上げられたとき、会場に集まっていた人々のあいだから捲き起こった喧騒たるや、じつに想像もつかぬほどのものであった。だがそれは、たしかに私によって草せられた論題には違いなかったが、(そうした学園での余興討論会の他のテーマ同様)生徒たちを討論用の弁論術に習熟させるため以外のものではなく、そのことはじっさい私自身が、キケロの周知の格言「吾ラ法ノ奴隷タルモ、ソハ自由タルコトヲ得ンガタメナリ」に根拠を置いた、これを論破する正反対の論題を用意していたことでも明らかなところであった。だが私の攻撃者は、そちらのほうを読むなぞという手間はぜんぜんかけるはずもなかった。 「善良かつ尊敬すべきみなさん」と邪悪な演説者は大声を張り上げた、「この若者の提出したまことに忌むべき論題を注意してお聞きあれ。して、これに対していかなる反論がなし得るか御判断いただきたい」。こう言うと(私が書いた)詩句のうちからいくつかを繰り返したが、なかでも以下の数行ときては、他のいずれよりも反撥を受け、非難の口笛を浴びせられた。曰(いわ)く、
人間(ひと)の誤まてる 判断にて、僕(しもべ)また下郎の身たれど、繋がれたる鎖の 重み、いささかも堪(こた)えず。怒れる検察官また判官の印綬、 はたまた威嚇に満ちたる目差しも、怖るるに足らず。玉座の王侯、 また路傍に襤褸(ぼろ)をまとえる乞食をも、ひとしなみに視る。 その乞食の掌(てのひら)にこそ折々に、三途の川の渡し賃、 六文銭さえ落しやる。傲慢に膨れ上がり、黄金の角笛 吹き鳴らす殿方の張り上ぐる金切り声なぞ、いざ立たんとする 風の上ぐる、かそけき口笛に異ならず。これらの殿方に人々、 穏順(おとなし)き羊の群よろしく、服従を誓うそのあいだに、 同じくヒタと見詰める眼射(まなざ)しながら、わが追い求むるは 渡りに赴く鶴、はたまた雲中を翔ける妖怪の姿か、さなくば かのパスクイーノ、あるいはマルフォリオの石像。[訳註18]
原註
[1]──ヴェネツィアには「マガッツィーニ」と呼ばれる飯屋(オステリーア)、むしろ旅籠(はたご)といっても好いかもしれない店が何軒かあって、誰でも金目の物を持っていくと、亭主から値打ちの三分の二を現金で、残りの三分の一は葡萄酒で受け取ることができる。そしてあらかじめ決められた期限以内であれば、全額を払えば、それ以上の利子を取られることなく、抵当(かた)を取り戻すことができる。 [2]──トレント州ならびにリッカーティ地方については、これ以上なにも言う必要はあるまい。訳註
[1]──ダ・ポンテは、後年ドレスデンに赴いて、このジローラモという弟の死に目に遭うことができなかった。 [2]──ヴェルゲリウス『エグロガエ』(牧歌)I-一六。原文ラテン語。 [3]──海面に少し顔を出している、ほとんど「干潟」といっても言いすぎではないような無数の小島からできているヴェネツィアの向かい、本土の海岸にある町。 [4]──ダ・ポンテの愛人の名前はアンジェラだから、この名前ではない。A.ヴィヴァルディの第二作目の歌劇《偽りの侠気を装うオルランド》(一七一四)に登場する人物。魔術使いの異教の女王エルシルラに仕え、男装して活躍する、嫉妬深くて油断のならない女策士。 [5]──この話は多分にダ・ポンテが自分の好いように潤色してあるといわれ、信用がならない。 [6]──トレヴィーゾ在住の作家で書籍商(一七三六年生まれ)、悲劇や喜劇論を書いている。 [7]──「犬と猫の物語」という副題がつけられている。この物語詩はダ・ポンテの作品の中でも評判になったもので、後年(一七八八年)、彼の『詩作の試み』のうちに収められている。 [8]──そうはいっても、本訳が底本としているBUR版の『回想録』には、この詩は収められていない。 [9]──フランスの百科全書派ジャン=ジャック・ルソーの「自然に帰れ!」の主張に沿った設問。 [10]──パドヴァは、中世以来ヨーロッパにその名を知られた大学都市で、大学の権威を誇って、保守的な勢力の牙城であった。 [11]──ヴェネツィア共和国建国以来、その隆盛に大いに貢献した元老院も、このころになると富裕市民階級のクラブのようになって、自己の利権保持に汲々としていた。 [12]──わが江戸後期、松平定信の寛政の改革を諷して『世の中に、か(蚊)ほど煩(うるさ)きものはなし、文武文武(ブンブブンブ)と夜も寝られず」と歌って、手鎖の刑に処せられた太田蜀山人を思い出させる。 [13]──前出の「自己の教区を深く愛する、気宇壮大かつ学識豊かな司教猊下」のこと。 [14]──ガスパロとカルロ・ゴッツィの兄弟は、十八世紀末のヴェネツィアで活躍した知識人。ガスパロは英国のアディソンやスチールに倣った良識に富み高級なジャーナリスム評論を展開した『ガゼッタ。ヴェネタ』あるいは『オッセルヴァトーレ・ヴェネト』などの週刊紙を発行した。いっぽう弟のカルロは、近代派やゴルドーニに対抗して、イタリアの伝統演劇「コンメディア・デ・ラルテ」を擁護、『トウランドット』あるいは『三つのオレンジの恋』などの物語劇を発表した。 [15]──じじつナポレオン軍の侵入により、ヴェネツィア共和国は一七九七年に崩壊、その千年にわたる存在の幕を閉じる。 [16]──ピエトロ・バルバリゴ。一七一七年生れで「背曲がり」という綽名(あだな)を奉られていた僧侶。この少し前に共和国異端審問官に任命されていた。 [17]──例の「コンメディア・デ・ラルテ」の、代表的登場人物のひとり。強欲で無学な商人。 [18]──パスクイーノの石像は、ローマのナヴォーナ広場のかたわらに、いっぽうマルフォリオの石像はカンピドリオの丘の麓に置かれて、ともに教会や市政府に対する諷刺を記した張り紙を貼りつけられ、これら権力に対するローマ市民の溜飲を下げる役割をはたした。(7)
「姓名はなんというか?」 「ロレンツォ・ダ・ポンテです」 「出身は何処か?」 「チェーネダです」 「チェーネダ出身、ロレンツォ・ダ・ポンテ、ヴェネツィア共和国元老院の命令と布告により、以後、尊厳なるヴェネツィア共和国領内のいかなる学校・神学校・大学においても、決して教授・教諭・教官などなどの職務につくことを禁ずる。違反するにおいては、烈火の怒りを受くるものとす。閉廷、退場」頭を下げると、私は両手とハンカチを口に当てたが、それは笑いをなんとか堪(こら)えるためだった。そして早々に退散した。[ヴェネツィア]総督宮殿の大階段のところで、弟とメンモ氏とにぶつかった。二人の顔は死の恐怖で青ざめていた。だが私の顔からこぼれた微笑みが彼らを安堵させた。メンモ氏は一再ならず(ヴェネツィア)共和国審問官の任に就いたことでもあり、自国の法律と政策には精通していたから、事の次第を聞くと天にも昇る表情で、思わず「大山鳴動!」と口走った。だが、すぐに唇に指を当てると私を抱擁し、家に連れて帰った。その日の残りは「矯風会」と連中の厳かな「閉廷、退場」を嘲けって、無礼講のドンチャン騒ぎに暮れ、夜に入るころザグーリ氏のところに行ったが、同氏にしても、喜びと驚嘆のいずれが勝ったか、なんとも言えぬところであった。 メンモ氏はハヤその夕べのうちに、ありがたくも私に対し自分の家に止宿するよう申し出て下さり、お蔭で数ヵ月というもの快適なおもてなしと、哲学的な論談のうちに過ごすことを得た。その間に私はまた、この二人の保護者のお計らいにより、[ヴェネツィア]共和国の住人のうちでも最高の学識をそなえた著名人の方々に御紹介いただくことを得、私の身に起った事件と、それよりもむしろお二人の信用のお蔭をもって、皆さまから暖かく迎えられ、歓迎された。そんなわけで私は、自分の身に起った不幸のことなぞ、スッカリ忘れてしまうほどであった。なにしろ文学的評価においても、また人々の関心という点でも、私は血気に逸る若者の心が希うに足るすべてを獲得することができたのであるから。 メンモ氏は私のために、気前よくその財布の紐を緩めて、たいへんな好意から諸事の費用を進んで賄ってくれた。お付き合いいただいた方々といっては、いずれも身分が高くて文学の素養で有名な人物ばかり。ヴェネツィアの美女たちは競って私に、賛辞と愛想を振り撒いてくれた。誰もかれもが私の顔を見たがり、書いた詩句を聞きたがり、心の捩じくれた「矯風会」の連中と元老院、およびその判決の悪口を述べ立て、非難したのである。 私が幾人かのイタリアで名高い即興詩人たちと識る機会を得たのは、ちょうどこの頃のことであった。そのうちにはロレンツィ僧院長、ストラティコ僧正とアルタネージ氏などがいて、私も即興詩競技会に参加して技を競ってみた。弟も同じく腕を競い、我々二人の詩句は何度か人々の喝采、それもかなりの喝采を浴びたこともあった。私たちは「チェーネダの即興詩人」という異名を取ったほどである。この、いかなる主題についても、またどんな韻律を用いても、即興で気の利いた詩句を朗唱する、あるいは歌ってのけるというのは、イタリア人の特技、独壇場といって好かろう。それは我々の國語がどれほど詩的であるか、またどのような詩形にも適する言葉であるかを考えてみれば好い。なにしろその優雅さ、音楽的なメロディ、語彙の豊富さでもって、他の言葉を用いる詩人たちが長時間にわたる習練と思索を経てさえ、なかなか書きおろすことができないような事どもをば、「一気呵成ニ」述べてしまうに適しているのである。そうして述べられた事どもは、ただに優美かつ美しく飾り立てられ、聴くによろしく、褒むべきものであるだけでなく、また聴く者の心を楽しませ、驚かせ、天空の彼方に連れ去ってしまう。それは、かの比類無きジャンニ、あるいはダル・モルロのみならず、ラ・コリルラ、バンデッティーニその他の女流即興詩人達を聴く幸運に恵まれた者達が、口を揃えて言うところでもある。[訳註1] この私のうちに新たに、まったくもって偶然に開花した才能は、メンモ氏の私に対する好意をいっそう掻き立て、同時にまた私の将来のために図(はか)ってやろうという気を起こさせたのである。ところがまさにその好意がもとで、危うく私の身の破滅となりかねない事態が起った。というのは博識と気宇の壮大さによって、おそらく[ヴェネツィア]共和国に比肩する者がないこの高名な人物は、家に一人の若い女性を置いていた。その女は、肉体的また精神的にも、さして見るべきところのない者だったのだが、およそ性悪女たる者が持ち得るあらゆる手練手管と狡猾さとを備えており、メンモ氏の心に専制的に君臨して、彼を盲目的な情熱の虜にしていた。たとえ私が、彼をその過ちに気付かせ、災いを除こうと試みても、まったく無駄だった。三、四ヵ月の間、私は幸いなことに彼女の不興を買わずに過ごすことを得た。メンモ氏は私と一緒に読書や思索に多くの時を過ごし、また共に外出することも、他の時期にそうしつけていたより多かった。とはすなわち、私のためにということで、いろいろする仕事があったというわけである。この事情が、問題の女性に好き勝手をするチャンスを与えることに繋がったのである。そして私にとって不運なことに、彼女がある若者を好きになるということが起ってしまった。若者のほうも、当初メンモ氏の気にも叶い、同氏は彼女を彼と結婚させようという気にもなっていたほどだったのだが、ここで取り立てていうほどのこともない事件が起って、幾許も経ぬうちに同氏の機嫌をいたく損なうはめになってしまった。その揚句メンモ氏は若者を家から追い払ったばかりでなく、彼女にも同人との接触を禁止してしまったのである。ところが彼女は若者にゾッコン惚れ込んでおり、この決定にとうてい堪えることができなかった。そこであらゆる方法で、いつもの手管を総動員してメンモ氏の決心を翻させようと試みたが失敗したのち、涙ながらに、自分のために執り成してくれるよう、私を泣き落としたのである。 私の口利きは無駄ではなく、その日のうちに恋人は、私とメンモ氏自身の手により家に連れ戻された。一家中の喜びのうちに結婚の話が纏まり、その条件と日取りまでもが取り決められる運びと相成った。何時にも増して喜びに満ち溢れた晩餐後、私は例のとおりメンモ氏の居室に行った。彼の居室は、家の三階にあって、私の部屋とは隣り合わせだったのである。数時間が快適な哲学的思索のうちに過ぎていった。寝にいく時間になると、別れ際にメンモ氏は私をしっかりと抱き締めて、こう言ったものだ。「楽しい夢を見られるが好い。君は今日、わがテレーザを仕合わせにしてやってくれたのだから」。これがあの性悪女の名前だったのである。 私の部屋の入口は階段に近いところにあった。眠っている人を起こさないように、静かにそこに近づいていくと、部屋の奥から何か低い声で囁くような、ハッキリしない音が聞こえた。いったい誰が話しているのか耳をそばだてて聴くと、二人の恋人たちと知れた。家全体を領していた完全な静寂のせいで、彼等が話していた一語一語がスッカリ聞き取れた。「ダ・ポンテの奴は」と男のほうが言っていた。「御主人の心に影響力を持ちすぎている。奴はこの家で、我々にとって危険すぎる。お前も、お前の母さんも、我々の友達みなが寄ってたかっても絶対折れなかったあの人の心を、アッという間に変えてしまったあのやり方をごらん」。――「もしもあんたがそう思うなら」と言うのは性悪女、「何日も経たぬうちに、私が奴をこの家から出て行くようにしてみせるわ」。 この言葉を耳にしたとき、私がどんなに愕然としたか、言うまでもなかろう。呆然自失のあまり、暫くの間、言葉を失い、身動きさえもできなかった。やっとのことで自室に、夢見心地で吾を忘れて戻った。いったいどうしたものか、心を決めかねた。その夜の残りは、千百の考えが頭を駆け巡った。朝になるとメンモ氏の居室に行って、前夜耳にしたことをスッカリそのまま話すことにした。「ダ・ポンテ君、君は何か悪い夢でも見たのだよ」と、この善良な紳士は落ち着いて答えた。そこでもうその話はせずに、その朝は一緒に過ごした。朝食の用意ができたとやっとお呼びが掛かったのだが、そこでメンモ氏も私の話が夢でないことに気がつき出した。二階に降りていったのだが、そこでは家族と一緒に例の女も座っていた。彼女は私と目を合わせず、挨拶しても返事もせず、他の人々には出したのに、私にはチョコレ−ト(=ココアのこと)のカップもくれなかった。メンモ氏は、自分のカップを私に渡すと、部屋から出ていってしまった。直ぐにその後を追って、我々は一緒に家を出た。が、彼も私に、また私も彼に、起こった件については一言も口を利かなかった。とはいえ彼が、この件について思いをめぐらせているのは明らかだった。昼御飯の時刻に家に戻ったが、彼女はこの時も私に対して、朝にしたのと同じ振舞いでのぞんだ。会食者はいつもより多数だった。メンモ氏は怒りで震えていたが、私のほうが内心もっと怒り狂っていた。「どうしてダ・ポンテに給仕せんのかね?」と、とうとう大声で言った、「だって自分の手と貴方の手が揃っているんだから、なにも私がわざわざお給仕するまでもないじゃありませんか」が、答えだった。これを聞くと、血がカッと、まるでヴェスヴィオ火山の噴火のように頭に昇るのを感じて、私は思慮が自重を勧めるのも聞かずに、席を蹴立てて立つと自室に取って返した。そして多からぬ衣類を小脇に抱えて船着き場に駆けつけると、毎夕のパドヴァ向け定期便に飛び乗った次第である。 ヴェネツィアを発ったとき、私の懐には僅か十スクーディしか入っていない有様だった。旅費(その一部は陸路だった)を払ってしまうと、残るはなんと六スクーディ! 私の意気消沈は想像がつこうというものである。二人の恩知らずのお蔭で私は一挙に、恩人であり保護者、友人、それに率直に申し上げると「師匠」を失ってしまった。そればかりではない、この紳士(カヴァリエーレ)の好意が私の裡(うち)に呼び起こした将来に対する希望さえもが、雲散霧消してしまったのだ。加うるに、差し迫って自分が落ち込まねばならぬ赤貧の境遇が目にちらついた。私にはパドヴァに住んでいる弟が一人いて、同市の大学での勉学をほどなく終えるところだった。だが、この若者は私を助けてくれるよりも、むしろ彼のほうが援助を必要としているくらいだった。むしろ私はパドヴァの町で友達を見つけて、彼に自分の置かれた情況を打ち明けた上で、いくらかの助けを得られればと考えていたのだ。だがこの点でも、私は思い違いをしていた。私の当てにしていたのはダルマチア[訳註2]出身の僧侶で、さる奥方の庇護のお蔭をもって、パドヴァ大学で教会法教授のポストを得た人物だった。私は彼と、彼を好いていたメンモ氏のところで知り合ったのだ。この男はラテン語なぞホンのちょっとしか識らなかったのだが、自分の講義の見本として、多数の学生やパドヴァの教授連を前にして行わなければならない講演の原稿を、メンモ氏に預けたのだった。同氏はそれを私に渡して、読むように言ったのだが、読んでみると、正直のところマッタク話にならぬと言うよりなかった。これを聞いてメンモ氏はたいへんガッカリし、そのことを当人にも伝えた。幸いなことに彼は強情でも傲慢でもなかったので、自分の文体が大して洒落てもいなければ、またラテン語としてじゅうぶん純粋でないことを認めるに吝(やぶさ)かでなかった。もう三十年このかたキケロを読んだこともなければ、ヴェネツィア[の学校]では必読の作家であるエラスムスやカエサルなぞスッカリ忘れてしまっていたのだ。それ以外の点では、彼の講演が内容的には見事なことは間違いなかった。ただ一両日のうちにパドヴァへの出立が迫っていた。そこで、メンモ氏が彼のことをとても気にしているのを見て、私は文体の点に関して、講演を書き直してみましょうと申し出た。そして僅か二十四時間の間に、その仕事をやり遂げたのだった。彼はその原稿を携えてパドヴァに赴き、講演を行い賞讃と栄誉とを獲得したのである。彼が私に、言葉でもまた手紙によっても、どれだけ感謝したか、またメンモ氏と、そして私に対して、永遠の謝意の印として、どれほどの約束をしたかについて、ちょっとやそっとでは言うこともできないほどだったのである。 という次第で私は彼を訪ね、彼も先刻じゅうぶん御承知のあの女の話をし、私が陥(おちい)った不幸な情況に対する幾許かの援助を求めようと考えていたわけだ。そこで私は彼の自宅に、晴れやかな心持ちで出掛けた。入り口の扉を叩きながら、ごく当たり前の動作で目を上げると、頭が慌てて引っ込むのが見えたが、それはどうもかの善良なる僧侶のものだったように思えた。少し経って、下男が入り口を開けたが、私の教授先生にお目にかかりたいという話を聞くと、当惑気味に「教授先生様は、今は御在宅ではありません」と答えた。どうも騙されたのではあるまいかと思ったので、事をハッキリさせようと、私は家からやや遠ざかり、彼が出てこないかどうか見張ることにした。大学に出掛ける時間がもう直ぐだと判っていたのだ。じっさい幾許も経たぬうちに彼は出てきた。時をおかず彼に近づくなり、「イヤお坊様、貴方がどんなお人柄か、教えていただけてありがとうございました」と、それだけ言うと私はもう行き掛けたものだ。だが彼はシッカリ私の服の裾を摑むと、千百の言い訳を始めた。だがその言うところを聞けば聞くほど、彼の不人情と心の卑しさが知れるばかりだったので、抑える手を振り払うと、その場に彼を残して立ち去ることにした。いっぽうメンモ氏は、私がパドヴァに着くやいなや手紙を書いておいたのだが、この男に全ての事情を報せて、私をよろしく頼むと頼んでおいてくれたのだった。だがこのメンモ氏からの依頼も、またごく最近に私が彼にしてやった援助の記憶も、このダルマチア男の石のような心を、気前好く、恩を知るものとまでは言わなくとも、せめて人並みにすることはなかったのである。自分が馬鹿にされるのではないかという怖れが、奴をして丁重な申し出を私にするよう仕向けたのであり、その申し出にしてからが、おそらく私が受けないでくれれば好いがと、密かに希っていたものである。そしてじっさい私は、それらを決して受け付けなかった。奴は自分の講演の無様(ぶざま)な元原稿を、私の手許に残してきたことを思い出し、私が怒ったのを見て、それを公表するのではないかと震え上がったのである。その心配に気が付いたので、私は翌日直ぐに、問題の原稿を奴に送り返してやり、以後、奴に二度と会おうとはしなかった。奴は事の次第を、自分なりにメンモ氏に書き送ったのだが、それでも次のような文言(もんごん)でその怖れを告白しないわけには行かなかった。曰(いわ)く、「ダ・ポンテは、私に講演[の原稿]を送り返してくれることでもって、私のためにそれを書き改めてくれるより、もっと大きな贈り物をしてくれました。あれを取り戻すためなら、私は五十ゼッキーニ払っても好いと思っていたのです」と。だが私は、奴の評判を永久に損なうような文章を公表して鬱憤を晴らす代りに、そんなことは頼まれてさえもおらぬのに、こちらから進んでそれを送り返してやったのだ。それも奴さえもが狼狽するような寛大さをもって、比類なき卑劣さと忘恩に報いたのだ! ただしかし、奴が私の訪問を受けた時に示した態度は、以後私に自分の貧乏を誰にも知らせず、隠しておく必要の重要性を教えた。そこで逆に私は以後、自分を金持ちで裕福と思わせるように心掛け、出来る限りにおいて、そうした外見を保つよう努めることにしたのである。 私の[ヴェネツィアからの]出立があって何日か経ったところで、メンモ氏は、私が彼の家に残してきた僅かな衣類を親切に送り届けてくれた。それを着て私は、チャントした身なりで町(=パドヴァ)のカフェなり公共の集会場、つまり人前に出られるようになった。小ザッパリして、じゅうぶん手入れの行き届いた格好を見せびらかしたわけだ。土地の五十リラを五十等分(とは一日一ギネアということ!)して、五十日間は食いつなげるようにし、その間に「ヨリ好キ日ノ来タランコト」を希ったのである。というわけで、私は一日に使える額が一リラ、つまりヴェネツィア通貨にして二十ソルディだけでもって暮らしていくこととなった。そのうちから宿泊費に八ソルディ、毎朝のコーヒーに五ソルディ、残りの七ソルディが一日のパン代というわけだ。こうして連続四十二日間というもの、パンと黒オリーブの漬物だけで喰い繋ぐという芸当をやってのけたのである。この黒オリーブという奴は、塩が利いていたので水を飲みたいという気を起こさせる効果があった。こうやって他人は申すに及ばずわが兄弟にも、自分の置かれた詩的というには余りに厳しい倹約生活をヒタ隠しに隠し通したわけだ。だがこの窮状にも、とある奇妙な事件が起って、幸いにも終止符が打たれることとは相成った。 ある若者、彼は(トランプの)「ダーメ」のゲームの名人と自惚れていたのだが、あるコーヒー店[訳註3]に貼り紙を出して、誰とでも勝負してみせると宣言したものだ。いっぽう私には、このゲームならば誰にも負けないという自信があった。そこで一勝負してやろうという気になり、申し込んだら、当人も受けて立ち、掛け金と勝負の回数を取り決めた。私はじつは、もし負けたら第一回戦分を払える金しか持っていなかったのだ。けれども私が勝ったので、その後も勝負を続けることになり、それほどの時間も掛けずに、決められた十二回戦全部を勝ってしまった。しかもそのうちの十回は、点数倍のゲームだったのである。彼はその場で直ちに私に二十二ピアストレを支払い、自分のほうが下手だと認めた。その場に居合わせた何人かの大学生の若者は、友達の仇(かたき)を取ってやろうと考えたのでもあろうか、その金額を見て今度は「オンブレ」[訳註4]の勝負を申し込んできた。土地の仕来りでは、こうした申し出を断るのは失礼ということになるので、心ならずも私は挑戦を受けざるを得ない羽目となった。とはいえ私は運好くこの連中を相手にしても、勝つことを得て、真夜中の鐘が鳴る前に、旨い晩飯にありついた上、ポケットには三十六ピアストレの金を入れて帰宅した次第である。この思いも掛けない情況の好転は、将来についても好い前兆となった。続く数日間、私は賭け続けたのだが、いつもツキに恵まれて勝ちを取ることになった。 とはいえ、こうした生き方は、どうも私の気に食わなかった。たしかに[パドヴァの]町でも最も気高く、また高名な方々ともしばしばお会いし、言葉を交わす機会があったことは事実である。とくにあの比類なき才人チェザロッティ氏[訳註5]は、メンモ氏のお蔭がより大きかったか、あるいはまたわが詩句がお気に召した故(ゆえ)か、私をたいへん気に入って下さったのであった。だが、こうして人の情けが私に拒否したところのものをば、運の女神の庇護のもとに見出したとはいえ、私は過去の経験に照らし合わせて、もっと真っ当な道を歩まねばならぬと思い定め、断然パドヴァの町を捨ててヴェネツィアに戻る決意を固めた。カテリーノ・マッツォーラ[訳註6]は博識にして優雅な詩人、かつ恐らく初めて滑稽物のオペラ台本執筆に手を染めた人物だが、私は彼とはメンモ氏宅で親密な友人関係を結んでいた。そのマッツォーラが、直ちに私をかの騎士殿(カヴァリエーレ)のところに連れ戻そうと欲したのである。 彼から、私は二つの事実を知った。第一は、例の若造が、私のヴェネツィア出立の僅か数日後に、メンモ氏宅からまた改めて追い払われたということ、そして第二は、あの性悪女がメンモ氏に言ったには、先日のような扱いを私にしたのは、私が彼女に惚れていたからで、あの仕打ちは、ひとえにそんな想いから私を癒してやるためだったと言い、それをまた同氏に信じ込ませたということで、この話を聞いて、メンモ氏は「彼女の思慮と慎みを大いに賞讃し、同時に哀れな友人ダ・ポンテの心の弱さを気の毒がった」というのだ。こんな怪しからぬ言い掛かりを黙って聞いていることは到底できず、私はなんとかして彼の誤解を解いてやろうと思った。そこでこちらから進んで、彼に会いに行ったものだ。私は、彼自身と、またテレーザからも、単に暖かいばかりでなく、大喜びで迎えられた。その日のうちに部屋と、それから食卓に席も与えようと言われたが、その申し出を受けるのはお断りした。ただしょっちゅう彼に会いに行き、彼の方も私のところにやって来た。何日も経たぬうちに、我々の親交は旧に戻ったばかりか、以前に倍増すものとなった。 また高潔なザグーリ氏[訳註7]も、[メンモ氏と]同様の喜びで私を迎えてくれ、自分の家事担当秘書として私を雇ってくれると共に、学問上の話し相手として遇してくれた。彼とは、多くの至福の時を過ごした。この人物は博大な知識の持ち主で、詩人としても優れ、雄弁をもって鳴り、美術に関しても好き趣味と愛好心に溢れた騎士であられた。己れの資産が許すより以上の気前の好さを発揮され、自分自身よりも芸術を愛しておられた。有名のジョルジョ・ピザーニ氏に私を紹介してくれたのは、彼である。ピザーニ氏は当時のヴェネツィアにおけるグラックス[訳註8]ともいうべき人士で、この人については先に行って、この「回想録」の中で、もっと詳しくお話しする機会があろう。ピザ−ニ氏は、自分の子供たちの教育を私にスッカリ任せると申し出られ、私も喜んでその責をお引き受けすることに同意した次第である。というような次第で、一挙に三人もの高貴かつ有力な市民方から御愛顧と庇護を受ける身となり、その方たちから競って友情と[金銭的]恩恵を賜わる仕合わせとなったわけである。 この時期、私はホンの少しの詩作しか行わなかった。というのも二重の職務に追われていたわけだし、またそれよりも恐らく、[ヴェネツィアという]土地柄のもたらす様々な楽しみが、[当時の]私のような年齢、かつ才気渙溌な者にとっては、まったくピッタリということもあって、詩作にゆっくり耽る暇(いとま)を残さなかったからである。加うるに私は、友人たちの望みに任せて、しばしば即興詩コンテストにも参加した。こうした行事は当時たいへんな流行(はやり)になっていたからだが、正直をいうと私は、こうした競技は、チャンと書き下ろす[正式の]詩作とは断然相容れないものと心得ていた。じっさいの話、洒落た見事な詩句を即興で吟じまた唱ってのける才人の数は多いにしても、いざ筆を執って書くとなっても、凡庸な詩人に堕さぬような者はごく僅かしかおらぬというのは、じつに驚くべきことと言わなければならない。 そうこうしているうちに、例の怪しからぬ女が私に関して信じ込ませたとんでもない誤解について、メンモ氏の目を覚まさせるチャンスがとうとうやってきた。私はそれまでにも何度かこの件を持ち出して、あけすけに事情をぶちまけたのだが、彼のほうは頑固に自分の思い込みに固執して、我々の仲は再び決裂しかねない有様だった。ある日のこと、そしてそれは生涯でたった一度だけ、最初で最後のことだったが、「いったい誰が相手だと思っているのかね?」と私に言ったものだ。これは、ヴェネツィアの紳士方なら口癖のようにいう文句なのだ。私は「ハイ」と応え、「じゅうぶん心得ていなければ、これほど率直にも、またザックバランにも申し上げません」と続けた。聞いて私の気持ちを理解した彼は、私を抱擁して礼を言った。「そうでありましたら」、と私は続けた、「(言っていることが本当だと)貴方に納得していただけるようにする義務が私にはあります。そしてテレーザに一言もお洩らしならならぬとお約束いただけるなら、そういたしてみましょう」――「フーム」が彼の返事、「もし出来るなら、私を納得させてみたまえ。何も言わずにいようから」という次第で、私は仕事に取り掛かった。 テレーザは情熱的な性格の持主だったが、似たような性格の女がおおむね皆そうなように、色恋の相手をいとも簡単に取り換え引き換えする癖があった。そこで失くした愛人の代わりを世にも簡単にみつけることとして、彼女の家に親しく出入りする、ある若者に目を付けたのだ。この青年は財産の点で運に恵まれず、この貧乏という不運を、金持ちの女性との結婚で補なってやろうと決め、それ以外のことはどうでも好いと考えている人物だった。これを看て取るや、私は彼が私と友達になるようことを運んだ。私がメンモ氏と親密な仲なのを見て大いに喜び、彼は直ぐに自分の考えを私に打ち明け、応援してくれと頼んだものだ。私は彼に、どんなことであろうと力になって上げようが、ただしそれは、(一)テレーザ本人から、彼女が私に被せたのはじつは濡れ衣だったという正直な告白を取り付けること、その上さらに、(二)その事実を、騙していた騎士殿(=メンモ氏)に、彼女自身が打ち明けるようにさせる、この二つの条件を満たした上でのことだ、と話を取り決めた。青年はいとも容易にテレーザから、これら二つのこと共を行う約束をとりつけた。というのも彼女が、(その手練手管で)すっかり盲同然にしてしまった人物(=メンモ氏)相手なら、何をやろうと罰せられるわけがないと思い上がっていたからである。
訳註
[1]──即興詩人。ここにダ・ポンテが名前を挙げている即興詩人達は、当時かなり名を知られた連中で、フランチェスコ・ジャンニ(一七六〇〜一八二二)、とくに女流のラ・コリルラ・オリンピカ(本名マリア・マッダレーナ・モレルリ、一七二七〜一八〇〇)は有名。じつはダ・ポンテがヴィーンで出会うことになる、ハプスブルグの宮廷詩人ピエトロ・メタスタジオも、若い頃即興詩人をしていたことがある。この即興で詩を詠んで、機智を競う競技には、わが国の井原西鶴などが興行して評判を取った、俳諧の大矢数(大阪生玉神社で一晩に四千句!)に通ずるものがある。 [2]アドリア海東岸、現スプリットを中心とする地域。当時はヴェネツィア共和国に属していた。 [3]コーヒーは十八世紀後半にアラブ諸国(トルコが有名)からヨーロッパに伝えられ、最新流行・人気の飲み物となった。コーヒー店は知識人が集って、議論を戦わす溜まり場であり、ゴルドーニには「コーヒー店」という芝居があるほどである。 [4]「ダーメ」(フランス語で「ダーム=dames」)も「オンブレ」(フランス語で「オンブル=hombre」)もトランプのゲーム。 [5]メルキオール・チェザロッティ(Melchiorre Cesarotti、一七三〇〜一八〇八)。当時のイタリアで有名な詩人、パドヴァ大学教授。 [6]Caterino Mazzola(?〜一八〇六)。ヴェネト地方のロンガローネ出身の劇詩人。後出のように、ドイツのザクセン大公の宮廷に仕えていたときにダ・ポンテの面倒をみてやった。ヴィーンの宮廷で楽士長をしていたアントニオ・サリエーリの友人でもあり、ダ・ポンテを彼に紹介して、ダ・ポンテがヨーゼフ一世皇帝の知遇を得、モーツアルトと知り合うキッカケを作ってやったのもマッツォーラである。 [7]Antonio Zaguri(一七三二〜一八〇六)。ヴェネツィア共和国元老院議員。文人・知識人で、ジャコモ・カザノーヴァとも親交があり、両者の書簡からダ・ポンテの動静について情報が得られる。 [8]Tiberius Graccus(紀元前一六二〜一三三)。古代ローマの民衆派政治家。スキピオ・アフリカヌスの孫で、護民官に選ばれて、土地の占有を拡大しようとする貴族派に対抗して農地改革を推進し、市民の間の貧富の格差を解消しようとするが、暗殺される。前出のジョルジョ・ピザーニも、ダ・ポンテの頃の貧乏貴族ならびに下層市民階級を基盤にして、保守派富裕階級を糾弾、市政改革を推進しようとしたので、グラックスになぞらえられた。(8)
もしもピザーニが詐欺師だったら、 はたまた威張屋、盗っ人、ツビ舐め男で、 婆ァ売女(ばいた)と二六時中つるみ、 チンポ振り廻して、お奉行様を馬鹿にしたとて、 はたまた大家(たいけ)の殿様よろしく、 百人のオカマと、同人数の娼婦を侍(はべ)らせたとて、 オオ神様・仏様! そんなこと、いずれも奴を ヴェネツィア大法官(アヴォガドール)に選ぶ妨(さまたげ)となろうか! ところが奴は国法(おきて)をキチンと守り、 誰であろうと横車・横領・弾圧、 いかなる不正も、いっかな我慢せぬ男なりゃこそ、 お偉方(グランディ)にもハッキリ物言い、 大評議会でエーモ(・アルヴィーゼ)やトロン家の一味に、 己れの意見を、シッカリ述べる。 なりゃこそ元老院、あるいは(共和)国のお偉方から、 無法無態な仕打ちを蒙(こうむ)り、 彼に対して誣告(うったえ)が起る。 四十委員会(クァランティーア)曰(いわ)く、 「奴が毎月手にする物は、乞食(かったい)の頭陀袋(づだぶくろ)一つ、 それだけあれば、もうタップリ」、 また「大法官の肩衣(かたぎぬ)を(ピサーニの)、 糞ヒリ野郎(マーマ)[原注2]にくれてやるなぞ、もっての外、 言うも愚かな狂気の沙汰」。 とはいえ奴等は、ヒリ立て糞(=ピサーニ)から 出てくる宝石(いし)が、糞ったれ仲間の間では、ついぞ見掛けぬ 真(まこと)の宝物(たから)と、シッカリ十分、先刻御承知。 かつこれこそが、奴等が憤怒(いかり)の真の原因(もと)、 これこそ奴等がガナリの動機(きっかけ)、 しかも悪党ども、そのこと一切合切(いっさいがっさい)ヒタ隠し。 けれども奴等は、吠えるに任せておくさ、 なぜなら奴等が際限(きり)なく血道を上げ、 騒ぎ立てるは、公益のためならず。 さなくて、奴等がこの人物(=ピザーニ)、 聖人、義人、善き市民、かつまた法の擁護者に、 抱かにゃおられぬ、憎しみの毒がそうさせる。 かてて加えて、勝手気儘や不当な華美に歯止めをかけ、 小人数支配を狙う狂った野望を押し止どめる、 この人物を憎んで止まぬ、奴等の心もまたその原因。 これこそ、元老院が今や大童(おおわらわ)、 昼はひねもす夜はよもすがら、尻(ケツ)の穴ほじり屋そこのけに、 彼(=ピザーニ)の尻追いかけ廻す、真(まこと)の理由(わけ)。 奴等は彼をば片意地の、睾抜きロバに仕立て上げ、 貴族身分も剥ぎ取った上、 何処なと、マドラス、カナダにでも、所払いで追い出す所存。[訳註3] というのも市民魂、自由な弁舌、 卑怯におさらば、怖れ知らずに高く挙げたる頭(こうべ)などなど、 これらこそ正に、奴等にとっては恐怖の種。 どうか今一度よく考えて、オオ神様! 御覧あれかし、貴方がたの好い加減な驕(おご)りで、 ガタガタにされた祖国の姿。 実入りや、家柄の誇/埃(ほこ)り、 格式、それに資産ばかりを考えずに、いま少し 国庫の収益、司法の意見も重んじられては如何(いかが)? 溢るる学識もて、お役に立とうと 待ち構えている方々に、小煩い口出し我慢する手間、 省いて上げたら如何なもの? 方々が、好かれと信ずる方策をば、 政庁の場で述べに行くのに、とくに謝礼を貰わずとも、 気持ちを悪くはされぬはず。 未だハッキリ目にすること叶わぬ、 とは心中の意向や目論見について、 実際の結果見られる、その時までは、予断せぬのがなにより肝要。 また人々の言うことの裏に、偏屈まる出し、 抜け目ない市民の不正な狙いがありはせぬかと、 無用の詮索いたされぬこと。 己れらばかりが独り賢(さか)しく、 知識は独り占めの強欲をば、いささかなりとも控えた上、 奇矯の振舞い正してみては? 誰かが貴方に真実(まこと)を告げて、心に起る最初の思い、 それを大切に、従うこと。言ったが(エ−モ・)アルヴィーゼ、 あるいはピエ−ロ(・トロン)かと、無用の詮索、せぬが好い。 頭にシッカリたたき込むのは、 これはみんなの共和国、 みんなの物で、誰か個人の持ち物には非ず。 誰かが不満の嘆きを上げれば、 それは必ず相応の、なんらか理由(いわれ)あればこそ。 とは貴方がた、なんでも独り占めしたがるからさ。 有無を言わさず当人を「嘆きの檻」に入れる代りに、 まずは予審か兵役に廻して、腹に溜った不満を吐けるよう、 計らってやるのが至当というもの。 だがどうしても当人が、貴方がた、いずれも一票、 表決投ずる評議会に、まかり出(いで)たとなった時、 そうなった時には嫌な顔せず、無駄な口をも利かれぬこと。 とどのつまりは、これだけお話、お聞かせ申した上からは、 間違っても逃げ口、ありと覚(おぼ)し召されぬこと。 この格言は先刻御存じ、「稲妻光れば、お次は雷。」この小唄(ソネット)はヴェネツィア方言で書かれていたので、それこそ誰にでも分かり、アッという間にコーヒー店でも、集会所でも一膳飯屋でも、それこそ何処でもその噂で持ち切りとなった。[原注3]大いに皆に気に入られたわけだが、それがまたお偉方たちの怒りに油を注ぐこととなった。長老達の長衣(トーガ)や鬘、亭主達の貴族めかした尊大ぶりを小馬鹿にし、私を気に入りピザーニを好いていた女性方は、この唄を宙(そら)で憶えて、大喜びで朗唱してのけ、ドッと挑発的に笑いこけては、中でもいちばんカラシの利いた句をば、それも自分がからかわれていると思いそうな当の人物に向かって、繰り返したものだ。 という次第で、本命(=ピザーニ)を直接攻撃することができないとなれば、代りに子分(=ダ・ポンテ)の方を叩いてやろうと連中は思ったわけである。告発の口実も、また告発人も見付けるのに手間暇は掛からなかった。ある卑劣漢がいて、この男は私がときどき顔を出していた店の常連だったが、この者が誣告罪審理裁判所に、私について種々の告発をおこなったのだ。金曜日だった日に[原注4]、私がサラミ・ソーセージを食べた(としたら奴も私と一緒に食べたわけだ!)、それから日曜日にも何回か教会に行かなかったというのだ。その当人たるや、生まれてこの方、一度もおミサなぞ聴いたこともないというのに! この二つの告発内容を知らされたのは、同裁判所の裁判長を勤めている当の人物からで、彼自身が誰よりも先に、直ぐにもヴェネツィアから退去したが好いと私に忠告をしてくれたのである。「もしこの二つの告発で十分でないなら」とは、私を憎からず思っていてくれたこの紳士の言葉、「ほかの理由をいくらでも持ち出してくるだけのこと。なにせ連中は君を有罪にしようと思っているのだから、なんとしてでも有罪を証明してのけるだろうからな」。この言葉に、私の友人・縁者達は私の自由が、そして場合によっては生命さえもが、危険に曝らされていると判断した。高潔の人士ジョヴァンニ・ダ・レッツェ、この方の家にわが弟が、秘書というよりもむしろ友人の扱いで住まわせていただいていたのだが、そのダ・レッツェ氏は、自分の田舎の別荘を安全な非難所として提供してくれ、そこに告発問題のほとぼりが冷めるまで、私が退避するよう勧めてくれた。だが私は、ピザーニに対しても、また私自身に対しても、これほど不当な扱いをしてのけた土地、自己の真の利益にこれほど盲目な国、その崩壊がこれほど間近に迫った町[訳注4]に、もはや愛想が尽きてしまっていた。そこで永久にヴェネツィアを去ると心に決めたのである。わが三人の保護者のところと、ほかの少数の友人の許に出向いてその旨を告げたが、いずれも目に涙を浮かべながら私の決意を聞き、それに賛成してくれた。かくて私は祖国を捨て、ゴリツィアに赴くこととなった次第である。